(池田 信夫:経済学者、アゴラ研究所代表取締役所長)
4月9日に行われる日米首脳会談の最大のテーマは「脱炭素化」である。パリ協定に復帰したバイデン大統領は大型の地球温暖化対策を打ち出し、2050年カーボンニュートラル(CO2排出実質ゼロ)を宣言した菅首相は、地球温暖化に関するパリ協定の「2030年CO2排出26%削減」という約束を踏み超える大幅な削減を打ち出す見通しだ。
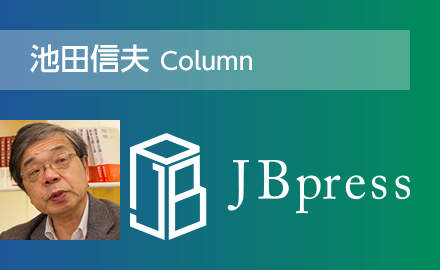 他方EU(ヨーロッパ連合)は今年(2021年)6月にも国境炭素税(国境調整措置)を打ち出す方針で、バイデン政権も国境調整の協議に応じる方針を出した。日本でも環境省と経産省で別々に有識者会議が始まり、マスコミも「世界の流れに乗り遅れるな」とあおっているが、ちょっと待ってほしい。
他方EU(ヨーロッパ連合)は今年(2021年)6月にも国境炭素税(国境調整措置)を打ち出す方針で、バイデン政権も国境調整の協議に応じる方針を出した。日本でも環境省と経産省で別々に有識者会議が始まり、マスコミも「世界の流れに乗り遅れるな」とあおっているが、ちょっと待ってほしい。
国境調整という名の保護主義
地球環境を守るという目標に反対する人はいない。それがコストなしで(あるいはコストを減らして)できるなら、どんどんやるべきだ。1970年代以降、日本企業のやってきた「省エネ」は世界のお手本であり、それによってCO2排出量も減った。
しかしそういう「低い所にぶら下がっている果実」はもう取りつくした。2050年に排出ゼロという大胆な目標は、省エネだけでは達成できない。それは企業が化石燃料を使う設備を廃棄し、国民が自動車に乗るのを減らす必要がある。
そのコストを社会全体で負担するのが炭素税で、これは化石燃料などから排出される二酸化炭素(CO2)の重量に応じて課税する。EUではすでに各国で炭素税をかけるほか、域内で排出枠の取引システム(ETS)を設けているが、これだと域外から輸入する化石燃料などに課税できないため、EUの工業製品が不利になる。
そこでEU域内の税率との差額を関税として輸入品にも課税するのが国境炭素税である。たとえば域内の炭素税率が1トン1万円で、輸出国の炭素税が5000円だとすれば、その差額5000円をEUが関税として徴収する。
国境炭素税が今までの温暖化対策より強力なのは、多国間の合意が必要ない点である。パリ協定のような条約では各国の合意が必要で、アメリカのように脱退すると無効になってしまうが、国境炭素税は関税だから一方的に課税できる。













