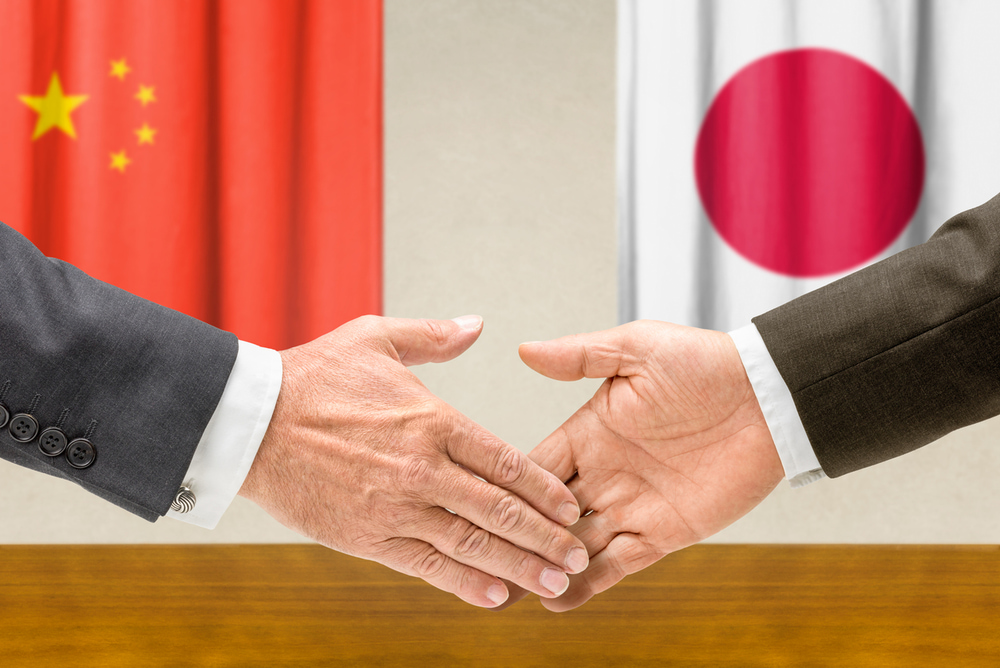外交評論家 エネルギー戦略研究会会長 金子 熊夫
昨年来、新型コロナウィルスの感染拡大に関連して、中国に対する厳しい批判が、かつてないほど国際的に高まっています。特に日本は地理的に近く、大きな影響を受ける立場ですから、中国問題は政治家や外交官だけに任せないで全国民で真剣に考える必要があります。
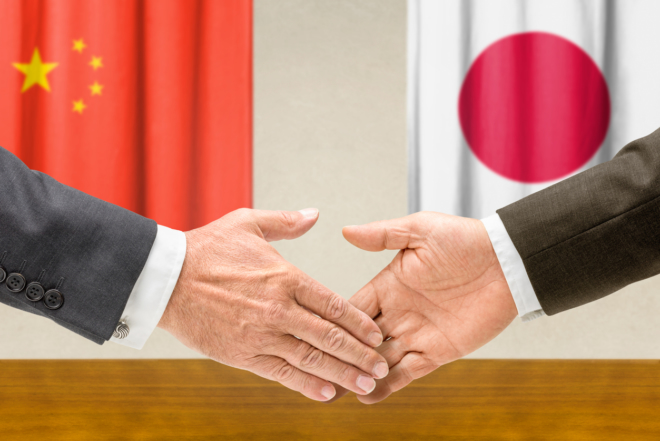
Zerbor/iStock
今回中国は、いち早く国内のコロナ鎮圧に成功したことを誇示しただけでなく、各国がコロナ対策で忙殺されている隙に、まるで火事場泥棒的に、南シナ海や東シナ海(尖閣諸島周辺)に進出し、軍事的拠点を構築するなどの実力行動に出ました。そのことを国際的に批判されると開き直り、自国外交官に対し、徹底的に反撃せよ、恐縮したような姿勢は一切示すなと訓令を発しました。これを彼ら自身「戦狼(せんろう)外交」と呼んでいます。卑近な表現をすれば、まさに「盗人猛々しい」というほかありません。
最近では、中国は国産ワクチンを大量に外国に輸出し、それを勢力拡大の手段に使っているとみられる節があります。「一帯一路」政策はそのための隠れみのという見方も、決して的外れではありません。
特に今年は、中国共産党の創設100周年で、習近平指導部は今年を重要な節目の年と位置づけています。これからさまざまな強引な手を打ってくるでしょう。その都度、一喜一憂し過剰反応することなく、中国の出方を冷静に見極める覚悟が肝要です。その時に必要なのは、中国を、そして日中関係を、長い歴史の流れの中で大局的にかつ多面的に把握することです。
ということでこれから数回に分けて「日本は中国とどう付き合っていくべきか」という大テーマについて考えていきたいと思います。
とは言っても、この限られたスペースで長く複雑な日中間の歴史と現状を網羅的に論じることは到底できませんので、まず手始めに、私自身の中国とのこれまでのお付き合いについて、いくつかの個人的体験やエピソードを交えながら、お話していくことにします。
吉田元首相と加藤紘一君の思い出
30年に及ぶ外交官生活の中で、中国問題だけを特別に担当したことも、北京や上海などに長期在勤したこともありません。実は、外交官試験に合格した後、最初の任地を選ぶ時に、中国を選ぶこともできたたと思いますが、そうはせず、米国を選びました。正直なところ、中国には全く魅力を感じていませんでした。
当時は毛沢東の全盛時代で「共産中国」のイメージはいかにも暗かった。日中間に国交は無く、北京に日本大使館は存在しなかったので、中国を知るためには台湾で勉強するしかありませんでしたが、台湾に行く気にはとてもなれません。
やはり欧米の先進国に行って華やかな生活がしたいという気持ちが強く、中国(台湾)勤務は、「貧乏くじ」を引くようなものだと内心思っていました。
実は、最初の海外赴任に先立って、私たち同期生十数名はそろって大磯に行き、外務省の大先輩である吉田茂元首相を表敬訪問しました。その時、元首相は上機嫌で、おいしいトウモロコシをご馳走してくれました。最後に訓示のような形で数分だけ話された中で「諸君、中国問題は大事だから大いに勉強したまえ」とぽつりと言われたのを記憶しています。
理由は詳しく語られませんでしたが、若き日に通算10年近く中国各地に勤務し、苦労した経験があるだけに、中国には特別の思い入れがあったようです。戦後、米軍占領下の日本で長年首相を務め、サンフランシスコ平和条約に署名(1951年)し、同日、日米安保条約にも署名した元首相としては、日本外交の基軸たる日米関係は、自分自ら基礎固めをしたが、日中関係は手付かずだ、だから諸君らがしっかりやってくれという叱咤(しった)激励の気持だったのでしょう。
そうした吉田さんの期待に応えて、同期の中で一人だけ中国語の研修を命じられ、台湾に行った人がいます。後年外務省を辞め、亡父の後を次いで政界入りし、防衛庁長官、内閣官房長官や自民党幹事長を歴任した加藤紘一君(故人)です。彼が当時どこまで日中関係の将来を予測していたか分かりませんが、彼なりに期するところがあったようです。2年間の台湾での研修を終えて、最後の1年を米・ハーバード大で過ごすことになったので、一時期小生と一緒でした。
その頃彼がよく言っていたのは「10億の国民を飢えさせず、腹いっぱい食わせるのは、それだけでも大変なことだ。それを共産党は何とかやっている」とのことで、それなりに中国共産党の努力を肯定的に評価していたようです。その後、毛沢東による「文化大革命」で10年近くも中国国内は大荒れに荒れましたが、加藤君の中国観は基本的に一貫していたように思います。
田中角栄首相の訪中(72年)により日中国交が正常化してからは、彼は師匠の大平正芳外相(後に首相)の右腕として対中外交にまい進し、そのため日本国内では一部から「親中派」「媚中派」とみられた時期もありましたが、彼は生涯、日中友好親善のために尽くしたと思います。
私の最初の中国訪問
一方、私自身は、ワシントンからいきなりベトナム戦争中のサイゴン(現ホーチミン市)へ赴任し、そこで大変な目に遭いました(後日詳しくお話する予定)。68年秋に久しぶりに帰朝。本省でいろいろな部署を経験しましたが、直接中国を相手に仕事をする機会はほとんどありませんでした。
日中国交正常化の翌年、本省国連局で地球環境問題を担当していた私は、日本政府からの派遣職員として、新設の国連環境計画(UNEP)事務局に出向していました。事務局本部はスイス・ジュネーブにありましたが、約1年で、国連総会決議により本部がケニアのナイロビに移転したので、私も家族(妻と1歳の長男)とともに移動しました。
そこで在勤中の75年春、所用で中国に出張することになり、妻子同伴で、生まれて初めて中国の地を踏みました。北京空港に着いたときは夕方で、空港ビルは狭く、薄暗く、不安を感じたほど。毛君という若い通訳の案内で、どうにか天安門広場近くの有名ホテル「北京飯店」にチェックインしましたが、特別貴賓室を用意していてくれたのにはびっくり。
その部屋には、直前まで、社会党の成田知巳委員長が宿泊していたとのことで、室内の調度も一流品。食事は本格的な宮廷料理で家族も大満足。おそらく日本の外交官ならとてもこれほど厚遇されなかったでしょうが、国連の幹部職員ということで、至れり尽くせりの待遇でした。
翌朝、まだ暗いうちから外でザワザワという異常な音がするので窓越しにのぞいてみると、なんと物すごい数の人と自転車が、街灯もない暗い中で、まるでウンカのようにうごめいていました。工場や職場へ向かう労働者たちでしょうが、みんな、例外なく黒い人民服、黒い帽子で、黒い自転車に乗っているので、まるでアリの大集団に取り囲まれたような不気味な感じでした。
その後暇ができたので、特別の許可をもらい、市内の名所(天壇、明の十三陵など)を見物したあと、八達嶺から万里の長城に登りましたが、そこでも、大勢の人だかりでした。特に妻と長男は、日本の普通の女性や子どものように赤やピンクの服装でしたが、それがよほど珍しかったらしく、行く先々で大群衆に包囲され、しげしげと見つめられたのには閉口しました。妻も、これほど多くの観衆の目にさらされたことは今まで一度もないと言っていました。当時の中国は貧しく、人々の生活水準は、我々日本人の想像を絶するほどでした。

zhudifeng/iStock
その後中国へは何度か出張しましたが、時には、先方に無理をお願いして、地方を旅行しました。当時はまだ鄧小平による改革開放政策の前で、地方の多くは「非開放地区」として一般の外国人には立ち入り禁止でした。行ってみると、確かに生活環境はひどいもの。あるところでは粗末な宿泊施設で、電気も水道もなく、朝まで万事これで用をたしくれと言って、小型の魔法瓶1杯の水を渡されました。現在の中国の豊かな状況を思うと、まさに隔世の感があります。かつて故加藤紘一君の言ったことの意味がようやく実感をもって理解できたように感じました。
「二つの中国」問題で苦労
その後、1980年代半ばに私は、外務省傘下の日本国際問題研究所(東京都港区虎ノ門)に出向し、約7年間、研究局長兼所長代行として、外交問題に関する調査研究活動を指揮しましたが、同時に「環太平洋協力委員会」の事務局長も務めました。この委員会は、故大平首相の提唱により設置されたもので、首相の盟友の大来佐武郎氏(元外相)が委員長。委員には官学民の大物や著名人が名前を連ねていました。
同じような委員会は、アジア太平洋地域の主要国にできており、その上に「太平洋経済協力会議」(PECC)という大きな組織があり、毎年いずれかの加盟国で総会が開催される仕組み。たまたま88年は日本の当番で、大阪で開催されることになっていたので、私はその準備に没頭していましたが、一つ大きな問題に直面しました。それは、それまで中国を代表していた台湾に加えて、中国(PRC)を正式メンバーとして加盟させるかどうかで、いわゆる「二つの中国」問題がもろに絡むので、調整に苦労しました。大来委員長と私は手分けして北京と台北に何度か出向いて交渉した結果、台湾は国家としてではなく、「台北」ということで引き続き参加するという線で何とか落ち着きました。
ところが、大阪会議の直前に各国首席代表が東京で集合し、竹下登首相(当時)に表敬訪問することになり、そろって首相官邸に行ったところ、各国代表を1人ずつ首相に紹介する段になって、中国代表が「台湾代表と一緒では困る」と、暗に台湾代表を列から排除してほしいと言い出しました。結局、台湾代表は最後に、あたかもオブザーバーのような形で紹介することでかろうじて一件落着しましたが、この時ほど、中国が原則や面子に強くこだわる国だということを痛感させられたことはありません。
この原則とメンツへの強いこだわりは、古来中国外交の特徴であり、今後の同国との交際においては特に留意すべき点だと思われます。
(その2に続く)
(2021年2月8日付東愛知新聞令和つれづれ草より転載)
編集部より:この記事はエネルギー戦略研究会(EEE会議)2021年2月8日の記事を転載させていただきました。オリジナル記事をご希望の方はエネルギー戦略研究会(EEE会議)代表:金子熊夫ウェブサイトをご覧ください。