外交評論家 エネルギー戦略研究会会長 金子 熊夫
前回の続きですが、私が、外務省傘下の日本国際問題研究所の所長(代行)をしていた1980年代半ばの思い出の中で、もう一つ、どうしても忘れられない出来事があります。
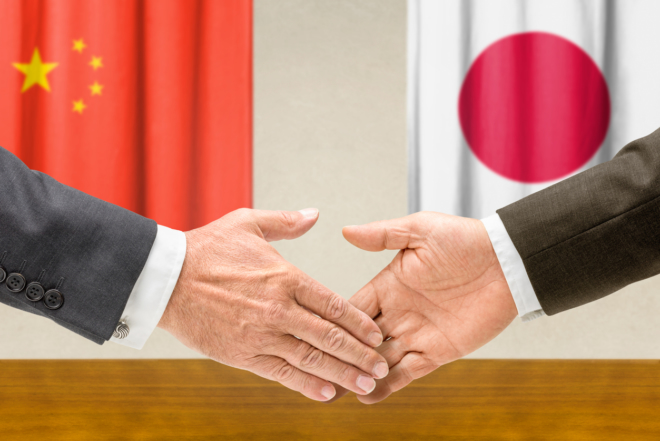
Zerbor/iStock
若い中国人研究者の不審死
かねてから日中の学者、研究者や若い外交官同士の交流促進を重視していた私は、上海の国際問題研究所を訪問した折、そこで若い優秀な日本研究者S君を見つけ、日本に特別研究員として招聘しました。日本語は完璧に近く、しかもハンサム、今流に言えばイケメンで、研究所の女性職員たちにも人気がありました。S君を教師にして中国語会話クラブを開き、私も参加しました。時々拙宅にも呼んで、家族ぐるみで付き合っていました。川崎市の多摩川沿いの彼の自宅アパートに招待されたときは、新婚早々の美人の奥さんの手料理をご馳走になったこともあります。
昨今の日本には珍しいほど礼儀正しく、研究心も旺盛で、将来必ず日中友好に役立つ有為な人材だと期待していました。ところが、来日して2、3年経ったある日突然交通事故でS君が亡くなったとの知らせを受けました。ちょうど私は海外出張で東京にいなかったので、その時の状況は正確には把握できませんでしたが、その死因には俄(にわか)に納得しがたいものがありました。後から聞いた情報を総合すると、単なる突発的な事故死ではなく、どうも異常なものが背後にあったと思われてなりません。一説によると、奥さんは中国共産党員で、いわばお目付け役のような人だったらしいとか。似たような話は他でも耳にしたことがあるので、やはりそうなのかと思いますが、確証がないまま、この件は未解明の不審事件として私の記憶の中に鮮明に残っています。かけがえのない人材を失ったことは今でも残念です。
他方、前回触れたように、1988年に、私が事務局長として万事取り仕切った大阪での太平洋経済協力会議(PECC)は非常な盛況で、これが契機となって翌年、同会議は政府レベルに格上げされ、「アジア太平洋経済協力会議(APEC)」として再スタートを切りました。中国はPECCのメンバーであったことから自然にAPECの正式メンバーとして迎えられました。中国のPECC加盟実現に一役買ったと自負する私も、苦労した甲斐があったと喜んでいました。
日中蜜月時代の思い出
今思えば、この時代は1972年の国交正常化以後で、日中関係がベストの時代だったと思います。建国第一世代の毛沢東、周恩来が相次いで死去(1976年)し、文化大革命もようやく終息。代わって復権した実力者・鄧小平が、改革開放政策を打ち出し、開明的な胡耀邦が中国共産党の総書記、趙紫陽が首相に就任。さらに、日中平和友好条約調印(1978年)で日中関係は一気に蜜月時代を迎えました。
この時期、私は公務で頻繁に訪中しましたが、行くところはどこでも大歓迎を受け、私もすっかり中国贔屓(びいき)になりました。行く先々で即興で我流の漢詩を作り、酒席では日本式に吟詠して拍手喝采をもらったこともあります。北京では、旧知の錢其琛氏(後の外相、副首相)の好意で、国賓級の賓客しか招待されないとされる中南海の釣魚台での晩餐会にも招かれたりしました。他方、東京・世田谷の拙宅には、中国大使館のお歴々や訪日した中国の要人がよく遊びに来てくれました。
余談ながら、丁度その頃、作家の故山崎豊子は、中国残留孤児を主人公とする小説「大地の子」のための取材で訪中していましたが、それまで彼女の取材受け入れを頑なに拒否していた中国当局は、胡耀邦総書記直々の好意的計らいで、中国国内を自由に旅行し取材できたということです。
当時北京で大使をしていた故中江要介氏(私が本省条約局と旧南ベトナム日本大使館で直属の上司として仕えた大先輩)から直接聞いたことですが、山崎豊子自身も、「大地の子」のあとがきでそのことをはっきり書いています。特に印象的なのは、「中国を美しく書かなくて結構、中国の欠点も暗い影も書いてよろしい、それが真実であるならば、真実の中日友好になる」と励まされたということで、総書記の人間的魅力と懐の深さが如実に感じられるエピソードです。
瀋陽での衝撃と癒し
ちなみに、この残留孤児問題については、その後、私自身が瀋陽(旧満州の奉天)を訪れた時のことも書いておかねばなりません。周知のように、瀋陽郊外の柳条湖は、1931年9月18日にそこで旧日本軍による鉄道爆破事件が起き、日中15年戦争勃発の契機となったところですが、その現場に、「9・18歴史博物館」が建っています。建てたのは、胡耀邦の後を継いだ江沢民政権時代で、江直筆の「勿忘国耻」の4文字が正面の外壁に大書されており、館内には、日中戦争時代に日本が犯したとされる様々な残虐行為が蝋(ろう)人形や現場写真などを使って生々しく展示されています。
中国人の対日反感を殊更煽るようなこれらの展示物の羅列ですっかり気分が滅入っていたところ、出口近くに等身大よりやや小ぶりの、三人の親子の銅像がひっそり置かれているのを発見しました。台座には、「感謝中国養父母碑」と書かれており、元残留孤児だった日本人関係者が贈ったものだということが明記されています。これを見て、私の気持ちがどれだけ癒されたかは言うまでもありませんが、日中関係の長く複雑な歴史を振り返るとき、忘れてはいけない1つの視点であると強く感じました。
胡耀邦時代について、ついでにもう一つ特筆しておきたいことは、彼が1983年に来日した際に、日本の青年3000人を中国に1週間招待するプランを披露して日本側を驚かせたことです。また、中曽根康弘首相(当時)とは、「兄弟のように非常に親しい仲だった」と自ら述懐しており、来日中には中国の首脳として唯一広島の原爆ドームなどを視察しています。このような指導者が1980年代の中国に実際にいたということは記憶しておくべきことだと思います。
当時、私も、おそらく多くの日本人と同様、日中友好関係はこのまま胡耀邦=趙紫陽体制の下で順調に発展し続けるものと楽観していました。そして、かつて故加藤紘一君がよく言っていた通り、将来日中と米国は、二等辺三角形ではなく、正三角形のような、望ましい関係に成熟して行くであろうと期待していました。
天安門事件ですべてが一変
ところが、胡耀邦の政治改革は、保守派の強烈な巻き返しに会い、徐々に勢力を失い、ついに1987年に総書記を解任され、失脚。「罪状」は「ブルジョア自由化」に寛容すぎたためとされています。その後失意のうちに病死(1989年4月)。そして、彼の死を悼む学生や市民たちは北京の天安門広場に集まって大規模な追悼デモを行いますが、それが引き金となって、2カ月後、天安門広場事件が突発します。

luxizeng/iStock
この事件のことはここで詳しく説明するまでもないと思いますが、とにかく、この事件を契機として、それまで極めて友好ムードに包まれていた日中関係は180度変化します。
この事件で、西側先進国は一斉に対中制裁を発動し、日本も同調を求められましたが、日本政府は、制裁は逆効果を生むだけで、一層中国政府を頑なにする、むしろ中国を国際社会の責任ある一員として成長して行くように誘導するべきだとして、対中経済協力(第3次円借款)を継続する道を選びました。平成天皇・皇后(現上皇・上皇后)の訪中計画についても、国内に様々な意見がありましたが、天安門事件の3年後、1992年10月に実現させました。
もし日本も対中制裁していたら
こうした30年前の日本政府の一連の判断が正しかったかどうかについては、様々な見方があり、現在でも議論が分かれるところです。あの時欧米諸国と一緒になって徹底的に中国を叩いておくべきだったという意見もあります。もしそうしていたら、中国の国際社会での地位は低下したままで、その後の飛躍的な経済発展は不可能だった、少なくとも20年か30年は遅れていたかもしれません。
近年の中国共産党の態度、とりわけ香港の民主化運動弾圧、国内の少数民族の処遇、東・南シナ海での強権的態度、さらに、前回の拙稿の冒頭で触れた新型コロナウィルス感染問題への取り組み方や、えげつない「戦狼外交」等々を考えると、30年前の日本の対中外交は、果たして妥当であったと言えるのかどうか。厳しい歴史的再評価を免れないと思います。
他方、私自身は政府のこの時の決定に直接加わっていたわけではありませんが、当時の外務省の責任者たちの心情には理解できる部分があるとも感じています。これらの点は、今後の日中関係を考える上で避けて通れない重要な問題点であると思いますので、後日、本欄で深く検討してみたいと考えております。
(その1はこちら)
編集部より:この記事はエネルギー戦略研究会(EEE会議)2021年3月22日の記事を転載させていただきました。オリジナル記事をご希望の方はエネルギー戦略研究会(EEE会議)代表:金子熊夫ウェブサイトをご覧ください。














