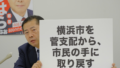連日名演が続いているフェスタサマーミューザの7日目は読響と鈴木雅明さんによるロシア・プログラム。来日が叶わなくなった山田和樹さんはチャイコフスキーの交響曲第2番《小ロシア》とラフマニノフの交響曲第2番をプログラムミングしていたが、鈴木さんは前半をボロディンの交響曲第2番に変更し、後半のラフマニノフの2番は予定通りの演奏となった。
2番&2番のロシアものがそのまま実現されたのは、偶然だったのだろうか。前半のボロディンからパワフルな読響サウンドがミューザの壁を打ち鳴らした。ちょっと大仰な感じのするイントロから躍動的で面白い音楽で、大地を踏みしめて踊るコサックの靴音を想像した。木管の素朴な愛嬌、低弦の濃い口の語り、金管の勇ましさにわくわくした。医者で化学者だったボロディンは温厚で陽気な人物で、チャイコフスキーと同じ53歳で急死したが、亡くなる直前まで友人たちと歌い踊り(謝肉祭の週間だった)上機嫌だったという。
偶然にも、最近ボロディンの『弦楽四重奏第2番』とラフマニノフの『ピアノソナタ第2番』をよく聴いていた。ボロディンの2番のカルテットは天上的すぎる。もしかしたら一番好きなカルテットかも知れない。2番シンフォニーの初演は不評だったが、改訂版は好評で人気作となった。
鈴木雅明さんの指揮は吸い込むときの息が3階席まで聞こえてくるほど情熱的で、ロシア音楽には何より真剣さと体力が必要なのだと思われた。そのパワーの中に、楽譜と向き合い奥の奥まで入り込む「不動」の姿勢も見えた。読響の真剣さと、細部まで愛情に溢れた演奏が素晴らしかった。
後半のラフマニノフ2番では、更にロシア音楽の本質的な核心を聴かせた。ラフマニノフは貴族の出身で、革命を避けて後半生はアメリカに亡命した。交響曲第2番は亡命前にドレスデンで書かれたものだが、この前も後も、結局ラフマニノフは徹頭徹尾「ロシア的音楽」を書いた。ラフマニノフの芯にあるのはグリンカに始まる西洋化されたロシア音楽より前の、古い古い音楽である。ストラヴィンスキーは別の方法でこれを行ったが、ラフマニノフはロシア正教の伝統的な宗教音楽を研究し、近代以前のロシアの精神を探し求めた。
ロシアの芸術の中心にあるのは、とても透明で精妙なエッセンスで「過ぎたときを再びともに生きる」という感覚である。
1楽章の始まりは夢のようだが、夢を見ているという意味ではなく、過去に生きてきた膨大な先祖の眠りに触れようとする、儀式の始まりの気配が感じられる。シンフォニーがこのように始まるのは、珍しいようにも思う。「これから夢の大きな塊に触れていく」という、覚醒から集合無意識への下降をイメージした。
ラフマニノフのピアノソナタ2番の、全てが粉々になってしまう感覚が、シンフォニーの2番にもあって、それが美とか懐かしさに繋がっていることがいつも魔法のように思われる。ラフマニノフの問いとは、つねに「私は一体何者か」ということである。アイデンティティの探索が音楽の中で行われている。プーシキンを読み、ロシア語を話し、チャイコフスキーを敬愛するラフマニノフにとって、その答えは「私はひとりのロシア人である」ということだった。
国家に対して複雑な想いを抱いている人間は、「私の祖国は…」と語り出してはいけないのだろうか。ここのところ、誰もが日本を悪く言う。太った人が自分のことを太っているというのはいいが、他人から言われたら嫌だろう。日本人が日本を悪く言うだけでなく、世界中の結構な数の人々が日本を悪く言う。そのことに、日本人全員の心が麻痺している。同じように自分の国を平気で悪く言う。ラフマニノフがどこにいてもロシア人であったことを思い、この不条理に心が割れそうになった。
宗教でもオカルトでもない。膨大な数の祖先が自分の生きている大地に眠っている。自己卑下し、ここまでアイデンティティが不確かになってしまった日本とは何なのだろう。政治が悪いからといって外国に逃げたとしても、「自分自身」はどこへ行っても不動の何かであるはずだ。
この一連の感染症の問題で「国家」は明らかに存続不能な機能になっている。何も政治論を語りたいわけではない…日本という方法、美意識の中に影のような救いを求めるのもいいかも知れない。しかし、もっと生々しい「私」が、ラフマニノフの音楽に刺激され現れるのを実感した。
読響はこの夏ますます絶好調で、先日の飯守さんから1週間も経っていない演奏会だったが、骨格の大きな勇壮なロシア音楽は見事というよりほかなかった。ラフマニノフはメランコリックで美しい旋律を書いただけではなく、誰よりも優れた運動感覚を持っていて、2楽章と4楽章の律動感には独特のものが波打っている。新しいもの好きのラフマニノフはメルセデスやブガッティを乗りこなし、スピード狂だった。ヘリコプター開発のために米国の企業で10万ドルの寄付をしている。自分でも飛行運転してみたかったはずだ。
有名なアダージョの後の戦闘的な(?)アレグロ・ヴィヴァーチェは、映像で見ると若い指揮者でも体力が足りなくなってへろへろになっていることがある。鈴木雅明さんの凄味が爆発したのがこの4楽章で、書かれた作品が18世紀のものであろうと、20世紀のものであろうと、そこに大きな炎を吹き込んでみせるマエストロの精神力に驚かされた。この日の音楽は3日、4日経っても自分から離れることはなく、電車の中でも、ワクチン会場でも、焼き鳥の匂いがする街の中でもずっと頭の中にあった。「自分は一体何者だろう」という作曲家の洞察は、今の自分にとってもリアルなものだった。
編集部より:この記事は「小田島久恵のクラシック鑑賞日記」2021年7月31日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は「小田島久恵のクラシック鑑賞日記」をご覧ください。