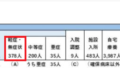8月13日に開幕した第16回バレエフェスティバルのAプロの最終日を観た(8月16日)。会場は東京文化会館。2021年は困難な状況下での開催となったが、ガラ公演の中止などにも関わらず、例年に比べて一層パワフルに感じられた「祝祭」だった。
カンパニーによっては長期間劇場がクローズしているため、ダンサーにとって久々に日本で踊れることは大きな「生きる喜び」だっただろう。1976年から続くこのフェスティバルでは「超」がつく一流ダンサーが東京に集結するが、その一流ということの意味を改めて考えた回でもあった。
「ゼンツァーノの花祭り」で登場したマチアス・エイマンを見て、とてもシンプルに「彼は本当に心から踊っている」と思い、そのことに「一流とはこういうことか」と思った。技術にもまして心が伝わってくる。個性とは心だ。そう感じさせてくれるダンサーのひとつひとつの動きは、見る者の心にも深く刺さり込む。ほとんど音のしない着地や、気品あるブルノンヴィル・スタイルの下半身に「オペラ座のダンサーは本当に見事だ」と思いつつ、相手役のオニール八菜さんを優しくサポートするマチアスの穏やかな表情に、より感動した。
オリガ・スミルノワとウラジーミル・シクリャローフの「ロミオとジュリエット」一幕のパ・ド・ドゥは、スミルノワのこの世のものではない宝石のような美しさに釘付けになった。スミルノワ(ボリショイ)とシクリャローフ(マリインスキー)の共演というのは、ロシアではよくあるのだろうか? 1940年初演のラヴロフスキー版は厳かな演劇性があり、二人が踊るロミオとジュリエットは神話的な人物に見えた。シクリャローフがスミルノワを心から尊敬して「今日でこの踊りが最後になるのが名残惜しい」と思っているように感じられた。ロミオの跳躍は高く、宝物のようなジュリエットへの愛が、鳥のように軽やかに身体を飛ばせるのだろうと思った。
職業柄、このフェスに登場するダンサーの半数に、過去に様々な形でインタビューしていた。そんなこともあって「彼らは心が素晴らしいから踊りが素晴らしい」と思うのかも知れない。気さくで優しいドロテ・ジルベールが、フリーデマン・フォーゲルと踊った『オネーギン』の第1幕のパ・ド・ドゥは、それぞれオペラ座バレエ団とシュツットガルトバレエ団の来日公演で彼らの踊りを見てきた。別の場所で役を掘り下げてきた二人が、東京で共演している様子は奇跡のようであり、一秒たりとも見逃せなかった。
ダニール・シムキンの『白鳥の湖』の第1幕のソロは、久しぶりに観るシムキンに興奮しているうちにあっという間に終わってしまった。シムキンにも昔取材した。今も幸せな日常を送っているのだろうか。2010年のエトワール・ガラで初めてインタビューしたマチュー・ガニオは、あれからずいぶん大人になった。バランシンの『ジュエルズ』から「ダイヤモンド」を踊ったが、アマンディーヌ・アルビッソンと白と銀の衣裳で並ぶと、オペラ座の最も理想的なカップルに見える。アルビッソンは、バレエの神の世界からの贈り物のようなバレリーナで、あまり長くない脚もふくめて理想的なフィギュアをしている。「アマンディーヌは才能だけで踊っている」と言っていた方がいたが、なるほどそうかも知れない。マチューは、そうでもない。サラブレッドだけど、故障も多く悩んでいた時期も長かった。ただ美しいだけでなく、人間味を感じる。それでも、彼の優しい心が生きているのはやはりバレエの美の世界なのだ。二人が踊る「ダイヤモンド」は、日常とは別の天上界のバレエだった。
あまりに素晴らしいパ・ド・ドゥは、ダンサー同志が本当に恋をしているように見える。ロミジュリやマノンは特にそうだ。ロイヤル・バレエの金子扶生さんとワディム・ムンタギロフの「マノン」は、小悪魔マノンに夢中になるデ・グリューの心理が、見事な演劇性とバレエの技によって表現された。ロイヤルのダンサーが踊るマクミランは、特別なオーラがある。
アレッサンドラ・フェリとマルセロ・ゴメスの「ル・パルク」では、ダンサー同志の根強い信頼関係と、魂の絆を見ているようだった。二つの身体が踊っているというより、二つの魂が踊っていた。永遠の運動だった。このダンスのためのモーツァルトのピアノ協奏曲を、ピアノ(ピアニストの菊池洋子さんがこの曲をはじめ数多くの演目で名演奏)とオーケストラの生演奏で聴けたことで、プレルジョカージュの「コンテンポラリー」も新しいニュアンスをともなって観ることができた。
エカテリーナ・クリサノワとキム・キミンの「海賊」は、可愛らしく可憐なクリサノワの魅力と、若き王将のようなキミンの華麗さが客席を沸かせた。バリエーションからバリエーションに移るとき、キムが「これは、本当に素晴らしい舞台だ」という表情になり、さらに気合を入れた跳躍を見せてくれたのは感動した。ダンサーが感じている感動は、客席にダイレクトに伝わってくる。ダンサーが舞台で幸福であることが、客席にいる自分の感動だ。
ユーゴ・マルシャンがBプロのみの出演になったため、フリーデマンは『オネーギン』の1幕と3幕を別のダンサーと踊ることになった。カンパニーの仲間であるエリサ・バデネスは気心が知れているはずだが、心理的には1幕より3幕のほうが激しい。バデネスのタチヤーナはますます成長していて、フリーデマンも前回の来日公演以上にオネーギンの屈折したパーソナリティに溺れていた。この役を踊ることに深い感謝を感じているのかも知れない。
初日から大きな話題となっていたスヴェトラーナ・ザハロワの『瀕死の白鳥』は、舞台にいるザハロワがもっと若いダンサーに見え、最初は別人かと思った。ロシアバレエの女王は、驚くほどあどけない姿で、命絶えゆく白鳥の最後の数分を見せたのだが、確かに「人間」というより「霊」の表現であった。少し前にルグリとのガラで観たスミルノワの「瀕死」も素晴らしかったが、この二人のカリスマ性は今最もバレエファンを熱狂させるものではないだろうか。
トリを飾ったマリーヤ・アレクサンドロワとヴラディスラフ・ラントラートフの『ライモンダ』は、アレクサンドロワの大御所感が素晴らしく、本人もかなり聡明でユーモアのある人なのだが、舞台に「圧をかける」ような踊りが面白かった。ラントラートフは夏っぽいいつもより短いヘアスタイルで、初めてボリショイで取材した8年前より大人の顔つきになっている。ラントラートフもアレクサンドロワも、才能ある若手から追い上げられて大変なのかも知れない。でも「私たちは私たちなのよ」とラントラートフに発破をかけているのは彼女なのではないだろうか。スターやメジャーや表現者が凄いのは、継続して芸を見せていることに尽きる。彼ら二人のパ・ド・ドゥには、バレエの世界で生きることの様々なドラマが見えてくる。まったく素敵なカップルなのだ。
コンテンポラリーは少な目だったが、自分自身がどんどん古典好きになっているので満足感が大きかった。菅井円加さんとアレクサンドル・トルーシュの「パーシスタント・パースウェイジョン」(ノイマイヤー振付)、ジル・ロマンの『スワン・ソング』(ジョルジォ・マディア振付)はその中でも新鮮なコンテンポラリーの魅力を見せてくれた。
オーケストラは東京フィル。指揮はワレリー・オブジャニコフとロベルタス・セルヴェニカス。「オネーギン」や「マノン」やその他のバレエでも、シンフォニー・オーケストラが奏でるとバレエのドラマが格別になると実感した。オーケストラとマエストロの功績は大きい。
(余談だが、バレエ・フェスの指揮者といえば、バックステージでルグリの取材をした2000年に、ミッシェル・ケヴァル氏がダンサーたちから大人気だったのを思い出す。第一回から第10回まで振られていたが、記者の私にまでニコニコ話かけてくださって、上機嫌で素敵なマエストロだった)
フィナーレでは、オリンピック閉会式に負けない花火が舞台に映し出され、ホール全体にも投影された。花火の音は止まらず、これはまるで火薬事故…と大笑いしてしまったが、次から次へと光を絶やさぬように飛び出す花火に、やがてじんわりしてしまった。「逆境にこそ、祝祭が必要」ということなのだろう。19日からBプログラムもはじまる。

出演ダンサーの幕に彩られた東京文化会館のホワイエ
編集部より:この記事は「小田島久恵のクラシック鑑賞日記」2021年8月18日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は「小田島久恵のクラシック鑑賞日記」をご覧ください。