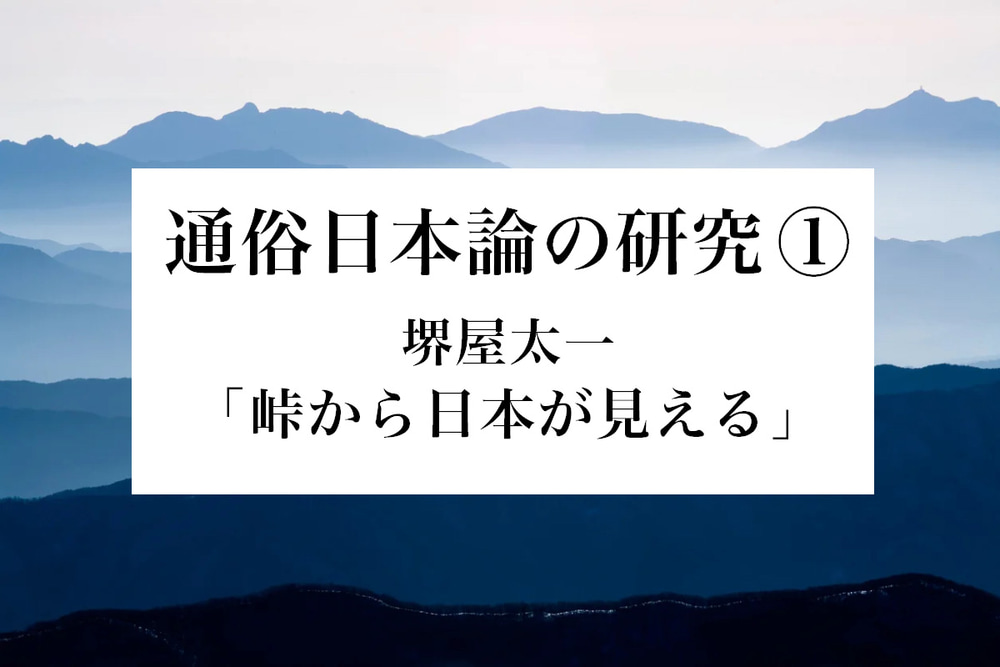本連載では、作家・評論家などが執筆した通俗的な日本論の分析を行っていく。ファクトチェックによって間違いをあげつらうのではなく、なぜそのような日本論が当時発表されたのかという、社会的な背景についても考察していきたい。

VDCM image/iStock
俗に「プレジデント史観」という言葉がある。『プレジデント』などのビジネス誌にしばしば載る、歴史の教訓をビジネスに活かそうという記事の総称である。「織田信長に学ぶリーダーシップ」「坂本龍馬に学ぶ交渉術」といった類の記事を目にした方は多いだろう。
こうした記事がいつ頃から量産されるようになったかはまだ調べていないが、元祖「プレジデント史観」論者と言えば、堺屋太一になるのではないか。説明するまでもないが、堺屋太一は通産官僚から小説家・評論家に転じ、以後も経済企画庁長官に就任したり橋下徹を支援したりするなど政界にも深く関与した、多彩な活動で知られた知識人である。大阪万博・沖縄海洋博などを担当した異能の通産官僚だったこともあり、経済評論・社会評論関係の著作を中心に発表しているが、歴史評論(史論)も多く発表している。
今回取り上げる堺屋太一の著作は、昭和57年(1982)に刊行された『峠から日本が見える』(実業之日本社)である。同年、NHK大河ドラマ『峠の群像』が放送されているが、同作は堺屋の同名小説を原作としている。というより、堺屋は最初から大河ドラマの原作小説の執筆をNHKから依頼されていたようである。
堺屋の『峠の群像』は、「忠臣蔵」事件、すなわち赤穂浪士討ち入り事件を通じて元禄時代を描いた小説である。この小説の解説本として発表されたのが歴史評論『峠から日本が見える』で、堺屋の元禄時代論が全面的に展開されている。
なぜ堺屋は元禄時代に注目したのか。それは、1980年代を迎えた日本と、元禄日本は類似していると考えたからである。元禄時代には表面的な繁栄の裏で危機と転換が迫っていた。江戸幕府は農本主義から重商主義への転換という改革に踏み切れず、「峠」を越えることに失敗し、経済は下り坂に向かっていった。今の日本も石油価格の高騰、日米貿易摩擦、財政赤字など同様の困難に直面している、と堺屋は警鐘を鳴らしたのである。
本書の論点は多岐にわたるが、最大の特徴は5代将軍徳川綱吉に仕えた経済官僚である荻原重秀の貨幣改鋳を極めて高く評価した点だろう。通説では、荻原は貨幣の質を落とす(金銀の含有量を減らす)ことで経済を混乱させたと批判されてきたが、堺屋は貨幣改鋳を画期的政策として再評価し、荻原を「天才」と絶賛する。
もっとも、荻原の貨幣改鋳への高評価は、堺屋の独創ではない。歴史学者の大石慎三郎は著書『元禄時代』(岩波新書、1970年)で、「拡大した経済体制下にある元禄時代には、当然いままでより多くの通貨量を必要とした。そしてそれを満たして経済を円滑に運転させることこそ、為政者の責務であった。元禄の改鋳で幕府が通貨量をふやしたということは、このような意味から、ほめられて然るべきことで、けっして非難さるべきことではない」「当時日本の金銀鉱山はすでにほとんど枯渇しており、また幕府の備蓄金銀も使い果たしているという現実をふまえ、しかも通貨量をふやすという課題を満たすためには、それ(筆者注:貨幣改鋳)以外に方法がなかったのではないか」と指摘している。
けれども堺屋は、大石よりも積極的に貨幣改鋳を評価し、荻原を礼賛している。「荻原には、財政を経済政策として考える発想があった。17世紀の末にこうした考えの持主が現われたのは誠に驚異的であり、当時の西欧の経済学に比べても数等進んでいる」とまで述べているのである。
実のところ、荻原重秀が通貨需要の増大に対応するために貨幣改鋳によって通貨供給量を増やしたという主張を裏付ける、信頼できる史料は乏しい。荻原の貨幣改鋳の最大の目的は、出目(改鋳による差益金)による幕府財政の改善である、という見解が現在では一般的である。結果的に景気を刺激しただろうが、意図的にインフレを狙ったかどうかは定かでない。
ところが、堺屋説は批判を受けることなく大きな影響力を持ち続け、特に現代のいわゆる「リフレ派」に継承されている。たとえば経済評論家の上念司氏は、貨幣改鋳は「デフレを脱却し、マイルドなインフレを実現するための有効な手段」であると説き、荻原重秀は「管理通貨制度の本質」を理解し「極めて先進的な金融理論を持っていた」と激賞している(『経済で読み解く 明治維新』KKベストセラーズ、2016年)。作家の百田尚樹氏も『日本国紀』(幻冬舎、2018年)で「ケインズより240年も早く現代のマクロ経済政策を先取りした日本人」と記している。
とはいえ、堺屋の解釈と、現代のリフレ派の解釈は同じではない。堺屋は、幕府が経費削減・増税の努力を怠り、安易に貨幣改鋳を繰り返したため、悪性インフレに陥った、と批判する。その後、新井白石や徳川吉宗の急激な金融・財政引き締め(インフレ退治)によって大不況に陥ったと説く。バブル経済とその崩壊を予測するのかような驚くべき先見性である。
一方で上念氏は貨幣改鋳による激しい物価高騰を否定し、積極財政は常に正しいと宣言する。1970年代の大石、1980年代の堺屋、2010年代の上念氏と、時代を経るごとに貨幣改鋳の万能性がどんどん強調されていったのである。アベノミクスという壮大な実験が早くも忘れられつつある2020年代、荻原重秀はどのように再評価されるのか、興味が尽きない。