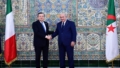新国のレパートリーであるジョナサン・ミラー演出の『ばらの騎士』。4回公演の千穐楽の4月12日を観た。先の3回の公演をすでに鑑賞したオペラ・ファンたちの間では、サッシャ・ゲッツェルの指揮と東フィルがとんでもなく素晴らしく、ゲッツェルの指揮姿はカルロス・クライバーのレジェンド(1994年のウィーン国立歌劇場での来日公演)を彷彿させるとの噂だったが、噂は真実で、ゲッツェルのお陰でかつてないほどの熱気と密度でこのオペラを鑑賞したという感想。今まで聴いた「ばら騎士」の中で、ダントツのベストだった。
ゲッツェルとは数年前、楽屋で少し話したことがあった。当時音楽監督を務めていたイスタンブール・フィルが現地で紛争に巻き込まれたので、オケの皆が心配で仕方がないと泣きそうな表情だった。指揮者に腹黒い人と胸が白い人がいるとしたら、「この人はシロのような気がする」と咄嗟に思ったものだ。1970年生まれなので、今年52歳。プロフィールを見ると、あまりがつがつと出世を追い求めるタイプではなく、それぞれの現場で真摯なプロフェッショナリズムを発揮する職人肌の人のように思える。

新国立劇場「ばらの騎士」より
撮影:寺司正彦 提供:新国立劇場
キャストは元帥夫人のアンネッテ・ダッシュ以外、予定されていた外国人キャストはすべて日本人歌手に変更になったが、いい稽古だったのか、1幕から歌にも芝居にもゆとりと香りのようなものがあった。
A・ダッシュは10年前と全く同じ若々しい美貌…と言うと嘘になるが、元帥夫人が似合う憂いのあるマダムになっていて、躁鬱の激しい複雑なキャラクターを濃い演技で演じていた。オクタヴィアン小林由佳さんのズボン役は絶品だが、何度も演じているオクタヴィアンの中でも、この演出ならではのイノセントで「若さゆえに何もコントロールできない」感じがよく出ていた。
オクタヴィアンは、まだ1幕では自分が何者かわかっていない。愛する元帥夫人は、さっきまで上機嫌に甘えてきたかと思うと、ヒステリックに振り払おうとしたり、不吉なことを口走ったり、情緒不安定のカタログで、とても10代の男が手に負える代物ではない。「僕なんかのどこがいいの?」とオクタヴィアンは年上の愛人に聴く。「それゃあ、若くて可愛いいだけで何も知らないところがいいのよ!」と心の中で答えてしまう自分がいる。オーケストラの緻密で複雑な音楽に、歌手は少しも出だしを間違えずについていく。
元帥夫人が最もたくさん歌うのは1幕だが、夥しい音符を歌いながら演技も完璧で、愛人のオクタヴィアンを部屋から追い出す場面では、異様なほどの緊張感が走った。家臣に呼び戻させようとするが、彼は馬に乗って行ってしまった…その後に元帥夫人が一人で煙草を吸うシーンがたまらない。演出家は2年前に亡くなっているが、この煙草のシーンは秀逸だと思う。
1幕から大活躍のオックス男爵は、わが国が誇るバス妻屋秀和さんが好演。セクハラ満載の無神経のカタログのような役だが、「貴族独特のおおらかな愉快さとユーモア」も感じさせなくてはならず、コミカルな中に僅かな英雄性のようなものも隠し持っている感じ。作曲家は最初、オックスをオペラのタイトルにしようとしたという。バッソ・ブッフォの名役の中でも天辺級の難しい役だ。妻屋さんは実に素晴らしく、たくさんのアイデアを盛り込んで演じていた。最終日は、主役に見えた。

新国立劇場「ばらの騎士」より
撮影:寺司正彦 提供:新国立劇場
トータル4時間10分のオペラには二回休憩が入るが、1幕のあとの2幕はテクスチャー的に全く性格の異なる音楽で、1幕はえんえんと元帥夫人のメランコリーが基調になっているため、雨雲のようにメロディとメロディがつながって灰色の天蓋を作り上げている。2幕は、オクタヴィアン登場のシーンの音楽の「派手さ」に驚愕した。音量のレベルが一気に上がり、天変地異が起こったような、英雄的で輝かしいサウンドが響き渡った。ゾフィーがオクタヴィアンを一目見て恋に堕ちた瞬間の音楽で、あのようなまばゆい音楽をまとって現れた男性を、女性は愛さないわけにはいかない。こんな音を出すピットのゲッツェルに愛を感じた。
ゾフィーの安井陽子さんは10代の乙女にふさわしい透明なコロラトゥーラで恋のときめきを歌い、姿も可愛らしかった。侍女のマリアンネを歌う森谷真理さんは二期会公演では元帥夫人を歌っていたが、そう思って見るからか、この役も面白そうに演じられていた。
ゾフィーの父ファーニナルはバリトンの与那城敬さん。10年前に見た『道化師』の美男子シルビオがまだ記憶から抜けないが、17歳の娘を持つ父親は、だいたいああいう外見だろう。なぜかイタリア俳優のジャンカルロ・ジャンニ―ニを思い出していた。成金の金持ちで貴族の称号がなんとしてでも欲しい打算家の父だが、最終的には3幕でオックスの不道徳を制裁する。与那城さんの雷親父っぷりも魅力的だった。
ゲッツェルの指揮姿は最初から最後まで全部見えた。音楽を全身で作り上げていて、どれだけ譜面にかじりついて研究したのか、指揮者にとって分厚いスコアが恋人なのではないのかと思うほどののめり込み方で、オペラを指揮することの「熱さ」には、これくらいのものがあってちょうどいいと思った。歌劇場でのポストがあるのかと思っていたら、まだないのがとても意外だった。しかるべきところに決まれば、英国ロイヤルオペラとパッパーノのような蜜月が続くのではないかと考える。

新国立劇場「ばらの騎士」より
撮影:寺司正彦 提供:新国立劇場
3幕の前半はドタバタ。メイドに扮装したオクタヴィアンがオックスをコテンパンにする。オックスの私生児たちがきゃあきゃあと乱入する。それでも未練がましい助兵衛男爵に「ものごとには終わりがあるのです」と強く制した元帥夫人は、どんな英雄より勇ましくカッコよかった。アンネッテ・ダッシュはゆうに170センチを超える見栄えのするスタイルなので、黒いスーツドレスと大きなつばのある帽子がよく似合う。
このオペラでは、どの人間関係も破綻している。1幕の元帥夫人とオクタヴィアンからそうだ。愛し合っていても次の瞬間に夫人はヒステリックになり、「あなたまで他の男たちと同じようなことを言うの?」と怒り始める。オックスは最初から他人のデリカシーなど理解しようとしない。ファーニナルは嫌がる娘を力づくで嫁がせようとする。「人と人との相互理解はこんなにも難しい」ということを骨の髄まで学ばせてくれる、こんぐらかり塩梅なのだ。モーツァルトだってここまでの人間の心の葛藤は書けなかった。
唯一の和解は、元帥夫人とゾフィーの間にある。それはオペラ史上まったく新しい「女性の寛大さ」の発明で、そこで美しい大団円へ流れ込む。「一目で好きになったのね」とマルシャリンがゾフィーに語り掛ける場面で、一気に泣けた。オクタヴィアンはあの若さで、一人の女に未練を感じながらも新しい女のもとへ行くという経験をする。作曲家が葬式の時に演奏して欲しいと遺言に残した元帥夫人、オクタヴィアン、ゾフィーの三重唱は、このキャストでは感動的すぎた。
初演では『ばらの騎士号』まで鉄道に現れて優雅なお客たちがこれを見るために集まったが、そのときも大成功だったという。悔しいほどに、女心のオペラなのである。
『ばらの騎士』が初演されたのは1911年で(劇そのものは18世紀が舞台らしいが)ジョナサン・ミラーは1911年の風俗を女性のファッションの細部やセットの美術に盛り込んでいる。初演に寄せた2007年のインタビューでも、演出家20世紀初頭の大戦前夜の時代について触れていて「オクタヴィアンは戦死し、ゾフィーは未亡人になるでしょう」と語っている。
ヴィスコンティは1911年を舞台にした『ベニスに死す』で、死にゆくマーラーを描いたが、実際の美少年のモデルのポーランド人「ウワディスラフ」は、その後ユダヤの強制労働で酷使され、70代になったとき痛風の脚を引きずりながらパリの映画館で『ベニスに死す』を見た。「私の美しい母は、子供の前で煙草など一度も吸わなかった…」というのが彼の感想だったという。滅びゆく貴族の時代の、最後のきらめきのような残光が、1911年には集約されている。

新国立劇場「ばらの騎士」より
撮影:寺司正彦 提供:新国立劇場
切なさと優しさと…3幕では、3つのターンテーブルから流れる3つの円舞曲が、自在につまみをひねって高く鳴ったり低く鳴ったりしていたように聴こえた。まるでオーケストラの魔法だ。カーテンコールで少し小さめのタキシードに蝶ネクタイをつけたゲッツェルは、ピットのメンバーに感謝を向け「こんなに幸せなことって…」と言う感極まった表情になった。ピットの楽員さんたちも、いつまでもいつまでも舞台に向かって拍手をしていた。『ばらの騎士』が舞台にかかるとは、劇場にとっても観客にとってもこんなに素晴らしいことなのだ。この日で終わってしまうのが本当に名残惜しかった。