1. エネルギッシュな“ワル系”叩き上げの圧倒的勝利 ~上海ロックダウンは、現代の「大躍進政策」(毛沢東)~
党大会の結論
蓋を開けてみれば、習近平氏の圧倒的な勝利であった。
10月22日に閉幕した5年に1度の中国共産党の党大会にて決まった新たな人事の話である。短期的に見れば、予兆はあったので「想定外」とまでは言えないが、中長期的に考えると、こんなことになったか、と嘆息しつつ、驚かざるを得ない結果だ。
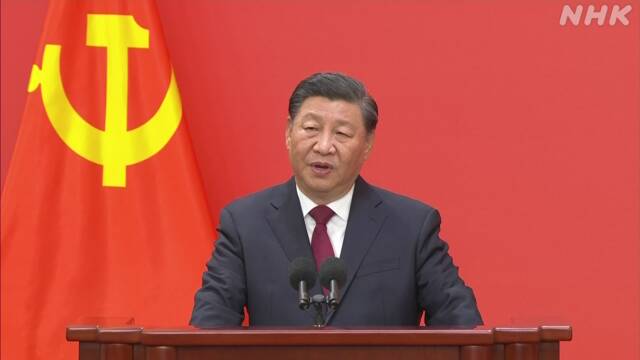
NHKより
各種報道で詳述されているので、ここでは詳しく取り上げることはしないが、要点を私なりにまとめると以下になる。
- 習近平氏の党総書記再任が確定。既に69歳の氏が3期目を迎えることは異例(3期目も本来ご法度だが、七上八下と言われるとおり、68歳になっていたら退任が普通)。
- 中央政治局常務委員7名(チャイナ・セブンと言われるトップ)の事実上全員が習派。
- 党中央政治局委員24名(1名減員)も事実上全員が習派(ちなみに女性もゼロに)。
- 中央軍事委員会も、異例の定年延長も含めて習派で固める。
- 北戴河会議(8月に長老たちが集まって次の人事などを協議したとされる)では、習氏の手法や経済政策への非難があり、党総書記・中央軍事委主席・国家主席の3つ独占はないとも言われたが、今回、三職独占が事実上決まり、江沢民氏・朱鎔基氏などの長老の姿は、今回の党大会では見られなかった。胡錦涛氏(習氏の前任)は、不可解な形で最終日にメディアの前で途中退席。
- 汪洋氏、李克強氏など共青団派(共産主義青年団派)は、軒並み退任。次代のエースと目されていた団派の胡春華氏は、常務委員に昇格どころか、中央政治局委員から脱落。
以上、乱暴にまとめれば、異例の権力集中である。これまでの先人の苦労、つまり、極力、多様な意見を反映するようにして、一人に権力が集中することを避けて来た諸先輩方の尽力をあざ笑うかのような布陣である。
歴史を無視した権力集中
50年に満たない私の人生だが、中国との付き合いはそれなりに長いと自負している。
大学時代には、まだマイナー言語だった中国語を第二外国語として選択肢し(東大では、私の頃は2クラス。ドイツ語やフランス語を選択するのが普通だった。その後、現在は5クラスほどに増えていると聞く)、人生初の海外旅行も1か月の中国旅行(バックパッカー)で、役所に入ってすぐに担当することになった円借款でも、重慶モノレール案件など対中交渉を一部担当していた。
その他の役所時代の仕事においても、例えば、ロシアの石油資源の獲得にしても(太平洋パイプライン。中国の動向を見つつ、モスクワと交渉)、システム・インフラ輸出政策にしても、中国の動向を意識しないわけにはいかず、常に注視し続けていたと言って良い。
最近でも、コロナ前までは、地域の産品の中国展開を四川省政府や(株)イトーヨーカ堂のご協力なども得て成都等で毎年のように展開し、北京や上海で開催される日中リーダー会議にも毎年参加していたこともあり、かれこれ、30年ほど中国政治をそれなりの関心を持って眺めてきた。
このように、それなりにではあるが、ずっと中国を見て来た立場から言えば、習近平体制になるまでは、中国は「歴史に学ぶ」姿勢が濃厚であったと言ってよい。反省と言う方が適切かもしれない。毛沢東時代に戻ってはならないという強い危機感である。
建国の父であり、尊敬を一身に集めていた毛沢東は、直前に百花斉放・百家争鳴をぶち上げて共産党批判をも歓迎する姿勢を示していたにも関わらず、1957年に反右闘争をしかけ、権力を集中させる。そして、1958年からは、いわゆる大躍進政策を推進し、経済的に大失敗をする。
核武装や高度経済成長によって先進国であるアメリカ合衆国やイギリスを15年以内に追い越すと宣言したのは良かったが、非科学的な政策を進めすぎたため、61年までの3年で、人災と言える大飢饉により頓挫。死者は少なく見積もっても1500万人(多い見積もりだと5500万人)とされている。先の大戦で日本人の死者は、軍人・民間人を合計で310万人とされるが、比べるものでもないが、凄まじい人的被害である。
ちなみに、この1961年は、中国建国以来、飢饉により出生数が最低だった年となっているが(1187万人)、最近の中国の出生数低下は著しく、昨年(2021年)、この数字を抜いたことで話題となった(1062万人)。
こうした大失敗への反省から、権力が過度に集中してしまうことへのリスクを避けるべく、特に鄧小平氏の主導により、巧妙に、多様性や権力の分散化が図られてきたのが習近平体制以前の中国の在り方であり、知恵であった。高齢者は政治の表舞台からは退場し、少数に権力が固まらないようにしていた。
習近平体制になってから、徐々に権力の「永久化」や「集中化」が進み、今回、一つの完成を見たと言って良い。既に、政治局常務委員の数も減り(9→7 ※その前は7人ではあったが)、今回、中央政治局委員の数も減らす(25→24)などしているが、更に少数に権力を集めていることも気がかりである。
個人的体験にはなるが、かつて中国と仕事で向き合っていた際、相手と交渉していると、例えば、現在のSTEP、かつての特別円借款の日本製の範囲を巡る分母の捉え方などに際しては、かなりギリギリと制度の限界を突いてきたりしていたが、そのしたたかさが印象として強い。
しかし、仕事を離れて、個々人との付き合いになると、どこか牧歌的な風情がある。良い人が多いのだ。苛烈な時代を経験した社会ならではの、反省からくる強(したた)かさと優しさ。ああいう酷い時代にはならないようにしようという社会的コンセンサス。上に政策あれば下に対策あり。「志那は国家ではなく、社会だ」と喝破した勝海舟の言葉などが思い出される。
しかしまた、余裕がない時代に逆戻りしつつあるのか、最近の中国からは、残念ながら、その牧歌的雰囲気が徐々に消えつつあるように感じる。
習近平氏の目指す姿
ここからは、多分に勝手な私見となるが、習近平氏が描いている中国(および自ら)の将来についての姿・想いについて述べてみたい。習近平氏の想いを、私になりに簡単に3つにまとめると、以下である。乱暴にまとめれば、①共産党の維持・発展、②経済は犠牲にしても良い、③軍事は大切、である。より丁寧に書くと以下となる。
① 共産党絶対体制の維持・発展(乱暴に言えば、国家がどうなっても共産党を守る。その点、前の体制(胡錦涛体制)・共青団たちは気迫が足りず信頼に値しない)
② 共産党のためであれば、一部の経済成長を犠牲にしても一向にかまわない。むしろ、一部の「勝者」の創出は、共産党支配を揺るがしかねない(共同富裕の推進)。
③ 共産党支配の確立のため、台湾統一を果たしたい。結果、自らは、日本帝国主義(共産党自体が本当にどこまで戦ったかはともかく)や国民党と果敢に闘って権力を確立した毛沢東のように(経済政策は一時的に失敗しても)敬われる存在になりたい。
それぞれについて、多少の説明を加えたい。
①は、日本人目線から言えば違和感を伴う希望であるが、本来は一政党にすぎないはずの共産党の方が、事実上、政府より上にあるという異形の国家である中国においては、さほど不思議ではない。一党支配の正当性の根拠は実は薄弱でもあるので、そうした議論が起きないほどに、圧倒的な支配を確立するしかないという恐怖の裏返しでもある。
この点、胡錦涛体制は、習近平氏から見ると歯がゆかったに違いない。国民各位の経済力の向上などに伴い、勝手な発言・行動が、彼の目線からみると許しがたいほどに増長していたわけで、共産党の支配が揺らぎかねないとの危惧が、習氏の中に濃厚にあったように思われる。
そして、自分が権力を握った瞬間から、特に私利私欲をむさぼる(ように見える)江沢民派を中心に要人の逮捕を繰り返し、ハエもトラも叩くとばかりに、腐敗を一掃したところまでが乱暴に言うと第一弾である。この第一弾は、貧富の差の拡大からルサンチマンを抱く多くの国民の溜飲を下げたことは言うまでもない。やはり共産党は頼りになる、との思いを国民に強く植え付けた。一定の成功だったと言って良いであろう。
そして今回、返す刀で、第二弾として、これまでも多少追い込んではいた共産主義青年団の幹部たち、完全に「ひ弱」なエリート集団である共青団系の要人たちを主要な地位からパージすることで、自らの権力基盤を完全に確立したわけである。いわば、ひ弱なエリートたちを追い出して、本当に現場が分かっている強者たちで政治を行うという動きである。
習氏は、副首相まで務めた父がいるため、いわゆる2世エリートと言えなくもないが、下放(農村での苦労)なども経験しており、彼のアイデンティティは、農村など現場を知悉したたたき上げ、というところにある。共青団系は、その多くが市町村ではなく県庁に出向する日本のエリート中央官僚のように、地域に行くにしても、本当のズブズブの現場というよりは、綺麗なところしか見ていないという傾向がある。
習氏は、そうした共青団系の「ひ弱さ」「現場知らず」を毛嫌いしている印象があり、自身は一応、清華大卒であるが、側近たちは、学歴その他から見ても、超一流エリートといった面々ではない。胡錦涛時代のやり方を見ていても、共青団系のやり方が、共産党を守るためには、物足りなかったのだと思う。
余談にはなるが、習政権になって、「教育における過当競争を排す」という名目で、学習塾の禁止などが実施されて大きな波紋を呼んでいるが、もしかすると、過当競争撲滅以上に、本気で、受験勉強だけのエリート教育を極力排そうと思ってのことかもしれない。
話を元に戻そう。習近平氏の共産党支配護持のための権力確立についてである。今回の共青団系の事実上の追放(上記の第二弾)は、②の経済成長と絡んでくるが、第一弾の時ほど、国民の拍手喝采となるかは疑問なところである。国民生活が立ち行かないほどに経済が落ち込んでしまっては、国民からの支持が得られないからである。
広東省書記の前任・後任として、同省の経済成長を著しく進化させた団派の汪洋氏・胡春華氏が上記のとおりパージされる中、その二人の後任で経済政策の評判が良くない李希氏が広東から常務委員入りをしたのが象徴的だが、今回は、これで本当に経済が伸びるのか、という布陣である。上海ロックダウンにより、経済成長を著しく犠牲にした李強氏が上海市トップから首相となり、また、北京市でも経済的にはすこぶる評判が良くないとされる蔡奇氏も常務委員入りした。
実際、発表日を不思議に延長して(党大会を意識?)ようやく公表された第二四半期の経済成長は3.9%止まりとなり(しかも、数字としてもやや怪しい)、年率5.5%成長の国家目標の達成は絶望視されている。第一四半期に至っては、0.4%成長にとどまり、知人によれば「あの日本より低い成長」と揶揄されているようであるが(日本人としては微妙な表現だが)、その大きな要因は、上海などの主要都市におけるロックダウン施策にあると言われている。
「ゼロコロナ政策」を推進すべく、上海ロックダウンが決行されたことが記憶に新しいが、その時期の上海に暮らしていた知人に、状況を聞いていると、現代における結構な悲劇である。徹底して外出が出来ず、日に日に減りゆく水を前に、命の危険も感じたそうだ。様々な悲劇的映像がネットを賑わしている。
このロックダウンは、特に、習氏の意を強く汲んだ忠臣の李強氏(上海市トップ)が実施したとされるが、コロナ禍の初期に、欧米の感染爆発に比して感染者が少なかったことを過度に誇ってしまったがために、「欧米社会は、今や中国に学ぶべきだ」と嘯いてしまったことから、習近平体制・共産党としては、メンツを守らざるを得なくなってしまったことが大きい。
もちろん、もう一つのこの政策の背景として、科学的に効果が高いとされる欧米製のワクチンを使えなかったことも無視できない。シノバック製に拘らず、欧米のワクチンを活用していれば、ここまでの政策は必要なかったかもしれない。
まさに、科学に基づかずに、スローガンとして「米国を追い越す」と掲げて、威勢よく突き進む姿は、大躍進時の毛沢東氏に重なるものがある。上海ロックダウンは、形や規模は違うものの、現代の大躍進と見ることもできなくはない。
大躍進だけでも、上記のとおり、その死者数などから見て歴史の大悲劇であるが、今後、紆余曲折を経て、その後の更なる大悲劇とも言える文化大革命みたいなものが、現代において繰り返されることだけは、何としても避けてもらいたいところだ。
「歴史は、一度目は悲劇として、二度目は喜劇として繰り返す」と喝破したのはマルクスであるが、マルクス主義から、共産主義の諸政策は学ばずとも、この言葉だけはしっかりと学んで頂きたいと感じる。
確かに、共産党を守るため、一部の勝ち組を作って、貧富の差の拡大による不安定な社会にするよりは、「共同富裕」(元々は、毛沢東の用語)ということで、平等性を大切にする方が安定感は増すかもしれない。しかし、既に香港市場などでマーケットの洗礼を浴び始めているが(株価急落)、全体が落ち込んでしまっては元も子もない。
最後に、③についてだが、台湾侵攻・統一は、隙あらば、悲願として必ず成し遂げたいと思っていることであろう。共産党や人民解放軍の“独裁”の正当性は、まさに日本軍や国民党軍との戦いの中から生まれてきているものである。何とか戦後約四半世紀もの間、それを保ち続けてはいるが、その正当性は、時と共に徐々に薄れて行ってしまう。
そして、現時点においてももちろん、共産党は、多党制の中で、選挙によって民主的に選ばれているわけではないことから、正当性は、戦の中からしか生じ得ない。過去の戦だけに正当性を求めるのではなく、現在にそれを求めるのは、習近平氏の立場からしたら自然であろう。
そして、それが達成できた時には、習氏は紛れもなく毛沢東と並ぶ存在となり、今回成し遂げられなかった「党主席」ポストの復活と習氏の就任や、習思想の毛思想並みへの昇格なども達成できるであろう。そのことにより、当面、共産党の支配は安泰となるのは間違いない。
2. ひ弱な“良い人系”エリートの逆襲? ~今後の展開から、日本の現状と帰趨を考える~
エネルギッシュな“ワル系”叩き上げの世界と中国・日本
今回の習近平氏の一強体制の確立も象徴的だが、世界において、如何に、エネルギッシュな“ワル系”叩き上げの力が増しているか、存在感を持っているかについてつくづく感じざるを得ない。考えてみれば、プーチンにしても、トランプにしても、同じような系譜に位置づけることができる。
もしかすると後世の学者が解明してくれるのかもしれないが、現代の社会では、社会「科学」的に解釈して、そういうエネルギッシュな“ワル系”叩き上げが、のさばりやすい、ということになってしまっているのかもしれない。或いは、戦乱の歴史を紐解けば、ひ弱な“良い人系”エリートが民主的な枠組みの中で、活躍できるという時代の方が珍しかったのかもしれない。社会が今後、残念な変遷を見せていくのか、個人としても不安である。
しかし、嘆いていても仕方がない。我が国で言えばどう分析してどう考えるべきであろうか。
敢えて言えば、先日亡くなった安倍元首相や、安倍政権を官房長官として支えた経験も豊富な菅前首相は、「エネルギッシュな“ワル系”叩き上げ」に位置づけることが出来るかもしれない。特に安倍政権では、一度退陣して復活したご本人もさることながら、詳述は省くが、官邸の周りを固める官僚たち・菅官房長官(当時)などに至るまで、割とそうしたタイプで固められていた気がする。トランプはもちろん、習近平やプーチンにも当たり負けしていなかった感じを受ける。
ただ、今は岸田政権だ。残念ながら岸田氏本人はもちろん、周りの方々も、一部の例外を除いて、世界のエネルギッシュな“ワル系”叩き上げに対抗できる感じがしない。友人や人間としては、「聞く力」に満ちた、和を尊ぶ方の方が良い事は改めて書くまでもないが、政治は結果が全てである。(個人的には存じ上げないが、)胡錦涛氏や汪洋氏や李克強氏や胡春華氏が如何に良い人であっても、パージされてしまっては意味がない。
ここで、少し、ちょっと遠回りになるが、我が国の今後を考える上で、まず、習一強体制の中国の今後について考えてみたい。
先述のとおり、何よりも共産党の支配の維持・発展が大切なので、経済状況は、一般論的には、今後厳しくなっていくことと思われる(=共産党支配のために犠牲にされる)。一つには、マクロ経済政策を担う人材面の問題が大きく(有能な者が既にパージされている)、さらに、より本質的には、社会の安泰のため(共同富裕のため)、民間主導での最先端企業を伸ばすよりも、むしろ彼らを叩き、雇用その他を重視する非効率な国営企業系を優遇すると考えられるからである。
考えてみると、実は、現在の中国が掲げる「共同富裕」は、岸田政権が当初描いていた「(分配を中心とする)新しい資本主義」と似ていなくもない。岸田政権は、その後、分配中心だとマーケットの受けが悪いことを察知し、成長も分配も、と舵を切った。むしろ、マーケットに対しては、成長があってこその分配だと、「インペスト・イン・キシダ」などと唱えて、宗旨替えをしたと言っても良い。元々チラ見せしていた「金融所得課税」などは、少し出して株価が下がると見るや、今は全然聞かれなくなった。
良く言えば柔軟な対応、悪く言えば、「岸田さんは、一体何がしたいのか。腰砕けではないか」ということになるが、この「腰砕けではない岸田政権」を気合でやって見せているのが習近平政権の中国である。株価が下がろうが、投資が引こうが、平気で共同富裕のため、取り締まりなどを徹底して、アリババその他の民間企業の成長を犠牲にしてきた。さらには、繰り返しになるが、科学を無視して、自国製ワクチンとゼロコロナ政策にこだわり、人権も何もなく、大都市ロックダウンを強行し、経済にダメージを与えている。
このように、ある意味で既に、腰が定まった形で経済を犠牲にして、共産党統治を見せつけ、党の権威を高めていることからも明らかだが、中国経済は、かなりの確率で減速モードとなって行くであろう。しかし、当然ながら、景気が冷え込めば国民の不満が高まるのが常である。問題は、その不満をそらすべく、別の関心を内に向けるか外に向けるか。
内に向けるとすると、かつての毛沢東時のように、国内でとてつもない血が流れることになる。血祭りにあげる対象の問題である。今回の共青団系のパージは、見方によっては、そうした事態を避けるための積極的な「逃走」「サボタージュ」かもしれない。汪洋氏や李克強氏などは、いわゆる先述の「七上八下」的には(年齢的には)、残留しても良かったわけであり、現に、そういう報道もあるが、半分はあきれて、半分は火中の栗を拾わないためにか、本人たちが進んで身を引いたという説も強い。
通例、中国では、総書記が政治を、首相が経済を担うとされ、習体制でも、一期目の着任当初は、首相の李克強氏主導の経済政策ということで「リコノミクス」などともてはやされた時期もあったが、経済の実権も結局は習氏が握っていくこととなった。であるにも関わらず、この経済減速の状況で、さらなる不況に直面して、国民の不満をそらすために血祭りにあげられるターゲットになってはたまらない、と考えたとしても不思議ではない。まあ、気分としては、「もうやってられない」という思いに近いのかもしれない。
パージされたのか、自ら遁走したのかはさておき、結果として新政権は習派の独占状態になったわけだが、逆に言えば、責任を取らせる者(いけにえ)が内部にはほぼいない、ということになる。
経済失政などの結果としての国民の不満のはけ口を内に向けることが完全には難しいとなると、不満の矛先が向けられるのは外である。中国は、インドや南シナ海、尖閣諸島など、各地で無数の争いを巻き起こしているので、「ネタ」には事欠かないが、最大かつ最も正当性が主張しやすく、国民の共感が得られやすいのが台湾である。
上記の③という意味からも、そして、予想される経済悪化の結果からも、台湾侵攻の可能性はかなり高まっていると断じざるを得ない。昔から経済悪化から軍靴の音が聞こえるといわれるが、台湾侵攻に繋がることだけは、絶対に避けたいところである。
ひ弱な“良い人系”エリートの戦い方
最後に、ここまで述べて来たような「エネルギッシュな“ワル系”叩き上げ」の世界で、特に隣国中国が特にその様相を強める中で、ひ弱な“良い人系”エリートたる我々はどうすれば良いのだろうか。上記の問題意識の続きになるが、以下、3点、整理しつつ述べて行きたい。
具体的には、
① 攻めはできずとも守りはしっかり固める
② 仲間と連帯し、長期戦に持ち込んで頑張る
③ とはいえ、エネルギッシュな“良い人系”叩き上げ精神も見せる
の3点である。
まず、①についてであるが、本来、攻撃は最大の防御という言葉もあるように、相手を威嚇することが、結果として本来、最大の防御になり得るのは、自然の理である。力による力での対抗は、事態を悪化させるだけ、との言説もあり、理解できなくはないが、エネルギッシュな“ワル系”叩き上げを止められるのは、力でしかない。
ソ連崩壊後に、ウクライナが核兵器を持ち続けていて、米国がバイデン大統領ではなく、本当に軍隊を出動させかねないトランプ大統領であれば、おそらく、プーチンはウクライナ侵略を(少なくともキーウを含む全土同時侵攻を)思い止まったであろう。
そういう意味では、尖閣にしても台湾にしても、中国の武力侵略を食い止めるのは、また、金正恩の北朝鮮、プーチンのロシアによる侵略を食い止めるのも、わが国による積極的な攻撃能力であることは論を待たない。しかしながら、ひ弱な“良い人系”エリートのわが国では、そんなことは望むべくもないし、実際、「反撃能力」ですら、国内で大議論となっているのが現実である。であれば、せめて、守りはしっかり固める、ということが当然だがまずは大切である。
その際、②と関わって来るが、自分だけで守るのではなく、周囲と協力して守るというのが、ひ弱な“良い人系”エリートのとる最上の策である。この点、否応なく、事実上軍事的には日本を占領しているアメリカと協力するのは、当然として、台湾・韓国、そして、実は、今回パージされた共青団系なども含む、中国の「仲間」たちが大切になる。
繰り返しになるが、今回の共青団系の「追放」は、見方によっては、「自ら引いた」とも言える。あたかも、毛沢東戦術のように、「敵が進めば我は退く」を実践しているようにも見える。つまり、裏を返せば「敵が退けば、我は進む」わけで、即ち、彼らが経済政策その他で立ち行かなくなった時に、バーッと再度実権を握ることを考えていないとも限らない。
表立っては言いにくいわけだが、今の上海ロックダウンなどの在り方、言論の自由がない体制に辟易としている中国人たちは少なくない。既に、国外脱出している人たちも少なくないが、欧米や日本で平和に暮らしたいと願っている。彼らの多くは、我らと同じく、ひ弱な“良い人系”エリートたちであり、もはや、天安門事件の闘士たちのように体を張って闘う気迫はないが、弱者には弱者の戦略がある。時が来るまで身をひそめるというやり方だ。
短期的な決戦は難しいが、長期戦に備えて、近い仲間としっかりと連携を図るのが、ひ弱な“良い人系”エリートがしっかり考えるべき戦略である。
そして、最後の③、即ち、ひ弱な“良い人系”エリートの仮面をはがして、エネルギッシュなたたき上げ面を出して行くという点だが、これは、政治面・軍事面で発揮するのは困難かも知れないので、特に経済面で発揮すべきである。
中国の軍事的脅威がここまで増してきたのも、根底には、もちろん経済成長がある。経済力が無ければ、軍事力は基本的には伸び様がなく、軍事大国のロシアがウクライナ相手に苦戦している要因の一つも、その経済力の弱さである。裏を返せば、経済力が確立していれば、国防・安保の半分、もしかすると8割くらいは達成したようなもので、まずは、そこに注力するのが大事である。
つまり、ひ弱な“良い人系”エリートたちが、政治や軍事で、エネルギッシュな“ワル系”叩き上げと対峙するのは困難であっても、経済であれば、対峙の仕方があると言える。しかし、ここにおいても、最後は、アニマルスピリット(ケインズ)が必要である。
わが国経済は、絶対的な力はまだあるものの、相対的には、一人当たりGDPにしても、世界に占めるGDPの割合にしてもズルズルと順位を下げており、最近の円安も、彼我の金利差を超えて、こうしたファンダメンタルな成長力の弱さにあるとみることも出来る。特に、日本経済においては、企業の新陳代謝が極端に少ない。
国家として、メディアなどの批判を避けるべく、教育環境をどんどん無菌化し、およそ不条理・理不尽を排除して、ひ弱な“良い人系”エリートしか育てない社会にしてしまった日本では、諸外国と比べて、圧倒的にベンチャー企業などが生まれ・育つ割合が少ない。かつては、アメリカが驚愕するようなベンチャー企業が多々成長した日本であるが(逞しい創業者たちが創った、ソニー、松下、ホンダなどなど枚挙にいとまがない)、今やその多くが大企業となり、新たなベンチャーが、世界を揺るがすような企業が殆ど生まれていない。
理由は簡単で、「やる人」がいないのだ。私は、経産省時代を通じて、政策担当者として、日本企業が世界で勝てるために、という政策に広い意味ではずっと関わり続けているが、政治家も官僚も、これまで、散々、ファンドを作ったり、補助制度を整備したりして側面支援をしてきた。これはもう、政府が準備するものとしては、世界的に見ても十分な水準にあると言える。
日本にはよく、ベンチャーが生まれるエコシステムがないと言われるが、エコシステムの起点は、すべて「やる人」なのだ。約500社の創設に関わったとされる渋沢栄一氏や、上述の戦中・戦後の数々の起業家たちを待つまでもなく、まず、やる人がいないと始まらない。
いわば、各種支援制度を整え続けてきた日本は、野球で言えば、スタンドで応援したり、栄養ドリンクを供給したり、練習環境を整えるフロント的なことをする人たちはたくさんいるが、肝心の選手が少ないという状況のようなものだ。選手層が薄ければ試合にならない(誤解無きように書いておくが、大企業からチャンレンジするということも含んでの「選手」である。自動織機から自動車に展開したトヨタ、楽器から発動機の会社を生み出したヤマハなども、「ベンチャー」精神と言ってよい)。
政治家も官僚も、そして多くの国民も、あとはもう、本気で日本から成長する企業を生み出すには、世界で輝く企業を創るには、自分たちを含め、大組織のエリートが、アニマルスピリットを発揮して挑戦するしかない、ということに実は気づいている。私の経営している会社は鳴かず飛ばずなので、偉そうなことは言えないが、そんな思いもあって、私も経産省を飛び出し、世界で戦える日本を創るべく創業をした。
岸田さんにそれを望むのは無理かも知れない。和をもって尊しとなす典型のような方で、ある意味で日本の現状の象徴のような方である。ひ弱な“良い人系”エリート社会が選ぶ宰相としては、もっとも社会を忠実に反映しているとも言える。
ただ、日本の安全を守るには、国際社会で名誉ある地位を占めるためなら、良い人系であっても、せめて、経済面で、エネルギッシュに叩きあげて頑張るべきではなかろうか。辞任した岸田内閣の山際大臣はスタートアップ担当大臣であった。いわゆる商工族としては、経産省の期待も高かった方で、勉強家・政策通であったと聞く。獣医の道から政治に進んでおられる点もチャレンジ精神に満ちておられるとも言える。ただ、統一教会関係では、さすがにナイジェリアやネパールに行った記憶はあるだろう、と非難されていたが、やや残念な身の引き方であった。
山際さんが、いっそのこと、自ら「世界で戦えるスタートアップを創る」と宣言されて起業をされてはどうだろうか。仲間の政治家や、経産官僚など、数名がついて行くのではないか。大臣時代に培った国内外の人脈や知見を活かせるとなれば、成功確率も高い。資金も人材も引っ張りやすいであろう。結果として、低迷する岸田政権の支持率アップにもつながる気がする。
最後はやや乱暴な議論となったが、こうした平和な乱暴さ、経済面におけるアニマルスピリットが大事だとつくづく感じる。ひ弱な“エリート系”国家の日本ではあるが、是非、一部の方々におかれては、少なくとも経済面で、エネルギッシュなたたき上げ系の覚悟を持ってチャレンジしてもらいたいと痛切に願う今日この頃である。













