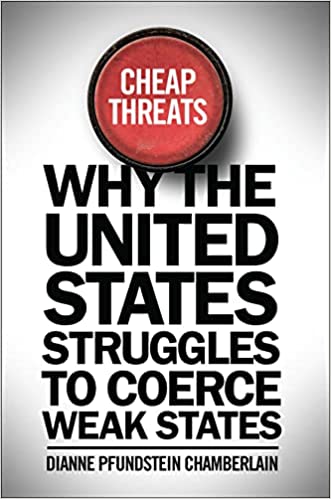国際政治は、暴力によるコミュニケーションが支配する世界です。これは暴力が国家間のバーゲニングの全てを決めるというわけではありません。暴力は国際政治における欠くことのできない部分を依然として占めているということです。
これには誰もが目を背けたいでしょうが、残念ながら残酷な事実です。国家によって暴力が直接に行使される行為が戦争です。

Cemile Bingol/iStock
暴力と外交
暴力は外交の手段としても使われます。その1つが「強制外交」です。相手を軍事力により恫喝することで、自らの意志を強要する外交術です、このことについて、ノーベル経済学賞受賞者のトーマス・シェリング氏は以下のように喝破しています。
暴力は、それが用いられるのではなく、それが生起する恐れがあるときにもっとも合目的なのであり、うまくいくのである。うまくいく脅迫とは、実行される必要のない脅迫である。
(『軍備と影響力』齋藤剛訳、2018年〔原著1966年〕17ページ)
ここで1つの疑問が生じます。それは、ある暴力による脅迫はうまくいく一方で、別の恫喝はうまくいかない、ということです。一体、何が暴力による威嚇の成否を決めるのでしょうか。
この難問に正面から挑んだ力作が、ダイアン・チェンバレン氏(コロンビア大学)による『安い威嚇—なぜアメリカは弱国を強制するに苦戦するのか—』(ジョージタウン大学出版局、2016年)です。
冷戦後、アメリカは国際システムにおける単独の大国になりました。比類なきパワーを持ったアメリカは、直感的に考えれば、弱い国に自らの政治的意思を強要することなど、容易ではないかと我々は思いがちです。
しかしながら、アメリカは、これに苦戦しているのです。
成功する威嚇と失敗する威嚇
この研究における彼女の主張は明確です。すなわち、犠牲を忌避する安っぽい威嚇(cheap threats)には、たとえそれが大国によるものであっても、小国は従わないということです。逆にいえば、高い犠牲を厭わない威嚇(costly threats)には、国家は従いやすいということです。
ここでのポイントは、国家が威嚇をブラフ(はったり)だと判断して、相手の要求を拒否するのではありません。国家は相手の脅しを疑うから、それに従わないとよく言われますが、必ずしもそうではありません。小国の指導者は、大国による威嚇が本物だと分かっていても、しばしば強制されないのです。だから、国家は挑戦国に付け入るスキを与えないために、あるいは弱腰であると誤って学習させないために、抑止や強制の脅しを実行するべきだというのは間違いです。
国家の指導者が大国の強要を拒むのは、大きな犠牲を払う覚悟がない威嚇をした場合なのです。その主な理由は、強制を受ける側は威嚇を行ってきた国家に損失を強いれば、その指導者は引き下がるだろうと期待することにあります。
アメリカはヴェトナム戦争で6万人近い若者を死なせてしまいました。この反省から、米軍は人的犠牲を極小化する戦争術を開発して、実践するようになりました。これはアメリカ人の命を救うことになりましたが、皮肉にも、アメリカによる暴力の威嚇の政治的効果を低下させました。
その結果、軍事力による脅迫が多く実行されることになり、人的被害はかえって大きくなるのです。このことについて、彼女は以下のように主張しています。
パラドックスがある。武力行使をより容易なものにして、より効率的なものにする努力は、戦争に至らない強制ツールとしての武力の効用を弱めてしまうのだ…自国の兵士や標的の市民の両方の人的コストを極小化するアメリカの努力は、実際には、人命の損失を生じさせる可能性をより高めてしまうことになりかねない。なぜならば、これらのことは、安っぽい強要の威嚇に直面した国家が抵抗することを促し得るからである(同書、225ページ)。
チェンバレン氏の研究は、いくつかの興味深い発見につながっています。冷戦後、アメリカは国際システムにおける単独の大国になったために、ソ連というライバル国が存在する二極システムの時に比べて、国際危機において強要の威嚇をより頻繁に行ったことです。
1945-1989年の冷戦期において、アメリカは49回の国際危機の内で11回、強要の威嚇を発しました。その割合は22.4%です。ところが冷戦後、アメリカは14回の国際危機の内で8回も強要の威嚇を行っています。その割合は57.1%に達しています。アメリカは長い冷戦期より短い単極期において、より頻繁に強制外交に訴えているのです(同書、63ページ)。
これは近年に行われたアメリカの対外軍事介入を分析するプロジェクトの成果と合わせると、一層、興味深い知見を明らかにします。若手政治学者のシディタ・クシ氏(ブリッジウォーター州立大学)とモニカ・トフト氏(タフツ大学)は、建国以降のアメリカの軍事介入をデータ化しました。その結果、アメリカは約400件の軍事介入を行っており、その半数を1950ー2019年の間に実施しています。驚くのは、全軍事介入の25%が冷戦後に集中していることです。
こうしたデータが、アメリカは、そのパワーを抑制する競争相手国が存在しない「単極の瞬間」(チャールズ・クラウハマー氏)において、軍事力による恫喝や軍事介入を乱発していたことを示しています。
この時期にアメリカは世界を自国のイメージ通りに作り替えようとして、アフガニスタンやイラクなどに侵攻したり、軍事同盟であるNATO(北大西洋条約機構)を「1インチも東に拡大しない」との口約束を反故にしたりして、ヨーロッパで拡大するとともにコソボ紛争で軍事力を行使しました。誇張した言い方になりますが、アメリカが世界で「暴走」していた時期なのでしょう。
強制外交に苦戦するアメリカ
それではアメリカの暴力による強制の威嚇は、どのくらい成功しているのでしょうか。
冷戦期において、アメリカは敵国を脅して相手国に自らの要求をのませた割合は、11事例中6件であり、成功率は約55%になります。しかしながら、冷戦後になると、アメリカの要求に屈したのは、8事例中のわずか2件に過ぎず(「砂漠の攻撃」作戦とUNSCOMⅠ)、その成功率は25%に低下してしまうのです(同書、88―89ページ)。
標的になった国家の反応にも差があります。冷戦期において、相手国が抵抗したのでアメリカが恫喝を実行したのは、わずかに1事例です(パナマへの軍事介入)。他方、冷戦後には、アメリカの脅しの標的になった国家は、6事例中の5件で抵抗したために、アメリカが威嚇を行動に移すことになりました(同書、70ページ)。
それらは、湾岸戦争、ハイチへの侵攻、イラクでの砂漠の狐作戦、コソボ紛争でのベオグラード空爆、アフガニスタン戦争、イラク戦争です。要するに、アメリカは強くなった時の方が、相手を脅して屈服させるのに苦労しているのです。
1962年のキューバ・ミサイル危機では、アメリカはソ連を威嚇することにより、キューバからミサイルを撤去させることに成功しました。ジョン・F. ケネディ政権は、フルシチョフ首相に対して、核戦争のリスクを冒し、軍事衝突ひいては核の応酬になった場合に甚大な犠牲を払う覚悟で自らの要求を強要したのです。
キューバ侵攻を行うことになれば、米軍はキューバ軍やソ連軍と戦うことになるので、大きな損害が見込まれました。米ソに核兵器が相互に撃ち込まれたならば、とてつもない数の市民が両国で命を落とすことになったでしょう。フルシチョフは、事態が制御不能になることを恐れて、最終的にキューバから核弾頭と中距離ミサイルを撤去することに同意しました。このようにアメリカの高い犠牲を厭わない威嚇は、ソ連を動かした大きな要因だったのです。
これとは対照的だったのが、2011年のアメリカによるリビアへの「安っぽい」威嚇でした。リビアでは、ムアンマル・カダフィ大佐による独裁政権が、これに反対する本格化した運動を厳しく弾圧しました。バラク・オバマ大統領は国連安保理決議に基づき、カダフィ大佐に対して、即時停戦をするように求めるとともに、それに従わない場合には、軍事行動を含む重大な結果(consequences)になると脅しました。その一方で、オバマは「リビアに地上部隊を派遣しない」と明言しています。
このオバマの姿勢は、カダフィにはアメリカの覚悟を疑わせる兆候に映ったようです。カダフィにとって、アメリカが主導するNATOとの対決は意思の戦いでした。すなわち、リビアの国土を守るカダフィと犠牲者を極力抑えたい西側には、犠牲の覚悟に大きな差があったのです。
カダフィ大佐の報道官だったセイフ・イスラム氏は「ここはわれわれの国だ。リビアで戦い、リビアで死ぬ。リビア国民がNATOを決して歓迎しないだろうし、米国民を歓迎することも絶対にない」と発言して、妥協を拒否しました。その後、米英仏を中心とするNATOの多国籍軍がリビアを空爆して反体制派を助け、カダフィは反対勢力により拘束されて死亡しました。このようにアメリカの強制外交はうまくいきませんでした。
同じような失敗は、イラクでも繰り返されました。1991年の湾岸危機の際、アメリカはイラクにクウェートから撤退するよう要求しました。アメリカを中心とする多国籍軍はイラク軍に対して圧倒的な優勢であり、その意図もバクダットに伝わっていました。イラクのタリク・アジズ外相はジェイムズ・ベーカー国務長官に「我々はあなた方の意図に幻想は持っていない」と語っています。そもそもジョージ・H. W. ブッシュ政権は1989年12月にパナマに侵攻して、同国を占領しているので、その恫喝がイラクにブラフと受け取られる余地はほとんどなかったでしょう。
それでもイラクがアメリカの要求を拒否したのは、サダム・フセイン大統領や側近が、イラク軍がアメリカに主導された多国籍軍に犠牲者を強いれば、そのコミットメントを貫き通せないだろうと信じたことによります。
アメリカは多くの国から部隊を派遣してもらい、戦費も各国が分担しました。これによりアメリカが払うコストは抑えられた反面、威嚇は安いものになってしまい、その効果を損なったということです。続く2003年でもアメリカの威嚇はイラクに効きませんでした。フセイン大統領は、戦争による犠牲者を少なくしたいアメリカが、犠牲を払ってでもバクダッドまで進軍する意思を疑っていたのです。
まとめると、強制の威嚇は、自らが大きな犠牲を厭わないものでないと、外交的な道具としての効果は低いということです。自分たちの要求を相手に受け入れさせるには、相応の高いコストを払う覚悟を持たなくてはなりません。コストのかからない恫喝は行いやすい反面、望ましい結果を得ることにはつながりにくいのです。威嚇で覚悟する犠牲とその効果は、トレード・オフの関係にあります。
威嚇と抑止
チェンバレン氏によれば、威嚇のコストは、
① 自国の市民の犠牲をどれだけ厭わないか
② 軍事戦略がどれだけ戦死者を避けるものであるか
③ どれだけの財政的負担を覚悟するか
④ どのくらいの殺傷の意思と付随的損害を受け入れるか
といった変数と事例に特有な文脈的変数によります。
①は徴兵制や予備役を動員すれば、それだけコストは高くなります。逆に、志願兵や民間軍事会社に頼れば、コストは下がります。②は「軍事における革命(RMA)」に影響されます。地上軍の派遣はコストが上がる一方で、無人機による攻撃や空爆による作戦は、人的損害を低く抑えられるために、威嚇のコストは下がります。③は同盟や有志との合同作戦を行おうとすれば、負担が分担され、コストは下がります。④は人道的見地から軍事攻撃において民間人の犠牲を減らそうとすれば、皮肉なことに、威嚇の効果は減少してしまうのです。
強制外交における威嚇の理論は、抑止にも応用できます。すなわち、抑止の脅しが犠牲を厭わないものであれば、相手に敵対的行動を思いとどまらせやすいということです。バイデン政権によるプーチンへの核使用を抑止する威嚇は、ロシアとの核兵器の応酬になれば、膨大なアメリカ人の命を犠牲することになるので、それは効果的でしょう。
しかしながら、クレムリンがウクライナに核兵器を使用するのを思いとどまらせることは、難易度が高くなります。なぜならば、ロシアの核使用がウクライナに限定される限り、アメリカ人は犠牲にならないからです。
保守派のダグ・バンドウ氏(ケイトー研究所)は、やや悲観的過ぎる見解かもしれませんが、抑止におけるコストと効果について、以下のように的確に指摘しています。
アメリカの抑止の試みは失敗しそうだ…核戦争で脅す、より厳しいアプローチも、彼(プーチン)を思いとどまらせそうにない。アメリカはその国を守るために一人の命たりとも犠牲にするつもりがない国に対して、ロシアが核兵器を使用することを阻止するために、アメリカが核戦争と本土の破壊の危険を冒す準備はあると想像するのは、果たして信頼できることなのか。
他方、ロシアの西側諸国への恫喝は、高い犠牲を厭わないものになっています。
第1に、ロシアは部分動員を実施して、自国の市民に負担を強いる行動にでています。第2に、ロシアはウクライナでの軍事作戦では、既に1.5万人を超える犠牲者をだしています。第3に、ロシアは単独で戦費を賄っています。第4に、ロシアはウクライナの民間インフラ施設を破壊し続けており、多くの無辜の市民を殺傷しています。
国際政治の威嚇の研究が正しければ、プーチン大統領による抑止の脅しは効果的なものになっており、NATOは引き続きウクライナへの直接の軍事介入を思いとどまらざるを得ないでしょう。
編集部より:この記事は「野口和彦(県女)のブログへようこそ」2022年10月31日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は「野口和彦(県女)のブログへようこそ」をご覧ください。