
T_Mizuguchi/iStock
『洛北集』(1943)から
第3回は『洛北集』(甲鳥書林、1943)からの秀句を取り上げていく。
「自序」には、
私は本来、與謝野門下の席末に列り、新詩社の流風を呼吸して成長したものである。・・・・・・(中略)自己の内奥の卒直なる告白に外ならぬ多年の作品は遂にすて去るに忍びず、敢てこれを一巻としてまとめるに至った(同上:2-3)。
とある。
そして「思慕郷里を離れているわけではない」が、全巻から「社会と民族とに関する私の情熱」を読み取ってほしいとする。ただ今回は「ふるさと」の歌を中心にみていこう。
(前回:高田保馬の「感性」と「理性」②:歌集からの「感性」分析の方法論)
1932年(49歳)
1.針を買ひ 糸を買ひ来て ほころびを 縫ひつゝ思ふ ふるさとの家
この時期の高田は京大教授専任ではあったが、九大教授も兼担していて、半年ずつの講義を続けていた。歌は「ふるさとの家」を「思ふ」とされているから、京都の単身赴任先での一首である。
「針・糸・ほころび」が結びついた部屋の情景が浮かんでくる。しかし、単身なので自らが縫うしかない。明治生まれの50男が裁縫するのだから、本人の気持ちを忖度すればおそらくは楽しくはなかったであろう。
しかしそれをやりながら、かつてならば母がそして今ならば妻が縫ってくれたはずの佐賀県小城郡三日月村の生家を思い起こした。ふるさとの景色や人々に託した「思い」とは別に、「針仕事」からもふるさとへの気持ちが伝わってくる。
上の句は、高田にとっては様々な事情から仕方がない行為であるが、「買ひ」と「縫ひ」という表現に諦念を断ち切る響きがあり、その先に「ふるさと」を思うことにより、精神的には救いが読み取れる。
2.耕して 一生貧しき 村人の 次ぎ次ぎにして 土にかへるも
歌の内容は社会学者の観察そのものであり、通常は散文表現になるのだろうが、和歌に託したのはなぜか。高田家は代々天台宗の僧籍であり、父清人は第16代目に当たる。明治初年の廃仏毀釈により神学をまなび、高田が生まれた頃は神職を家業としていたが、田地二町歩を所有していた自作農でもあった。作男が二人いたという(高田保馬博士顕彰会、2004:37)。
『回想記』では「農村の人として」の感想が詳しく綴られている。
私共の幼時は、此小村の家數も少し多かった。そして、その大半までは自作農であった。三四十年の間、親の次は子、子の次は孫、代々正直に朝から晩まではたらいた。而も今は、大抵は小作農として立つことになってゐる。・・・・・・正直にはたらいて、働きぬいて得た結果は何か、世間並にも及ばぬくらしと、土地の喪失と、借金と。・・・・・・もとよりこれは個人のしわざではない。社會のしわざである。然らば社會は農村に何をしたか。(中略)事がらは極めて簡単である。一方に於ては自給性の喪失。他方に於て、生活標準の變化。これは資本主義生産の發達の両側面と考えてもよい(同上:50-51)。
このような感慨をもちながら、ふるさとの農村の現況と農民の一生を和歌に詠みこんだ。「耕す土にかえる」村人の一生が、資本主義社会の側の動きによって定められてしまったことへの社会学者の悲しみが伝わってくる。
社会学・経済学からの提言
当時の高田の研究はその主軸を社会学からすでに『経済学新講』に移していたから、これらは勃興期の資本主義による「農村の没落」を回避する手段としての提言でもあった。それは「農村をして自ら立たしむる道」(同上:58)である。具体的には、「農業の多角的経営、即ち生産物種類の増加と経営の合理化とを中心とする、同時に産業組合の利用、技術の進歩などがすすめられる」(同上:58)ものであった。
そして、最終的には「農村が自ら使用するものは之を自ら作る」ことを勧めて、村全体での「自給性の恢復」(同上:59)を強調した。
令和の今日では「自律性」と「自立性」を強化して、「地産地消」を実行しようという主張になろうが、これはこの10年続いてきた「地方創生」の理念でもあることに留意しておきたい。ここにも高田特有の「遠視力」が認められる。
1933年(50歳)
50歳になり、
3.病みたれば 幾年ぶりか 故郷の つゝじ花咲く 頃をわが居り
4.身も老いぬ 故郷老いぬ 大方は そのかみ人の すでにあらざる
が合わせて詠まれている。
3は病気になり、久しぶりに三日月村の生家に戻ってきた時の歌であろう。つつじが咲いているから時期は5月上旬か。わが家を取り巻く景色は変わっていないが、毎年繰り返して咲く「つつじ花」が鮮やかな色であるだけに、病気の辛さや暗さとの対比効果が大きい。
4では、すでに「身も老いぬ」として老化が意識され始めている。加えて、景色は変わらないとはいえ、ふるさとに住む人々にも着実な老いが認められるようになった。時の流れが上の句で慨嘆されている。
加えて、下の句では「そのかみ」(其の上)すなわちその当時の人たちは、「すでにあらざる」(もはや誰もいなくなった)状態が重なっている。病気で帰省して、これでは寂寥感がいやおうなしに強まるだろう。
「そのかみ」には、『広辞苑』(岩波書店)、『大辞泉』(小学館)、『日本語大辞典』(講談社)いずれもで「其の上」が充てられているが、『基本古語』(大修館書店)では「当時・往昔」になっていた。『全訳古語例解辞典』(小学館)では「其の上・往昔」と折衷されていたが、「当時・往昔」が一番分かりやすい。
さらに4では、上の句で「老いぬ」が二度繰り返され、下の句が「すでにあらざる」なのだから、時間の流れの無常さがひしひしと伝わってくる。「老い」自体が時の流れの結果であるうえに、往時の知人が「あらざる」では、時の流れが重なって帰省した高田に押し寄せてくる。
1934年(51歳)
51歳では、
帰郷(十月)
5.耳すまし きけばし聞ゆ 初秋の 遠くの村の 秋蝉のこゑ
がある。久しぶりの10月のふるさとでも、耳を澄ませば遠くから秋蝉の鳴き声が聞こえてくる。生家周辺は農地だから音を遮る建物がなく、かなり遠くから蝉の声が聞こえたのであろう。「耳」と「蝉のこゑ」は聴覚であり、「初秋」と「遠くの村」は視覚的なことばであり、両者が組み合わされた情景描写になっている。
高田が京都塔の段下町に郷里の家族を呼び寄せて生涯の住居を得たのは1936年だから、この時期の三日月村の生家には家族がいた。帰郷して家族に会ったのだから、和歌にも穏やかさが滲み出ている。
1935年(52歳)
それは52歳でも同じであり、
6.吹き通る 青田の風に 日もすがら いねて書よむ ふるさとの家
では、田植えが済んだ頃に、二階の窓を開けて、初夏の爽やかな風を受けながら、読書三昧の落ち着いた生家での暮らしが浮かんでくる。読み疲れて居眠りしながら、ひもすがら(終日)すなわち朝から晩まで好きな本を読んでいる光景の自己描写になっている。ここにも穏やかさが感じ取れる。
しかし1937年に日中戦争が始まり、38年に「国家総動員法」が成立すると、身辺にも「いくさ」すなわち戦争の影が忍び寄ることになる。
1938年(55歳)
7.夫(つま)も子も いくさにあらむ この村の をみな群れつゝ 稲刈れる見ゆ
では、筑紫平野の稲刈りにすらその断片が詠みこまれるようになる。
稲刈りをするのが夫や息子という男たちではなく、村の「をみな」たちなのだという。しかも「群れつゝ」みんなで協力し合って稲刈りしているのである。なぜなら、夫も息子も「いくさにあらむ」、すなわち兵隊として中国戦線に投入されていて、秋の稲刈りという村の一大行事にさえ出て来れないからであった。代わりに妻や娘たちが、近隣総出で「群れつつ」働くさまが観察されている。
稲刈りに不在の夫や息子がはるか遠方で「いくさ」に従事して、残された「をみな」による近隣総出の「稲刈り」が詠われているので、中国戦線と三日月村という空間の対比と、「いくさ」の男たちと「稲刈り」の女たちというジェンダーの区別もまた鮮明に描かれたことになる。
ただしここでは「ふるさと」の歌に限定しているので、まもなく始まる太平洋戦争に関する歌は別の機会に紹介したい。
1940年(57歳)
日独伊三国軍事同盟が成立した1940年でも、
8.川柳 枝ふきみだす 風ありて かさゝぎいくつ とまりあへずも
としてふるさと情景が詠まれている。
川柳の枝がさかんに揺れるほどの強い風が吹いているなかで、これも日本では筑紫平野を中心に九州北部にだけしか生息しない「かささぎ」が題材となった。
「かささぎ」はカラス科の鳥ではあるが、尾が長く、肩と腹が白い。一説によると、秀吉による朝鮮出兵の軍が帰還する際に持ち帰ったとされる。それで「カチガラス」「朝鮮カラス」「高麗カラス」とも言われている。筑後方言では「コウケガラス」と呼ばれていた。通常の烏よりもおだやかな顔をしていて、攻撃性もない。
俳句では秋の季語であるので、情景としては秋の突風により、川端の柳が揺れすぎて、「かささぎ」がしっかりと柳の枝にとまれないことが詠まれている。「あへず」は(多く他の動詞連用形に付き)…「しきれない」ことを意味する(『基本古語』)。これもまた、生家付近の一コマであろう。
同じく三日月村の題材として、
9.車夫として 一生をすでに 老いにける 人も親しき ふるさとの驛
がある。
ふるさとの駅は国鉄(現JR)久保田駅であり、生家から徒歩で15~20分くらいかかる。明治大正時代には人力車が利用されたこともあり、それを引く車夫という職業に従事する男性も少なくなかった。最寄りの駅に常駐するのは現在のタクシーと同じであるから、自然と顔見知りになるのである。
『日本歴史大事典』(小学館、2007)によれば、最盛期の1896年には全国で21万台に達したとある。しかし相次ぐ路面電車の普及やクルマの増加により、減少の一途をたどることになった。「『日本歴史大事典』では、「人力車夫は都市の『貧民』の代表的存在でもあった」という記述もある。
『イラストで見る昭和の消えた仕事図鑑』(KADOKAWA、2021)によれば、「人力車」にも階層があり、上から「おかかえ」、「やど」、「ばん」があり、最後が「もうろう」(朦朧が語源)と呼ばれたとしている。詠われたのが駅の常駐だから、おそらくは「ばん」(組織化された車夫集団が、駐輪場で待機し、客から求められて運転する)(同上:54-56)であったであろう。
その顔見知りの車夫が年を取り、ふるさとの久保田駅の出口で親しく挨拶をする情景が優しく歌われている。もちろんその裏側には、57歳の高田もまた老いに直面していた。
珍しく職業が題材になっていて、景観としては「車夫と駅」が連結しながら、「人、一生、老い」という感慨がそれに重ねられて、「ふるさとの駅」で合体した。
高田の日常は病いとの闘いないしは共存であったから、
10.病みぬれば 心しみじみ よりていく わがふるさとは 遥なるかな
もある。
顕彰会の「年譜」によれば、1940年12月に「胃疾」のため京大病院に1ヵ月入院とある(高田保馬博士顕彰会、前掲書:243)から、この時期に作られた一首であろう。
病気のために動けないが、こころは遠くふるさとを偲ぶ。「よりていく」は「寄る」だが、単にふるさとに近づくというのではなく、むしろふるさとに「こころが向く、ひかれていく」(『基本古語』)のだろう。しかし、佐賀県三日月村は京都からははるかに遠いという感慨が込められている。
上の句では、病気になり、心はふるさとに向かうという動きが一方ではあり、下の句でははるかかなたの佐賀のふるさとは全く動かない、そして自分もまた動けないという諦観も感じられる。
1942年(59歳)
太平洋戦争中の1942年の歌には、
11.暮れなづむ 夕の空を けさやかに 隈どりて長し ふるさとの山
がある。
この時期は翌年の民族研究所・所長の就任や44年の京大定年退職の準備があり、ふるさとには帰れなかった。その日常が日没前のふるさとの景色を思い出させて、この歌を詠ませたのだろう。「ふるさとの山」は天山であり、生家から遠望できる。
興味深いことに今回使った『洛北集』(甲鳥書林、1943)の奥付の承認印はいつもの「高田」ではなく、「天山二郎」が押されている(写真1)。残りの写真3葉はいずれも「高田」が押されていた。手持ちの高田本では、『マルクス経済学論評』(改造社、1934年)にも「天山二郎」が押印されている。
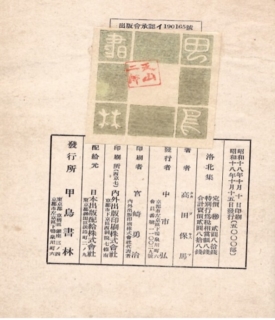
写真1 『洛北集』(1943年)奥付
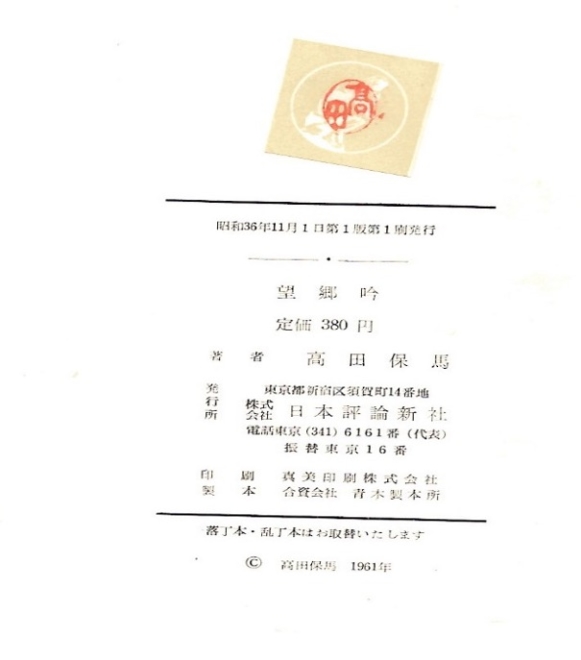
写真2 『望郷吟』(1961年)奥付
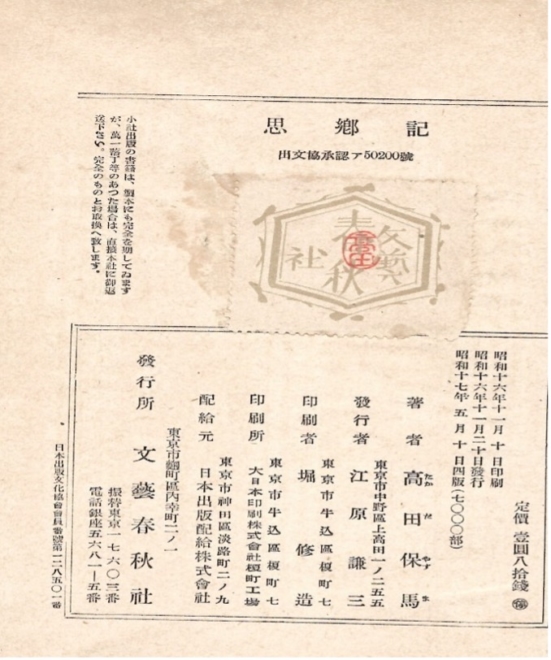
写真3 『思郷記』(1941年)奥付
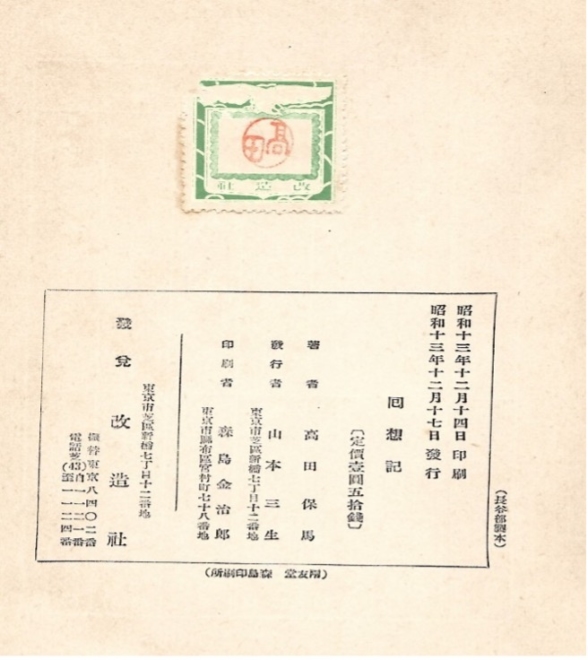
写真4 『回想記』(1938年)奥付
天山二郎
さて、「暮れなづむ」は「泥む」で、滞ることを意味するので、なかなか暮れない時間の流れを表している。夕焼けの空が暗くならない中で、遠望すれば、天山が夕暮れの中にくっきりとその姿を浮かべている。
「けさやか」の「け」は接頭語であり、「動詞・形容詞に付いて…の様子だ、…というぐあいだの意を添える」(『基本古語』)。それで、「さやか」(清か・明か)なので、「けさやか」は視覚的にはっきりしたさまを意味する。夕暮れなのだが、遠くの山並みの稜線がまだはっきりと見えるのである。「天山二郎」面目躍如」というところか。
1942年(59歳)
同じ年には、
12.ふるさとに 老姉とはむ よもぎ餅 幼(いとけな)き日の おもかげに立つ
がある。これもまた、幼い頃に姉と一緒に食べた「よもぎ餅」を通して、ふるさとを偲ぶ歌である。
「ふるさと」が「おもかげ」のなかにあり、いまは老いた姉も高田も「幼かった」ころの風景の一コマである。「はむ」は「食む」で、たぶん自家製の餅を一緒に食べたふるさとの春の思い出なのだろう。「よもぎ」も「よもぎ餅」も春を表わす季語である。
1943年(60歳)
そのふるさとにも戦火が近づき、1943(60歳)では
その直前に(函館にて親戚に別る)
13.肉親の きづなしみじみ 思ほゆれ 會うてすなはち 別れ来にける
がある。
本連載ではいずれ北海道旅行中に詠まれた歌も紹介するが、13もまた「北海道旅中吟(五月下旬)」の一首である。『洛北集』では、冒頭に1931年の「北海道への旅」で詠まれた歌が11首、末尾には1938年「北海道旅中吟」として25首が掲載されている。
肉親のきづなで函館で会ったものの、すぐにも別れてしまう。血縁者が函館に出かけた高田に会いにきたのだが、それは直後に別れるためであった。血のつながりをしみじみと感じながら、「會うてすなはち」(会ったその場で)別れることになる無常さが滲んでくる。
これもまた「時代」なのであろう。
(次回につづく)
【参照文献】
- 小西甚一,1969,『基本古語辞典』<改訂版> 大修館書店.
- 澤宮優・平野恵理子2021,『イラストで見る昭和の消えた仕事図鑑』KADOKAWA.
- 小学館編集部,2007,『日本歴史大事典』小学館.
- 高田保馬,1938,『回想記』改造社.
- 高田保馬,1943,『洛北集』甲鳥書林.
- 高田保馬博士顕彰会,2004,『社会学・経済学の巨星、世の先覚者 高田保馬』同顕彰会.
- 吉野浩司・牧野邦昭編,2022,『高田保馬自伝「私の追憶」』佐賀新聞社.
【関連記事】
・高田保馬の「感性」と「理性」①:高田保馬とは誰か?
・高田保馬の「感性」と「理性」②:歌集からの「感性」分析の方法論













