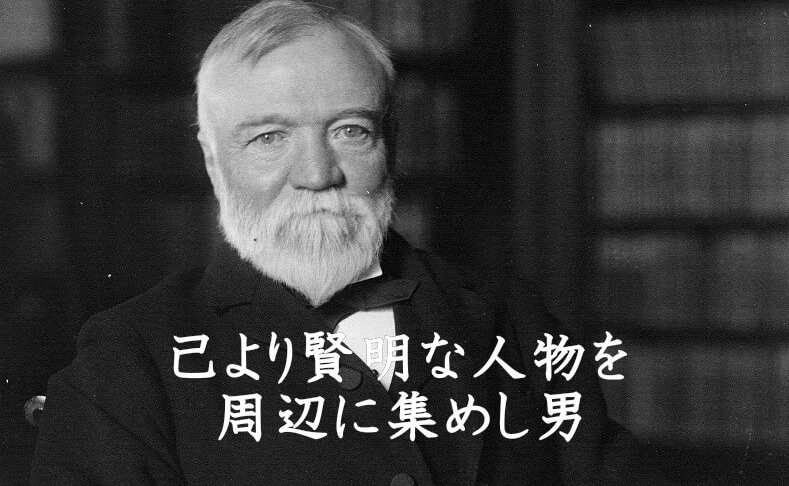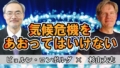安岡正篤先生は指導者に求められる三つの恥として、「親孝行をしない」「優秀な人材を活用しない」「人のために尽す徳業がない」を挙げておられ、此の事はそれなりに皆尤もなことだと思います。「親孝行をしない」ということで言えば、『孝経』の中にも「孝は徳の本なり…親孝行というのは全ての道徳の根本である」とありますが、自分の親を愛せない者がどうして妻を愛したり子供を愛したり出来るのかということです。まして他人おいてをやでしょう――上記は以前、私が「北尾吉孝日記」中で述べた言葉です。
「親孝行をしない」については、正に上記の通りです。本ブログでは以下、残り2点につき私が思うところを申し上げておきます。先ず、「優秀な人材を活用しない」。例えば既に亡くなった方で名前までは出しませんが、嘗て某企業の経営者は二番手を悉(ことごと)く切ることで有名でした。副社長をぱっと切り捨てて言うセリフは何時も、「人がいない、人がいない」と。自分のポジションに強く執着し、自分は続けられるようするために、周りに優秀な人材を置かなかったのです。残念ながらそうした類は現実に、いると言わざるを得ません。
対照的には、米国の「鉄鋼王」アンドリュー・カーネギー(1835年-1919年)が挙げられます。彼の墓碑銘には「己より賢明な人物を周辺に集めし男、ここに眠る」と書かれています。リーダーとして大事なのは、如何なる大志を抱き如何に優秀な人を多く集わせて、彼等彼女等と共に自分がやるべきを明確にし、その志念を共有化して行くというプロセスです。志という字は武士の士に心と書きますが、「士という字を見ると、十と一。十は大衆、一は多数の意志を責任を持って取りまとめること、あるいはその人たちの一般的指導者を表します。ゆえに志とは公に仕える心、多くの人を引っ張っていく責任の重たい士の心」(拙著)を言うのです。
次に、「人のために尽す徳業がない」。何時の世にでも社会的課題は山積しています。徳業とは、その克服の一助となる事業を世の為人の為やって行くことです。そういう意味から言うと、徳業など山程あります。にも拘わらず「人のために尽す徳業がない」のは、自分の徳が十分ではないからでしょう。「徳は事業の基(もとい)なり。未だ基固からずして棟宇(とうう)の堅久なる者有らず」(『菜根譚』)――事業を発展させる基礎は徳であり、此の基礎が不安定では建物が堅固ではあり得ません。事業とは真に徳業でなければ、長期的には存続し得ないのです。
経営者は世の為人の為という志を抱き、世の為人の為になる製品やサービスの提供あるいは利便性の向上等に、真摯に取り組まねばなりません。「君子は義に喩(さと)り、小人は利に喩る」(『論語』)と言いますが、徳無き事業「利業」だけで行くと、その弊害は必ず出てき、会社は必ずおかしくなります。私自身は、「公益は私益に通ず」と信じています。つまり、世の為人の為になる活動をして行けば、軈(やが)て自らの利益にも繋がるということです。ですから、SBIグループ創業以来、徳業を目指してきました。
編集部より:この記事は、「北尾吉孝日記」2024年5月20日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方はこちらをご覧ください。