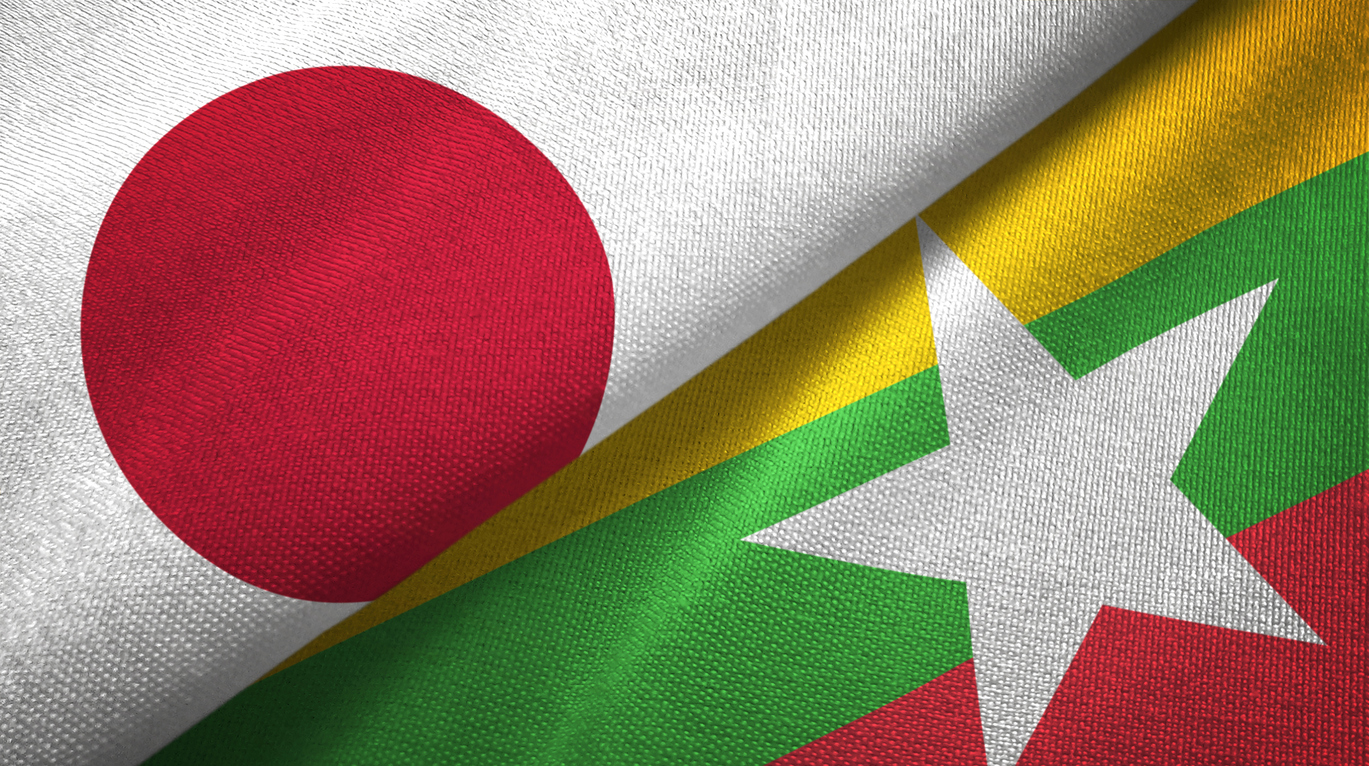
Oleksii Liskonih/iStock
日本ミャンマー協会会長の渡邉秀央(わたなべ・ひでお)氏が7月31日に死去していたことが報道された。自民党で衆院議員を6期務め、内閣官房副長官、郵政相などを歴任し、自由党や民主党などでも参院議員を2期務めた。そして官房副長官だった時期にミャンマー国軍と交流した際の人脈を活用し、政界引退後の2012年に「日本ミャンマー協会」を立ち上げて会長に就任した。
2012年当時と言えば、長期にわたって軟禁されていたアウン・サン・スーチー氏が解放されて政治活動を再開させ、ミャンマーの民主化への期待が膨らんでいたときであった。日本ミャンマー協会は、「ミャンマーはアジア最後のフロンティア」という謳い文句で高まった日本の政・財・官界のミャンマーへの関心を組織的に誘導するために、大きな役割を果たした。
私自身、2021年ミャンマー国軍によるクーデターが発生した後、ミャンマー情勢について論じさせていただいた時期に、頻繁に渡邉氏について言及させていただいた。


ミャンマー国軍は、戦中に日本帝国軍が設立した、という神話があり、右翼業界で、特別視されている。故・渡邉氏の場合には、その種のイデオロギー的視点に立ったミャンマー国軍擁護の発言が目立つ人物であった。渡邉氏の子息である日本ミャンマー協会事務総長・渡邉祐介氏が、「欧米諸国は愚かだ、ミャンマー国軍と提携して中国に対抗しよう」、という内容の文章を、英字紙『The Diplomat』に投稿して、話題になったこともあった。

この問題は、渡邉親子らの視点からは、人権擁護・民主派が、現実離れした主張で日本の国益を貶めている、というふうに映るらしかった。その観点から見れば、私も立派な人権擁護・民主派であったかと思う。
だがそのような不毛な偏見で隠されてしまっていたのは、果たして故・渡邉氏らの思想は、現実的なものだったのか、ということだ。私が終始問い直したかったのも、その点だ。
21年のクーデター以降、ミャンマー国軍が、国土を平穏に統治している、などということは起こっていない。戦乱が広がっているだけではない。国軍側は、民主派・少数民族派の動きに対して、劣勢だ。私に言わせれば、国軍の力と権威を盲目的に信じて、国軍関係者に投資し続ける態度こそが、現実離れしたものだった。
この問題は、より広い視点に立った時の日本の対外援助のあり方への問いにも直結している。日本のODA(政府開発援助)は、20世紀の草創期に、アジア中心に実施され、大きな成果を出したと評価されている。それはアジア諸国、特に東南アジア諸国が、飛躍的な経済発展を遂げたことによって、裏付けられていると考えられている。特に日本のODA成功の神話を支えているのは、円借款の形で貸し付けたODAが、発展した東南アジア諸国から利息付きで返還されてきたことだ。
ODAはビジネスになる、ODAをビジネスに活かさなければいけない、という視点は、ちょうどミャンマーが「アジア最後のフロンティア」と位置付けられていた第二次安倍政権発足時に、確立された考え方となった。
1990年代に世界一のODA国になってからしばらくの間は、世界的な援助の潮流にあわせた王道路線で、日本の地位を確立しようとする動きが高まった。国連難民高等弁務官として活躍した経験を持つ緒方貞子氏がJICA(国際協力機構)理事長だった時代(2003~2012年)には、アフリカ向けのODA予算が増大し、特に貧困対策などの活動が主流となった。
しかし第二次安倍政権時代に、アジア向けのODA予算額が復活していく。JICAの部署で一番景気がいいのは中小企業振興課(日本の中小企業にODA事業を活用して海外進出することを促進する部署)だ、と揶揄されるような時代が到来した。ODAを日本の経済力の復活に活用する、という視点が、主流化したのである。東南アジア諸国がもはや日本のODAを必要としなくなっていく中で、ミャンマーは残された未開の有望株として「最後のフロンティア」と喧伝されたのである。
JICAがJBIC(国際協力銀行)を吸収合併したのは、2008年のことであった。この小文で統合の評価をするのは難しく、適切ではない。ただ当初派手に言われていたほどの完全統合が実現したわけではない、ということだけを確認しておけば、十分だろう。
歴代のJICAミャンマー事務所長は、有償資金協力(貸付業務)を行うJBIC系の出身者の人事で固められている。毎年1,000億円以上を円借款でミャンマーに投入していたのだから、当然ではある。
全ては、「アジア最後のフロンティア」であるミャンマーが、他の東南アジア諸国のように経済発展して、ODAを媒介にしてミャンマーに進出した日本企業を潤わせ、さらには利息付で借入額を日本に返還していく、という故・渡邉会長らが政財官界の有力者に力説していたシナリオは、必ず現実化する、という見込みに基づいてのことであった。
果たしてこの故・渡邉会長のバラ色の構想は、本当に、日本がミャンマー国軍を気遣い続けさえすれば必ず実現するはずの「現実的」なものだったのか。貸し付けたお金が踏み倒されたり、焦げ付いたりする恐怖におののくあまり、日本外交の行動範囲すら不必要に狭めてしまうような可能性は全くない、と断言することこそが、「現実的」だったのか。
私は専門を「紛争分析・平和構築」という領域で持っており、その観点から国際協力活動なども観察している。私に言わせれば、2010年代からミャンマーの「民主化」は危うい薄氷を踏むプロセスでしかなかった。「アジア最後のフロンティア」は、政治情勢を度外視して、自己都合で勝手な期待をミャンマーに投影していた方々が語っていた夢物語でしかなかった。
それにもかかわらず、2021年クーデター以降においてすらなお、ミャンマー国軍と運命共同体で突き進む覚悟を定めるなどという態度は、全く「現実離れ」したものでしかなかった。
ミャンマーの現在の状況を見て、そして日本外交の手詰まり感を見て、私自身は、2024年8月現在、まだ自分のほうが正しいかったのではないか、と考えている。
■














