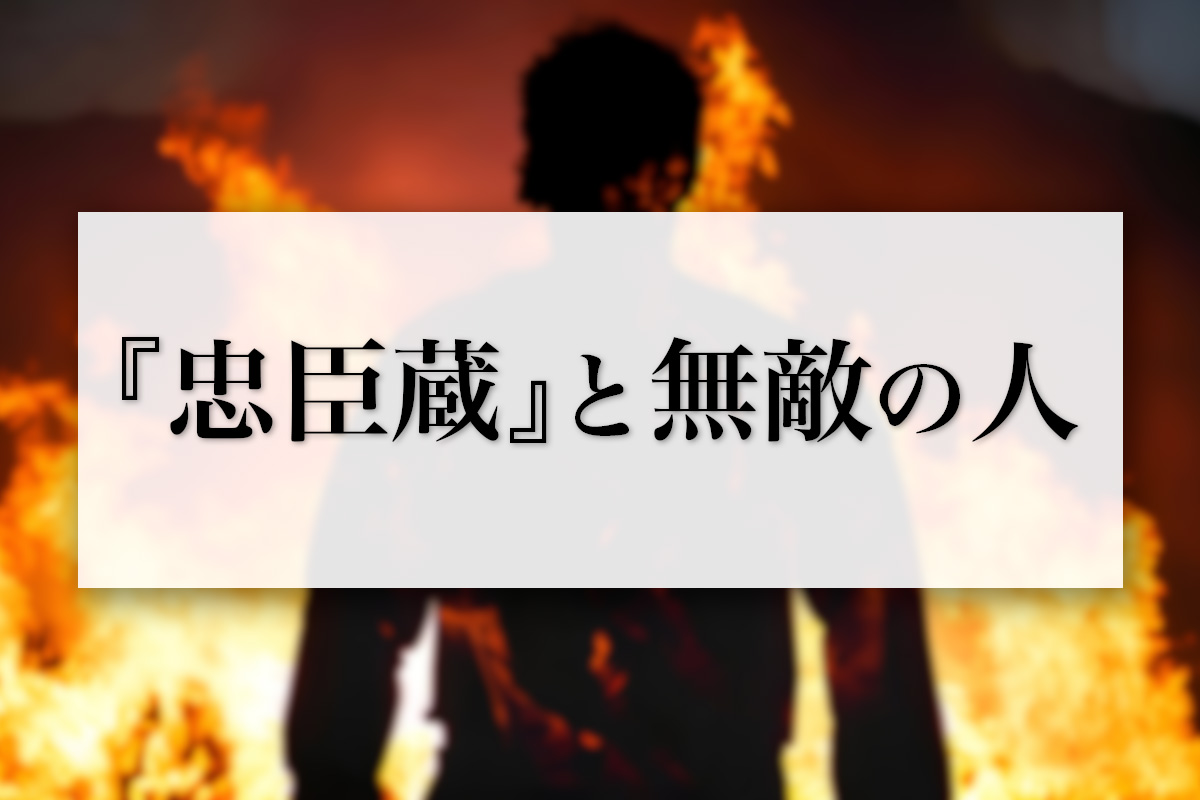かつて毎年12月は、『忠臣蔵』の映画やドラマが公開・放送されるのが慣例となっており、師走の風物詩であった。元禄15年(1702年)12月14日は、大石内蔵助率いる赤穂浪士が吉良邸に討ち入りをした日だからである。
ふと赤穂浪士の討ち入りを思い出すと、「無敵の人」事件を連想した。失うものが何もないゆえに自暴自棄となり凶悪犯罪に走る人物をネットスラングで「無敵の人」と呼ぶ。近年は「無敵の人」による犯行と思われる事件が相次いだ。

TDL/iStock
京都アニメーション放火殺人事件を起こした青葉真司被告の裁判員裁判で、京都地方裁判所は今年1月25日、死刑判決を言い渡した。青葉被告は不幸な生い立ちで、人間関係や仕事に恵まれていなかったようである。
安倍元首相銃撃事件で殺人などの罪で起訴された山上徹也被告の公判前整理手続き(裁判の前に証拠や争点などを絞り込む手続き)も進行中である。山上被告は、母親の統一教会入信により家庭が崩壊したと主張している。
岸田文雄前首相の演説会場で爆発物を投げ込んだとして殺人未遂や爆発物取締罰則違反などの罪で起訴された木村隆二被告の初公判も来年2月に行われる。木村被告への取り調べでは、被告が引きこもりだったことに検事が触れ、「かわいそうな人」「木村さんの替えはきく」などと人格否定発言をしたことが問題になった。
意外かもしれないが、江戸時代から現代に至るまで「忠義の武士」として絶大な人気を持つ赤穂浪士(四十七士)にも「無敵の人」の側面があった。赤穂浪士は主君浅野内匠頭(長矩)の恨みを晴らすためと称して、吉良上野介(吉良義央)を討ったが、良く知られているように、彼らは最初から討ち入りで意思統一できていたわけではない。
浅野内匠頭が吉良上野介を江戸城で斬りつけた、いわゆる松の廊下刃傷事件が起こったのは元禄14年(1701年)3月14日で、浅野内匠頭は即日切腹となった。赤穂藩は改易となり、4月19日には赤穂城を明け渡した。
だが赤穂浪士の指導者であった大石内蔵助(良雄)は、主君の仇討ちよりも、浅野内匠頭の弟である浅野大学(長広)による御家再興を目指していた。筆頭家老だった大石の立場からすれば、それは当然の行動だった。大石はむしろ入念な討ち入り準備を口実に、堀部安兵衛(武庸)ら早期の討ち入りを主張する江戸急進派の暴発を抑えていたのである。
ところが元禄15年7月18日、浅野大学が広島藩浅野宗家にお預けとなり、御家再興は絶望的となる。赤穂藩が再興されない以上、無職となった赤穂浪士たちが武士に戻ることはほぼ不可能である。これにより大石内蔵助は同志を集め、吉良邸討ち入りを決定する。赤穂浪士たちは失うものが何もなくなったからこそ、討ち入りを実行したのである。
では、赤穂浪士はなぜ討ち入りを行ったのか。『忠臣蔵』の影響で一般には「主君への忠義」と考えられているが、同時代史料を見ると、必ずしもそうとも言えない。
元禄14年8月8日、江戸の堀部安兵衛は山科の大石内蔵助に対して書状を送り、決起を促しているが、その中には興味深い一節が見られる。江戸では、身分の上下を問わず、町人たちも、赤穂浪士たちは必ず吉良邸に討ち入りすると噂している、というのだ。
堀部は同年8月19日の書簡でも、御家再興を優先する大石を批判し、浅野内匠頭様の仇を討たなければ、仮に大学様が百万石を与えられたとしても一人前の武士とは認められないだろう、という世間の噂を伝えている。形式的には浅野大学の名誉のために討ち入りすべきと主張しているが、実際には、堀部自身の名誉のためであろう。
堀部は「高田馬場の決闘」で活躍したことで江戸庶民に広く知られていた。剣客として名高い堀部は世間の評判を気にしており、世間が期待する主君の仇討ちを行わなければ、武士としての自分の面目が立たないと考えていたのである。
赤穂浪士の討ち入りには、将来を閉ざされ「無敵の人」となった彼らが、野次馬の無責任で過激な意見に煽られた側面がある。これは現代にも通じる教訓ではないだろうか。
青葉被告は公判で、秋葉原で無差別殺傷事件を起こした加藤智大・元死刑囚のことを「他人事とは思えなかった」と語っている。当時のワイドショーが秋葉原事件を連日煽情的に報道したことが、青葉被告に悪影響を与えた可能性はあるのではないか。
青葉被告の犯行は被害妄想に基づく独善的・自己中心的なもので、彼に同情する声は少ない。しかし安倍晋三元首相銃殺事件を起こした山上徹也被告に対しては「義士」と称賛する声が散見された。
前述の通り山上被告にも、不遇な人生を送ってきたという意味で「無敵の人」の側面がある。彼を英雄視したり彼の境遇に同情したりするような風潮は、「無敵の人」による犯行を助長しかねない。この手の世間の反応や報道姿勢、犯行動機の憶測には、いま一度注意深く考える必要がある。