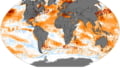2024年の消費支出に関する総務省の家計調査によると、日本の家計における食費の負担がかつてないほど増していることが明らかになりました。
個人消費、食料高が重荷 エンゲル係数43年ぶり高水準https://t.co/StalkPxGZC
— 日本経済新聞 電子版(日経電子版) (@nikkei) February 7, 2025
消費支出全体は実質で前年比1.1%減少し、1世帯あたりの平均消費支出は30万243円となりました。そのうち食費の割合を示すエンゲル係数は28.3%に達し、1981年以来の高水準となりました。

maroke/iStock
食品価格の高騰が家計を直撃しています。特にコメは前年比27.7%の値上がり、生鮮野菜や果物も大幅に価格が上昇しました。
11/17日経「エンゲル係数 日本圧迫」消費支出に占める食費の割合を示すエンゲル係数が日本で急伸し、G7で首位となっいる。エンゲル係数が高いのは貧しい発展途上国とされてきましたが、「衰退途上国」の日本でも同じことが起きているようです。 pic.twitter.com/Rka9jkP7mU
— 橘 玲 (@ak_tch) November 17, 2024
一般的に、エンゲル係数が高い国は発展途上国とされてきました。つまり、現在の日本の家計に余裕がないことを示唆しています。
これ、想像以上に深刻な問題で、
要はエンゲル係数が上がりまくってるから、ふりかけがおかずの代用品になってるってことだからね。牛肉が高い→豚肉で代用しよう。
豚肉が高い→鶏肉で代用しよう。
鶏肉すら高い→おかずが作れない。→ふりかけにしよう。 https://t.co/uXG0jFZWor
— 生活保護ごはんアカウント (@NAMAPOMESI) November 28, 2024
もちろん、近年は外食の普及や食文化の変化もあり、エンゲル係数がそのまま貧困度を示すとは言い切れませんが、物価上昇が家計を圧迫し、実質賃金の伸びが追いつかないまま、日本の貧困化が進行している可能性には留意すべきです。
外食が増えたので、エンゲル係数は昔ほど貧困の指数ではないが、外食の値段がすごく上がった。インフレで貧困化が進んでいる。 https://t.co/4hsOvYnHgw
— 池田信夫 (@ikedanob) October 19, 2024
内閣府の1月の消費動向調査によると、2人以上の世帯のうち「1年後に物価が5%以上上昇する」と予測している人は5割を超えました。消費者心理も萎縮する一方です。
日本で「インフレ期待」が起こらない一つの原因は高齢化。
現役世代はインフレで賃金も上がるが、年金生活者にとってはインフレは絶対悪だから、需要の価格弾力性が高い。それが新型スタグフレーションの原因かもしれない。 https://t.co/wBd1tBweUp— 池田信夫 (@ikedanob) July 5, 2024
一方で、日本の農業を保護するために高関税が維持され、その結果、国内の食料品価格は上昇し続けています。
農業もそうですね。高齢化し弱小の日本農業を守るために高関税にして、日本のエンゲル係数は約30%、アメリカの15%の2倍、生活がだめになる。
飼料も肥料もエネルギーもほぼ輸入しているのに、最後に口に入る「食料自給率」とか言うお経。 https://t.co/JW27qawVTF— 魏徴X (@GICHOGI) November 24, 2024
エンゲル係数の上昇こそが、日本経済の実態を最も端的に示しているのかもしれません。
GDPよりもエンゲル係数のほうが正しい経済指標であると言う学派はあったかな。
— 戯画兎 (@giga_frog) February 2, 2018
生活が苦しくなり、食費の割合が増え、自由に使えるお金が減っていく――。それでも、政府は「緩やかな回復基調」などと言い続けるのでしょうか。