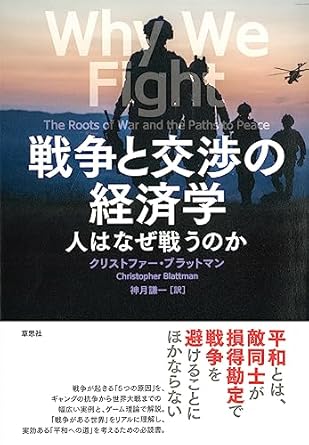Zephyr18/iStock
国際関係論/国際政治学(IR:International Relations)は、独立した社会科学の1つの専門分野とみなされることもありますが、この学問の本場ともいえるアメリカの大学・大学院では「政治学部(Department of Political Science/Politics/Government)」で学んだり、研究したりするのが一般的です。
その「政治学」は、この数十年で「科学化」が進みました。高度な統計テクニックを駆使した「仮説・検証」型の論文や実験政治学の研究が増えたのです。こうした政治学における「定量アプローチ(quantitative approach)」は、ラリー・バーテルズ氏(バンダービルト大学)から「定量帝国主義」と痛烈に批判されましたが、その勢いは衰えていないようです。
はたして、国際関係論は本当に「政治科学化」、すなわち定量的アプローチに支配されてしまったのでしょうか。この重要な問いに1つの答えをだしたのが、ジェフ・コルガン氏(ブラウン大学)です。
かれはアメリカの主要な政治学部の大学院教育に着目して、そこにおける国際関係論のコアー科目で必読文献として学生に予習を課している学術書や論文などを網羅的に調べることにより、その政治科学化の程度を論文「国際関係論はどこへ行くのか―大学院教育からのエビデンスー」(Jeff D. Colgan, “Where Is International Relations Going? Evidence from Graduate Training.” International Studies Quarterly, Vol. 60, No. 3, 2016, pp. 486–98)において明らかにしました。
その結果は、意外にも国際関係論はそれほど「政治科学化」していないし、理論を置き去りにする「仮説・検証」の研究が過度に評価されているわけでもないということでした。
この論文の主な発見は次の通りです。
第1に、国際関係論(IR)と政治学の部分的な分離が生じているということです。政治学の「ビッグ3学術誌」(APSR:American Political Science Review, AJPS:American Journal of Political Science, JOP:Journal of Politics)の内、国際関係論でトップ3に入るのはAPSRのみであり、IO:International Organizationが突出して1位、IS:International Securityが3位に位置づけられています。
第2に、「仮説・検証」の計量分析の論文は、出版されている本数に比べるとシラバスでの採用数が低いことも分かりました。必読文献のトップはケネス・ウォルツ著『国際政治の理論(Theory of International Politics)』(勁草書房、2010年〔原書1979年〕)であり、2位はジェームズ・フィアロン氏(スタンフォード大学)の画期的な論文”Rationalist Explanations for War”(International Organization, Vol. 49, No. 3, 1995, pp. 379–414)の師弟コンビによる研究です。
前者については、拙ブログ記事「K. ウォルツ『国際政治の理論』と日本の国際政治学」、後者については「戦争のバーゲニング理論再考」で解説していますので、よかったらお読みください。
フィアロン氏の論文には、私の知る限り、邦訳がありませんので、原文を読むしかないようです。なお、かれの理論を構成する2つの中核概念である「コミットメント問題(commitment problem)」と「私的情報(private information)」と戦争の関係については、クリストファー・ブラットマン氏(シカゴ大学)が『戦争と交渉の経済学―人はなぜ戦うのか―』(草思社、2023年)で豊富な事例を使いながら、丁寧に解説していますので、興味のある方は、ぜひとも、ご一読することをおススメします。
第3に、定性志向か定量志向の学術誌のどちらかを重視するという、アメリカの政治学部の大学院の分断化もみられます。
私が重要だと思ったのは、大学院教育がそれぞれ異なりすぎると、相互知識の空白が生まれてしまうために、大学間の交流が難しくなるので、たとえ指導教員が必ずしもあまり価値を見いださなくても、画期的な研究にふれることは、大学院生にとってためになる、というコルガン氏の指摘です。
我が国の「国際関係論(国際政治学)」には、「理論系」、「歴史系」、「地域系」、「思想系」などがあり、それらが学問の多様性を保っているとしばしば肯定的に評価されるようです。
確かに、これには一理あるのですが、このコインの裏側は、日本の国際政治学が体系化されていないということでしょう。それぞれのアプローチに立脚する研究者が、他のアプローチの研究者と対話しようとしても、そもそも共通の学問的基盤がなければ、それは不毛に終わりかねません。
私は、こうした問題の深刻さをウクライナ戦争に関する学者との意見交換で痛感しました。すなわち、誠に残念ながら、日本の「国際政治学者」とは、ほとんどマトモな意見交換ができなかった一方で、アメリカの政治学者とは、それが成立したのです。詳しくは、私がアゴラに寄稿した「ウクライナ戦争をめぐるコープランド教授との対話:自由な言論空間の重要性」をお読みください。

ここで私が強調したいことは、知的交流や相互批判というものは、対話の土台があるからこそ成立するのではないか、ということです。
国際関係論における「方法論的多様性」は、いうまでもなく重要である一方、あまりにバラバラな学問体系は、学者同士の対話や知的蓄積を難しくするという見逃せない問題を生じさせます。日本の「国際政治学」は、後者の課題に対して、そろそろ真剣に取り組み、その答えをだすべき時に来ていると私は思ってます。