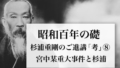私は、野党が再編するとするなら、そのキーマンの一人が政界を引退した足立康史氏だと考えている。
国会会での暴言王と言われたり、質疑の面白さばかりが注目されるが、実は、日本維新の会における知恵袋だったことは、意外に知られていない。野党議員の中でも、生粋の政策通であり、議員立法には抜群の能力を発揮していた。
来る7月の参議院選挙を前に、最近、各種の動画に出て、日本維新の会との軋轢や、国会の予算審議や法案審議についての見解を発言している。そこで、足立康史氏の動向について触れながら、今後の彼の越し方を邪推してみたい。
政界引退後の動き
- 衆院選での他党候補応援
- 足立氏は2024年10月27日投開票の衆議院選挙において、日本維新の会を離れた後、自民党や公明党の公認候補の応援に積極的に参加。特に注目されたのは、公明党の前職候補の応援演説で、「維新はいらない」と発言したこと。この行動は、維新との決別を明確に示すものとして話題になった。
- メディア出演と発信
- 引退後、足立氏がメディアを通じて活発な情報発信を行っている。たとえば、2025年3月27日にYouTubeチャンネル「楽待チャンネル」に出演し、経済ジャーナリストの須田慎一郎氏と対談。「【政治の裏側】『維新の足立はもう終わり』”辞め維新”足立康史が忖度なしでぶった斬る!」というタイトルで、維新や政治の裏側について語った。
- また、保守系月刊誌「WiLL」(2024年11月号)で「維新 最大の恥部を暴く」と題した記事を寄稿し、維新の内情を批判的に暴露した。
- 政界復帰の可能性
- 現在のところ、足立氏は明確に政界復帰の意向を示してはいないが、メディア出演や発言から政治への関心が完全になくなったわけではないと見られている。一方で、維新との関係が修復困難な状況にあるため、復帰するとしても別の形で政治に関与する可能性が考えられる。
政界に対する発言
- 政治の透明性や公正さを重視する姿勢は変わらず、経済産業省官僚出身の経験を踏まえた政策論を展開している。
- 2025年3月27日のYouTube対談では、橋下徹氏を「素晴らしい政治家」と評しつつも、現状の政治に対する問題を指摘。また、「国民の手取りを増やす努力」が政治の重要な課題であると強調し、これを阻害する動きに対して批判的な立場を取っている。
日本維新の会に対する発言
足立氏は引退後、日本維新の会に対して一貫して厳しい批判を展開。以下に主な発言を列記する。
- 党の体質への批判
- 「WiLL」の寄稿では、維新の馬場伸幸代表の強権体質、橋下徹氏のオーナー気取りな振る舞い、松井一郎氏の無節操さを名指しで批判。党が透明性や公正さを失い、「嘘まみれ体質」に陥っていると指摘。
- 2024年10月23日のX投稿では、「日本維新の会は、明日にも、選挙戦を停止して、解党した方がいい。このまま投開票日を迎えても、何の価値も生み出せない」と過激な意見を述べている。
- 政策への失望
- 2025年3月31日のX投稿で、「結局、国民の手取りを増やす努力に、茶々を入れ、水を差し、腰を折ったのが日本維新の会なのです。話になりません」と発言。維新が掲げる改革路線が実質的に空洞化しているとの見方を示す。
- 党の変質への嘆き
- 2025年3月27日の「楽待チャンネル」出演では、「日本維新の会は”空気を読む政党”に変わってしまった」と嘆き、かつての改革志向が失われたと批判。党員民主主義や政治資金の透明性改革が進まなかった点を問題視しました。
背景と動機
足立氏の維新批判の背景には、2024年6月に党から受けた6カ月の党員資格停止処分がある。この処分は、4月の衆院東京15区補選での党の機関紙配布が公職選挙法に抵触する可能性をSNSで指摘したことが原因。処分を受け、無所属での出馬を検討していたものの、維新が大阪9区に対抗馬を擁立したため、引退を決断。
この経緯から、党への不信感や「だまし討ちのようにされた悔しさ」(2024年10月9日、読売新聞インタビュー)が批判の原動力となっていると考えられる。
まとめ
足立康史氏は政界引退後、維新への批判を強めつつ、他党候補の応援やメディアでの発信を通じて政治への関与を続けている。
政界に対しては透明性や国民本位の政策を求める姿勢を維持しつつ、維新に対しては党の変質や政策の空洞化を厳しく非難。特に「解党すべき」「価値を生み出せない」といった発言は、党との完全な決別を示しているだろう。
今後の動きとしては、メディアや言論活動を通じて影響力を維持する可能性が高いものの、維新との関係修復は困難な状況。
足立康史 vs. 橋下徹
- 2017年の初衝突:番組批判を巡る応酬
- 発端: 2017年12月、橋下氏が告知したAbemaTVの番組「橋下徹のニッポン改造論」に対し、足立氏が「つまらん」とXでつぶやいたことがきっかけ。この番組は教育無償化をテーマにしていたが、維新の議員が呼ばれていなかったことに足立氏が不満を示した形。
- 橋下氏の反応: 橋下氏はこれに激怒し、「維新の国会議員は観ないでよろしい。理解できんやろうし、日本には不必要。早く消えろ」「足立の国会活動ほど独りよがりでつまらんものはない。早く国会から消えてくれ」と連続投稿で痛烈に批判。
- 足立氏の対応: 足立氏は翌日、「教育をテーマとする番組に維新議員が呼ばれないことに異議申し立てをしたが、ネット番組に政治的公平さを求めるのは間違いだった。謝罪して撤回します」と謝罪。これを受け、橋下氏も「僕の足立さんに対する表現を撤回し、謝罪します」と応じ、一時的に和解。
- 2021年の泥沼バトル:文通費問題と離党発言
- 背景: 2021年12月、日本維新の会内で文書通信交通滞在費(文通費)の改革を巡る議論が過熱。足立氏は党内討論会で「政治資金規正法に服することができないルールを強制するなら離党する」と発言し、波紋を広げた。
- 橋下氏の批判: 12月20日、橋下氏は 、「足立議員は自分の主張が通らなければ離党すると公言。このやり方は組織に絶対的に必要とされる者しか使えないカード。大物やねー。どうぞ離党してと言われたらどうするんやろ?このやり方は最後の手段。通らなければ離党するのみ。こんな手法を常に認める組織などない。分かってるよな?」と皮肉を込めて投稿。
- 足立氏の反論: 同日、足立氏は引用リプライで「もちろん、分かっています。今回の文通費問題の処理は、日本維新の会が更に飛躍していくために絶対に間違えてはいけないテーマであると腹を決め、臨んできました。こんな荒技、二度と使いたくないです」と返答。自身の行動が党の未来を懸けた決断だったと主張。
- さらなる応酬: 橋下氏は足立氏の態度を「謝罪すべき」と要求し、「足立議員は維新から退場すべき」とまでエスカレート。一方、足立氏は離党を示唆した発言を撤回せず、両者の対立は「泥沼バトル」としてメディアでも報じられた。
- その後の関係性
- 和解の兆し: 2021年11月、維新の代表選を前に、橋下氏はインタビューで「足立さんから謝罪を頂いたのでもう何もありません。今は良好な関係です」と発言し、過去の衝突を水に流したと強調。しかし、X上での直接的なやり取りはその後も散発的に続き、完全な和解とは言い難い状況が続いている。
- 2022年の再燃: ロシア・ウクライナ問題に関する橋下氏のコメントに対し、足立氏が「昨年末から壊れてる」と批判するなど、意見の相違が再び表面化。
特徴と傾向
- テーマ: やり取りは主に維新の政策(文通費改革、教育無償化など)や個人の政治手法に関する意見対立が中心。
- トーン: 橋下氏の皮肉や挑発的な口調に対し、足立氏は時に謝罪しつつも自身の信念を強く主張する姿勢が見られる。
- 影響: 両者の応酬は維新内部の緊張関係やイデオロギーの違いを浮き彫りにし、支持者やメディアの間で賛否を呼んでいる。
これが、SNS上における足立康史vs橋下徹の中身の概略。
足立氏の論調の一つが、この強烈な個性を持つ橋下徹氏が創始者となった維新の会批判に及ぶ。というのも、橋下徹のオーナー政党だった維新の会(大阪、全国の両方)が、維新の党是を忘れ、改革政党としての歩みを止めてしまったことを批判しているのかもしれない。
足立康史 vs. 維新の会
ではそんな足立康史氏は、維新の会批判をどのように展開してきたのだろうか?
足立康史氏は元々、経済産業省官僚として21年間勤務した後、2012年に日本維新の会の結党に参加し、国会議員として4期12年を務めた。特に党の国会議員団政務調査会長や憲法改正調査会長など要職を歴任し、維新の政策立案や大阪発の改革を推進する中枢メンバーだった。しかし、2024年6月に党員資格停止処分を受けたことを機に、維新との関係が決定的に悪化し、批判のトーンが強まっている。
きっかけ
2024年4月の衆院東京15区補欠選挙で、維新が公認候補の陣営を通じて機関紙を配布した行為を、足立氏がX上で「公職選挙法に抵触する恐れがある」と指摘。これが党執行部との対立を招き、6月に党員資格停止6カ月の処分が下された。
その後の動き
処分後、足立氏は当初無所属での出馬を模索。しかし、維新が大阪9区に新たな公認候補を擁立する方針を決定したため、2024年10月6日に次期衆院選不出馬と政界引退を表明。しかし、引退後も維新批判をやめず、自民党や公明党候補の応援に回るなど、維新への反発を明確に示す。
批判の内容と具体例
足立氏の維新批判は、党の運営方針、政策の方向性、人材育成の欠如など多岐にわたる。以下に主な批判ポイントを挙げる。
① 党運営への批判:独裁性と強権性の指摘
足立氏は、維新が「しがらみのない改革政党」を標榜しながらも、内部では独裁的・強権的な運営が目立つと主張。
例
自身の公式サイトで、「オーナー政党が独裁性や強権性を強める様子をまざまざと見せつけられた」と記述。具体的には、馬場伸幸代表や吉村洋文共同代表の下で、党内の異論が抑圧され、執行部の意向が優先される体質を問題視。
2024年10月の発言
維新が大阪9区に「刺客」を立てたことを「馬場代表の横暴」と呼び、党内の民主的な議論が欠如していると批判。
② 政策の方向性への不満
足立氏は、維新が当初掲げた「身を切る改革」や「大阪都構想」などの明確な目標を見失い、政策が曖昧になっていると指摘。
例
2025年3月14日の関西テレビの対談で、維新が自民・公明と新年度予算案で合意したことを「0点」と酷評。「財源確保に行財政改革『など』とあるが、『など』は増税しかない」と述べ、維新が大阪で進めた教育無償化の「大阪方式」を捨てて「東京方式」を採用した点を「政策立案の詰めが甘い」と批判。
全国政党化の失敗
2024年10月27日の関西テレビ「LIVE選挙サンデー」で、馬場代表に対し「維新の『全国政党化』は失敗だったのでは?」と追及。維新が大阪偏重から脱却できず、全国的な支持拡大に失敗していると主張。
③ 人材と組織への失望
足立氏は、維新の人材育成や組織運営が不十分だと繰り返し発言。
例
2024年10月25日、大阪での公明党候補応援演説で、「維新は小さい自民で、人材はいないし、政策もない。日本維新の会はいらない」と発言。維新が新たなリーダーや政策を生み出せず、自民党の補完勢力に成り下がったと見なしている。
批判を繰り返す理由
足立氏が維新批判を続ける動機は、個人的な確執だけでなく、彼の政治理念や維新への期待とのギャップに起因するのか?
理念との乖離
足立氏は維新の原点である「透明な政治、公正な経済、安心な社会」を実現する意欲を持ちつつ、それが現在の執行部の方針と一致しないと感じている。特に、党が大阪優先から全国政党化を目指す過程で、改革の軸がぶれたと見ているようだ。
処分への反発
党員資格停止処分を「不当」と受け止めつつも受け入れた一方で、執行部への不信感が強まり、批判を通じて維新の体質改善を促す意図がある可能性も。
政治的影響力の維持
引退後も発言を続けることで、維新内外での議論を喚起し、自身の政治的レガシーを残そうとしていると考えられる。これは私の邪推。
最近の動向
2025年4月1日現在、足立氏は政界引退後も維新批判を続け、特に2024年衆院選後の維新の動向に注目していると推測される。
選挙後の維新への影響
2024年10月の衆院選で維新が議席を減らし、大阪でも苦戦したことが報じられており、足立氏はこれを「予見していた」と主張する可能性が高い。
他党との連携批判
自民・公明との予算案合意や、維新が立憲民主党を「たたきつぶす」とした路線が中途半端に終わった点を、引き続き攻撃材料にすると予想される。
まとめ
足立康史氏の日本維新の会・大阪維新の会批判は、党内の処分をきっかけに表面化したものの、その根底には長年の党内運営や政策への不満が蓄積していたことが伺える。彼の批判は、維新が「改革政党」としての原点を失いつつあるという警告とも取れ、個人的な遺恨を超えた政治的メッセージを含むもの。引退後も発言を続ける姿勢からは、維新への愛着と失望が交錯する複雑な心情が垣間見える。
■
引き続き次回は、彼の政策に関して取り上げる。