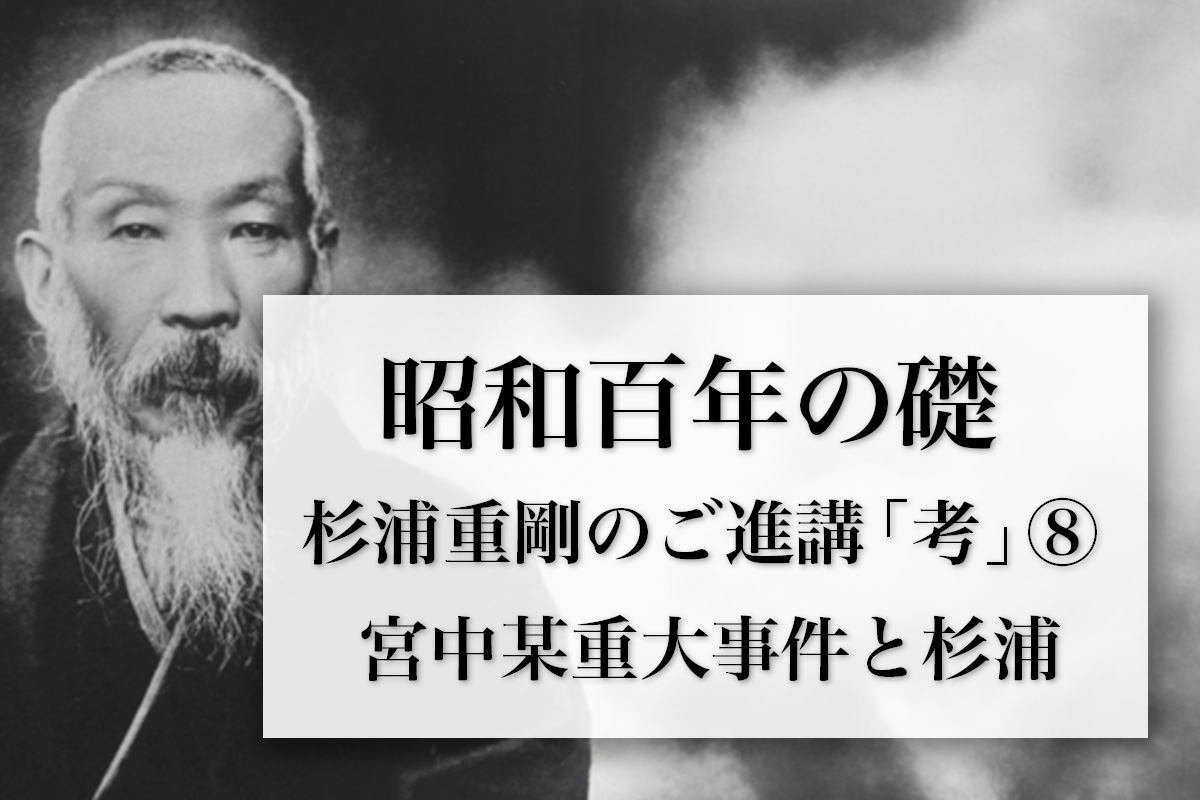
(前回:昭和百年の礎:杉浦重剛のご進講「考」⑦:「教育勅語」のご進講(2))
杉浦重剛と宮中某重大事件
本稿の最後に、裕仁殿下へのご進講とは少し離れるが、杉浦の人となりを知る上で欠かせない「宮中某重大事件」(以下、事件)と杉浦の関りに就いて述べる。
事件は良子女王殿下に関係していた。裕仁殿下に遅れること2年、1903年3月6日に久邇宮邦彦王と俔子妃(島津忠義公爵令嬢)の第1王女子として誕生した良子女王は、久邇宮邸に設けた御学問所で18年4月からご成婚までの5年余り、杉浦から「修身」の進講を受けた。
なお、女王殿下の進講御用掛には杉浦(修身)の他、鈴木元美(数学)、児玉錦平(仏語)、依田顕(化学)、小野潤之助(習字)、高取熊夫(絵画)、土取信(体操)、阪正臣(詩歌)、竹田みち(漢字)が任命され、後閑菊野が御学問所主任に当った(「児島本」)。それは、乃木が裕仁殿下に対して採った教育方式をそっくり模したものであった。
事件の嚆矢は、裕仁殿下が16年11月3日に「立太子礼」を終えた後、貞明皇后が始めたお妃探しにあった。良子女王が学習院女学部中等科3年に在学中の17年10月、皇后は中等科の授業を参観し、良子女王のおっとりと気品高い容姿をお目に留めた。
明けて18年1月14日、波多野宮内相から良子女王が裕仁殿下の妃に内定したことを伝達された久邇宮邦彦王は、宮中に参内し天皇皇后両陛下に内約受諾を言上した。婚約は1月19日に報道され、2月4日に良子女王は学習院を退学、4月13日からは杉浦らの進講が始まった。
皇后の参観から半年、婚約発表までは順調に進んだ。が、3カ月半後の18年5月初、元老山縣有朋公爵は赤十字病院前院長平井博士からある報告を受けて仰天した。博士は、学習院の色盲検査で良子女王の兄朝融王が色弱であると判り、将来、色盲遺伝の懸念があるという(「児島本」を参考にしたが、「モズレー本」には、20年に発行の医学雑誌に載った島津家の色盲の記事を平井博士が読み、山縣に知らせたとあり、山縣の陰謀を匂わせている。が、時期も話の筋も児島の記述に信憑性がある)。
元より芳しくなかった大正天皇の健康状態も、最後に国民の前に姿を見せたのが19年5月の東京遷都50年祭であり、12月26日の第42回帝国議会開会式臨御を中止したことからも推察されるように、皇太子ご婚約の頃から既に思わしくなく、山縣の驚きはひとしおで、平井博士にこう漏らした。
もし他日、帝国を統治し給う天皇に於かせられて、不幸にも紅緑の色彩を弁別し給わず、花も葉も一色と見、秋の紅葉も夏の緑葉も看別するの能力を欠き給う如き事ありては、ただご一身のご不幸のみならず、至神至聖なる皇統に永くかかる疾患を遺すは、真に恐懼の至りに堪えず・・
実は、邦彦王は宮内相から17年末に内意を受けた際、「わが家には、色盲または色弱症遺伝の疑問がある」と打ち明けていた。宮内相は出入りの医師による調査を勧め、邦彦王は「色盲遺伝子保有の女子が健全なる男子と結婚する時は、その出生の男子の半数だけ色盲になるが、その女子は皆健全にしてその子孫に色盲の遺伝することなし」との判定を宮内相に知らせていたのである。
が、そうとは知らない山縣は元老の松方正義侯爵、西園寺公望侯爵に事態を告げて相談した。結果、医学上の判断を明らかにしてから、然るべき方法で久邇宮家に婚約辞退を勧告すると決めた。鑑定した三博士連名の意見が18年10月に提出され、その要点は次のようだった。
- 色盲の家庭に生まれた健眼の女子と健眼の男子に生まれた女子は皆健眼だが、男子は半数が色盲になる
- 良子女王の場合はこれに相当し、王子の半数が色盲になる懸念がある
三元老は筆頭皇族の伏見宮博恭王が久邇宮家を説得するのが最善と決め、波多野氏の後任の中村宮内相を使者に立てて伏見宮に向かわせた。事情を聞いた伏見宮も愕然とし、「久邇宮に於いてご辞退在るを至当と考える」と述べ、翌11月上旬、久邇宮家にその意向を伝えた。
が、邦彦王は敢然として戦う決意を固めていた。邦彦王は、最初に良子女王に白羽の矢を立てた貞明皇后に「上(たてまつるの)」書を提出した。そこには、婚約を拝辞するのは次の二通りの場合しかないと記されていた。即ち・・・、
- 両陛下または皇太子殿下におかれて、その方が良いと思召されたとき
- 帝室の御血統に必ず弱点が発生するだろう、と邦彦王が自覚するとき
そして、17年末に波多野宮内相から内意を受けた後、宮家出入りの医師の「女子は皆健全にしてその子孫に色盲の遺伝することなし」との判定を得た上で、「安んじて誠意を以て御請け申し上げた」と、これまでの経緯が認められてあった。
ここで問題は、久邇宮家出入りの医師の鑑定と元老依頼の三博士との意見の相違、即ち、健眼の良子女王から産まれる男子に色盲が出るか否かに尽きる。そこで原敬首相は中橋文相を通じて、改めて東大教授5人から意見を徴することとし、その結果が18年12月21日にたらされた。
報告書には「色盲の遺伝については『メンデルの法則』が確立されている」とあり、邦彦王の子供に色弱がいるので、俔子妃は色盲因子保有者であるから、女王たちの半数が因子保有者となるとし、「而して、良子女王殿下が色盲遺伝子保有者に在らせられると然らざるとは、可能性相半ばす」と結論されていた。
つまり、良子女王が色盲遺伝子保有者でなければ問題ないのだが、その確率は50%であるというのである。そうした中、いよいよこの問題に杉浦重剛が介入するのだが、ここで筆者は、杉浦の英国留学中の研究論文が「独逸の進化学の白眉ヘッケル氏の書」に引用された一件を想起する。
へッケル(1834〜1919年)は、ドイツの生物学者、医者、哲学者であり、ダーウィンの進化論普及に貢献した人物であるから、杉浦が「メンデルの法則」に知悉していないはずがない。しかも事件が公になる20年頃には、杉浦の良子女王への進講は3年目に入っていたのである。
事実、邦彦王から相談も受けていた杉浦は20年12月4日、御学問所に辞表を提出して、以後の行動が皇室に迷惑を及ぼさないよう手配し、御学問所の東郷総裁、浜尾副総裁にも助力を求めた上で、両殿下のご成婚実現に向けて活動を開始した。裕仁殿下への進講は20年10月に終わっていたが、良子女王への残りの進講を修了して、お二人のご成婚を見届けるまでは死なないと決めていたのである。杉浦の論はこうであった。
そもそも婚約の破棄は、常人も不徳とする所である。それを些々たる体質上の欠点を理由として、皇室がこの不徳をおかされるのでは、帝国の皇道に一大瑕瑾をのこし、国民の道義を指導することはもはや不可能となろう。第一せっかく婚約成立した両殿下に対して、無残にも強いて之を割き奉らんか、御心身の上にいかなる結果を来すやもわからぬではないか。
こうした事情を打ち明けたからであろう、「玄洋社」の頭山満や「浪人会」の内田良平ら右翼の巨頭も動き出し(彼らには皇太子訪欧阻止の目論見もあった)、薩摩島津家の血を引く良子女王の皇室入りを面白く思わない山縣がこれを阻止しているとの陰謀説(「モズレー本」は専らこれ)や、北一輝・大川周明らの「猶存社」による山縣暗殺論の噂まで流れる始末となった。
そんな21年2月8日、3月3日から9月3日までの皇太子ご訪欧が正式決定、15日に報道される前に、原首相は8日の閣議で事件について話し、中村宮内相に、誰かが責任を取ってでも、事を収めねばならないと語った。中村は50%の確率に賭けることを決意(「児島本」)、山縣公説得に動く。公を訪れて諸般の状況を説き、自分の責任でご婚約に変更ない旨を発表したいと述べた。山縣はこう応えた。
宜しい。ことは頗る重大であるから、本来なら直ちに聖断を仰ぐべきだが、今日にては陛下は御脳の御宜しくない時であるから、それも出来ず。己(おれ)は純血論なれど、己の主張は採るに及ばず。貴様は気の毒であるが、事の落ち着きを見て辞さねばならない。己に遠慮はいらぬから貴様の思う通りにやれ。
斯くて、宮内庁は21年2月10日、「良子女王殿下東宮妃御内定の事に関し、世上種々の噂あるやに聞くも右御決定は何等変更せず」と発表した。こうして宮中を揺るがした某重大事件は落着、皇太子は3月3日、横浜港に浮かぶ御召艦「香取」艦上の人となった。
杉浦は御用掛に復帰して23年後半まで良子女王への進講を続け、24年1月26日のご成婚から18日後の2月13日、68歳10カ月の生涯を閉じた。これを小笠原長生は「果たすべきを果たし、尽くすべきを尽くした理想的忠臣の終焉として、真に申し分の無いもので、翁の人格を語るにはこの一事で沢山である」と語っている。
「回想本」に「追慕の涙」と題する追悼文を寄せた弟子の金光悌爾は、「詩歌」という題目に絡めて杉浦が漏らしたこんな話を披露している。それを紹介して稿を結ぶ。
今度は、女王殿下にもこの同じ題で御進講申し上げようと思う。今にね、御二人が御一緒になられた折に「杉浦翁がこんな事を申した事がある」などと御話合になる時節が来るんだからね、フフフフ・・
【参考文献】
「回想杉浦重剛―その生涯と業績」杉浦重剛顕彰会 1984年発行
「昭和天皇の学ばれた『倫理』御進講草案抄」杉浦重剛著/所功解説 勉誠出版 2016年初版
「教育勅語―少年昭和天皇への進講録」杉浦重剛著/所功解説 勉誠社 2024年初版
「杉浦重剛座談録」猪狩史山・中野刀水著 岩波文庫 1941年初版
「昭和天皇の教科書『国史』原本五巻縮写合冊」白鳥庫吉著/所功解説 勉誠出版 2015年初版
「天皇Ⅰ 若き親王」児島襄著 文春文庫 1980年初版
「天皇ヒロヒト 上」レナード・モズレー著 高田市太郎訳 角川文庫 1983年初版
「昭和天皇のご幼少時代」原敬関係文書研究会 NHK出版 1990年初版
「大正天皇」F・R・ディキンソン著 ミネルバ書店 2009年初版
「井上毅とヘルマン・ロエスラー」長井利浩著 文芸社 2012年初版
「教育勅語の真実」伊藤哲夫著 致知出版社 2011年初版
「奇跡の昭和天皇」小室直樹著 PHP研究所 1985年初版
「乃木希典」福田和也著 文春文庫 2007年初版
「小村寿太郎とその時代」岡崎久彦 PHP研究所 2010年初版
【関連記事】
・昭和百年の礎:杉浦重剛のご進講「考」①
・昭和百年の礎:杉浦重剛のご進講「考」② ご進講の題目と内容
・昭和百年の礎:杉浦重剛のご進講「考」③:「致誠日誌」を読む(1)
・昭和百年の礎:杉浦重剛のご進講「考」④:「致誠日誌」を読む(2)
・昭和百年の礎:杉浦重剛のご進講「考」⑤:「致誠日誌」を読む(3)
・昭和百年の礎:杉浦重剛のご進講「考」⑥:「教育勅語」のご進講(1)
・昭和百年の礎:杉浦重剛のご進講「考」⑦:「教育勅語」のご進講(2)













