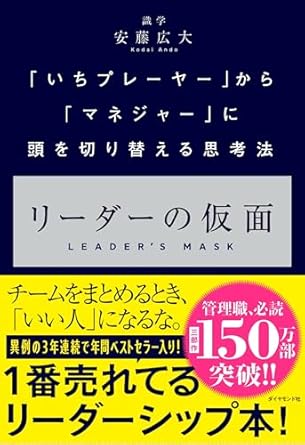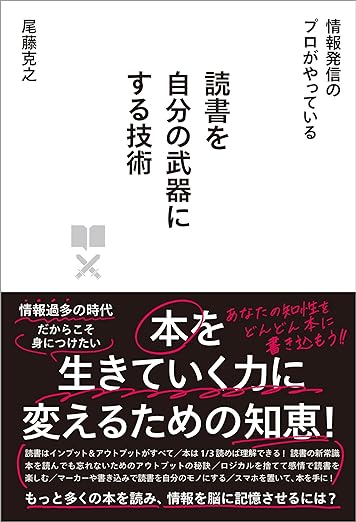tadamichi/iStock
「識学」とは、組織内の誤解や錯覚がどのように発生し、どのように解決できるか、その方法を明らかにした学問です。
今回は、「若手リーダー」に向けた刺激的なマネジメント論を紹介します。
「リーダーの仮面」(安藤広大著)ダイヤモンド社
[本書の評価]★★★★★(90点)
【評価のレべリング】※ 標準点(合格点)を60点に設定。
★★★★★「レベル5!家宝として置いておきたい本」90点~100点
★★★★ 「レベル4!期待を大きく上回った本」80点~90点未満
★★★ 「レベル3!期待を裏切らない本」70点~80点未満
★★ 「レベル2!読んでも損は無い本」60点~70点未満
★ 「レベル1!評価が難しい本」50点~60点未満
組織内の情報非対称性と粘着性
企業には「組織慣性」と呼ばれる、変化に抵抗し既存の方法を維持する慣性がはたらきます。その中でも、情報の非対称性と粘着性は組織行動を阻害する要素として知られています。
<情報の非対称性>
組織内の異なる立場(経営者と従業員、上司と部下など)では保有する情報に差異が生じます。この状況から、情報優位者による自己利益優先や情報不足による不適切な意思決定などの問題が発生します。
例えば、プロジェクト遅延の原因が部下の怠慢なのか技術的困難なのかを上司が正確に判断できないことがあります。そのため適切な評価が難しくなります。また、社長の方針が階層(役職)を経ていくごとに曲解されて伝わらなくなることも、情報の非対称性の特徴です。
<情報の粘着性>
情報の粘着性とは、組織内で情報や知識が簡単に移転・共有できない性質を意味します。ベテラン社員の経験則や特定部署の専門知識は容易に伝達できません。
あるベテラン技術者は、材料の感触や機械の音から最適な調整方法を瞬時に判断できます。社内でこの技術を言語化しようと考えましたが、「指先に伝わる感覚が硬めに感じたら力を抜く」といった感覚的技術はマニュアル化できず、若手への伝承が困難でした。
<影響と対策>
組織慣性は企業活動を阻害し、イノベーション機会の喪失や競争力低下を招きます。持続的成長のためには、過去の成功体験に囚われず、常に学習し適応する組織文化の構築が不可欠なのはこのためです。
ピラミッド型は正しい組織のあり方
組織慣性への対応策として、これまでは組織設計に焦点が当てられてきました。フラット化組織、オープンアーキテクトなどは、上司と部下の関係性に着目しています。つまり、組織の構成員内部に限定された施策が主流だったと言えます。
しかし、近年の世界的な不況やデフレにおいては、従来型の組織設計アプローチだけでは十分な効果を発揮できないことが明らかになってきました。組織内部の改革だけでは、大きな経済環境の課題に対応するには限界があるのです。
安藤社長は組織のあり方について次のように解説します。
「皆さんの職場はどんな構造になっていますか?経営者がトップにいて、その下に役員、部長、課長といった中間管理職が並び、一般社員が土台を形成する。そんな『ピラミッド構造』が一般的ではないでしょうか。近年、この『ピラミッド』という言葉に嫌悪感を持つ人も増えています」
「現代社会で苦戦している日本の大企業を見ると、ピラミッド組織に問題があると思いがちです。しかし、これは誤解なのです。ピラミッド構造には独自のメリットがあります。識学では、組織の成長スピードを重視した場合、ピラミッド構造が最も効率的で最速の組織形態だと考えています」
すでに出来上がった会社組織にいる人は、ピラミッド組織に適したマネジメント法を実践する必要があります。しかし、「ピラミッド構造だと上に決済をとるまで時間がかかって、なかなか決まらない」という声も聞きます。これは、大きな誤解だと、安藤社長は言います。
ピラミッドの形が悪いわけではなく、「ピラミッドに合わせて組織が運営されていない」ことが原因です。それぞれのリーダーが持つ責任の範囲が曖昧だから、1つ1つの決定を押し付け合い、意思決定のスピードが落ちるのです。
<識学安藤社長との対談から学ぶマネジメント論>
2025年4月1日に識学にて安藤社長と対談をしました。本稿は対談時のやり取りを記事化したものですが、読みやすいようにアレンジを加えています。

右:安藤社長、左:筆者 於:株式会社識学にて
尾藤 克之(コラムニスト・著述家)
■
2年振りに22冊目の本を出版しました。
「読書を自分の武器にする技術」(WAVE出版)