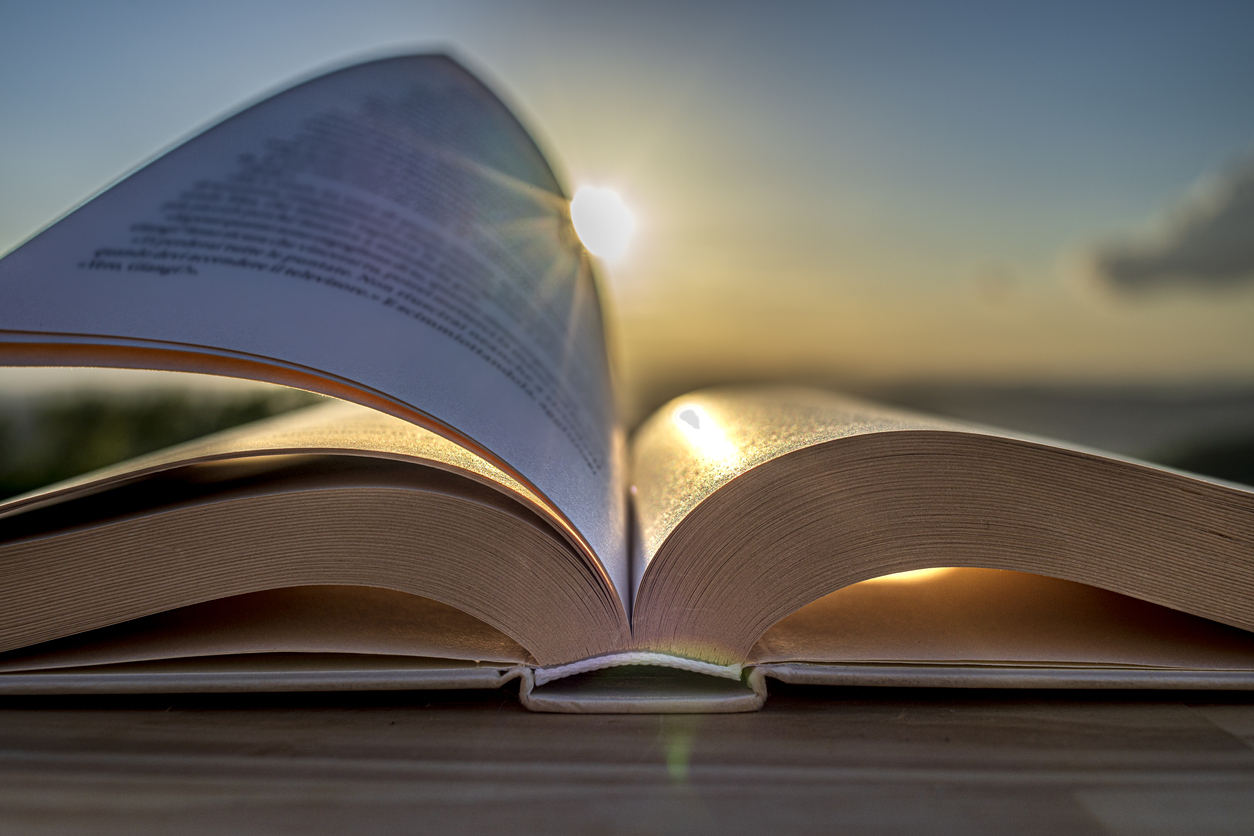
Alberto Gagliardi/iStock
種蒔く人
マルサスの『初版人口の原理』(1798)を復刻した1926年版では、その巻末附録として掲載されたボーナー「マルサスの第一論文」に、「マルサスは種蒔く人であった」(同上:246)というピアソンの評価が引用されている。
およそすべての学術研究では、「種蒔く人」、それを「大きく育てる人」、そして刈り取れるまで「育て上げる人」が必ずいる。それらの人々はすべてその分野における先覚者であるが、後続の私たちの目標となり、日々の研鑽を励ます存在でもある。
細分化と多様化による次世代への伝達困難性
170年以上の歴史をもつ社会学は、21世紀になり細分化と多様化がますます進んだ結果として、学問全体の多元的現象が鮮明になった。これには喜ばしい側面もあるが、細分化と多様化だけでは成果の共有と次世代への伝達が困難になる。
そこで個別的には、自らの問題意識に合わせて研究者の観点からその「源流」と目された先覚者を選び、その総合的理解に努め、独自の内容での「展開」を試みことになる。私の50年間もそのように努力した。
先覚者の成果を学び、「時代解明」を心がける
それぞれの分野では、先覚者の独自の方法に基づき知的営為の結果として、変化する時代との学的格闘を伴いながらのオリジナルな成果と課題が明らかにされてきた。そのため、後の世代へとつないでいくには、先覚者の成果と到達点を多面的に論じることで、オリジナルな観点からの「時代解明」を心がけて、学界や社会全体の閉塞感を打破できるように試みるしかない。
人文・社会科学系列でも、各分野の碩学には、『国文学五〇年』(高木市之助、1967)、『社会学四〇年』(福武直、1976)、『宗教人類学五十年』(古野清人、1980)、『故郷七〇年』(柳田國男、1997)、『社会学わが生涯』(富永健一、2011)、『ある社会学者の自己形成』(森岡清美、2012)など公刊された自分史があり、私もまたこれらに折に触れて励まされてきた。
同時にそのような表題はないにしても、高田保馬のように100冊を超える学術書とエッセイを使い分けて、エッセイや和歌で自分史を語った碩学もおられる注1)。
多様な研究スタイル
ささやかな50年の研究歴ではあるが、地方在住の私が見ても変動が激しい現代社会では、そこに生きる市民、住民、国民、柳田國男の「常民」などのさまざまな人間像が群生して、時代のなかで変遷する社会規範や価値観なども交錯し、現代的なライフスタイルは文字通り多様化したとの印象が強い。産業化、都市化、高齢化、少子化、国際化、情報化などで特色づけられる現代社会の全体像が掴みにくくなったうえに、どの立場からしても現代社会がもつ課題は多くなるばかりである注2)。
50年間の個別的研究では、私なりの判断により時代で求められる専門的テーマを選択して、都市に住む人々(市民、住民、若者、高齢者などに類別)の社会調査(質的調査と量的調査)を行ってきた。とりわけ札幌市は全国でも最先端の少子化が進む大都市であったために、隣接の高齢化分野そして地域福祉分野についても研究し、そのうえ札幌市で30年にわたり審議会や委員会での議論に加わり、政策過程にも参画し、自らの処方箋も提示してきた注3)。しかし、もちろん限界も多く、どこまで貢献できたかと問えば、忸怩たる思いがある。
「個人と社会」をめぐる「言説のゆれ」から独自性を探求する
なぜなら、社会規範だけを取り上げても、現代社会では競争と共存、格差と平等、均衡と闘争、移動と定住、持続的成長と持続的安定、公共性と私性、全体化と私化、ジェンダーとジェネレーション、コンフリクトと共生、管理と自発性など社会学の究極の課題である「個人と社会」をめぐる言説のゆれがあるからである。
当然のことに研究者の資質によって、これらのいくつかを選択し、研究の成果を提示することになるが、決定版には程遠い。研究者はそのささやかな一部を分担することで満足せざるを得ないし、その成果はすぐに乗り越えられる運命でもある。なぜなら、「学問上の仕事にはたえず進歩がともなう」(傍点原文 ウェーバー、1921=1962:142)からである。
普遍性と個別性の両輪
もっとも学界全体で見れば、異なった視点と結論が衝突し、交錯し、融合して、新しい論点が誕生する。これは学問の発展として期待される可能性に富む道筋であろう。
学問は普遍性とともに研究者の個性を活かすところに開花する。そこにはテーマに即した考え方と方法があり、独自の資料収集法や分析方法、そして結論へと導く推論の仕方がある。社会学ではインタビュー法や公刊資料などを駆使した質的調査法、質問紙を作成してランダムサンプリンクした対象者に面接して尋ね、その結果を計量的に処理する量的調査法が双璧だが、もちろん両者は互いを排除するわけではない。
くわえて最近では、デジタル映像をチェックしたり、路上観察したり、民俗学的な口碑を採集して、これを丹念に蓄積する方法も兼用される。そしていずれもその過程で、いわゆるセレンディピティというおもいがけない偶然による価値ある発見や興味深い創造が得られることがある注4)。
社会学=IBM+リアリティー+ヒューマニズム
ところでミルズの1954年の論文に“IBM Plus Reality Plus Humanism=Sociology”があり、心臓疾患により1962年に急死した後に、ホロビッツが編集した遺稿集に採録されている(ホロビッツ編、1963=1971:437-444)。この公式は社会学の特徴をよくとらえていると考えて、長らく教養課程の「社会学講義」でも紹介してきた。
まず、1954年時点でのIBMも驚きだが、これはもちろん調査結果のデータ整理、統計学的処理、図表にまとめるといった実証的側面を象徴する代名詞である。アップルなどの新興メーカーが登場するまでは、IBMが文字通りアメリカのコンピューター技術の精粋を集めたメーカーとして世界に君臨していた。
ミルズは「調査技術は、数学的厳密さと同時に、より広い意味と関連のもとに、仕事をしなければならなくなってきている」(ミルズ、前掲論文:443)として、IBMという表現を使っている。
リアリティー
そして、調査結果やさまざまな統計からのデータによって、テーマとして取り上げた社会現象のリアリティーを確保することで、社会学の実証性が維持できる。すなわち「視野の広さと洞察の深さをもってだけでなく、リアリティーをもってなさねばならない」とした(同上:443)。
このリアリティーとは「現代の現実的な諸問題に、正面からとりくむ」ことを表わす(同上:443)。46歳で急死するまで、ミルズはこれを忠実に実行した。
ヒューマニズム
ヒューマニズムは論文ではヒューマニスト的関心とされていて、実質的には
- 全体としての社会にとって、われわれの研究テーマはどのような意味があるか。また、この社会的世界(Social world)はどうなっているか
- この社会で優勢な人間のタイプにたいして、その研究がどのような意味をもつか
- 研究テーマがこの時代の歴史的傾向にどのように対応しているか、またどの方向にむかってこの主要な傾向が動いていくか
などを問い続ける姿勢を指している(同上:440)。
学部3年生の時に翻訳され、大学院修士課程で購入したこのミルズの遺稿集からは、この社会学の公式以外にもたくさんのことが学べた。
ホロビッツが遺稿の配列を工夫して、それらは「権力」、「政治」、民衆」、「知識」に分けられる。これらの論文に加え、代表的な著作である階級・階層論の実証的研究書である『ホワイト・カラー』(1951=1957)、アメリカ社会の権力構造論の白眉となった『パワー・エリート』(1956=1969)、そして現在までも読み継がれてきた画期的な社会学方法論である『社会学的想像力』(1959=1965)などは、社会学への入口において大きな刺激となった。
このうち、入学した大学の社会学講座に『社会学的想像力』の翻訳者である鈴木広先生がおられたことは、まさしく「運」であり、同時に出会いから先生のご逝去までの約50年間の「縁」でもあった。
連載の基本方針
以上を前提にして、本連載の基本原則を明記しておきたい。
(1)基本的にはこれまで発表した単著を1冊ずつ取り上げて、そのテーマ設定の理由、研究方法、「縁、運、根」に関するエピソード、そこでの結論と発展への視点を要約する。
(2)そのテーマの先覚者が遺した文献との真摯な対話を通じて、何をどのように学んだか、その研究成果の問題点は何か、現代日本のどこに応用できるか、それを行うことにより、いかなる展望が得られるかをまとめる。
(3)自然科学や医歯薬系の学問とは異なり、社会学ではいわゆる「発明・発見」はない。しかし、社会の「法則」や「命題」などはこれまでの先覚者の業績にもかなり散見されるから、自らの単著でもそのような傾向が確認できたならば、従来の学説研究上の「法則」や「命題」に代わる新造語や新図式を提示して、いわゆるneologism(neology)を実践する。
(4)共著や編著における自らの担当論文についても、単著での試みの後に、同じような方法で新造語や新図式の発見をできれば紹介したい。
(5)すべてが自らの著書の総括であり、次世代次々世代に対してのメッセージの意味を込めている。
持ち場の自覚
社会学界では従来このような試みはあまり見かけないが、たとえば折に触れて再読してきた丸山眞男(1964)の「追記および補註」のような位置づけである。丸山の「追記・補註」は論文への「解説」であったが、私は著書とした。
しかし、丸山がいうようにそのような試みは「実に奇妙」であり、「著者自らやるということは、ある意味ではこれほど僭越で傲慢な態度はなかろう」(同上:577)。
その通りかもしれないが、丸山が意図的に「学問を職業としない方々にも研究成果を届けて、そこからも鞭撻と率直な批判を期待しお願い」(同上:583)してきた実践は、私にも思い当たるふしがある。
私の場合は、自治体でコミュニティ政策、高齢化、地域福祉、少子化、児童虐待などの分野に取り組まれていた方々への学術的なメッセージの意味が強かったが、社会学の成果を政策情報へと昇華させることは、私なりの「持ち場の自覚」(同上:565)でもあった。
この自作品への「追記・補註」の試みがどこまで続けられるかについても、「縁、運、根」次第であろう。「根を詰める」わけではないが、最終ゴールまでの精根だけは維持したいと願っている。
■
注1)不十分ながら、高田生誕120年記念に『高田保馬リカバリー』を編集して、その社会学の側面における大きな貢献についてまとめたことがある(金子編、2003)。また、これまで未着手だった高田「和歌集」3冊からの秀歌を抜き出して、私なりの評釈を加えた(金子、2025近刊予定)。
注2)1993年にこれらをゼーション現象として『マクロ社会学』(新曜社)で一冊にまとめた。その後1999年から2017年までのほぼ18年間で、同じパラダイムで「講座・社会変動」(ミネルヴァ書房)を企画して、全巻10冊と別巻の11冊で完結した。
注3)このような理由で、2020年度に「札幌市・市政功労者」として表彰されたことは、私の社会学研究に基づく学問的実践の評価でもあると喜んでいる。
注4)セレンディピティについては、金子(2018:64)に詳しい。通常の定義は「予期されなかった、変則的な、また戦略的なデータを発見すること」(マートン、1957=1961:97)である。
【参照文献】
- Horowitz,I.L.,(ed.),1963, Power, Politics and People-The Collected Essays of C.Wright Mills, Oxford University Press.(=1971 青井和夫・本間康平監訳『権力・政治・民衆』みすず書房).
- 金子勇・長谷川公一,1993,『マクロ社会学』新曜社.
- 金子勇編,2003,『高田保馬リカバリ―』ミネルヴァ書房.
- 金子勇,2018,『社会学の問題解決力』ミネルヴァ書房。
- 金子勇,2025,「高田保馬の『理性』と『感性』-社会科学と和歌の両立」神戸学院大学現代社会学会編『現代社会研究』第11号(近刊予定).
- Malthus,T.R.,1798=1926,An Essay on the Principle of Population, Printed for J.Johnson.(=1962 高野岩三郎・大内兵衛訳『初版 人口の原理』 岩波書店).
- 丸山眞男,1964,『増補版 現代政治の思想と行動』未来社.
- Merton,R.K,1957,Social Theory and Social Structure,The Free Press.(=1961 森東吾ほか訳『社会理論と社会構造』みすず書房).
- Meyers,M.A.,2007,Serendipity in Modern Medical Breakthroughs, Arcade Publishing.(=2015 小林力訳『セレンディピティと近代医学』中央公論新社).
- Mills,C.W.,1951,White Collar-The American Middle Class -,Oxford University Press.(=1957 杉政孝訳『ホワイト・カラー』東京創元新社).
- Mills,C.W.,1956,The Power Elite, Oxford University Press.(=1969 鵜飼信成・綿貫譲治訳『パワー・エリート』(上下)東京大学出版会).
- Mills,C.W.,1959,The Sociological Imagination, Oxford University Press.(=1965 鈴木広訳『社会学的想像力』紀伊國屋書店).
- Weber,M.1921,Wissenschaft als Beruf.(=1962 出口勇蔵訳「職業としての学問」『世界思想教養全集18 ウェーバーの思想』河出書房新社:129-170).













