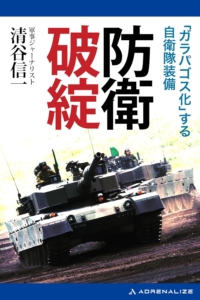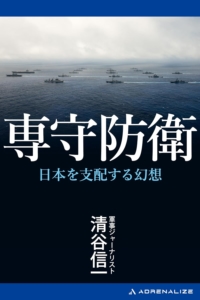川重裏金問題のキモは防衛省の査定の甘さにあります。そして同じ分野で二社あったにもかかわらずに、競争原理が働いていない。であれば潜水艦事業はじめ、他の分野でも統合して生産効率を高める方が防衛費を効率的に使えることになります。

海上自衛隊HPより
そしてその一方三菱重工ではこの問題が発生していなかった。この手便宜供与に厳しいので「ケチ菱」と言われていたわけですが、同社では実は守屋事務次官時代に抜本的なコンプライアンスの見直しをした。当時営業や事業所から総務は仕事ができなくなると責められたが、結果はどちらが良かったか。便宜供与しなくても潜水艦の発注はあるわけです。
むしろ問題は防衛省側にあります。原価管理はザルということです。だって同じ潜水艦を2社で作っていてなんでわからないのですか?更に申せば空自の救難ヘリだって、入札前の単価は23.75億円だったのに調達が始まると50億円以上に倍増した。
そして装備庁は何の調査もしていない。明らかに官の側が主導した官製談合=犯罪です。それを調査もしなかった。同様に陸自の装甲ドーザーも1億円で作れると、2・6億円のトルコのFNSS案を退けて日立が落札したわけですが、調達始まると6億円以上でした。しかも性能では遥かにFNSS案に及ばない。少なくもと試作の段階で原価計算はできたはずです。
防衛省は原価計算に関して無能だし、何ならばインチキとわかって見逃している。こんな役所の予算を3年前の1.6倍に増やして、更にGDP比2パーセントまで増やすなど狂気の沙汰です。
だぶつく防衛予算「使わないと」 川重の裏金、国税が暴いた「鉱脈」 朝日新聞

海上自衛隊の潜水艦修理をめぐる裏金接待問題で、川崎重工業への税務調査が終結した。裏金による所得隠しは6年間で約13億円に上り、その他の申告漏れを含めて約10億円を追徴課税されたとみられる。背景に浮かぶのは、多額の裏金作りができるほど防衛予算がだぶついていた実態だ。
つまりはご案内のように、まともに査定ができないということです。
裏金作りに協力してきた下請け会社の社長は、生々しいやりとりを覚えている。
指を2本立てて、川重の担当者が言う。「これだけ使わないかん」
社長が「2千万円ですか?」と尋ねると、担当者は答えた。
「ゼロが1個足らん」
社長はこう振り返る。
「使わないと翌年の予算が減らされる、裏金を作ってでも使いきらんとあかん、ということだったのではないか」さらにカネの流れをさかのぼると、この会社が川重の裏金作りの中核的な役割を担っていることがわかった。川重を起点に1次下請け、さらに2次下請けを経由して裏金が還流する――。明らかになったのは、そんな重層的なシステムだ。
こうして捻出された裏金が、海上自衛隊の潜水艦乗組員らへの物品や飲食に使われていることもつきとめた。
つまり防衛省は下請けまでチェックをしていなかった、あるいはできなかったということです。更に申せば金だけではない。取引先に天下りを受け入れさせている「ステルス天下り」もありそうです。以前の技本の陸担当装備官の再就職先は防衛関連ではありませんでしたが、その取引さでした。この手を使うと待機期間なしに天下りができます。メーカーはその分の人件費を上乗せさせれば防衛省にバレることはない。
一般に、企業の裏金作りは取引の発注者に対して水増し請求するケースが多いとされる。だが川重の場合は、発注者である防衛省にそれを行った形跡はなく、支払われる防衛予算の中から多額の裏金が作られていたとみられる。
「川重と防衛省・自衛隊の付き合いのなかで、予算の見積もりの甘さが慢性化していたのではないか」
調査の内情を知る関係者は、そう指摘する。
それは過去三菱電気などで過大請求がバレることが証明されているからです。つまりは川崎重工の悪質性は極めて高く、確信犯的だったということです。
原価計算の基になるのが、作業員数と労働時間を掛け合わせた「工数」だ。だが、工数の算出根拠を企業側に依存せざるを得ない構造的な課題があり、企業側が工数を実際よりも水増しして申告する過大請求の事例が続出。この制度に絡み、1998年には自衛隊の装備品の調達を担当する調達実施本部(当時)の元幹部が東京地検特捜部に逮捕されたほか、会計検査院も防衛省側のチェックの甘さを指摘してきた。
工数の水増しは昔から恒常的に行なわれており、今でも行なわれているでしょう。そして利益率は8パーセントから15パーセントに。リスクを全く負っていないのに、利益が2倍近くになるわけですか、濡れ手に粟で、事業の合理化なんかするわけがない。
潜水艦修理をめぐって、川重は海自側の意向を受け、過去の受注の際の実績を反映させるなど原価調査を経て算出された工数ではなく、作業効率などの要素が忠実に反映されていない「標準工数」をもとに会社見積もりを算定していたことが防衛監察本部の調査で判明。海自側もこの見積もりを基に予定価格を作っていたため、「官側が作る予定価格自体に架空取引の原資となるバッファーが含まれる余地があった」(防衛省関係者)。
さらに、13年12月の海自の経理部門内の会議で、「会社見積額を減額査定することはしない」との趣旨の方針が示されていたといい、潜水艦修理は長年、「『(業者側の)言い値』に近い額が契約金額になるリスクが高まっていた」(監察本部の報告書)という。
よく2社ある方が、競合が働くと既存企業を擁護する人がいますが、それがインチキだということです。潜水艦事業は統合しても何の問題もない。むしろ統合することによってダブりを減らし、購買も統合することで合理化は可能となる。更に申せば監督する企業が一社で済みます。
防衛省には、過去の実績を調べ、原価計算の実態が適正かを確認する「原価調査」といった制度があるにもかかわらず、15年6月には調査対象を各年1艦に限り、対象の艦も事前にすり合わせることを海自と造船団体が申し合わせるなど、制度が事実上「骨抜き」になっていた実態も明らかになっている。
つまりは馴れ合っていたということです。更に申せば、ゲーム機は論外ですが、本来必要な雨具や工具を裏金でかっていたということは、このような需品がまともに調達されていない、ということです。兵器にはじゃぶじゃぶ金を使うが、それを支える基盤の需品はケチる。これでは戦時に戦えないと思います。
そしてこのような需品や備品に関してはこれだけじゃぶじゃぶ防衛費が増えても、予算がつかない。形があれば買い替えをしない。ことに危険なのがリチウム電池です。本来期限は5年ほどですが10年以上交換されずに、定期的な充放電をおこなっていないものが多数あります。本来このようなものにこそ増やした予算を使うべきです。
■
■
財政制度分科会(令和6年10月28日開催)資料
防衛
防衛(参考資料)
財政制度分科会(令和6年10月28日開催)資料
防衛
防衛(参考資料)
編集部より:この記事は、軍事ジャーナリスト、清谷信一氏のブログ 2025年4月8日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は、清谷信一公式ブログ「清谷防衛経済研究所」をご覧ください。