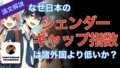zimmytws/iStock
トランプ政権は、貿易相手国に対し5日に発動した一律10%の相互関税に加えて、9日に実施予定だった国毎に異なる税率の追加につき、90日間の交渉期間を設け、一時停止した。制裁中のロシア・イラン・北朝鮮には一律課税を実施せず、また報復関税で米国に対抗した中国には追加分も含め145%まで税率を引き上げた。
これにより米国の日本産品輸入業者は今後、一律分10%に加え、自動車・鉄鋼・アルミでは追加14%を加えた24%の税負担を強いられることになり、日本側が輸出価格を下げるか、米国輸入業者が税額の一部を持ち出すかしない限り、米国民は10%(追加3品は24%)高く日本産品を買うことになる。また90日間の交渉の成り行き次第では全産品が24%UPになる。
高くなっても日本以外からは買えない物品なら、引続き購入されるだろうが、競争力のない日本品は輸出が難しくなる。この課題への対応を石破首相から任された赤沢経済再生担当相は来週にも渡米し、カンターパートのベッセント財務長官及びグリアUSTR代表と追加分14%の軽減などについて協議を行う。
赤沢大臣は取材陣に10日、追加分の一時停止を受け「まだ10%の相互関税、アルミ、鉄鋼、自動車、これに課された関税はそのままであると承知しているので、引き続き、我々としては強い懸念を伝え、強く見直しを申し入れる」と述べた。
大臣の意欲は多とするが、必要なのは「意気込み」よりも緻密な交渉戦略だ。ベッセントは名うてのファンドマネージャだったし、グリア代表は第一次トランプ政権で茂木敏光氏のカンターパートだったライトハイザーUSTR代表の首席補佐官を務めた通商法の弁護士である。また石破首相が茂木氏を敬遠したとの話が事実ならその狭量は国益を害しよう。
民間のM&Aや事業買収は、双方の利害が一致した場合にのみ成立するが、その多くの場合より強くそのディールを成立させたいと思う側が、相手により多く譲歩することになる。但し、両者とも手の内を見せないから、相手方の諸事情を調べ上げて交渉を有利に運ぼうとするのである。
政府首脳が「真意が判らない」とも述べたようだが、トランプやベッセント財務長官やナバロ上級顧問の口から折に触れその目的が語られている。各人それぞれに濃淡はあるものの、①貿易赤字・財政赤字の軽減、②米国製造業の復活、③減税財源の確保、④中国弱体化、の4件に集約できよう。それらの達成が米国の目指す国益だ。
9日の一旦停止を見る限り、④中国弱体化がやはり本命のようだ。グリア代表も11日、「戦略的敵対国である中国に依存してしか生活水準を維持できないとしたら、それは非常に危険な立場だ。だから、これを加速させる必要がある」と「Fox and Friends」に語っている。
また第1次政権の17年に実施したトランプ減税の期限が本年末なので、これを継続する財源として関税収入の維持拡大③も重要だろう。なお、9日に発表された3月の関税収入は2月比15億ドル増加の87.5億ドルで、22年9月以降の最高額となった。10%の増し分だけでも8.8億ドルに上る。
■
そこで日本が採るべき政策だが、これらのどれにどう対応すれば日本の国益に資するか、或いは日本の国益の毀損度が軽いのかを詰めることだ。ここまでは石破首相が口にするセリフだが具体策こそが重要である。そこで、①は日本の貿易黒字の減少に繋がり、②は日本国内の空洞化に影響すると判る。③と④は①と②の結果であるから、以下では①と②について考えてみたい。
筆者が考える対米提案は、1)コメの輸入拡大、2)石油・天然ガスの輸入拡大、3)武器の輸入拡大、4)自動車の輸出戦略の4件である。以下に夫々の内容を述べる。
1)コメの輸入拡大
ここ数ヵ月降って湧いたように出来したコメの高騰に対し、政府は100万トンとされる備蓄米放出をようやく始めたが、稚拙にも逐次投入だったためか値下がりは小幅にとどまっている。そこで筆者は赤沢大臣が、向こう3年間日本政府が毎年100万トンのコメを関税ゼロで米国から買う、と提案することを勧める。

既にカルフォルニア米、ベトナム米、タイ米、台湾米などが民間で輸入されていて、CIF価格(運賃・保険料込)は概ね1.0~1.2USD/1kgとされる。150円/USDとすると150円~180円、これに341円/1kgの関税が掛かるとして1kg約500円前後で仲介業者に渡る計算だ。5kgで2500円だが、店頭では経費や利益が4割ほど加わり3000円ほどで売られているようだ。
日本が海外からコメを輸入する場合のミニマムアクセス規制(MA米)は、専ら日本のコメ農家保護が目的で、数量にも用途(加工用・飼料用・援助用に限定)にも制限を課している。が、備蓄米放出に依っても高騰が収まらない原因はコメ不足、というのが今や定説になりつつある。
だからこそ、米国産のコメ100万トンを政府が備蓄用に関税ゼロで買うのである。180円/kgなら1800億円だ。それを500円/kgと言わず、先般の備蓄米入札価格並の21217円/60kg(353円/㎏)で卸せば、市場価格は下がり、政府にも(353円/kg-180円/kg)X100万トン=1730億円が入るので、これを翌年の購入やコメ生産の構造改革に当てれば良い。
少子高齢化でコメ農家は確実に減少しつつあり、これへの対策として大規模化・近代化等の改革は必至である。そのための時間と金を米国産米の政府直接買い付けで稼ぐのである。必要なら3年といわず5年でも良いし、その間にもし国内産米が余るなら米国以外への輸出に回せば良い。農産品の自由化は必ず交渉の俎上に上るから、先手を打って提案すべきである。
2)石油・天然ガスの輸入拡大
トランプの「Drill, baby, drill!」を満足させる案である。が、アラスカでの天然ガス開発への参画は石破・トランプ会談で合意済みだし、米国には、ロシア産を買って欧州などに転売している中国とインドを牽制するための玉も必要だろう。それ故、日本にはこれ以上回せないと言って来るかも知れない。が、そうなれば日本は貸しを作れるから、これも強く申し入れるべきである。
3)武器の輸入拡大
究極のWin-Win案だが、筆者は更に踏み込んで、核ミサイル付きの原子力潜水艦を10隻ほど買いたい、と提案することを奨める。その暁には在日米軍はほぼ不要になり(それに応じた安保条約や行政協定の改正が必要)、26年まで年平均2110億円掛かる「思いやり予算」や沖縄振興費(約2600億円)も軽減できるので、それを国防費に回せる。
原潜の調達価格は1隻1兆円といわれ10隻なら10兆円。原潜は核ミサイルを搭載してこその原潜だかから、金が掛かっても核付きでなければ意味がない。金正恩がリビアのカダフィのようにならない理由が核兵器にあるとすれば、核付き原潜こそが究極の抑止力であることは明白だ。もっともこれをトランプが受け入れるかどうかは判らない。
他方で米国は目下、第7艦隊の船舶修理の一切を横須賀基地で行っているはずで、この機能をハワイやサンディエゴで新たに構築する金と時間が米国にあるかどうかには大いに疑問が残る。インド太平洋の安全保障に関与しないという論は、米国議会には通用しまいから、トランプ政権には原潜の件と共に難題となるだろう。
4)自動車の輸出戦略
米国の関税目的の一つに「米国製造業の復活」がある以上、米国の輸入業者が関税の持ち出しをしない限り、輸出日本車の価格が従来分2.5%+24%=26.5%UPになることは避けられない。つまり、仮に今400万円で売られている車なら506万円になり、米国輸入業者は関税106万円を米国政府に納付することになる。因みに24年の米国向け自動車輸出は137万台(内トヨタ53万台)で金額では6兆円を超えた。
ベッセント財務長官が1月に「中国は、米国市場のシェアを維持するために価格を下げ続けるでしょう」と述べていたことをこの例の日本車輸出に当て嵌めれば、価格を400万円に据え置くことを意味する。この場合、輸入業社が26.5%の関税を収めるために日本車に求められる輸出単価は316万円(84万円引き)となる。つまり、316万円で日本メーカーが輸出を継続できるかどうかがポイントだ。

そこで限界利益の話になる。コストは固定費と変動費に分解できる。固定費は人件費や設備の減価償却費など、一定数以上の台数を作る場合にそれが40万台でも50万台でも同じ様に掛かるコストのこと。変動費は材料費・消耗用品費・エネルギー費・運送費・外注加工費(下請けへの支払い:これが変動費であることの問題点はここでは論じない)などの、生産台数に応じて変動するコストをいい、生産台数ゼロなら変動費も原則ゼロとなる。
限界利益とは、売上高から変動費を引いた金額をいい、この額が固定費を上回れば利益が出るし、下回れば赤字になる。仮に現状の損益構造を@400万円x50万台=2兆円の売上高で変動費が1兆円とすると、限界利益は1兆円で固定費が6000億円だから、利益は4000億円となる。
前述の316万円で50万台輸出すると売上高は15800億円となるが、変動費+固定費は16000億円なので▲200億円の赤字になる。が、320万円で輸出できるなら売上高16000億円は変動費+固定費の額とイコールなので損益ゼロとなる。つまり、1台当たり4万円を輸入業者に泣いてもらえれば、赤字を出さずに日本から輸出を継続できる。損益は米国生産分と連結してグループで決算すれば良い。
万一国内生産をやめることになれば、従業員の雇用は維持されず、下請け業者や物流会社などにも甚大な影響が出て、日本は空洞化する。米国に関税率の低減を求めるのは勿論だが、減税や原発の早期稼働で手取りを増やして国内需要を喚起することや米国以外に販路を広げる自助努力も重要だ。こうした工夫によって是非とも国内の空洞化を回避してもらいたい。