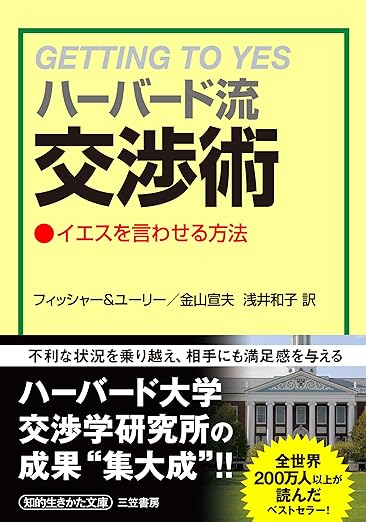日本政府が、アメリカ政府と関税交渉に入る。世界の諸国の先陣を切る。日本には1980年代からのアメリカとの間の貿易交渉の歴史がある。ベッセント財務長官の様子からは、期待がうかがえる。
アメリカは当初、高率関税を普遍的に導入する意図を持っていたが、今は超大国が一騎打ちで激突する米中貿易戦争に転化してしまった。中国の経済力は、他国とは比較にならない。他の諸国は、なかなかアメリカの高率関税に対抗する措置をとれなかったが、中国だけは例外だった。実力が違うからである。
中国に対して、アメリカにも強みがあるが、弱みもある。アメリカは早くも、対中国の高率関税対象から、スマートフォン、パソコン、半導体製造装置などの代替不可能品目を外した。
21世紀の国際政治の帰趨に大きな影響を与えると思われる米中対決とは別に、日本のような他の諸国は、事を穏便に済ませる措置を、アメリカとの間で合意してしまいたいところだ。アメリカも、米中貿易戦争の行方が見通せないだけに、他の諸国との間の「ディール」で成果を出す実績がほしいところだ。日本にとっては悪くない環境だと言える。
気になるのは、石破首相が「(関税措置は)本当に(米国の)プラスになるのか」といった空中戦に関心があるように見えるところだ。いわゆる「神学論争」に近い。
トランプ政権としては、「プラスになればなるし、ならなければならない」という態度で、プラスになるものだけを押してきているという立場である。
それに対して、「いや、トランプさん、あなたはバカだ、何がアメリカにプラスになるのかバカなあなたは理解していないようだ、そこで私が何がアメリカのプラスになるかを教えてあげる、答えは自由貿易主義の原則の維持だよ」といった態度で臨んでいっても、自爆するだけだろう。
学術的に行くのであれば、「交渉術」できちんと学術的な基本ポイントを押さえてほしい。たとえばハーバード大学大学院交渉学コースのフィッシャーとユーリーの古典は邦訳も出てベストセラーになっている。
この本のポイントは、「立場を見るな、利益を見ろ」ということである。「立場」とは相手が公式に表現している主張のことである。「利益」は、立場を支えている現実の関心対象だ。
交渉の基本は、「立場」の違いにとらわれず、「利益」の共通項を見出し、確認し、発展させることだ。トランプ大統領の粗い言葉や意表を突いた態度に惑わされず、アメリカの核心的利益を見出したうえで、日本の利益との共通領域を見出す、ということだ。
関税率を24%云々といった言葉尻にとらわれると、「それは不当だ」「計算方法が杜撰だ」「自由貿易の原則に反する」「日本だって色々と努力している」といった水掛け論的な反応だけをしてしまう。
トランプ大統領が「国際緊急経済権限法(IEEPA)」を根拠にして高率関税を導入することを宣言した背景には、現実の過去最大の貿易赤字(2024年度に1兆2117億ドル)がある。そして貿易赤字と連動したやはり史上最高規模で膨れ上がっている財政赤字がある。累積で2024年度に35兆ドルで、対GDP比で124%の水準に達している。
この巨額の財政赤字にもかかわらず、トランプ大統領は、空前の規模の減税を導入しようとしている。これも選挙の公約である。となれば、迅速な財政赤字の改善の提示は急務であり、イーロン・マスク氏のDOGEによる急進的な政府機構の縮減策なども、その文脈で行われているわけである。
これが現在のトランプ政権の核心的利益だ。自由貿易体制の維持とか、日本の対米投資額はいくらか、といった話は、仮に無関係ではないとしても核心的ではない。
日本はアメリカの貿易赤字/財政赤字を減らす方策をとるのかどうかが核心的利益である。そこに焦点を合わせなければ、何を言っても、迂回路である。
もちろん「MAGA(アメリカを再び偉大に)」の観点から言えば、財政赤字の削減は、選挙民であり納税者であるアメリカ国民の生活の改善につながるものでなければならない。ただそれは当面は、減税の断行、という具体的政策に還元させることができる。そこで減税を進めるための財政赤字の改善こそが核心的利益だ、と考えて間違いないだろう。
冷戦時代の雰囲気などを思い出してしまうと、「アメリカは自由主義陣営の盟主としての立場を誇示することにも利益を見出すはずなので国際秩序全体の観点から自由貿易主義の原則を強調してそれを維持するためには・・・といった話に持っていって・・・・」のような考え方も、成立しえたかもしれない。しかしトランプ政権では、無理だろう。
アメリカの赤字が減るかどうか、それだけだ。
ここで、仮に日本のほうがアメリカよりも総合的な国力が大きいとすれば、「あなたの言っていることは身勝手だ」といった姿勢を出すやり方もありうるだろう。だがアメリカの国力は日本を圧倒する大きさであり、その非対称性を前提にして日本の安全保障政策はアメリカに依存している。アメリカが困っていたら、一緒に悩み助けようとするのは、当然である。結局のところ、アメリカが倒れてしまったら、日本こそが非常に困ってしまうのだ。
この文脈において、日本が海外の米国国債保有者の中で最大勢力であるのは、かなり大きな事実である。
いずれにせよ、普通の人だったら、トランプ大統領と関税交渉する際に、まず冒頭で述べるのは、日本が米国債の最大債権国である事実だろう。
(ところが5万円の給付金出す話して大混乱するくらいに頑張っているので許してほしいって感じだからな、今のところ・・・) https://t.co/5q7psWwEZQ— 篠田英朗 Hideaki SHINODA (@ShinodaHideaki) April 10, 2025
アメリカの財政赤字の改善、あるいは財政破綻の回避は、日米両国の共通の利益である。換言すれば、国債保有者としての立場は、交渉を前に進めるためのカードとして使っていいだろう。
アメリカの貿易赤字の解消につながる品目ごとの関税率の設定や、日本側の措置の実施が核心だが、それに結びついた付帯的事項として、日本勢が保有する米国国債を売りさばいたりしないことはもちろん、さらなる政策的な購入の計画ですら、あるいは交渉の材料になるかもしれない。
いずれにせよ、トランプ大統領が「ディール好き」ということを、思考様式のレベルで捉えることが重要だ。交渉好き、ということは、核心的利益の共通項の発見と発展のプロセスが好きだ、ということだ。
万が一にも、「えー、国際秩序の観点から見た自由貿易主義の原則は・・・」といった説教めいた演説をしてはならない。
■
国際情勢分析を『The Letter』を通じてニュースレター形式で配信しています。
「篠田英朗国際情勢分析チャンネル」(ニコニコチャンネルプラス)で、月2回の頻度で、国際情勢の分析を行っています。