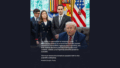「アゴラ」の池田信夫さんが声をかけてくれて、『江藤淳と加藤典洋』をめぐり行った対談が、早速公開されている。その末尾で『成熟と喪失』を主著とする江藤よりも、ほんとうは加藤の方が「成熟」していたんじゃないか、という話をした(31:00頃から)。
與那覇 なにが成熟なのかって江藤淳が〔『成熟と喪失』を書いた〕67年の時点で言ったかというと、まさに失われたものは戻ってこないんだと。近代化、そして敗戦という2段階を経て、日本人は「母なる、日本人にとっての自然な秩序」を滅ぼしてしまったんだと。
(中 略)
もう返ってこないという事実を認めて、それに耐え続けることが成熟なんだという風に、67年の時点では江藤さんは言ってたんですけど、その後に子供っぽくなっていくんですよね。やっぱり「あれは騙されてたんじゃないか」っていうのが、いわゆるWGIP〔の議論〕で。
その「アゴラ」に載った書評も、加藤についての考察を軸として、拙著の意義をまとめてくれている。とてもありがたい。

ところが日本では全体に、むしろ「子供っぽくなった江藤淳」に似た人の方が、増えている気がする。①いまの世の中は根本的にまちがっており、②それは国民を悪いやつらが騙してきたせいだから、③そいつをブッ殺して俺たち本来の姿を取り戻すぜうおおおお! みたいな感じだ。
平成のうちは「あ、WGIPガーな記事ばっか読んでるネトウヨの話ねw」と笑ってればよかったのかもだけど、令和には学者の国会たる日本学術会議の進退に絡めて、東大の先生まで人前でまったく同じ孤独な咆哮を上げるようになった。つまり、シャレにならない。
女性とマイノリティの口を塞ぎたいアカウントがいい具合に釣れている。
私たちはあるべき日本を取り戻す。
私たちを排除しない日本を取り戻す。 https://t.co/3J6sllQfKz— おきさやか(Sayaka OKI) (@okisayaka) May 16, 2025
なんでこうなのかと考えると、『成熟と喪失』と言ったときの「喪失」のニュアンスが、実感しにくい社会が生まれている。年を経るにつれ、徐々に少しずつ失われてゆき、変化を止めたり、まして巻き戻すことはできない。それが喪失だろう。
個人の人生で言えば「老い」だけど、平成の終わりから、ぼくたちの社会は老いを否認するようになった。いい感じにもう「老いちゃった人」の本だけは売れるけど、そんなゴールにどう到達するのか、途中の経過を誰も語らない……という話を、5年前に東浩紀さんとしたことがある。

與那覇いわく、いまの出版業界で売れるのは基本的に「若者本」か「晩年本」のどちらかである。前者は、成功した若手実業家が「起業して〇〇すれば成功する!」と若者を啓発する本。後者は、晩年にさしかかった文化人などが「人生は思い通りにいかないのだから流されるしかない、しかしそれでいいのです」と説く癒し本のこと。その両極端しか売れない状況はどこか不健康なのではないかと與那覇は前から感じていたという。
2020年12月のイベントのルポより
(強調は引用者)
じゃあ若者と晩年のあいだを生きる大多数はどうすんのよ、ってことだけど、理想の状態に「たどり着く」というよりも、いま、ギリどうにかなってる状態を「持ちこたえる」っていう発想が、要るんじゃないのかな、という直感がある。
父にせよ母にせよ、これが「ゴールだ!」という価値観を掲げすぎると、それをいますぐ寄越せ・取り戻せ・邪魔するやつは殺せ……みたいになりがちだ。江藤淳よりも加藤典洋の方に、そんな事態を避ける知恵=「成熟」への萌芽があったとしたら、やっぱり1970年前後の学生運動に本気で没入して、その末路を知っているからだと思う。
……といった話を、拙著の後記では加藤さんと上野千鶴子さんの「同い年・全共闘対談」を踏まえて論じていたのを(それぞれ東大・京大の全共闘参加者)、文藝春秋がネットにアップしてくれた。

同じ48年生まれの加藤典洋にむけて、上野千鶴子はこう問うている。70年安保の際、あれだけみなが既存の家族の自明性を疑ったにもかかわらず、気がつけば物書きを筆頭にして、昔ながらの父や母のイメージに還ってゆく人ばかりなのはどうしてか、と。
当時独身の上野に対し、現実の問題として「父」になっていた加藤はこのとき、いささかばつが悪そうだ。しかし上野が対話で口にした「持ちこたえる」という表現を反芻し、「かつていちど世界との間に持った関係をどう持ちこたえるかというさっきの話は、ぼく達の話したことの一つの核心だ」と問いを引きとる。
拙著、313-4頁
(対談は1986年5月の『國文學』)
いまの日本はベストじゃない。ていうかベストなんて他の国にもないし、そもそも原理的に実現しえないのかもしれない。だけど、少なくともそれに気づけて、できあいの安っぽい虚像に絡めとられないですむ状態を、キープしていく。「持ちこたえる」という言い方には、そんな感覚がある。
米国のトランプ現象から、日本のTwitterでの矮小なケンカまで。とかく片方の立場を絶対視して、相手側を全否定する「推しか、しからずばアンチか」になりがちな昨今だ。だけどそうじゃなく、両者のあいだに自分の足で立ち、自分の頭で考える立場を「持ちこたえる」やり方は、必ずある。

新潮社のオンライン新事業「本の学校」が、光栄にも2回目の講師として、ぼくを指名してくれた。この「推しでもアンチでもなく、生きるとは?」という観点から、拙著を未読の方にも伝わる形で、江藤と加藤の批評の意義をお話ししたい。
6/25(水)の19:00~、Zoomのウェビナーを使う形式で、視聴料もわずか800円での生配信。多くの方に、お申込みいただければ幸いです!
参考記事:



(ヘッダーは1969.1.19、陥落間近の東大安田講堂。時事通信より)
編集部より:この記事は與那覇潤氏のnote 2025年5月29日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は與那覇潤氏のnoteをご覧ください。