
早いもので師走も半ば、「今年をふり返る」系の企画が増える時期である。光栄なことに、昨年に続いて『文藝春秋』(2026年1月号)の読書欄が、「わたしのベスト3」に起用してくれた。

文学が社会に戻ってきた年だった。むろん、売上とかの話じゃない。
(中 略)
疫病や戦争など、関心を持たないことは「ありえない」とされる公の領域が生活を埋め尽くし、ファクト以外を「語るな」とされて、私的な感じ方は表に出すのを禁じられる。そんな時代は文学を足蹴にして、いま振り返れば怪しい「科学もどき」の解説ばかりを、垂れ流した。
488頁(強調を付与)
文学とは “あってもなくてもいいもの” の象徴で、その意味で常に不要不急である。なにかあれば真っ先に「要らない!」と言われる。実際、生涯に1冊も小説を、買って読まない人なんてざらだ。

このとき、2つの道がある。あえて言おう、卑小な道と高貴な道だ。
卑小な方は、なくたって別にいい文学の領域で「自分だけが助かろう」とするやり方だ。たとえばベストセラーを出せば、ないと困る①ビジネスの領域に “引き上げて” もらうことができる。
ヒット作がなくても、②社会正義の領域への移籍を狙う手がある。小説とか映画とか、どーでもいい趣味の話をくっちゃべってるように見えても、実は「社会を変える実践なんです!」みたいに言い張れば、ドヤ顔できる。

要するに、
①「小説なんて要らないけど、私は〇万部売れて映画になって、×万円ぶんGDPを押し上げたじゃないすかぁ?」
②「批評なんて要らないけど、私が論じるのを読めばSDGsとダイバーシティの考えが広まるじゃないすかぁ?」
な人たちは、文学の中でも “私だけは” 要にして急なんで、助けてください、と言ってる点で共通する。①は資本主義に肯定的、②は批判的という「右と左のイメージ」は、見せかけだけのニセモノで、本質的な対立はない。
年間読書人氏が、前回の拙稿に応答してまとめてくれたが、そんなニセモノ・カーニバルのうさんくささが、2020年代の読書界には立ち込めていた。先月末の「令和人文主義」をめぐる炎上は、溜まったガスにマッチを放ったようなものだ。

では、ぼうぼうと燃えた「自分だけ助かろう主義」の卑小さと異なる、高貴な道とはなにか?
ひとりで “よその領域” に逃げ出すのじゃなく、いつも不要不急で、公共的じゃなくて、「あなたの感想ですよね~?」みたく毎日嗤われる “文学の領域” そのものを、まるごと救おうと努める道だ。それこそが、連帯である。

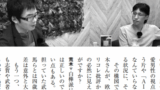
ベスト3には、今年ご一緒する機会に恵まれた①上田岳弘さんの短編集『関係のないこと』と、③荒木優太さんの編んだ『プロレタリア文学セレクション』を挙げた。が、もちろん会わないと連帯できないなんてことは、ない。
真ん中でとりあげた2冊目、文字どおり(ぼくが無知なのかもだけど)まったく知らない著者から送られてきた、②志良堂正史『他人の手帳は「密」の味』が、実は今回のメイン。

控えめに言って、驚くべき本だ。上のリンクのとおり、別に著名人じゃないパンピーのつけた手帳や日記を収集し、公開する図書室がある(有料)。なぜそんなことを始めたか、その哲学を、創業者自身が書き下ろしている。
一億総SNS社会の現在ほど、”個人” でいることが難しい時代はない。「個人的には…」と断ってネットになにか書くとき、実は誰もが他人の目線を意識しているからだ。芸能人がわざわざ公開する “プライベート” のように。
ほんらいなら私秘的な性行為を、あえて “人前” でやることでアテンションを稼ぐ手段がポルノだけど、いまやすべてがポルノになっている。内心で支持すれば足りることまで「推し活」と称して表に出すのも、要は感想のストリップ劇場だ。
——と、ぼくなら皮肉る事態を、志良堂氏は “私” の消えやすさ(fragile)として繊細に描き出す。
何かの作品を見たときに浮かんだ自分ならではの感情や感想は脆いものだ。定着する前に他人の感想を見聞きすることで、いとも簡単に上書きされてしまうし、
(中 略)
長い時間をかけて温めていたアイデアや信念も、時にフラジャイルだ。公開してリアクションやコメントを受け取れば、それがポジティブな助言だったとしても、何らかの変容を受ける。それを避けるには、公開せず自分の胸の内に秘めておくしかない。
志良堂著、234頁
だから本人しか読まないことが前提の手帳の中にしか、ポルノ化のフィルターをスキップできる場所がない。かつては “文学” の読み解きもまた、近い体験を提供したかもだけど、いまや推し活ハウツーが “批評” と錯覚される時代だからだ。


①感染症の抑止や被侵略国の支援と、②抑止や支援を「私はしてます!」と公言するのとは、別のことだ。ほんらいは①があって②に進むのだが、SNSがすべてをポルノにする社会では、②をやりたいから①にベットする順序の倒錯が起きる。
メディアがポルノスターの絶頂演技を流し続けた2020年代、ぼくらが忘れてしまったのは、相手と「密」な関係に入り、素顔で触れあうときの手触りだった。それを取り戻すためのリハビリこそが、来年からの課題だろう。

Webでは有料の部分なのでこっそり貼るけど、「わたしのベスト3」の末尾は以下のとおり。連載陣から22名が寄稿する年末回顧が、どうか、多くの人の年越しを豊かにしますように。
コロナやウクライナやガザをめぐり、公の場で正しいとされた言論が、わずか数年でいかに薄っぺらで、再読の価値もなく映ることか。それらに何が欠けていたかを、三冊の「文学書」は私に教えてくれる。
前掲『文藝春秋』2026年1月号、488頁
参考記事:
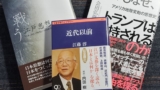

(ヘッダーは、私生活がポルノになるデジタル社会を予見した映画より)
編集部より:この記事は與那覇潤氏のnote 2025年12月15日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は與那覇潤氏のnoteをご覧ください。













