
社会主義を掲げて多民族を統合してきた連邦が解体し、1991年から2001年まで続いたユーゴスラヴィア内戦は、冷戦終焉にともなう最大の悲劇と呼ばれた。東欧とはいえヨーロッパに属する国で、白人どうしが殺しあう姿は世界に衝撃を与え、ちょうどいまのウクライナ戦争のような扱いだった。
9頁(強調を付与)
と、今日出る『Wedge』3月号の連載「あの熱狂の果てに」に、ぼくは書いている。1991~2001年は平成の序盤だが、ぼくにとっては中学受験から大学の卒論までのあいだで、青春そのものだ。

なにせ、いまのウクライナ戦争級の大事件だから、当時(主に)欧米の “意識の高い” カルチャーは、こぞってユーゴ紛争を採り上げた。毎年、賞を獲った話題の映画に最低1つは、「ユーゴもの」があるような感じだった。
色んな作品が日本でも評判になったけど、ちょっと “地味め” な1本が忘れられなくて、手もとにDVDを持っている。実は「レンタル落ち」なんだけど、それも含めて、ぼくにはすごく懐かしい。
1994年の映画で(日本公開は96年)、ネット配信はおろかDVDすらほぼなく、ぶ厚いVHSを実店舗で借りて見ていた。その分、最初は知らない作品を「ふと気になって見る」ことができたことの貴重さは、前に書いている。

『ビフォア・ザ・レイン』は、旧ユーゴ連邦の南端にあたるマケドニアが舞台で、監督も現地の出身だ。民族的には、主流派のマケドニア人はギリシャ正教徒、少数派のなかで最大規模のアルバニア人にはムスリムが多い。
マケドニアは、安定した政情のまま独立を達成し、隣接するコソヴォの地獄の紛争もまだ本格化していなかった。さっき “地味め” と書いたのは、なので本作は(人は死ぬが)狭義の「戦争映画」ではないからである。
が、だからこそ、いま最も滋味が深い。
作品の主題は、戦争そのものではなく、内戦がこの地域にも及ぶかもしれないという “始まりの予感” である。その分、それまで実現してきた複数民族の共存が、どう壊れるかが繊細に描かれる。
いずれもラブストーリーが絡む3部構成で、1部につき1名ずつ、「主要な人物」が撃たれて死ぬ。が、その撃たれ方は、常に予想を裏切ってくる。
「緊張が高まってますよ」と示唆する、粗暴な武装勢力めいたキャラが画面に映ると、この人たちが “対立する民族” のあの人を殺すんだろうな、と見る側はドキドキする。が、作品は――というか現実は、そう単純じゃない。
むしろ「え、そっち?」という殺され方が起き、展開が予見不能なのは、現実が多義的だからだ。どんな人も、民族だけを意識して生きてはいない。他人に言わない秘密や、自分でも整理できない気持ちを抱えて生きている。
『Wedge』の連載を書くにあたって、久々に見直したのは、理由がある。
今回は哲学者の東浩紀氏の新刊で、話題の紀行文集『平和と愚かさ』を採り上げた。旧ユーゴも訪れる同書では、ロマの視点に寄り添って最も著名な内戦を扱う名画を撮ったが、後にスラヴ至上主義に転回したE・クストリッツアへの言及が多い。
それで当時の記憶が疼いて、あのころ好きだった別の「ユーゴもの」を、また見たくなったのだ。
結果として、すごくいいマリアージュになった。
東氏の同書は、哲学的にはシュミットへの批判意識を蒸留したウォッカのような味わいだ。多義的な現実を、「正しいか、まちがいか」のふたつの極しか残らないほど切り詰めて捉えるのが、シュミットの友敵理論である。
そうした政治の論理は、シュミットが支持したナチスのように、戦争や殺戮を招くとしてよく非難される。だが、実は同じものが「平和」を語る際にも密輸入され、2020年代の日常に染み入ってきたことを、同書は指摘する。

戦争が始まると、非政治的な活動の領域は急速に狭まっていく。なぜある小説を読むのか、なぜある曲を聴くのか、なぜある選手を応援するのか、なぜあるひとと結婚するのか、すべてに政治的な意図が探られるようになる。……日本でも、右派左派を問わず分断を求める人々がSNSで行い始めていることでもある。
(中 略)
かつては戦争はよくないと叫んでいればよかった。ところがいまは、戦争はよくないと言うと、ではおまえは平和を取り戻すためにどちらの側で「戦う」のか、ロシアなのかウクライナなのか、イスラエルなのかハマスなのかと問われてしまう。平和についての語りが、戦いについての語りに引き寄せられてしまう。
25・28頁
ぼく流に言うと、そんな密輸業者が職名をロンダリングするための肩書が「専門家」だ。コロナでは日常のあらゆる所作に、ウクライナではSNSの全発言に、「それは敵側を利する」と因縁をつけるセンモンカが繁殖した。
いわゆるオッカムの剃刀で、シンプルに切り詰めた発想こそが、現実をよく捉える場合もある。だがセンモンカの解説や予測は、ことごとく現実から外れ続け、単なる「戦争屋」にしかならなかった。みんな知ってることだ。

『ビフォア・ザ・レイン』の主人公は、カメラマンである。報道写真とはもちろん、1枚の静画に現実を “切り取って”、世界に広める技術だ。
しかし、だからこそ彼(と恋人)は、自分が現実を単純化し、切り詰めてしまうことの怖さを知っている。その反省が、物語を動かしてゆく。
そうした複眼的な視点を促すことが、人文的に作品を味わうことの意味だった。それがいまは、”教養あるある詐欺” のビジネスにしか使われない。

ユーゴ紛争と、四半世紀後に勃発したウクライナ戦争とでは、もちろん色んなことが違う。だが最大の相違は、語り手が持つ教養の没落だろう。
ロシアが自由な取材を許すはずはないので、西側で流通する「ドキュメンタリー」はウクライナの目線になる。国の存亡がかかっている人びとである。当然 “盛り” も入ると思って、割り引くのはむしろぼくらの仕事だ。
ところが昨年、ついにアメリカから「バカか!」と怒鳴られるまで、TVが流す映像をそのままベタになぞる “解説” を、SNSで講釈するセンモンカもいたりした。そんな単細胞ぶりは、もはやヒトよりも環形動物を連想させる。

『ビフォア・ザ・レイン』の多義性は、タイトルそのものにも及ぶ。
このnoteの題名もそうであるように、「雨」は来るかもしれない “戦争” を指す不吉なメタファーだと解するのが、ふつうの見方ではないかと思う。少なくとも高校生だったぼくはそう見たし、今回も変わらなかった。
しかしまったく反対に、「恵みの雨」といったニュアンスの “救済” として、むしろ暴力の連鎖を終える希望の兆しが、雨に託されているとする解釈もできる。こちらの記事(のだいぶ下の方)で知って、ほほぅと思った。
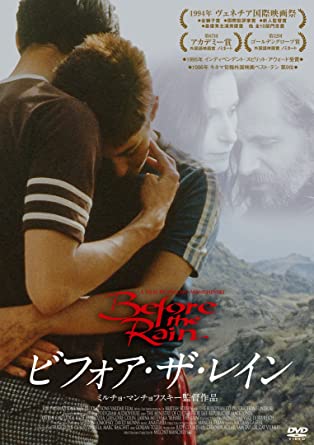
どっちかに決める必要は、別にない。
むしろ平和とは誰もが、本人にとっての “現実” が「自分への見え方」にすぎないことを知り、他人への見え方とのズレ(多義性)に寛容であるときに、はじめて達成される。人文主義とは本来、そのレッスンのことだ。

紀行文集である『平和と愚かさ』は、”旅” を通じて――つまりそれまでの「自分への見え方」を更新する体験との出会いを重ねる形で、綴られている。ぼくがコラムで紹介する際も、なによりそこを意識してみた。
『Wedge』は書店でも買えるが、多くの人は東海道新幹線の「グリーン席に置いてある雑誌」として知っていると思う。来月の19日まではこの号のはずなので、ぜひ目を通して、考える “旅” を作るきっかけになれば嬉しい。
新たな戦争への足音が、世界中で聞こえる、いまだからこそ。

哲学者が旅をしているのではない。旅することが哲学なのである。
かつて新たな開国のように言われた、冷戦後の情報環境のグローバル化は、かえって地球がまるごと「鎖国」したにも等しい閉塞に帰結した。熱狂を失って久しいその廃墟から、もういちど旅に出るきっかけを、同書は読者に示してくれる。
『Wedge』2026年3月号、10頁
参考記事:
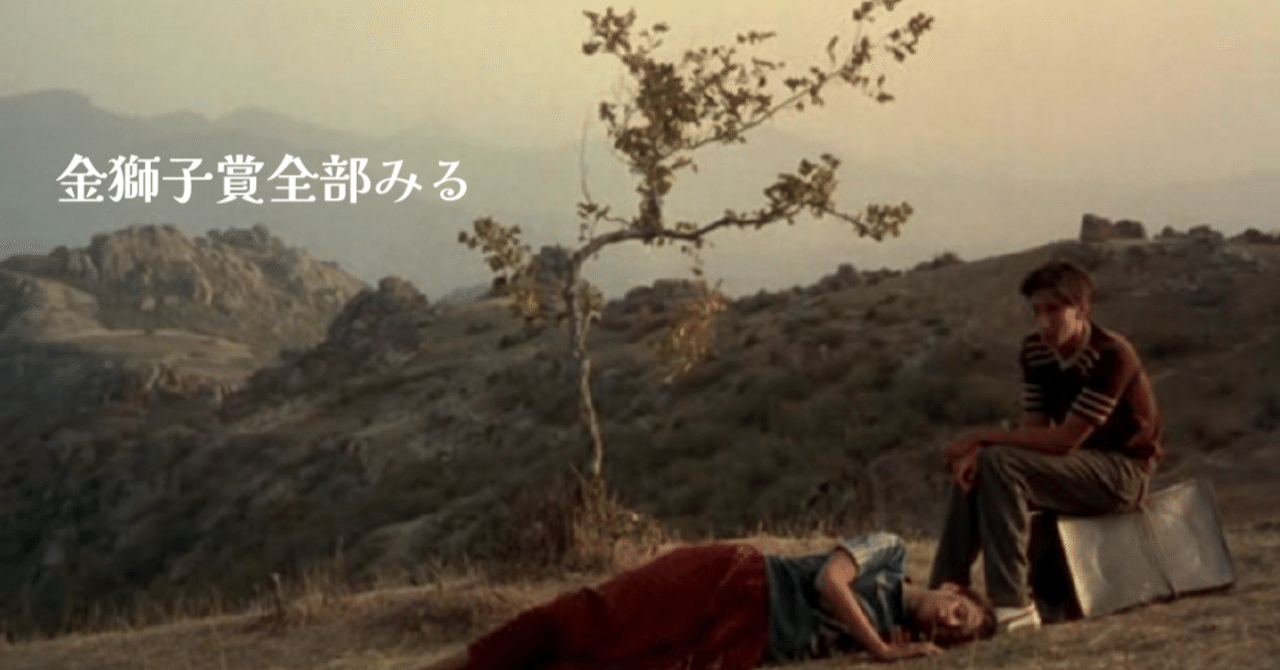
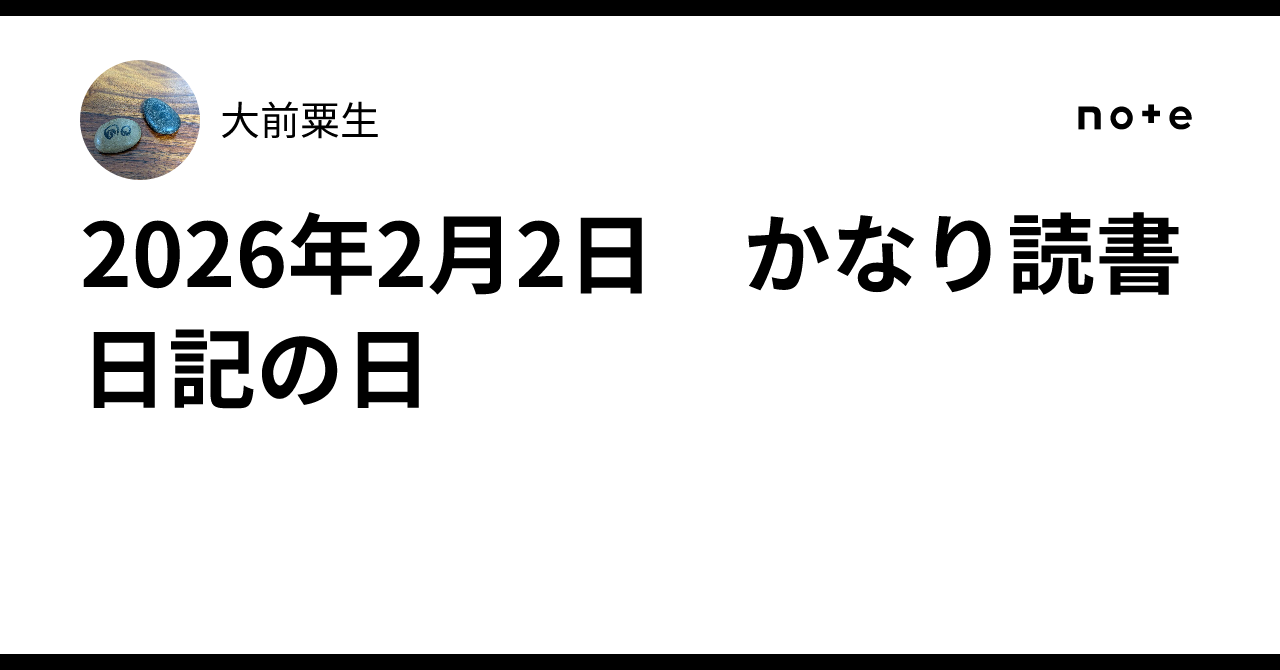
(ヘッダーは映画の冒頭を、このブログより)
編集部より:この記事は與那覇潤氏のnote 2026年2月20日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は與那覇潤氏のnoteをご覧ください。















コメント