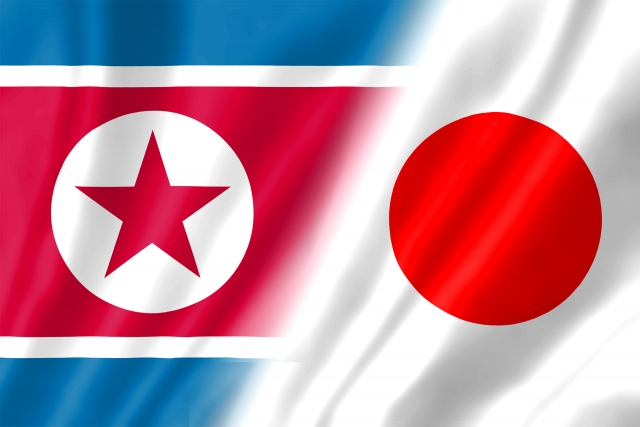林語堂がエッセイ集の中で、西洋人の握手をくさして、両手を握り上下させる拱手(きょうしゅ)を誇ったことは前回に触れた。中国人も今ではほとんど握手のあいさつが一般化しているので、もし彼が見たら、彼の皮肉は中国人自身に向かったに違いない。林語堂が西洋人の身体接触型マナーに対して抱いた嫌悪感は、開国後、世界に出た多くの日本人も同じように体験したことだろう。
野村雅一著『身ぶりとしぐさの人類学』(中公新書)によると、明治天皇が1979年、世界周航の途中、日本に立ち寄ったアメリカの前大統領、グラント将軍を謁見した、緊張の面持ちで初めて握手し、清朝のラストエンペラー、溥儀帝がスコットランド人教師のジョンソンと握手したのは、それに遅れること40年後の1919年だったという。そう考えると、中国に浸透した握手文化の伝播速度は極めて速いことになる。なにしろ、日本はまだお辞儀文化を守っているのだから。
ちなみに皇室担当として天皇皇后両陛下の外遊に同行した経験から言うと、陛下はヨーロッパでは出迎えの一般市民と触れ合う際、自然に握手をしておられる。国内とははっきりと使い分けがされている。
東西文明の比較だけでなく、日本と中国のあいさつ文化の違いも今は際立っている。以前はと言えば、日本のお辞儀と中国の拱手は異なるが、膝まづいて地面に頭をつけるほど下げる叩頭(こうとう)は共通していた。中国では特に、皇帝など高位の者に対して行われた正式な礼儀作法だ。ところが、そこにも大きな違いがあった。
日本に25年間滞在した英国外交官のアーネスト・サトウ(1843-1929)が、『一外交官の見た明治維新』(坂田精一訳)で幕末明治期に見た面白い経験を書き残している。ある中国人が日本人を見て、「叩頭ばかりしている日本人の礼儀作法は了解できない、と哲学じみたことを言っていた」というのだ。
西洋人からみたらもっと異様だろう。米人類学者モンタギューと米社会心理学者マトソンの共著『愛としぐさの行動学』(吉岡佳子訳、1982)も、西洋の握手と日本のお辞儀を並べて論じているが、日本人にとって「お辞儀とは人間関係の始まりである」といい、「人はより礼儀正しくしようと努めるあ、あまり、我妻が“ワンダウンマンシップ”(one-downmanship)と呼ぶところの“お辞儀コンテスト”を行うことがある」と誇張した表現を用いている。
まあ、それもやむを得ないだろう。なにしろ現在も同じような話を多くの中国人から聞かされる。日本人のグループは遠くから見てもすぐわかるそうだ。あいさつだけでなく、会話の中でも、とにかくお互いにお辞儀ばかりしている、という。そう言われて観察すると、確かにその通りだ。日本人の多い上海では、携帯をかけながら、あたかも目の前に人がいるかのように、ひたすらお辞儀をしている日本人サラリーマンの姿もよく見かける。お辞儀文化は相当根深い。
私が日本人の握手で気になるのは、政治家が街頭遊説で、腰を折り曲げ、両手を差し伸べて握手をしている光景である。よくお辞儀と握手を一緒にしてはいけないと言われる。あたかも相手に服従し、卑屈に見えるからだ。実際に、性根は同じなのだろうが、始末に負えないのは、いったん当選すると、その卑屈さの反動として、尊大になることだ。小さな権力を振りかざし、周囲の弱い立場の者に当たり散らす。有権者にしても、すれ違いざまに握手をしただけで、その人を理解しようというのがそもそも無理な話なのだ。ヒットラーでさえ、プライベートでは通りすがりの人々と握手をしていたというのだから。
握手は「奴隷の服従だ」と言ったのは、あのオルテガだ。(続)
編集部より:この記事は、汕頭大学新聞学院教授・加藤隆則氏(元読売新聞中国総局長)のブログ「独立記者の挑戦 中国でメディアを語る」2017年8月13日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は、加藤氏のブログをご覧ください。