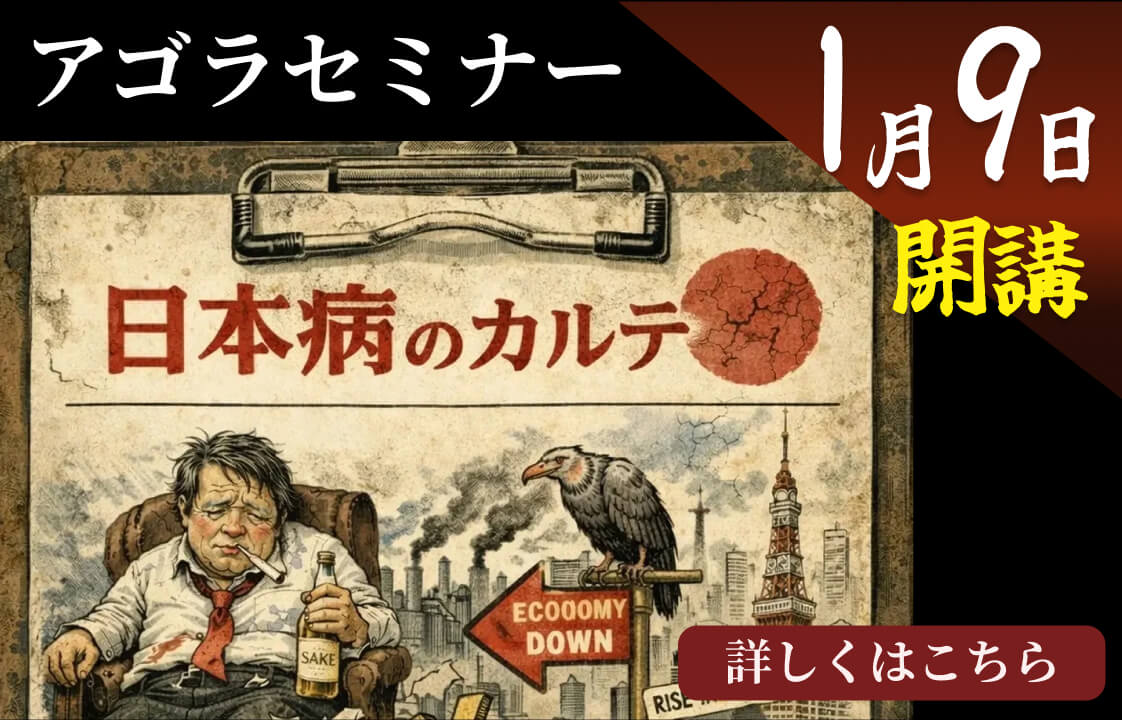学問的な歴史に興味を持ったことがあれば、「史料批判」という用語を一度は耳にしているだろう。しかしその意味を正しく知っている人は、実は(日本の)歴史学者も含めてほとんどいない。
史料批判とは、ざっくり言えば「書かれた文言を正確に把握する一方で、その内容を信じてよいのかを、『書かれていないこと』も含めて検証する」営みだ。結果として、文字面には表れていないとんでもない意味が、当該の史料(資料)には秘められていたと判明することもある。
簡略な例を出すと、AがBに宛てて出した書簡に「Cは悪人だ」と書いてあったとしよう。書簡自体は捏造ではなく、文字の翻刻も正確だとする。それでは「Cは悪人だった」とベタに歴史書に書いて、OKだろうか。
そんなことはない。まずA・B・Cの相互の関係を、当該の書簡以外も含めて確認する必要がある。「BはAの上役にあたり、CはAとポストを争っていた」といった史実があった場合、書簡の内容は鵜呑みにできない。AがBに対してライバルのCを、むしろ誹謗したのかもしれない。
次に、時代背景も調べなくてはいけない。Cが悪人である理由が「十分に親孝行していない」と書かれていたら、同時代の家族の慣行や思想の潮流を押さえる。Cの行為は当時の道徳的なタテマエには違背するが、「実態としてはみんなそうだった」といった事情が見えてきたら、やはりAによる讒言説が有力になる。
これが学問的な史料批判の真髄で、書かれたものを常にそうした態度で扱うからこそ、「歴史学者の書く歴史がいちばん信頼できるね」ということになっている。タテマエとしては(笑)。
なぜ(笑)が付くのかは、みなさんお気づきでしょう。2021年の4月に公表されたオープンレター(現代日本語で書かれ、翻刻上の問題は存在しない)について、私は当時から「史料批判」を行い隠れた意味を把握していたが、歴史学者でそうした人は、誰もいなかったからである(苦笑)。

史料批判を通じてオープンレターの内実に気づくチャンスは、それなりにあった。まずそもそも同レターは、文言としては以下のように謳う。
誰かが、性差別的な表現に対して声を上げることを「行き過ぎたフェミニズムの主張」であるかのように戯画化して批判すると、別の誰かが「○○さんの悪口はやめろ」とリプライすることがあります。
こうしたやりとりは、当該個人を貶めるために、「戯画化された主張を特定個人と結びつける」手法としてパターン化されています。
そこには、中傷や差別的発言を、「お決まりの遊び」として仲間うちで楽しむ文化が存在していたのです。
段落を分け、強調を付与
もちろんそうした品位を欠くコミュニケーションは、誰がやるにせよ褒められたものではない。ところがオープンレターが炎上する過程で広く知られたとおり、当のレター自体の署名欄でも、そうした「遊び」は行われていた。
ネットの「ネタ」として著名な架空の大学名を使い、「社会学部 学部生」とまで添えて「千田由紀江」と記入したのは、実績ある社会学者でフェミニストながらオープンレターの呼びかけ人たちと対立してきた、千田有紀氏への中傷行為であることは明白である。
上記の2022年1月19日の告発記事が載り、オープンレター自体がどういった「コミュニケーション」の場であったのかが明白になって以降に、署名を撤回することは十分に可能だった。それを怠った歴史学者に、史料批判や、ましてオンラインでの人権について云々する資格はない。

さて、以下は山形大学天羽研究室が保存・公開している、オープンレター署名者の一覧だが、実に多くの歴史学者、ないし歴史の研究者(社会学で現代史を研究する、とか)の名前がある。私自身がむかし歴史学者だったので、個人的に面識のある人も結構いる。
そうした学者に対して私たちは「先生はオープンレターに名前がありますが、署名する際に史料批判はされたのですか?」と、尋ねてゆかねばならない。もちろん攻撃的である必要はなく、ましてキャンセルなどは論外である。マナーを守り、礼を失しないように質問すればよい。
もし ①「史料批判をせずに署名した」のなら、その人は歴史研究者としてのモラルを守っていない。当然に反省を求めるべきだし、行いを改めないなら学者失格だ。
逆に ②「史料批判をした上で署名した」のであれば、その人はオープンレターの隠された狙いだったTRA(Trans Rights Activists)の示威行動に、それとわかって同意・協力・後援したことを意味する。だって、歴史研究のプロが史料批判に基づき、肩書つきで名前を貸したのですから。
その人の勤める職場にも、女子トイレはあるだろう。職場が大学であれば、女子スポーツのサークルや、女性用の更衣室・シャワールーム、場合によっては女子寮などの施設もあるはずである。賛否はあるが近年は「女性教員」に限る形で、研究者を公募する例もある。
史料批判を経て署名した教員は、それらのすべての場面で「私はトランスジェンダーで、女性だ」と主張する人を、一切の例外なく受け入れなければならない。オープンレターが実際には「いかなる史料か」をわかった上で、職名を掲げて本名でサインした以上、そうしないなら「嘘つき」であり、研究能力か人格かに欠陥がある。
ちなみに、能力と人格の双方に問題がある署名者もいる。それについては従前から指摘し、「歴史学者」の諸氏はどう感じるのかを問うてきた。

それでは末尾に、広い意味で歴史の研究者だと判明している、オープンレター署名者のリストを掲げておこう。氏名ないし肩書で「ぱっとわかる」例のみを拾ったので、おそらく実際には、署名した歴史の研究者は遥かに多い。
なぜなら、「呉座勇一と一緒に燃やさないでください!」と表明し自らの炎上を避けることが、2021年春の彼らの行動原理だったからだ。私は署名簿に名前があるので「燃やされずにすむ側です」とPRするはずだった駆込寺は、あにはからんや、むしろ焼かれるペスト患者たちのスラムであった。
彼らの卑小さが広めてしまった「とりあえず ”安全策” でキャンセル」な風潮は、学界やSNSを飛び越えて、この国の社会全体を巻き込みつつある。いま食い止めるためにこそ、戦犯たちの召喚と再吟味が必要だろう。

ぜひ多くの読者に、以下のリストをご活用いただきたい。オンとオフラインでの問い合わせを通じて、史料批判の意義を正しく研究者に理解させ、「誰もが参加できる自由な言論空間」を作ってゆくことを願っている。
澁谷知美 社会学
師茂樹 花園大学教授
伊藤春奈 編集者・ライター
富永京子 立命館大学准教授
玉田敦子 中部大学教授
能川元一 大学非常勤講師
加治屋健司 東京大学大学院教授
佐藤雄基 立教大学文学部教授
直井大河 明治大学文学部史学地理学科西洋史学専攻4年
衣笠 太朗 秀明大学助教
北村匡平 東京工業大学准教授
河上麻由子 大阪大学准教授
川口悠子 法政大学准教授
Unferth(ウンフェルス) 在野の研究者(近現代ドイツ史)
兼子 歩 明治大学政治経済学部専任講師
川瀬貴也 京都府立大学教授
原 基晶 東海大学 准教授
鎌倉佐保 東京都立大学
若林宣 著述業
鶴見太郎 東京大学大学院准教授
渡部宏樹 筑波大学 助教
茶谷さやか シンガポール国立大学准教授
伊藤憲二 総合研究大学院大学准教授
今井宏昌 九州大学講師
柳原伸洋 東京女子大学准教授、アウクスブルク大学研究員
福島幸宏 慶應義塾大学文学部准教授(有期)
伊藤俊一 名城大学教授
橋本一径 早稲田大学文学学術院教授
小田原のどか 評論家・彫刻家・出版社代表・多摩美術大学/京都市立芸術大学非常勤講師
本山央子 アジア女性資料センター理事、国際関係論研究
木村直恵 学習院女子大学准教授
金山浩司 大学教員
園田節子 立命館大学教授
山本浩司 東京大学経済学部 准教授
前川一郎 立命館大学教授
服藤 早苗 埼玉学園大学名誉教授
五野井郁夫 高千穂大学教授
倉橋耕平 創価大学准教授
米山リサ トロント大学教員
松下哲也 近現代美術史・文筆業
田瀬 望 大学非常勤講師
逢坂裕紀子 東京大学文書館特任研究員
森田直子 立正大学文学部准教授
周東美材 大東文化大学准教授
押尾高志 西南学院大学 講師
坂下史子 立命館大学文学部教授
東島 誠 歴史学研究者、立命館大学文学部教員
宮本ゆき DePaul University
榊原千鶴 名古屋大学教授
中野敏男 東京外国語大学名誉教授
土屋和代 東京大学大学院総合文化研究科准教授
北村嘉恵 歴史研究者・北海道大学教員
小檜山青 著述業
森 直人 筑波大学教員
永原宣 マサチューセッツ工科大学准教授
藤野裕子 早稲田大学
菊池信彦 関西大学
板橋拓己 成蹊大学
中澤達哉 早稲田大学教授
加藤陽子 東京大学文学部教授
川端美季 立命館大学
熊澤弘 東京藝術大学大学美術館准教授
小澤 京子 和洋女子大学 教授(芸術学)
根本敬 上智大学総合グローバル学部教授
金富子 東京外国語大学教員
毛利嘉孝 東京藝術大学大学院教授
ヒロ・ヒライ BH 主宰
加藤 公一 岐阜大学教員/歴史学徒
平体由美 東洋英和女学院大学教授
佐藤信弥 立命館大学客員研究員
貴堂嘉之 一橋大学教員
嶋理人 熊本学園大学講師
大森一輝 北海学園大学人文学部教員
星乃治彦 東京大学客員教授
George Wollaston 大学院生(修士課程) 日本史学
安藤さやか 東京藝術大学専門研究員、美術史研究者
花田史彦 研究・教育職
豊田真穂 早稲田大学
大門正克 早稲田大学特任教授
公開されている名簿の順
肩書は署名の当時
参考記事:逆に「よい歴史学者」の例は3つめに


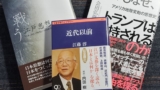
(ヘッダーはWikipedia「ロンドン大火」より)
編集部より:この記事は與那覇潤氏のnote 2025年2月3日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は與那覇潤氏のnoteをご覧ください。