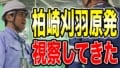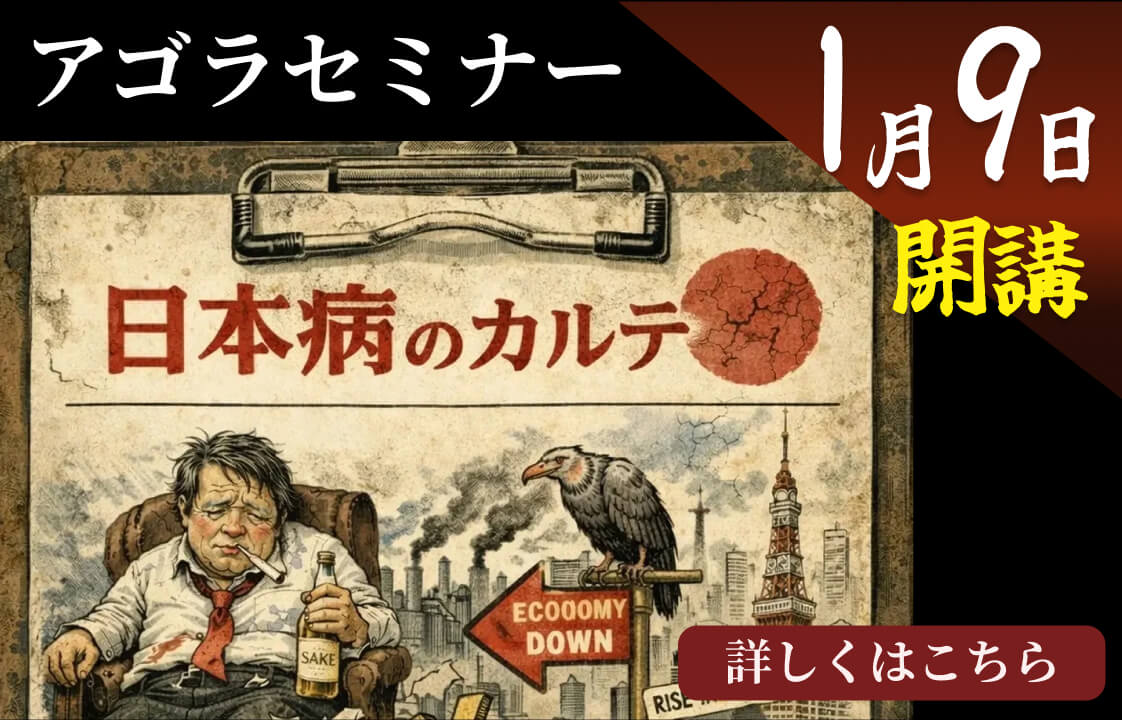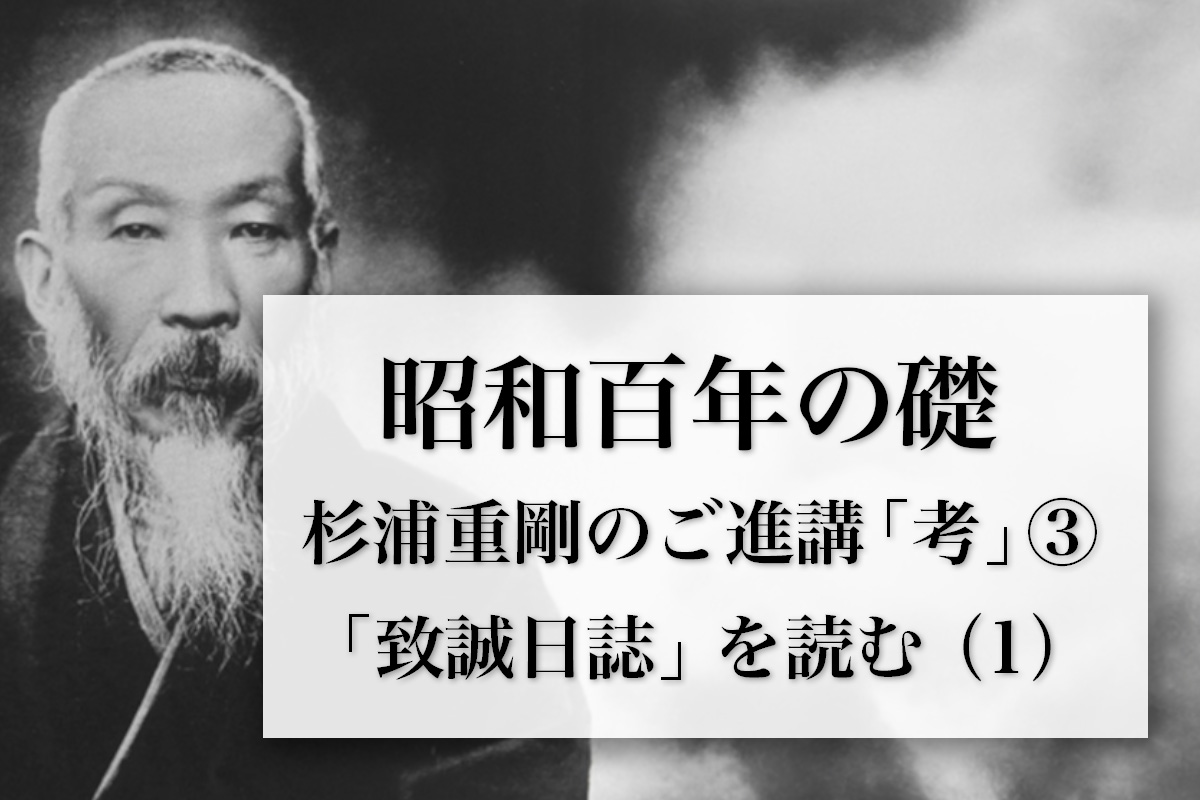
(前回:昭和百年の礎:杉浦重剛のご進講「考」② ご進講の題目と内容)
「致誠日誌」は杉浦重剛が東宮御学問所御用掛を拝命した1914年5月15日から日々欠かさず記した「日誌」である。
皇太子への進講は21年2月に終了するが、18年4月の婚約と同時に初等科を退学した良子女王への進講がなお約3年間続いたため、「日誌」は22年6月20日まで記された。それは皇太子と女王への足掛け9年間に亘る進講準備の記録である。
このうち14年5月から12月までと15年1月から3月までの約1年分の「日誌」が、「昭和天皇の学ばれた『倫理』御進講草案抄」に掲載されているので、杉浦が如何に進講準備に粉骨砕身注力し、工夫に腐心したかを知るべく、その全部を出来るだけ原文通りに掲げてみる。
※()は解説した所功氏の補足、【】は筆者のコメント、太字は筆者)。
大正三年甲寅(1914年)
5月
15日 浜尾男爵より午前九時、東宮御学問所倫理科担当の件に付き、所談あり。事、突然に出づるを以て、一両日の猶予を請ひ、(日本中学校に)出校の上、千頭(清臣)氏、猪狩(又蔵)氏に内話し、更に国学院大學に於いて、山田・石川両氏に内話し、何れも賛成を表せらる。
【千頭清臣(1856年生)は東大文学部卒後に東大予備門で教え、1886年英国留学。帰国後一高教諭や二高教授などを歴任した後、内務書記官、栃木・宮城・新潟・鹿児島各県知事を務めた】
18日 午前、猪狩氏に履歴書の謄写を托し、これを浜尾氏に致す。
23日 午前、国学院大学に於て、今井氏と出会し、同紙と共に宮内省に出頭し、波多野宮内大臣より辞令拝受。御礼の後、高輪御殿に到り、学問所諸氏に面会し、且内部を参観し、午後一時、(皇太子殿下の)拝謁仰せつかる。
6月
8日 出校。猪狩氏、深井寅蔵氏、井上雅二氏、青戸氏に参考資料を相談す。
【猪狩氏(1873年生)は本稿(その2)で述べた猪狩史山のこと。青戸氏は芝大神宮社司、国学院大学教授を務めた国学者の青戸波江(1857年生)で、称好塾に籍を置いた。深井寅蔵も称好塾に籍を置いた日本中学校教員】
9/11/12/14日 出校。参考書の調査、収集。
15日 午前、浜尾氏に抵り、相談する所あり。午後、白鳥(庫吉)氏に抵る。黄昏、浜尾氏来る。
【白鳥庫吉(1865年生)は、御用掛主任として進講の編成と運営に関わり、歴史家として国史、東洋史、西洋史を7年間ご進講した。教科書として『国史』全五巻を執筆し、歴代天皇の皇位継承の次第などを進講した。東郷総裁、小笠原幹事と共に杉浦の進講の多くに陪席した】
16日~19日 参考資料渉猟。
22日 参殿。初めて進講、「三種の神器」申上る。東郷総裁、浜尾副総裁、入江侍従長、白鳥主任、小笠原幹事等列席。夜、浜尾氏に抵る。此日、(貞明)皇后宮より御下賜品あり。
23日~25日 第二回進講資料等研究。 25日 中村安之助氏の独乙書の反訳を托す。
27日 参殿。種々の報告を聞く。夜、猪狩・中村両氏と共の研究。
28日 井上哲次郎氏を訪ひ、参考材料を得。
【井上哲次郎(1856年生)は東大初の日本人哲学教授。ドイツ観念論を日本に紹介し、東洋哲学研究も開拓した。『勅語敷衍』を著し、国民道徳を唱道】
29日 参殿。第二回「日章旗」御進講。大迫院長、浜尾大夫、白鳥・小笠原両氏列席。
7月
1日 第一高等学校卒業式に列し、参考に資す。午後、猪狩氏と今後の課程の方針を談ず。
2日 次学期教案の準備に着手し、材料を蒐集、繙読す。
3日 午前十時、殿下、新橋駅御出発、桃山御陵御参拝に付き、御奉送。午後、参考材料の研究。夜、中村氏を招く。浜尾氏より参考書来る。 4/5日 参考書繙読。
7日 午後三時四十分、殿下、新橋御着。奉迎。逸見氏より南洲遺物を示さる。
9日 猪狩・中村両氏と別々に研究。此日「クリフォルト」文集を借覧す。
11日 猪狩氏と談ず。光雲寺に抵る。 13日 参考書を読む。 14日 猪狩氏に談ず。
15日 参考書を読む。千頭氏、英文参考書目を供せらる。
16日 猪狩氏、趣意書起草成る。国学院に於て、参考書数冊を得たり。
18日 趣意書自写。「寛平遺誡」等写し成る。
20日 白鳥氏を訪ふて、方針を談ず。夜、国民道徳叢書を渉猟す。
22日 参内。天機伺。午後、教科方針研究。 26日 光雲寺に於て、猪狩・中村両氏と研究。
29日 『日本政記』抄。夜、『元田(永孚)翁進講録』を読む。
30日 青戸氏より『六史要覧』を借り、渉猟し了る。 31日 『日本政記』を読む。
8月
1日 白鳥氏と共に箱根御用邸に伺候。 3日 『日本政記』を読む。
4日 猪狩・中村両氏に商量し、次学期の教科梗概を定む。二三、参考書を読む。
【商量とは、 物事についてあれこれと考えることや相談すること、または相談して考えること】
5/6日 太田貞一氏は古歌の談あり。『明倫歌集』を借用。 7日 光雲寺集合。
8日 『青雲図賛』を松本真弦氏より借受、一読す。夜、『帝範』『明倫歌集』を読む。
9日 浜尾氏より招きに応じ、同邸に白鳥氏と鼎座し、八時間、歴史・倫理等の問題を談ず。
10日 午後、石川岩吉氏と談ずるところあり。『六史要覧』の写取を始む。『幼学綱要』を読む。『史稿』を渉猟。
【石川岩吉(1875生)は明治〜昭和期の教育家、後に国学院大名誉学長】
11日 『史稿』を渉猟。光雲寺に於て、猪狩・中村両氏と研究。夜、『幼学綱要』渉猟。『六史要覧』抄写、引続。
12日 『日本政記』論文を抄出し、六史(引続)。 13日 『六史要覧』引続。
14日 『史稿』再読。白鳥氏に抵り、談す。浜尾氏より有志意見書を貸与。『六史要覧』引続。
15日 上野奉迎。光雲寺に猪狩・中村両氏と研究。『六史要覧』写了。夜これを渉猟す。
18日 光雲寺に猪狩・中村両氏と会し、大に研究の歩を進む。有志意見書を精読す。
19日 『山鹿素行修養訓』渉猟。 20日『元田翁進講録』を読む。
21日 光雲寺に於て、猪狩・中村両氏と研究に従事す。
22日 長谷川昭道氏の『九経談総論評説』を読む。
24日 『大正修身訓』一読。服部広太郎氏を訪ふ。
【学習院教授だった服部広太郎(1875年-1965年)は、御学問所御用掛として「博物」を5年間担当した。1923年に徳川生物学研究所所長に就任、25年に設けられた生物学御研究所の主任も務めた。戦後も侍従職御用掛として陛下のライフワークである生物学研究を支えた】
25日 光雲寺に猪狩・中村両氏と研究に従事す。原稿数冊成る。
26日 山本信哉氏来訪。『寛平遺誡』等に関し、托す所あり。
【山本信哉(1873年生)は、日本の歴史学者、神道学者。東京帝国大学史料編纂所史料編纂官】
27日 太田量一・島弘尾氏と商量。太田氏より『皇国の手夫理』を寄せらる。
28日 『皇国の手夫理』及び文部省修身書渉猟。
29日 白仁氏来訪。光雲寺に於て、猪狩氏と研究に従事す。『竹内式部事績』、山県所蔵を聞知す。
30日 河村善益氏を訪ひ、快談す。夜、田中知邦氏『赤心一片』を読む。
【河村善益(1858年生)は判事、検事、貴族院勅選議員】
9月
1/2日 両校始業に付き、多少の参考を得たり。永原氏、修身教案提供。
3日 小林正策氏より『東宮勧読録』を借受。猪狩氏、草案作成数編成る。『進読録』渉猟。
5日 山県昌一氏を訪ひ、『竹内式部事績』を探求す。『柳子の新論』一部を恵まる。猪狩氏同行、『本朝蒙球』を渉猟す。
6日 光雲寺に於て、青戸・猪狩・中村三氏と共に、教科に関し、終日研究従事す。シユンヒ氏の『帝王教育書』の結論大意を聞く。
7/8日 青戸氏より『禁秘抄』『日本書紀』『古事記』『万葉集』の話を聞く。
11日 ご始業式に列す。外務省に小村氏を訪ふ。石川三吾氏より『野芹』借用。
【小村氏とは小村寿太郎の息子欣一。寿太郎(1855年生)は、飫肥藩の貢進生として進んだ大学南校で杉浦と出会って以来、国権主義・国粋主義の思潮を共有する親友。外交官となり在英日本大使館に勤務していた欣一は、寿太郎が桂第二次内閣辞職(1911年)で外相を辞した年の暮れに死去したのに伴い、帰国して父の爵位(侯爵)を継いだ】
12日 参殿。白鳥氏の「歴史」進講を傍聴す。
13日 福岡秀猪氏を訪ふ。光雲寺に於て、猪狩・中村両氏と商量す。
14~16日 第三回御進講の準備。15日 猪狩氏と商量し、更に夜、習読す。16日 山本信哉氏来訪。『寛平遺誡』抄写を貸与せらる。草間氏を訪ふ。
17日 第三回御進講「国」。浜尾、白鳥、小笠原三氏、立会。第四回御進講準備。
18/19日 第四回御進講準備。 20日 三浦周行氏来訪。参考の材料を聞く。
21日 第四回御進講「兵」。東郷、浜尾、宇佐川、小笠原諸氏、立会。第五回の準備に掛る。『寛平遺誡』抄写成る。 25日 青戸氏を訪ひ、敬神に関する研究。
26日 参殿。会議に列す。午後、素行会に於て、山本信哉氏に出会。夜、第五回の準備(浜尾氏より注意)。
28日 参殿。第五回「神社」御進講。東郷、浜尾、甘露寺、小笠原四氏、立会。
30日 『勅語衍義』其他抄読。
(その④:「致誠日誌」を読む(2)につづく)
【関連記事】
・昭和百年の礎:杉浦重剛のご進講「考」①
・昭和百年の礎:杉浦重剛のご進講「考」② ご進講の題目と内容