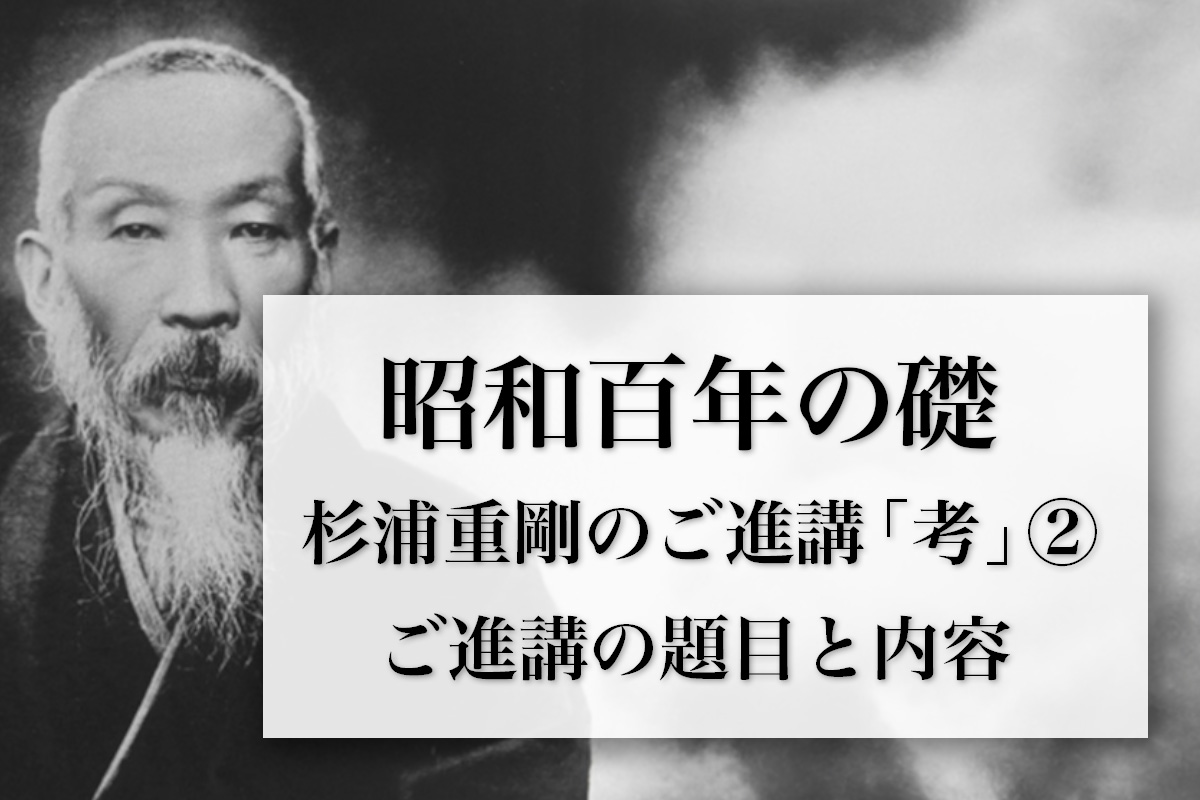
第一回目の進講は御用掛拝命からひと月余り経った1914年6月22日に行われた。題目は「三種の神器」であった。彼は次のように述べているが、拝命後に「生命を捧げて固より惜しむところがない」とも述べていた杉浦ならではの感想ではなかろうか。
(前回:昭和百年の礎①:杉浦重剛のご進講「考」)
今日第一回のご進講を申し上げた。昨日は医者に行って身体全部を診察してもらった。若し病気にでもなって今日の勤めを果たすことが出来なかったら、実に千秋の遺恨と思って注意した。今朝は先ず招魂社に参拝して、草稿を神前に供え、それから参殿してご進講申し上げた。丁度五分足らぬ位に講じ終わった。
進講当日の杉浦の日課は、午前3時起床、斎戒沐浴して暫し端座瞑想した後、一人静かに朝食をとり、6時に池袋の自宅から高輪の御学問所に人力車で向かう。7時に御用掛控室に入って心を落ち着け、殿下の登校を出迎えて、8時から進講を始めるというものであった。
杉浦は進講の眼目を、将来天皇となられる少年親王の人徳や見識を育成することに置いた。よって、基本方針を次の三点に置きつつも、その題目は古今東西の典籍は勿論のこと、偉人伝や花鳥風月や文物など森羅万象に及ぶという、趣向を凝らしたものだった。
一、 「三種の神器」に則り皇道を体し給うべきこと
二、 「五条の御誓文」を以て将来の標準と為し給うべきこと
三、 「教育勅語」の御主旨の貫徹を期し給うべきこと
進講草案の作成を補助した日本中学校教師(後に校長)の猪狩又蔵(史山)は1936年に『倫理御進講草案』(「原本」)を刊行した。それはB5版より少し大きい版の1180頁の大著で、定価12円(当時、米50kg相当)と高価ながら当時ベストセラーになった。が、収録されたのは御進講全281回のうち第1から第4学年までの153回分と第1学年後期の「教育勅語」11回分だけで、第5学年以降が欠けている。
1938年に「原本」を基に『倫理御進講草案抄』として「21題目の抄出本(120頁)」、「44題目の抄出本(353頁)」、「58項目の抄出本(500頁)」の三冊が出版された。本稿参考文献に掲げた『昭和天皇の学ばれた「倫理」御進講草案抄』は、この「44題目の抄出本」の再版である。筆者の住む横浜市の中央図書館に「原本」と「抄本」1冊が所蔵されているが、館内利用のみで貸し出しはされていない。
さて、その「三種の神器」の進講草案要旨が、倫理学者の深作安文博士(1874年生。井上哲次郎の学統を受け水戸学を研究、国民道徳論を提唱)が「回想本」に寄せた「杉浦重剛先生の『倫理御進講草案』を読む」にこう記されている。
三種の神器及びこれと共に賜りたる天壌無窮の神勅は我国家成立の根底にして国体の淵源又実に此に存す。是れ最も先ず覚知せられざるべからざる所なり。殊に神器に託して与えられたる知仁勇三徳の教訓は、国を統べ民を治るに一日も怠るべからざる所にして真に万世不易の大道たり。故に我国歴代の天皇は、皆此の御遺訓に体して能く其の本に報い、始に反り常に皇祖の威徳を顕彰せんことを勉めさせ給えり。是れ我が皇室の連綿として無窮に栄え給う所以また皇恩の四海に洽(あまね)き所以なり。左すれば将来我国を統御し給うべき皇儲殿下は先ず能く皇祖の御遺訓に従い皇道を体し給うべきものと信ず
深作は第4学年最初に講じられた「五条の御誓文」の進講草案の要旨も「回想本」に寄せているので以下に引く。
我国は鎌倉時代以降凡そ七百年間政権武家の手に在りしに、明治天皇に至りて再び之を朝廷に収め更に御一新の政を行われんとするに当り先ず大方針を立てて天地神明に誓わせられたるもの即ち五箇条の御誓文なり。爾来世運大いに進み憲法発布となり、議会開設となり、我国旧時の面目を一新したるも、万般の施設皆御誓文の趣旨を遂行せられたるに外ならず。単に明治時代に於いて然るのみならず、大正以降に在りても政道の大本は永く御誓文に存するものというべし。故に将来殿下が国政を統べさせ給わんには、先ず能く御誓文の趣旨を了得せられて、以て明治天皇の宏謨(こうぼ)に従い之を標準として立たせ給うべきと信ず
前述の通り『倫理御進講草案』には第五学年以降の分が欠けているが、猪狩は「回想本」の「杉浦先生進講記」に「倫理進講目録」として第7学年までの題目全てを記している。それらを一覧すれば、杉浦が後閑菊野のいう「日常の色々の行い」に絡めて「帝王の学」の粋を進講していたことが想像出来よう。
第1学年 大正3年(1914年)4月より9月まで
三種の神器。日章旗。国。兵。神社。米。刀。時計。水。富士山。相撲。鏡。成年。御謚。好学。納諫。威重。大量。敬神。明智。崇倹。尚武。(10月から翌4年3月までの「教育勅語」11回分は別途詳述する)
第2学年 大正4年4月より同五年3月まで
桜花。仁愛。公平。正直。改過。操守。犠牲。正義。高趣。清廉。御即位と大嘗会。明月。賞罰。蒔かぬ種は生えぬ。上杉謙信。百聞不如一見。紅葉。任賢。決断。赤穂浪士。新年。取長補短。梅花。雪。論語読の論語知らず。徳川光圀。
第3学年 大正5年4月より同6年3月まで
春。思而学学而思。遠慮近優。源為朝。転禍為福。大道遠而難遵。上和下睦。化行則善者勧。山水綸言汗の如し。用意平均莫由好悪。夏(以上1学期)。夏禹王。高而不危満而不溢。秋。倉廩実則知礼節。安危在己。菊。中大兄皇子。可明賞罰莫迷愛憎。好問則裕。博而寡要。ワシントン(以上二学期)。松竹。履霜堅氷至。君君臣臣。孔子。上則答乾霊授国之徳。田猟。陛下以簡御衆以寛。桃。動則思礼。蚤(以上3学期)。
第4学年 大正6年4月より同7年3月まで
五条御誓文。科学者。徳日新万邦惟懐。茶。先憂後楽。瀑布。日月無私照。ナポレオン(以上第1学期)。先神事後他事。徳川家光。政在民養。詩歌。コロンブス。惟徳動天。韓退之「雑説」敖不可長欲不可従。絵画。人口論。イソップ物語(以上2学期)。酒。文明。居上克明。ピーター大帝。音楽。大義名分(以上3学期)。(4学年までは週に2度(月木)、5学年からは週1度月曜の進講となった)
第5学年 大正7年4月より同8年3月まで
釈迦。和魂漢才。人万物之霊。陰徳陽報。黄金時代。君子慎其独。咸有一徳。鉄。満招損謙受益(以上第1学期)。修理固成。ソクラテス。至誠而不動者未之有也。他山之石。学而時習之。修其天爵而人爵従之。四海之内皆兄弟也。磁石。管仲。基督(以上第2学期)。関雎。民惟邦本。神農ヒポクラテスの詩。任重而道遠。中朝事実。天作檗可違。貞観政要人種。宝箴。浩然之気(以上第3学期)。
第6学年 大正8年4月より同9年3月まで
十三経に関する説明。大宝令。風声鶴唳。プラトー、アリストール。無恃其不来。有文事者必有武備。貞永式目(以上第1学期)。光華明彩。英国皇太子に関すること。常山之蛇。六論衍義。ストイック学派。秋声賦。スピノザ。鳶飛戻天魚躍于淵。ポンソンビー氏の君主論(以上第2学期)。中臣祓。ルーソー。カント、フィフィテ。抜本塞源。陥之死地然後生。伝教、弘法、親鸞、日蓮。勧善懲悪。発而皆中節(以上第3学期)。
第7学年 大正9年(1920)4月より同10年2月まで
祈年祭祝詞。ミル、ベンサム、スペンサー。柳。易の大要。国学四大人。進化論。老荘。万葉集。シェークスピア、ゲーテ。功成名遂身退。龍(以上第1学期)。ウィルヘルム二世。五風十雨。刑名字。マホメット。地水師。マキャヴェリー。運用之妙在于一心。水戸学(以上第2学期)。(第3学期は進講なし)
猪狩は漢語の題目について出典(尚書、論語、左伝、孟子、老子、孫子、詩経、中庸、日本書紀、古事記、花園院宸記、帝範崇倹篇など)と採用理由のいくつかを記している。
また桜花、紅葉、新年、梅花、雪などは「修身の題目として異彩を放つ」が、これは「堅苦しい徳目の他に、優美とか高潔とかという趣味上のことから次第に転じて、道徳に入る趣向であった」とし、「赤穂浪士」では、杉浦が講じながら四十七士の名をすらすらと板書したことや、「徳川家光」では、家光が三代目であることで、題目に採用する意義があったと記している。
その「異彩を放つ」題目のうち第三学年第一学期の「夏」について深作博士がその要旨を「回想本」に記している。それを読むと、猪狩のいう杉浦の「趣向」が理解できる。
草案は「夏の趣味の重なるものは、杜鵑(ホトトギス)、蛍、蓮、納涼等なるべし。紀貫之の歌に、“夏の夜のふすかと見れば郭公 なく一声にあくるしののめ(古今集)”などといえるは即ち杜鵑を詠じて其の風雅を賞したものなり」と始まる。高貴の御方の倫理を進講する教材として頗る妥当性に富む。
先生は、これに続けて唐の文宗と柳公権との連句に蘇東坡が更に四句を加えて完成したとし、「柳公権の詩には諷諫(遠回しの忠告)の語なきが故に、蘇東坡は之を不足として四句を加えたり。・・今文宗も殿閣の中に居るが為に、気を移されて他の苦楽を長く忘れて百姓(庶民)の上を思うに遑(いとま)なきなり。・・冬に当りて民の寒苦を懐い、夏に際して又其の暑熱を憐れむは、当に天子御仁心の致す所なるべく東坡の加筆ありて、此の詩美と箴(いましめ)とを兼ね備うるものというべし」とした。以て先生の妙手であられたことと、王者の師として大器であられたことと知るべし。
これも「異彩を放つ」題目の「イソップ物語」(第4学年2学期最後の進講)に関し、「モズレー本」は、殿下が立太子礼を終えた1916年11月3日の新聞各紙が、「外国の本では『イソップ物語』を愛読される」とし、「一番おかしかった物語は『男と二人の妻』であると漏らされた」と報じたことが記されている。
(その③:「致誠日誌」を読む(1)につづく)













