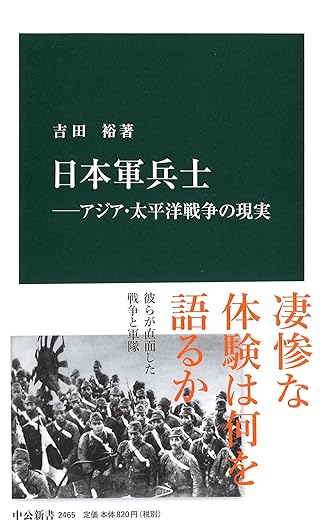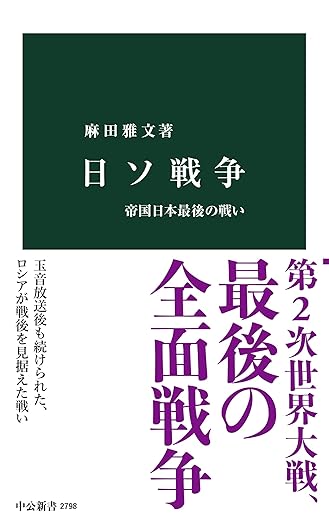pocketlight/iStock
毎年、7月~8月には太平洋戦争関係の書籍、特に新書が多数刊行される。今年は戦後八十年の節目の年なので、例年以上に刊行が活発であるが、残念ながら内容面、質で評価すると、必ずしも豊作とは言い難い。
ここ10年で太平洋戦争ものの最大のヒットは、吉田裕『日本軍兵士 アジア・太平洋戦争の現実』(中公新書、2017年)だろう。
太平洋戦争における日本軍の愚行・蛮行を記した書籍は数知れないが、それらは基本的に軍中央や司令官など上層部の戦略・作戦の拙劣さを批判するものである。それに対し吉田氏の著作は、「兵士の目線」を重視し、「兵士の立ち位置」から、凄惨な戦場の現実を捉え直しており、ミリタリーファン向けの本とは一線を画す。
太平洋戦争において日本軍は制海・制空権を次第に喪失し、補給を維持できなくなった。その結果として、多数の日本軍兵士が食糧不足により戦病死(餓死)したことは良く知られている。そうした兵士たちの苛酷な環境を、戦場での覚醒剤使用から軍靴の劣悪化まで、あらゆる側面から具体的に明らかにしたところに本書の特徴が認められよう。
『日本軍兵士』のような、社会史や民衆史の視点から戦争や軍隊を捉え直す研究は、日本のアカデミズムでは決して珍しくなく、むしろ純粋な軍事史の観点から戦争を論じたものより好まれる。しかし一般読者にとっては馴染みにくいテーマであり、本書のヒットは意外に感じられた。太平洋戦争に対する一般読者の知的関心の高まりを象徴する現象と言えよう。
記憶に新しいヒットとしては、麻田雅文『日ソ戦争 帝国日本最後の戦い』(中公新書、2024年)が挙げられる。太平洋戦争というと、日本は専らアメリカと戦っていたというイメージが強いが、近年はアメリカ以外との戦争に注目が集まっている。
広中一成『後期日中戦争 太平洋戦争下の中国戦線』(角川新書、2021年)もそうした視点からの意欲作であるが、『日ソ戦争』はさらに大きな話題を呼んだ。同書の商業的成功は、もちろん同書の内容的充実を前提としているが、ロシアが突如としてウクライナを侵略し、残虐な殺戮・暴行を繰り返しているという現状において、ソ連(ロシア)の軍事文化への関心が高まったことが背景にあるのだろう。
同書冒頭で麻田氏は、史料を博捜してソ連が対日開戦を決定するまでの過程を詳細に復元する。日ソ交渉もさることながら、米ソの駆け引きが興味深い。アメリカは、原爆完成後はソ連の対日参戦を望まなくなったと一般には思われているが、実際にはジョージ・マーシャル陸軍参謀総長のように、ソ連参戦を以後も望んでいた要人は少なくなかった。トルーマン大統領も原爆だけに賭けることは避け、ソ連への参戦要請と日本への核攻撃の準備を最後まで並行して進めた。
なお、日本がポツダム宣言受諾を決断するに至る終戦過程の研究は、開戦過程の研究と並んで、日本の歴史学界では熱心に行われてきた。しかし先月刊行された波多野澄雄『日本終戦史1944-1945 和平工作から昭和天皇の「聖断」まで』(中公新書、2025年)が典型的であるように、「日本はなぜもっと早く降伏できなかったのか」という問題意識に基づいて、日本側の事情に焦点を当てるスタイルが一般的である。
『日ソ戦争』は米英ソ中の思惑にも注目しており、先月刊行された千々和泰明『誰が日本を降伏させたか』(PHP新書、2025年)もまた、この問題を深堀りしている。
さて『日ソ戦争』の白眉は、満洲・南樺太・千島列島での日ソの激闘を、新史料も活用して復元したことだろう。日本の指導者層はソ連の仲介による講和の実現という希望的観測にすがっていたため、ソ連をいたずらに刺激しないよう、ソ連との国境地帯にいる部隊が対ソ戦の具体的準備をすることを抑えていた。
さらに、大本営がソ連の対日参戦の可能性に目をつぶり、前線部隊を南方戦線や日本本土に引き抜き続けた結果、ソ連との戦力差は開く一方であった。このため、従来はソ連は奇襲的(あるいは騙し討ち的)に対日参戦するや否や、火力や機甲戦力を活かした包囲殲滅作戦によって日本軍に圧勝したと考えられてきたが、日本軍が激しく抵抗、善戦した戦線が少なくなかったことを同書は個別具体的に指摘している。
加えて、ソ連の戦争犯罪を厳しく批判している点も特徴的である。日本の歴史学界における戦争研究は、侵略戦争への反省から日本の加害行為に重点を置いてきた。このため、ソ連の対日戦における民間人虐殺に対する非難は前面に出ず、むしろ関東軍が開拓民を見捨てたことが強調されてきた。
けれども麻田氏は、「開拓民やその家族といった非戦闘員を保護せず、無差別攻撃を行ったのはソ連軍である。このように満洲におけるソ連軍の加害を追及すると、満洲国時代の日本人から現地民への加害を持ち出して相対化を図ろうとする議論が見受けられる。しかし、それはソ連軍の蛮行を不問に付す理由にはならないだろう」と断言する。この明確なソ連批判の姿勢は、ウクライナ戦争におけるロシアの戦争犯罪を暗に非難するものであろう。
このように見ていくと、昨今の太平洋戦争ものは、実証的研究により、従来知られていなかった事実を解明した著作が増える傾向にあり、そうした著作に読者の支持が集まっていると評価できよう。
ところが、こうした「実証主義」の台頭に懸念を示す論者もいる。先月刊行された辻田真佐憲『「あの戦争」は何だったのか』(講談社現代新書、2025年)は、「近年の歴史研究は、左右のイデオロギーを批判し、従来の大きな見取り図(一五年戦争、東亜百年戦争)を解体し、事態を細分化していく傾向にある。
しかし、その結果、専門外の人間にとっては、なにが重要なのか、どの説が正しいのか、全体像が見えにくくなるという事態が生じている」と批判し、大きな見取り図を再構築する必要性を主張している。
辻田氏の問題意識は理解できる。確かに近年の太平洋戦争ものの新書を概観すると、テーマの個別分散化が進み、太平洋戦争全体の見取り図を提示するような本は少ないという印象を受ける。しかしながら、辻田氏の新著じたいが、「大きな見取り図」の提示よりも「実証主義」的な成果の紹介の方に傾いているように感じられる。
具体的に説明しよう。辻田氏の新著の第二章は「日本はどこで間違ったのか」と題するもので、「(アメリカによる対日石油全面禁輸を招いた)南部仏印への進駐を思いとどまれなかったのか」といった著名なifを複数検証した上で、「こうすれば戦争を回避できた」といった意見は多分に後知恵であり、当時の日本の指導者の立場から見ると、非現実的な選択肢であったと説く。「当時のひとびとを愚かだったと断じることは慎まなければならない」というのである。
だが、歴史の個々の局面における当事者たちの決断を、歴史の結果を知る後世の人間が後付けの理屈で「愚かだった」「狂気だった」と断罪するのではなく、当事者が決断するに至った「内在的な論理」を理解しようとする辻田氏のスタンスは、むしろ「実証主義」的な手法である。
一例を挙げておく。先月刊行された高杉洋平『帝国軍人 デモクラシーとの相克』(中公新書、2025年)は、昭和陸軍がなぜ戦争へと突き進んでしまったのかを、「狂信的」「暴走」といったレッテル貼りではなく、彼らの内在的論理から解き明かそうとする「実証主義」的な著作である。
前掲の南部仏印進駐問題について高杉氏は、アメリカが建国草創期から、モンロー政策(アメリカ大陸とヨーロッパ大陸間の相互不干渉)の伝統を有しており、現に満州事変の際にも日本を非難しつつ経済制裁は行わなかったことを指摘する。
そして「この点から考えれば、東南アジア問題、まして本国政府が既に降伏している仏領インドシナへの「平和」進駐に対して、米国がリスクを冒すことはないとの陸軍の判断自体は(間違いではあったが)、それほど不条理なものではない」と、南部仏印進駐がアメリカの激しい反発を招くことを予想できなかった陸軍に対して、一定の「理解」を示している。
辻田氏は言う。「歴史を振り返る意義は、過去を美化することでも、糾弾することでもない。重要なのは、なぜ当時の日本がそのような選択をしたのかを深く理解し、わがこととして捉え直し、現在につなげることにある」と。
この目的を達成するには、イデオロギーに基づく「大きな物語」を提示するのではなく、「実証主義」的なアプローチこそが求められる。
歴史学者の「実証主義」的な著作をマニアック、重箱の隅をつつく、細部に拘泥していて全体像が見えないと、評論家が批判するのはたやすい。だが「実証主義」は、歴史学が歴史を深く理解するための手法として磨き続けてきたものであることも、また事実である。そのことへの尊重なくして、新たな歴史像が生み出されることはあり得ない。