幕末最強の剣客集団を統率し、やがて自らの主人が敵に恭順の姿勢を示しても、武士道の節義を全うするために戦い抜いた新選組副長・土方歳三の生涯を描く。
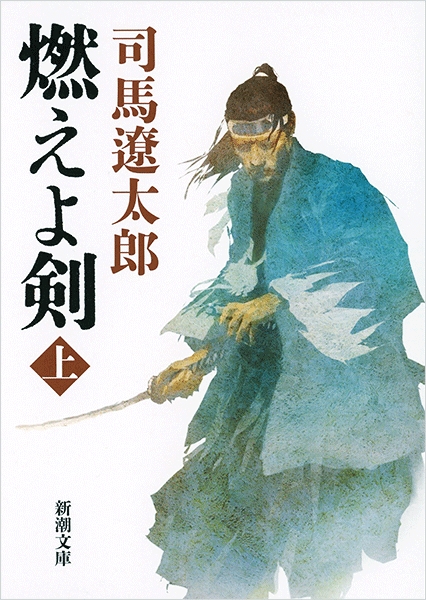
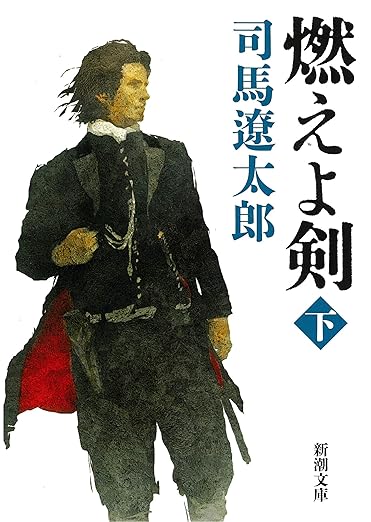
司馬文学の代表的作品である本書で筆者が訴えたかったことは何であろう。評者は、土方が、歴史という大勢に反してでも、さらに仕える幕府や会津藩という正義の後ろ盾を失いつつも、武士らしさという美徳を信じ、その一念に生き抜くという美学を通じて貫いた人物であるとして、日本史に残すべき人物として仕立て当てていることに本作品の意義があると感じる。
土方歳三は、武州石田村の生まれで生家は薬屋であり、家系からして武士ではない。その境遇が、土方をして、誰よりも武士らしく生きることを課すに至る。
彼の信じる徳目が他律的ではなく自律的であるがゆえに、新選組は、ついには徳川慶喜や松平容保が新政府軍に恭順の意を示すに至っても、勝機を東北に見出し、大鳥圭介や榎本武明を新たな盟友に、文字通り斃れるまで戦い続けた。この一事からも、新選組が単なる幕府の防衛組織ではなく、一個の思想的集団であることがうかがえる。
作品に描かれる土方は、京政界への周旋や情報収集に躍起になる局長・近藤とは異なり、あくまで戦に勝つことのみを目的として新選組の運営と作戦指導に専念した。生え抜きの喧嘩師にとり、正義の所在は時代により遷り変るはかないものである、それよりも、男は歴史を超越した徳目に殉じるべきとの思想が彼の倫理の底流に流れている。
筆者は、土方の思想を時代普遍的な徳目として「節義」と表現し、権勢が時代の流れで遷り変わる「歴史」と対峙して描いている。前者の体現者が土方であり、後者のそれがが、薩長、江戸幕府、そして近藤勇もそこに区分けされるだろう。特に、「政治家」として描いた近藤とのコントラストにより、新選組の中の土方の個性が際立つようになる。
その近藤は、政治家ゆえに権勢に敏感であり、東北戦争をまえにいさぎよく出頭、捕縛される。もちろん、喧嘩師の土方にはこんな敗北主義はないとして近藤を止めるも、近藤には、近藤なりの政治家としての美学がはたらいたのだろう。
『近藤は政治家になりすぎた、と歳三はおもっている。(諸般の情勢などはどうでもよい。情勢非なりといいえども、節義をたてとおすのが男であるべきだ。)』
(下巻・93頁)
土方にとり、東北戦争とは死地を明らかにする戦争だった。だが、そう思っているのは幕府軍首脳の中でも土方しかいない。函館に拠点を構え直した榎本や大鳥は、やがて函館の地に徳川家の末裔を元首と戴く共和制国家を樹立しようと構想した。彼らにとって函館とは将来の土地であり、再起の土地であった。
しかし、近藤や沖田という血の同志を失った土方にとり、現世に生きる意義は見いだせなかった。正義のための喧嘩を本分とする土方にとって、国家づくりという政治は土方歳三という生涯には縁のないビジネスである。政治に携わること自体が、自らの存在意義を否定する営為であることを、土方は京で周旋する近藤を横目に肌で感じ取っていたに違いない。あるいは、土方自身の自己のありように対する鋭敏な感覚がそう感じさせたであろう。
いずれにせよ、新選組の盟友亡きあと、函館という新地は、土方にとって死地であり、いかに美しく死ぬか、その一事だけが残された人生の主題である。
『歳三は、もはや生きているという実感を、お雪の体の中にもとめる以外に手がなくなっていた。いや、もう一つある。戦うということである。それ以外に、歳三の現世はすべて消滅してしまった。』(下巻・504頁)
(下巻・504頁)
土方の個性を描く伏線として彼の情事がある。いくばくかの女性と交わりをもちつつ、女性への恋慕を他人に感じ取られることが彼の恥部を構成した。「鬼の副長」」という立場があればなおさらである。
が、土方は土方であり続けるために女との情事は必要な要素であったことが分かる。いきさつを経て、彼はお雪に身を任せることになるが、お雪との会話で、土方は自分の生まれや境遇、副長としての辛苦から感じ入ることを、言葉や体で奥底なくお雪にぶつけている。お雪が、自分の物語を映し出す鏡、あるいは慰めの湖であるかのように、土方は、お雪を通じて生きるに値する自己として発見し、新選組副長・土方歳三として再び世に送り出されるのである。
作品をつうじて土方は厳格な喧嘩師として描かれるが、彼には、自らの自負心と立場を慰める憩いの相手が必要であった。筆者は土方のそのような側面を、周りに恥部を見せない「猫」として描いているが、矛盾性をかかえる性格で土方を描いているさまに、彼をよりドラマチックで魅力的な人物へと仕立てている。
読者が、土方を憐れみ深い、生粋の喧嘩師として魅惑される所以は、函館の一幕に凝縮されている。新政府軍が幕府軍艦隊を撃滅し、いよいよ函館へ上陸しようとするとき、土方は、連れ添った新選組の同志を、新時代を生き延びる使途として、故郷に戻るよう命令する。斎藤一、松本捨助、そして市村鉄之助。死と隣り合わせの京政界で決死の思いで治安業務に従事し、京を追われたのちも幕府再起を目して東北諸藩と戦うなど、死地を何度もくぐってきた仲間である。それこそ新選組の再起をも、彼らは願っていたかもしれない。
死を共にすることを信じていたであろう上司から放たれた最後の命令が、「戦地を離れ、故郷に帰れ」ということに、彼らは狼狽と悔しさを超える感情を持ち得なかったであろう。土方からすれば、彼らが存命すれば、新選組がなそうとした「正義」が新時代に理解される日が来ると期待したのかもしれない。あるいはそれ以上に、彼本来の憐れみの心を隠さずにいられなかったのかもしれない。
土方は、函館から上陸する新政府軍の猛攻にも臆することなくついには単騎となり突撃し、函館市街にはいり参謀府へ参上するところを長州部隊に囲まれ、いよいよ最期のときを迎える。彼は、自らを函館政府の陸軍奉行ではなく「新選組副長土方歳三」と称し、新政府軍の銃弾に斃れた。土方が長州部隊のまえに現れるさまは、「官軍は白昼に竜が蛇行するのをみたほどに仰天した」と描かれている。
歴史に抗い、節義を貫くことが男の美学であることを生涯を通じて証明した男が『燃えよ剣』の土方歳三である。彼と新選組の登場により、幕末史は権力移行の政治史ではなく、思想史や文学としての厚みをもつことになる。他人に情事を見られたくない土方だけに、冥途でほくそ笑んでいることだろう。
編集部より:この記事はYukiguni氏のブログ「On Statecraft」2025年9月24日のエントリーより転載させていただきました。














