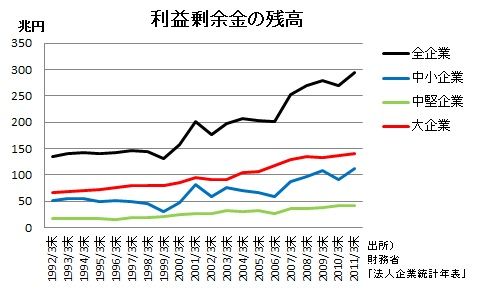Great Divergenceという言葉を最初に使ったのは、本書である。西洋が産業革命や資本主義などの「正しいコース」をたどったのに対して、中国がなぜ停滞したのかという従来の問いに対して、18世紀まで世界の最先進国だった中国をイギリスが抜く大分岐がなぜ起こったのか、という本書の問いは大きな論争を呼んだが、今日では「グローバル・ヒストリー」の一つのマイルストーンとみなされている。
Great Divergenceという言葉を最初に使ったのは、本書である。西洋が産業革命や資本主義などの「正しいコース」をたどったのに対して、中国がなぜ停滞したのかという従来の問いに対して、18世紀まで世界の最先進国だった中国をイギリスが抜く大分岐がなぜ起こったのか、という本書の問いは大きな論争を呼んだが、今日では「グローバル・ヒストリー」の一つのマイルストーンとみなされている。
本書が示したように、大分岐を生んだのが「資本主義」だという通説は疑わしい。18世紀のイギリスでは、資本は稀少ではなかったからだ。「産業革命」だというのも、当時の中国の高い技術水準を考えると疑問だ。西洋が中国を追い抜いた最大の要因は、土地と燃料だというのが、本書の仮説である。新大陸の発見や植民地の拡大で、西洋の経済成長を制約していた土地が「輸入」できるようになり、木材の代わりに石炭を利用したことで産業が発展したという。
 他方、FTによると、19世紀の初頭には日本と中国の一人当たりGDPはほぼ同じであり、今おこっている大収斂は、200年前の状態に復帰する動きと考えることができる。図のように、現在の中国の成長率は1950年代の日本とほぼ同じであり、かつて日本が15年間にわたって10%成長を続けた世界記録を抜いて、20年間も10%成長を続けている。このまま成長すると、2030年の中国のGDPはアメリカとEUの合計より大きくなり、1人あたりでも日本と並ぶ。
他方、FTによると、19世紀の初頭には日本と中国の一人当たりGDPはほぼ同じであり、今おこっている大収斂は、200年前の状態に復帰する動きと考えることができる。図のように、現在の中国の成長率は1950年代の日本とほぼ同じであり、かつて日本が15年間にわたって10%成長を続けた世界記録を抜いて、20年間も10%成長を続けている。このまま成長すると、2030年の中国のGDPはアメリカとEUの合計より大きくなり、1人あたりでも日本と並ぶ。
これは市場経済でグローバルに一物一価が成立するという当たり前の経済法則なので、その均衡に到達するまで止めることはできない。特に賃金の均等化は、あと20年は続くだろう。これは世界的には大収斂だが、日本国内では大分岐をもたらす。中国で生産できる製造業の価格も賃金も中国に近づき、雇用も流出するだろう。それと代替的な単純労働の賃金も、QBハウスのように中国に近づくことは避けられない。一部の人々が「デフレ」と騒いでいる現象は、こうした200年ぶりの歴史の逆転の一コマにすぎないのである。