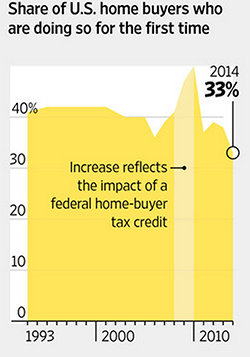1 交通強者と交通弱者
自分の足で歩くことができて、目が見えるとき、眼前の信号が青であるなら、横断歩道を渡るときに何の恐怖も感じない。日本では交通法規を守る運転者が大半であり、車が必ず赤信号で止まるからである。さらに、日本は歩行者優先が徹底しており、横断歩道上に歩行者がいる限り、自動車はたとえ進行方向の信号が青に変わっても発信することはない。つまり、私たちは目前の青信号を信じて、横断歩道を渡ればよく、横断歩道を進み始めたら怖いものはない。
しかし、移動に車いすが必要になったり、視覚障がい者になったりすると一転して横断歩道を渡ることが、命を懸けた一大事になる。だから、彼らは交通弱者と呼ばれる。過日、とある会合で交通弱者からの訴えを聞いた。障がい者の社会進出やノーマライゼーションが論ぜられて久しいが、その実現は容易でないことを改めて知らされた。
2 交通弱者の訴え
信号機のなかには歩行者自らが押して色を変える押しボタン式信号機がある。健常者にとってはボタンの向きも高さもほとんど気にならない。
A氏は事故で歩行機能を喪失し、車いすを常時利用する。また、左腕がマヒ状態であり、右腕は肩の高さまでしか上がらない。彼の移動圏内にある押しボタン式信号の押しボタンのなかに車道に面して設置されたものがある。あるいは、ボタンの位置が地面から130センチメートルのものもある。どちらの場合も肩までしか上がらない右腕を使って押しボタンを押すことはできず、仮に、棒などを使うとすると、ボタンを押すために車道に出なければならない。つまり、自力ではほとんど押すことをできず、実際には他の人が押すのを待つか、通りかかりの人に頼まなければならない。
しかし、困ったことにA氏が暮らす町の人口は1万人程度、彼が利用する横断歩道を人が通ることが少ない。
視覚障がい者に信号の色が変わったことを音で知らせる信号機がある。音響式信号機と呼ばれる。これを交差点などで聞いたことのある人も多いだろう。
隣り町に住むB氏は視覚障がい者であり、盲導犬を連れて移動する。彼は毎日、職場からの送迎バスを降りて、信号を1つ渡って自宅に戻るが、この信号は音響式信号ではない。どうやって、信号の色が変わるのを察知するのかと聞くと、聴力が発達しているので、耳を澄ませて車が来ないと判断して、恐る恐る道路を渡っているのだと言う。もちろん、盲導犬も動作で信号の色が変わったことを知らせるが、横断歩道を渡る決め手は自分の耳だそうである。
しかし、最近、音の静かな車が増えてきたため、道路を渡るのが恐くて、相談に及んだのである。
3 関係機関の取り組み
A氏もB氏も、ともに町役場、障がい者のための相談機関、警察などに相談をしている。しかし、どこも彼らの満足いく結果をだせないでいる。
その理由は、まず、第一に信号機を直す、取りかえることは民間人が勝手にできず、警察当局の判断が必要であること、第二に信号機を直す、取り換える場合には予算措置が必要であり、都道府県の本庁レベルでの意思決定が必要であるところ、財政厳しい昨今、人口が少ない地域の信号取り替えは、その優先順位が低いからである。
確かに、個人や会社が自分の都合の良いように押しボタンの向きを変えたり、信号機に勝手にスピーカーを設置して音楽を流されたら、むしろ危険である。さらに、予算の効率的な活用、費用対効果の高い国庫支出もまた、筋が通っている。交通弱者が不便を被る、換言すれば、危険にさらされてもやむなしとする理屈が通る。
4 創意工夫のバリアフリー
AB両氏は現在、道路を渡るに際し、「バリア」を感じており、その意味で彼らにとって、町での暮らしはバリアフルである。そして、人口の少ない地方郡部は、おそらく、同じような状況であると推察される。
形ある物でのバリアフリーの実現には必ず財源の裏付けが必要である。人口が少ない、対象障がい者が少ない地域は、1人の強烈なニーズがあっても財源配分で劣位におかれる。これに対抗するには、財源不要のバリアフリーを知恵と思いやりをもって作るしかない。
A氏の場合、人通りの多い時間を狙って外出をするように心がけると言う。自分の代わりに押しボタンを押す人を確保するためである。B氏は送迎バスの運転手に道路を渡らなくて良い所に車を止めてもらうように頼んだ。また、朝の散歩も、楽しみが半減したが横断歩道を利用しないルートを考えた。こうしてみると、バリアフリー環境を予算がなくても、個人レベルで作ることは可能である。
これから高齢者が増え、障がい者の社会参加が活発になるにつれて、小さな田舎まであったとしても、公的な空間がバリアフリーであることが求められる。その時に、予算がないからできないではなく、予算がなくてもしなければならないという発想に立って考えることが必要であろう。個人レベルでの対処法を公的空間へも応用することである。そうすれば、創意工夫と人の優しさで、箱物装置がなくてもバリアフリー社会がある程度、形成されうる。その結果、障がい者や高齢者の暮らしの質は多少なりとも上がり、彼らにとって暮らしやすい生活環境が生み出されると期待したい。
片桐 由喜
小樽商科大学商学部 教授
編集部より:この記事は「先見創意の会」2013年11月11日のブログより転載させていただきました。快く転載を許可してくださった先見創意の会様に感謝いたします。オリジナル原稿を読みたい方は先見創意の会コラムをご覧ください。