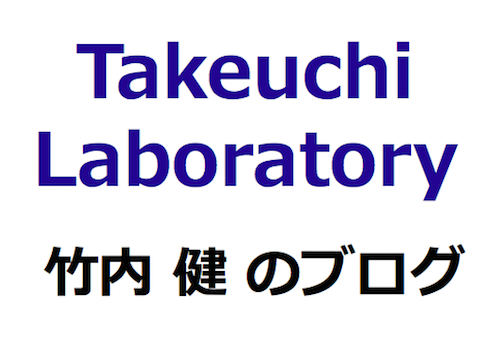企業の人材処遇においては、どうしても、貢献への期待に対する処遇という要素をなくすことができない。そうすると、期待外れというか、企業の立場からみたとき、期待貢献ほどには、実際貢献を実現できていない人材というものができてしまう。そのような場合を、比喩的に、人材の不良債権化という。
報酬は事前に決めるしかなく、成果は事後にしか判明しない。その限り、報酬とは、成果への期待、実際貢献への期待に基づいてしか決め得ないのである。あるいは、過去の実績に基づいて決めるにしても、それは、過去の実績の再現を期待してのことだから、やはり、期待への報酬であることに変わりはない。
故に、事後的には、どうしても、期待と実績との差ができてしまう。どのくらいの時間軸で調整するかという難問はあるにしても、この差は調整されなくてはならない。実績が期待を上回ろうが、下回ろうが、どちらにしても、調整されなくてはいけない。そうでなければ、人事制度の公正公平性が保てず、最終的には、組織統制の崩壊を招くことにもなりかねない。ここに、人事制度の要諦がある。
実績が期待を上回っているときは、それほど難しくはない、賞与等で対応すればいいのだから。問題は、実績が期待を下回っているとき、即ち、不良債権化だ。
不良債権化を回避する簡単な対応策というのは、事前の固定給与を小さくしておいて、事後的に、成果に応じた歩合給や賞与を支払うものである。実際に、保険の営業職員等の処遇制度にみられるもので、保険に限らず、多くの歩合的な営業職に、広く普及しているものだと思われる。
このような制度では、先払い的な期待への報酬が最低限に切り詰められていて、一期間(多くは1年だろう)のなかの事後的な実績に基づいて、その間の成果に見合った後払い的報酬で調整するわけだから、いわば一期清算型の完全な今払い的な報酬を実現しているのである。故に、期待外れ、即ち、不良債権化は起きない。
しかしながら、このような制度は、完全な個人責任のもとの行動と業績に基づき、かつ、成果の評価も販売額等によって客観的に定量化できるからこそ、なりたつもので、組織内での協働や、その協働を通じた人材の成長、また、組織内貢献の評価の仕組み等を考慮するとき、一般的な適用には、限界がある。
やはり、完全に期待的要素を取り除くことは難しいのである。つまり、人材の不良債権化は、一定の範囲において、避け得ないのである。
森本紀行
HCアセットマネジメント株式会社 代表取締役社長
HC公式ウェブサイト:fromHC
twitter:nmorimoto_HC
facebook:森本紀行