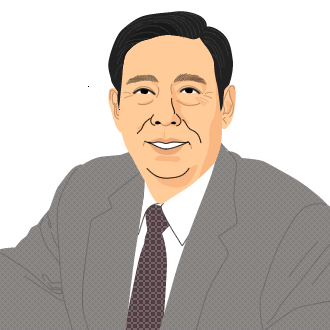今年のシカゴは春の到来が遅く、今朝も最低気温が氷点下で薄らと雪化粧していた。10日くらいまで、最低気温氷点下が続きそうで、来週の月曜日・火曜日も雪の予想が出ている。今住んでいるアパートは築50年くらいで、窓枠の取替え工事が順次進んでいる。そのため、カーテンを取りはずすようにと言われ、28日に取り外した。当初の工事予定は3月30日だったが、どんどんずれ込んで現時点で4月9日となっている。
カーテンがないと、夜中に屋外が冷え込むと、室内の温度も一気に下がる。今朝は、夜明け前に寒さで目が覚め、ホッカロンを張り、靴下を履いて、再び布団に潜り込んだ。米国では予定などあってないようなもので、約束時間が1時間以上ずれ込むことなど日常茶飯事で起こる。しかし、東京の真冬よりも寒い気温なので、予定通り工事をして欲しいものだ。大学のオフィスも寒いので暖房を入れたが、過電流となったためか、暖房機と同時に突然、パソコンの電源が落ちた。論文の校正に費やした2時間以上が、露と消えた。気を取り直して再チャレンジと思ったが、2時間分のロスに唖然呆然で気合が入らず、このブログを書くことにした。
まじめな話に移ろう。今月号のNature Reviews Cancer誌に、オピニオンとして「微少残存病変を叩くのが、がんの治癒への道?」というタイトルの論文が出ていた。白血病などでは、一定の抗がん剤治療後に、微少残存病変が検出されると、追加の抗がん剤治療が行われる。微少残存病変というと難しいように聞こえるが、簡単に言うと治療をした後に、画像検査や顕微鏡検査でがん細胞(がん組織)が無くなっているように見えても、感度の高い検査法(RNAやDNA)で調べると、がんが潜んでいると考えられる状態だ。
白血病の分野では日常臨床に応用され、高感度の検査では陽性だが、目に見えない(画像で見えない)ような段階で抗がん剤治療をすることで、治癒率が向上した。今、固形がんに対して、リキッドバイオプシーなどを利用して、目に見えないがん細胞を捉える可能性が高まってきた。がん治療はモグラたたきのように、一つの治療法で治療し、それが利かなくなると次の治療法へ移っていく。治癒を目指さなければこれでもいいだろうが、治癒を目指すにはパラダイムシフトが必要だ。常識的に考えれば、がん細胞が少ない方が完璧に叩きのめす可能性が高い。数十人規模の暴動は抑え込むのが簡単だが、これが1万人規模、10万人規模になると、収拾を図るのが難しくなる。もっとひどくなると内乱状態となる。進行がんと言うのは、内乱となってがん細胞の活動を抑えるのが難しくなった状況である。
当然ながら、リキッドバイオプシー陽性でも、本当に活発ながん細胞が潜み、それを放置すると内乱状況まで達するかどうかは、神のみぞ知るだ。ただし、ジョンスホプキンス大学の大腸がんのデータでは、大腸がん手術後にリキッドバイオプシーで陽性だった症例は2年以内にほぼ全例再発していた。これが再現されるなら、やはり、リキッドバイオプシー陽性・画像検査陰性である時点で、手を打つことが必要になると思う。しかし、このような時点で副作用の激しい抗がん剤治療を行うことは患者さんに取って負担が大きい。リスクとベネフィットの慎重な評価が必要だ。ネオアンチゲンなら、副作用リスクは非常に低いと思うが、効果的であるというエビデンスはない(調べていないからわからないという意味であり、効かないというエビデンスではない)。
新しい技術が生まれた時に、新しいコンセプトの治療体系を考えるべきだと思うのだが、標準療法が金科玉条のごとく幅を利かせている。抗がん剤で免疫系を痛めつけてから、免疫療法を利用するのは、論理的に考えてもおかしいと言い続けているが、標準療法絶対主義が大きな壁となり、科学的な議論が難しい。この壁を崩すことができるのは患者さんの力だと思う。それに期待して、私も、もうひと踏ん張りしたい。
編集部より:この記事は、シカゴ大学医学部内科教授・外科教授、中村祐輔氏のブログ「中村祐輔のシカゴ便り」2018年4月4日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は、こちらをご覧ください。