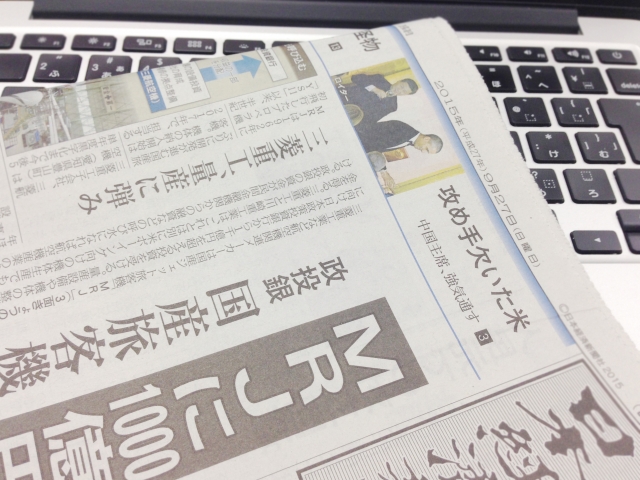若いがん研究者と話をする機会があったが、驚くほど基本的な事項が理解できていなかった。胚細胞変異と体細胞変異の区別ができない。「遺伝性がんの原因遺伝子は遺伝性のがんに特別なものではなく、それらの遺伝子が体細胞で変異をするとがんにつながる」などと言っても、不思議そうな顔をするだけで、アルファベットを知らない人に英語で話しかけているような錯覚を覚えた。
たとえば、両親から受け継いだAPC遺伝子のいずれかに機能を失う異常があれば、家族性大腸腺腫症(大腸に数千個ものポリープがほぼ100%の確率で発症する病気)になる。これは胚細胞変異、すなわち、精子あるいは卵子を通して遺伝子異常を受け継いでいる状態である。ただし、がん抑制遺伝子の2ヒット説として知られているように、両親のいずれかから受け継いだ正常側の遺伝子も機能を失わなければ(両方の遺伝子が機能を失う2ヒットが起こらないと)、大腸に腺腫(ポリープ)はできない。と、ここでも、2ヒット説に????との反応だ。
このAPC遺伝子の2ヒット異常が後天的に(生まれてから)起こると、家族性大腸腺腫症患者でない一般の方でも、ポリープが生ずる。p53遺伝子、RB遺伝子など、がん抑制遺伝子は2ヒット変異が一般的である。p53遺伝子に遺伝的な異常(胚細胞変異)があると、Li-Fraumeni症候群が発症する。p53遺伝子は人のがんの半数前後で異常が見つかるような代表的がん抑制遺伝子であるので、Li-Fraumeni症候群の場合には色々な臓器でがんが発生する。
がん抑制遺伝子は細胞の増殖を抑制していていると理解されているが、これに対してKRAS遺伝子に代表されるようながん遺伝子は遺伝子変異が起こると、それによって生じた異常タンパク質が持続的な細胞増殖刺激を引き起こす。がん遺伝子は1ヒットでがん化につながる。
と、かつては単純に説明していたが、最近は異常p53タンパク質ががん遺伝子のような働きをしていることもあると説明を加えなければならない。若い研究者は知らないだろうが、1980年代後半までは、p53遺伝子はがん遺伝子と分類されていた。これは、変異型p53遺伝子を細胞に入れると細胞増殖が活発になるからだ。
p53タンパク質は4量体として機能する。すなわち4つのp53タンパクがひと固まりとなって、働いているという意味だ。正常なp53タンパクと異常なp53タンパクが1対1の割合で存在すると、正常な4量体は2X2X2X2分の1の割合、すなわち、16個に1個しか存在しなくなる。この状態で、細胞の増殖抑制機能が十分に働かなくなり、一見、がん遺伝子のように考えられたのである。これをドミナントネガティブ効果と呼んでいるが、それに対しても????の反応となる。
自分が研究している分子を究めるのはいいが、あまりにも基本常識に欠けていると、これでいいのか日本のがん研究はと思いたくなる。平成の初めは、まさに、がん抑制遺伝子研究の時代であった。平成元年(1989年)にp53遺伝子が人のがんで2ヒット変異を起こしていることをジョンスホプキンス大学のVogelstein博士と一緒に報告した。APC遺伝子を報告したのは平成3年(1991年)だった。
もうすぐ年号が令和となり、新しい時代が始まるが、がんを治癒させるためのがん研究者ならば、がんの基本的な知識は持っていて欲しいものだ。
編集部より:この記事は、医学者、中村祐輔氏のブログ「中村祐輔のこれでいいのか日本の医療」2019年4月11日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は、こちらをご覧ください。