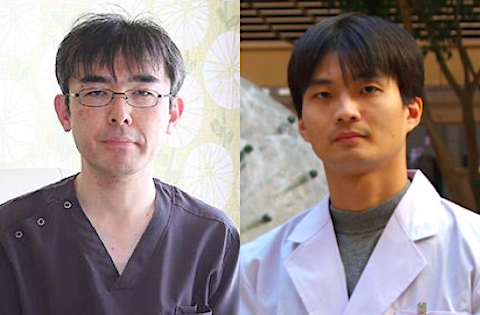「ふるさとは遠くにありて思うもの、そして悲しくうたふもの」という室生犀星の詩を思い出す。また、サブちゃん(北島三郎)の「帰ろかな」という歌が口をついて出てくる。当方のことではない。世界13億人の信者を抱えるローマ・カトリック教会の最高指導者、フランシスコ教皇の話だ。

▲アルゼンチン国民にビデオ・メッセージを送るフランシスコ教皇(バチカンニュース独語版2020年7月25日から)
教皇は第266代教皇に就任してはや7年が過ぎたが、その間、出身国アルゼンチンを訪問していない。共産圏初のローマ教皇に選出されたポーランド出身のヨハネ・パウロ2世(在位1978~2005年)は27年間の在位期間に何度も故郷を訪問し、ドイツ人教皇のべネディクト16世(在位2005~13年)は教皇就任後も出身地のバイエルン州とは密接なコンタクトを維持し、ドイツ国民から「われらが教皇」と呼ばれて大歓迎を受けた。
フランシスコ教皇は教皇就任後、南米のブラジルを訪問し、15年にはエクアドル、ボリビア、キューバを訪問。翌16年にはメキシコ、17年にはコロンビアをそれぞれ訪問し、18年はチリとペルーを訪ねたが、アルゼンチンは通り過ぎている。カトリック教信者が人口の1%にも満たないタイや日本を訪問し、中東のイスラム教国エジプトやアラブ首長連邦には足を向けるが、なぜか母国を訪ねていないのだ(「故郷に錦を飾れない『教皇』の悩み」2019年11月26日参考)。
故郷に足を踏み入れるのがタブーのように感じているのだろうか、それとも誰にも言えない理由があるのだろうか。そんな憶測が流れてきた。しかし、イタリア系の移民の血が流れているフランシスコ教皇が故郷を嫌っているわけではないのだ。
アルゼンチンのブエノスアイレス大司教だったホルヘ・マリオ・ベルゴリオ枢機卿は教皇に就任した直後、バチカンから自分でブエノスアイレスに電話し、知り合いのキオスクのおばさんに「教皇になったから、定期予約してきた雑誌は読めなくなる」と連絡した。故郷と強い繋がりのある枢機卿時代を過ごしたのだろう。知り合いや友人が少なくないはずだ。
フランシスコ教皇はやはり「帰りたい」のだ。そんな記事がバチカン・ニュースで26日、報じられていた。それによると、アルゼンチン南部コモドーロ・リバダビア教区で開催されたセミナーにフランシスコ教皇は約30分のビデオ・メッセージを送っている。その中で「利己主義を乗り越え、隣人を愛しなさい」というイエスの福音を引用しながら、「他者を救いなさい。お前たちは一人ではない」と語っているのだ。
何か自分に言い聞かせているような響きもあるが、心を打つメッセージだ。バチカン・ニュースが発信した写真を見てほしい。フランシスコ教皇はアルゼンチンに戻りたいのが分かる。同セミナーには同教区から約600人の聖職者たちが集まり、フランシスコ教皇のメッセージに耳を傾けた。
フランシスコ教皇は今年11月で84歳となる。故郷に戻るのにも、体力のあるうちしかできない。実兄ゲオルグ・ラッツィンガー神父の最後を見届けるためにドイツへ旅をしたべネディクト16世の姿を見てきたはずだ。近代教皇の中でも最高の神学者といわれるべネディクト16世は先月、最後の力を振り絞って兄のいるドイツまで旅した。フランシスコ教皇もあまり時間がないはずだ。「アルゼンチンへの伝言」にはフランシスコ教皇の望郷の思いが込められている。
ちなみに、故郷に戻れないフランシスコ教皇の事情については過去、メディアでも多くの憶測記事が報じられた。フランシスコ教皇がローマ教皇に選出された直後、新教皇の「過去問題」が一時、メディアに流れたことがあった。具体的には、アルゼンチン軍事政権との癒着問題だ。アルゼンチンの独裁政権下では3万人余りの国民が行方不明となった。彼らの多くは虐待され、殺害されたと推測されている。軍事政権により拉致、拷問された2人の神父に関して、当時イエズス会のアルゼンチン代表であったベルゴリオ枢機卿は迫害を恐れ、支援をしなかったというのだ。
それに対し、人権活動家で1980年のノーベル平和賞受賞者のアンドルフォ・ぺレス・エスキべル氏は、「アルゼンチンのカトリック教会では独裁政権を支援した司教たちもいたが、ベルゴリオ枢機卿はそうではなかった」と証言している。フランシスコ教皇は2015年、アルゼンチン独裁政権時代のバチカン関連文書の早期公開の意思を表明している(「フランシスコ法王の『過去問題』」2015年5月10日参考)。
ローマ教皇にとって自分の家は教会であり、故郷は神の懐だろうが、命を受けた出身地はやはり忘れることができないはずだ。ソーシャル・コンタクトを大切にするフランシスコ教皇にとってはなお更だろう。友人や知人もすでに高齢だから、再会の時間も限られてきた。また、新型コロナウイルスの感染で苦しむアルゼンチンの国民のことも心配だろう。教皇よ、「帰ろかな、帰るのよそうかな」と思案している場合ではない。
編集部より:この記事は長谷川良氏のブログ「ウィーン発『コンフィデンシャル』」2020年7月27日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方はウィーン発『コンフィデンシャル』をご覧ください。