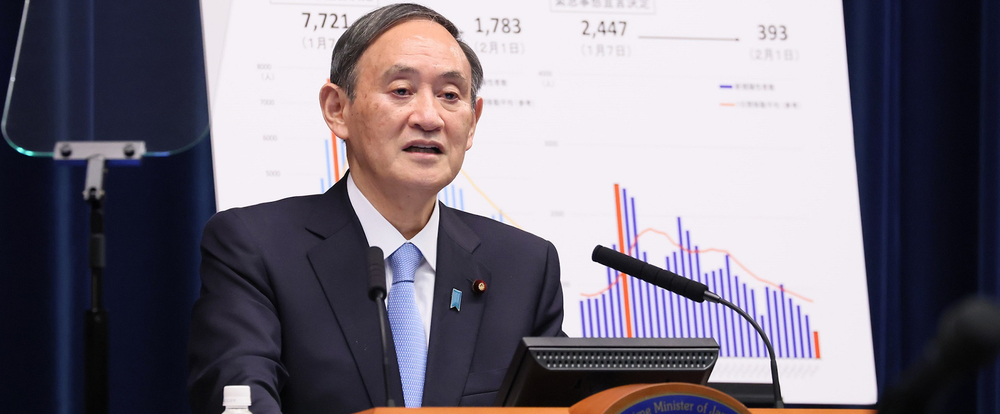オーストリアのクルツ政府は1日、新型コロナウイルスへのコロナ規制措置の期限が切れる今月8日以降、規制の一部を緩和することを決定した。具体的には、ショッピングセンターや美容院などの再開、そして学校の再開だ。外出制限は午後8時から翌日6時までと変わらない。FFP2の着用義務、2mのディスタンスなどのコロナ規制は継続される。

▲学校の再開に心を砕くオーストリアのファスマン文部科学相(オーストリア文部科学省公式サイトから)
このコラム欄で前日報じたが、1日夜(現地時間)に最終的に決定した内容を少し追加説明する。ショッピングセンターなどの営業の場合、FFP2マスクの義務化のほか、顧客の入店制限として従来の10平方メートルに1人のゲストから、20平方メートルに1人に制限することで、店内の混乱を回避する。
美容院の場合、客は48時間前にコロナ検査し、その陰性の証明が必要となる。学校は下級、上級クラスとも再開、生徒たちは簡単な迅速抗原検査(Antigen Schnelltest)を受け、授業は週2日間、「月曜日と火曜日」組と「水曜日と木曜日」組に2分されて行われ、教室の生徒数を制限する。これらの厳格な条件が現場で実行できるか否かは不明だが、最終的には関係者の責任となる。
営業の再開と学校の再開が決定されたというニュースを聞いて、自身もウイルスの専門家で元保健相だった野党「社会民主党」のパメラ・レンディ=ワーグナー党首は「大きな懸念がある」と見解を発表。同党首は学校の再開はやむを得ないが、同時に営業を再開することは感染危険を高めると考えている。
学校の行き帰りに、子供たちは地下鉄やバスなどを利用するうえ、おやつを買うために店に入る機会も増える。感染機会が増えるというわけだ。同党首にとって、学校を再開する場合は店を閉めるか、店の営業をするなら、学校は閉鎖すべきだという立場だ(「『学校ロックダウン』は避けられるか」2020年11月11日参考)。
新型コロナウイルスが感染した初期、感染危険は高齢者、糖尿病、高血圧などの持病がある人と受け取られ、若者たち、学校の子供たちは感染の危険が少ないといわれてきた。しかし、ウイルス学者たちはここにきて、「学校の生徒たちは感染危険だけではなく、感染拡散の恐れもある」と考えだしてきた。特に、ドイツのスター・ウイルス学者ドロステン教授(シャリテ・ベルリン医科大学ウイルス研究所所長)は、「子供は大人と同様、感染を拡大する危険性を有している」と警告しているほどだ。
クルツ政府が学校再開を決定した要因はまとめると3点考えられる。
①オーストリアには学校に通う子供たちが約100万人いる。上級クラスの生徒たちは昨年10月から自宅でのディスタンスラーニングとなり、学校の授業を受けることが出来ない状況が続いてきた。その結果、学習の遅れは大きい。ファスマン文部科学相は、「早急に対面教育を再開しないと文字通り失われた世代となってしまう」と懸念してきた。
②両親が働いている場合、学校を閉鎖する時、誰が子供たちをケアするかという問題が出てくる。新たな要因として、
③コロナ禍で生徒たちに精神的病にかかる者が増えてきたことだ。学校に行かず、友達とも会わずに家で学習していく日々の中、欝状態になったり、さまざまな精神的疾患になるケースが増えてきたのだ。
それも精神的病にかかりやすい生徒は、内向的で、友達もない子供より、友達も多く、明るい生徒の子供に多く見られるというのだ。内気で精神的に悩みやすい子供は既に体験を通じてどのように適応するかを学んできているが、明るく、社交的な子供たちはコロナ禍という異常事態に適応できず、精神的にストレスとなり、欝になったり、時には自殺への衝動が高まるケースが出てくるというのだ。
クルツ政権が学校再開という大きな賭けに出た最大の理由は③の要因だったという。学校を閉鎖し続ければ精神的に悩む子供たちが増加する、といった危機感だ。イラクやアフガニスタンから帰国した米軍兵士の中には精神的ストレス症状(心的外傷後障害=PTSD)で悩む者が多いが、コロナ禍では精神的に悩む若い世代が増えてきた。青年の中には未来に対して絶望的な思いが湧き、トラウマのような症状に陥るケースが見られる。
人間は自身が体験した辛い体験、思いを簡単には消去できない。若い世代だけではない。多くの人間は人生で体験した辛い体験をトラウマのように抱えて生きている。コンピューターのように消却スイッチがないから、忘れようと努力しても細胞が覚えているからだ(「ベルガモ市民『救急車のサイレン怖い』」2020年8月13日参考)。
学校再開は大切だ。同時に、感染防止という観点からいえば、英国発のウイルス変異種による新規感染者が増えている時、やはり大きな賭けとなる。直径100ナノメートルのコロナウイルスは今、人間の肺器官を損なうだけではなく、心の世界までその牙を剥いてきた。若い世代はその攻撃の対象となってきている。
編集部より:この記事は長谷川良氏のブログ「ウィーン発『コンフィデンシャル』」2021年2月3日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方はウィーン発『コンフィデンシャル』をご覧ください。