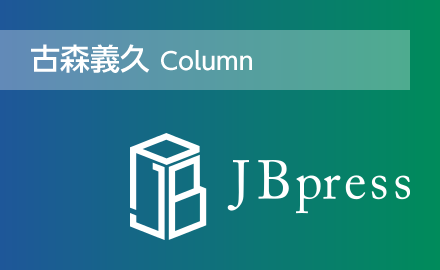時事通信が6日配信した「欧州大使館『沈黙しないで』」という記事を読んだ。「女性が多いと会議が長引く」という森氏の発言に対する抗議の意思表明のツィッターだ。駐日ドイツ大使館(イナ・レーペル大使)が音頭取りをして配信した投稿には「#DontBeSilent(沈黙しないで)」「#男女平等」などとハッシュタグが付され、6日夕までに4万件を超える「いいね」が付いたという。賛同する動きはフィンランド、スウェーデン、アイルランド、ポルトガル、スペイン各大使館などに広がっているという。

▲駐日ドイツ連邦共和国大使館とイナ・レーペル駐日ドイツ大使

このコラム欄でも一度、森発言に関連する内容のコラム(2月7日)を掲載したが、「森発言」は確かに女性蔑視と受け取られる内容がある。その結果、日本国内ばかりか、世界にまで森氏へのバッシングが広がったわけだ。
ところで、「森発言」はそんなに重大な出来事だろうか。女性蔑視の内容はあるが、発言の本人がその直後、「間違っていた」と謝罪したのだ。これで失言の騒動の幕を閉じてもいいのではないか。誰がそれ以上、森氏の失言を追及できるだろうか。換言すれば、森氏が辞任するまでそのバッシングを続けるのだろうか。
森氏は公職者だから、その発言には責任が伴うことは言うまでもない。だから、森氏は発言の間違いと自身が置かれた立場を理解して謝ったのだろう。前回のコラムでも書いたが、森氏の発言が森氏の思想、ビューポイントであったとすれば、森氏は批判を受け続けるだろうし、公職の辞任も排除できなくなる。が、失言であり、森氏の見解ではないとすれば、謝罪すればいいのではないか。森氏の発言を批判してきた人は、謝罪後の森氏の発言を見守っていて、同じ過ちが見られたら森氏の女性への見解を質せばいいだけだろう。
当方は東京五輪・パラリンピック組織委員会会長の森喜朗元首相とは全く縁がない立場だが、東京発の「森発言」に関連する記事をウィーンで読んでいると、「少々、度が過ぎるのではないか」と感じる。その思いが日毎に深まるのだ。特に、駐日ドイツ大使が率先してツイッターを発信し、“森氏叩き”に参戦していると聞くと、「ドイツも中国やロシアの人権問題で沈黙しないで」と、こちらも喧嘩腰になってしまうのだ。
メルケル独首相は欧米首脳としては12回、訪中し、ドイツ産業の復興のために腐心してきた。同首相は訪中する度に、人権問題も議題に挙げてきたと弁明してきた。そして昨年末の欧州連合(EU)と中国間の包括的投資協定の合意では、協定の合意を積極的に支援してきた。ロシアとの関係でも毒殺を図られ、重体となったナワリヌイ氏のベルリン療養を支援する一方、ロシアとの天然ガス・パイプライン建設問題(「ノルト・ストリーム2」)では「経済と政治は別問題」として、同建設の中止を求める欧州議会などの声に耳を塞いでいる。
メルケル首相の外交はロシアや中国など独裁国家に対しては積極的に関与しながら、経済的うま味だけはちゃんと享受してきた。両国の人権問題については、話すが経済的利益を損なうまでは主張しない。一種のアリバイ工作に過ぎない印象を受ける。
メルケル首相は2015年の難民の欧州殺到時には難民歓迎政策を掲げ、ナワリヌイ氏の場合は人道的支援を演じ、中国に対してはドイツ産業界のために人権問題の追及はあくまでもパフォーマンスの水準で留めてきた。トランプ米前大統領は大衆迎合政治家といわれ、メルケル首相も率先してトランプ政権を批判してきたが、メルケル首相の外交も別の意味で非常に大衆受けを狙った政策が目立つ(「メルケルさん!『立つ鳥跡を濁さず』」2021年1月29日参考)。
「森発言」に戻る。メルケル政権下の駐日ドイツ大使館はここにきて「森発言」を取り上げ、他の欧州大使館に呼びかけてバッシングを展開させている。ある意味でメルケル首相流の外交路線だ。しかし、「森発言」より、メルケル首相が展開させてきた親中路線の世界的影響はもっと深刻ではないか。森氏の場合、間違いを認め謝罪した。一方、プーチン大統領や習近平国家主席はその非人道的政策に対して謝罪した、とは聞かない。前者の場合、「失言」であり、後者は、「確信的思想」があるからだ。繰り返すが、旧東独出身で牧師の家庭で育ったメルケル首相には共産国・独裁国に対する、一貫性のある政策が欠けている。
ここにきて、「森発言」への批判には演出が先行してきた。「東京夏季五輪大会をダメにしたい人々が森発言を利用している」といった情報すら聞かれる。女性の権利擁護者は「森発言」問題をこれ以上煽ることを止めるべきだろう。さもなければ、肝心の女性の地位問題はぼかされ、一部の政治的工作に利用される危険性が出てくるからだ。
編集部より:この記事は長谷川良氏のブログ「ウィーン発『コンフィデンシャル』」2021年2月10日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方はウィーン発『コンフィデンシャル』をご覧ください。