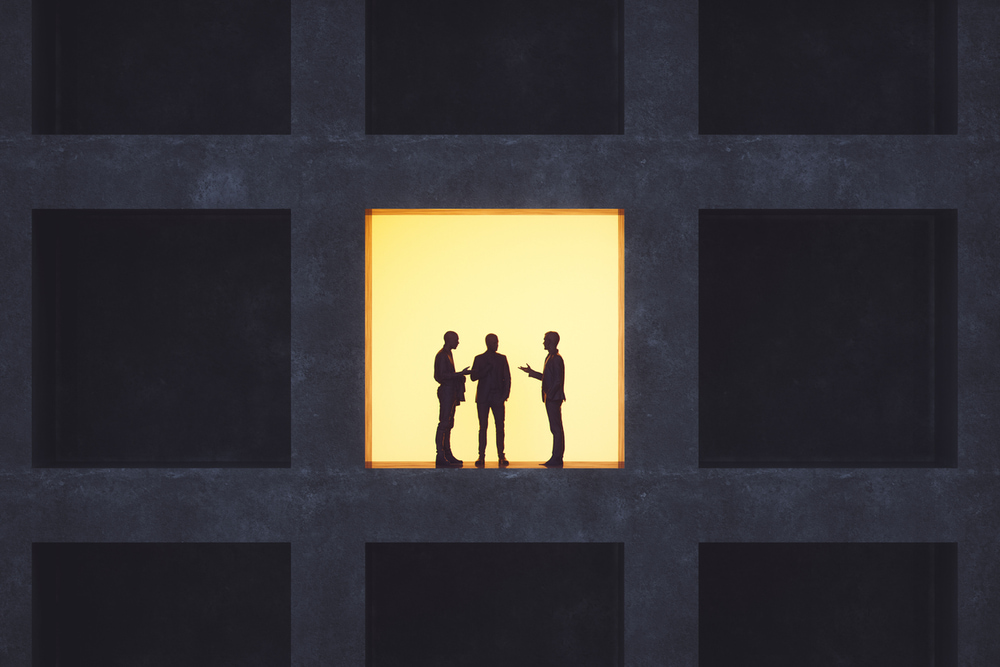国や地方自治体が業者から物品を調達したり、業者に工事を請け負わせたりする場合、原則、競争入札で契約者が選定され、価格等の契約条件が決定される。その際、開札よりも前に「予定価格」という価格が発注機関側において設定され、その額を超えない範囲の価格で落札者が決定される。つまり予定価格とは上限価格の役割を果たすものである(予定価格自体は随意契約でも設定されるが、価格の競争、調整がないと大した意味を持たない)。競争の手続が必ずしも十分な価格低下をもたらすとは限らず、場合によっては発注機関にとって高過ぎる結果になる可能性もあるのだが、予定価格の存在はそういった「高い買い物を防ぐ」機能を有している。
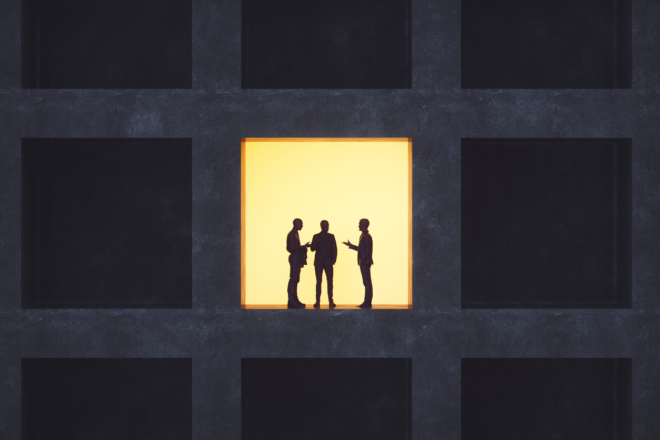
gremlin/iStock
この「予定価格」は、しばしば厄介な現象を引き起こす。予定価格の設定を誤れば有効な調達ができなくなる。低過ぎれば落札者がいなくなってしまい、調達ができず(再入札になり、時間をロスするので)、行政に支障が出る。予定価格はその時々の市況に応じて機敏に変化する柔軟性を持っていないので、競争の結果が予想外だった場合、発注機関は対処に苦労する。また、予定価格は確かに上限価格だが、裏を返せばそこまでは契約を可能とする額でもあるので、それを業者側が知れば、一者応札が予想されるケースでは満額取られてしまうことになる。一者応札でも競争の手続を採用した以上、競争の結果に従うしかなく、そこからの調整は予定されていない。
予定価格の引き起こす問題でここ数年、頻繁に生じているのが、予定価格の情報漏洩である。国の場合は予定価格の事前の公表はできないが、地方自治体の場合は選択できる。すなわち開札の前に上限価格がいくらなのかを開示することが可能である。各自治体の対応はバラバラである。事前公表から事後公表に切り替えるところもあれば、その逆もあり、また(金額や種類別で)併用するところもある。
予定価格が事前に公表されないと、どのような問題が生じるか。それは分かり易く、漏洩の危険が生じるということだ。競争入札に係る情報の漏洩が入札の公正を害する場合には、それは犯罪(官製談合防止法違反等)になる。自己防衛のために事前公表に切り替えた地方自治体は少なくない。
ではその逆はどうか。事前に公表されると何が問題なのか。かつてから指摘されてきたのは、上限価格付近での談合が容易になってしまうという点である。公正取引委員会などはそういった懸念を強調してきた。業種によっては予定価格をかなりの精度で事前に推測することは可能なのであるが、それでもぴったりとした数字が知れているのとそうでないのとには大きな差がある。
公共工事分野では、安過ぎる価格を防ぐために下限価格(法的にはややこしい制度の説明が必要だがここでは一般的にこのような言い方をしておく)が設定されることが多いが、その場合、事前に予定価格が公表されると、予定価格から一定の計算式に基づいて算出される下限価格もかなりの精度で予想されることになり、競争が激しければ価格が下限価格に張り付くことになる。複数業者が下限価格同額で応札すれば、抽選になる。そういう事態が公共工事で頻発して、建設業界は挙って予定価格の事前公表を止めるよう強く求めてきたし、国も同様の観点から事前公表に懸念を示してきた。そういった声を重視して、事前公表から事後公表に切り替えた自治体も少なくない。
各自治体の対応はバラバラである、といったのは、こういった事情のうち何を重視するかが異なるからだ。
つい最近、富山県舟橋村で予定価格の情報漏洩事件があり、村の幹部が官製談合防止法違反で逮捕、起訴された(「舟橋村の官製談合 村幹部職員と受注業者役員を起訴」)。同村ではこの事件をきっかけに予定価格の事前公表に切り替えたという。ある有識者が「情報を隠すから犯罪が起きる」などとコメントしたのをどこかで見たが、問題は単純ではない。予定価格を事前公表したことが談合を誘発したら、「情報を出すから犯罪が容易になる」とでもコメントするのではないか。
予定価格は手続上、開札の直前に決定することができなくはないのだが、公告(募集)段階で決定されていることが圧倒的に多い。それは「何を調達するか」が決まっているのだから、その段階で上限価格を決めておくのは当然、という発想があるからだ。発注者側の知識で予定価格を組むことができなければ業者から見積りをとってきて組むことになるのだが、一者だけからとると公正性が疑われるのでなるべく複数者からとることが求められている。いわゆる「五輪アプリ」の調達で内閣官房IT総合戦略室も複数業者から見積りをとったのだが、担当者がある業者の見積りを他の業者に見せたり、額をにおわせるような発言をしたりといった公正さを疑われる行為があり、第三者調査チームから「不適切」の指摘を受けて、関係者が処分されてしまった(「IT室幹部ら6人処分 オリパラアプリ不適切入札問」)ことは記憶に新しい。
複数の見積りを業者からとれば、一部業者が極端に低い額を示すかもしれない。発注機関が危惧するのは、これだ。一番低い額に合わせるのであれば簡単だが、仮にそれでよい調達ができなければ元も子もない。しかし高い額に合わせるならば、それ相応の重い説明責任が生じる。だから本音としては「そこそこいい値段」の見積りが欲しかったのではないか、そういう推測が可能である。いずれにしても複数業者から見積りをとる趣旨には反するので「不適切」ということなる。その後にくる競争入札への影響はなかった(不明だった)というのが第三者調査チームの結論のようだが、見積りをとった業者に応札の意思がない場合、一者応札が予想されているような場合には、調査で得られた事実を前提にするならば確かにそういうことになるのだろう。
今後、後継のデジタル庁も同様の問題を抱えるかも知れない。民間人材の積極登用が同庁の「ウリ」のようだが、果たして調達の問題についてはどうか。見積書作成作業の有償、無償の問題も含めて、正面から問い直すべき課題ではある。より根本的には、「予定価格」という硬直的な上限拘束性を有する価格制度の存在が引き起こした問題である、といえよう。
公共工事からシステム調達まで、性格は違うが、「予定価格」はしばしば行政を悩ませる「魔物」と化すのである。