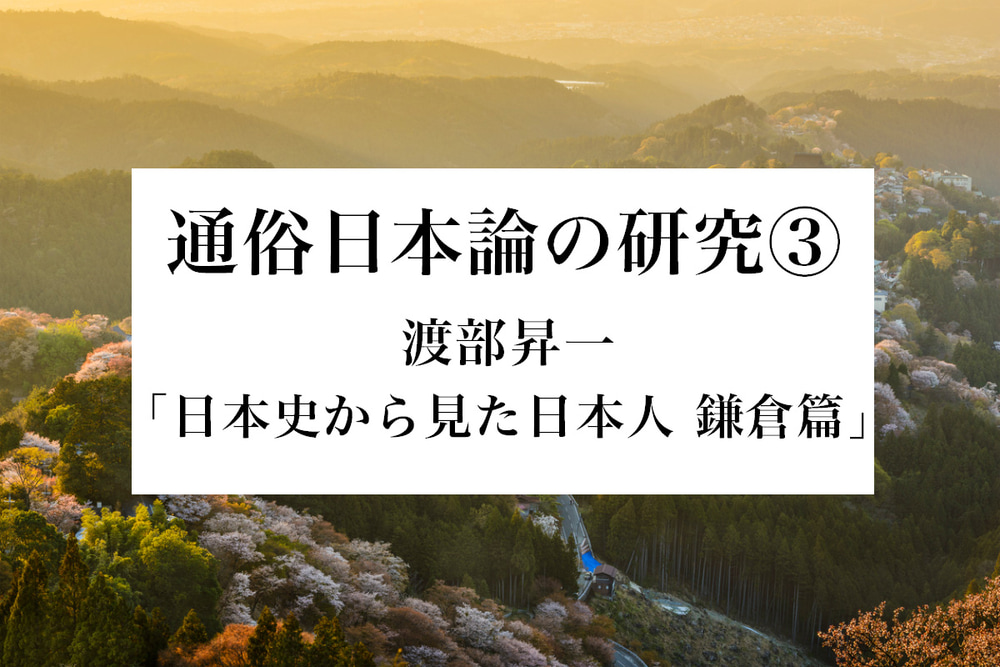通俗日本論の特徴として、歴史学の手法を批判・否定することが挙げられる。渡部昇一『日本史から見た日本人 鎌倉篇』もその例外ではない。一例として、楠木正成の評価を掲げておこう。

SeanPavonePhoto/iStock
鎌倉で挙兵し建武政権に反旗を翻した足利尊氏はいったん京都を占領したものの、その後、後醍醐方に敗れて西に逃れた。ところが尊氏は九州で再起し、東上の軍を起こした。南北朝時代の軍記物『太平記』によれば、楠木正成は後醍醐天皇に対し、京都をひとたび明け渡し比叡山に逃れることを献策した。
しかしこの現実的な提案を後醍醐らは「1年のうちに2度も天皇が京都を離れるのは不名誉である」として受け入れず、正成に尊氏迎撃を命じた。正成は「最後の戦いになるだろう」と思いつつも出陣し、湊川の戦いで激戦を繰り広げる。
けれども衆寡敵せず敗北必至となると、正成は弟の正季に向かって「どのように生まれ変わりたいか」と尋ねた。正季は「七たび生まれ変わっても、同じ人間界に生まれて、朝敵(朝廷の敵)を滅ぼしたい」と答えた。これを聞いて正成は「では共に願おう」と語り、兄弟差し違えて死んだという。
これについて渡部昇一氏は「これは『太平記』の伝承であるから、その情景を見ていた人の証言があるわけではない。だから根拠のない話だと言って捨てるのが近代史学の常識である。ところが近代史学ではどうであろうと、これは日本人には実によくわかる話なのである」と、上記の逸話の史実性を否定する歴史学の姿勢を批判する。
なお井沢元彦氏は『逆説の日本史7 中世王権編』(小学館、1999年)において、意外にも歴史学界の実証主義に近い評価を下している。すなわち「もちろん、これはフィクションである可能性が大きい。というのは楠木一党は全員その場で自害したのだから、二人の言葉を聞いた者は皆死んでいるはずだからだ。もっとも、その最期を本当に見届けた人間がいたかもしれないが、今となっては証明しようもない」と論じている。
とはいえ、井沢氏は、「ただ、このセリフ自体はフィクションであったとしても、正成がこのような思想の体現者であったことは疑う余地がない。正成は逃げようと思えばいつでも逃げられた。またこの戦いに勝ち目がないのも知っていた。しかしそれでも天皇に殉じた」と続けている。したがって結論は、渡部氏のそれと大筋では変わらないと言える。
さて渡部氏は、アメリカと戦って勝ち目のないことを最も良く知っていた山本五十六提督が聯合艦隊司令長官としてアメリカ太平洋艦隊と最前線で戦って戦死した例を挙げ、「楠木正成のパタン」であると説く。そして日本人が理想とする行動原理は正成のそれであると説き、次のように整理する。
- 天皇第一主義であって、その天皇がリーダーとして適格であるかどうかは問わないで、忠誠を尽くす。
- 武将として有能であるが、最高の政治的な決定を左右することはできない。
- 意見を述べるが、通らないと「今はこれまで」とあきらめて玉砕する。
- 七生報国という理念、つまり「後に続く者を信ず」という考え方を残した。
4の「七生報国」という言葉は『太平記』には見えず、近代の造語である。1と2については省略し、ここでは3に注目したい。
渡部氏や井沢氏は、楠木正成が玉砕を決意して出陣したと主張するが、はたして本当だろうか。『太平記』によれば、楠木正成は700騎を率いて足利直義(尊氏の弟)の大軍に突撃し、直義を討ち取ろうとした。直義は間一髪、逃げのびたという。
桶狭間の戦いに見えるように、前近代の合戦は、大将の首を取られたら終わりである。足利軍は尊氏勢と直義勢の二手に分かれており、一方の大将である直義を討ち取れば、戦局は逆転する可能性があった。楠木正成は必敗の戦いに赴いたのではなく、一定の勝算を持って出陣したと考えられる。
渡部氏が類例として出した山本五十六についても同様のことが言えよう。海軍内で投機的として反対論が大勢だった真珠湾作戦を、山本五十六は、採用されなければ聯合艦隊司令長官の職を辞するとまで述べて強引に認めさせた。
確かに山本五十六は、日米の戦力差から日本に勝算なしと捉え、戦争回避を望んでいた。だが日米関係の悪化にともない、国策の転換は困難と考えるようになり、開戦劈頭、航空兵力によって米海軍の本営に斬り込むという真珠湾作戦にのめりこんでいった。山本五十六は真珠湾作戦さえ成功すれば勝算ありと思っていたのであり、玉砕するために聯合艦隊を率いたわけではない。
楠木正成が天皇への忠義のために一命を捧げたという解釈が市民権を得るのは、むしろ江戸時代中期以降である。朱子学、国学、そして後期水戸学が台頭する中で正成の誠忠が強調されていき、やがて幕末の尊王攘夷運動の過激化や戦時中の玉砕・特攻につながっていく。正成の玉砕は「つくられた神話」にすぎないのだ。
【関連記事】
・通俗日本論の研究①:堺屋太一『峠から日本が見える』
・通俗日本論の研究②:渡部昇一『日本史から見た日本人 古代篇』