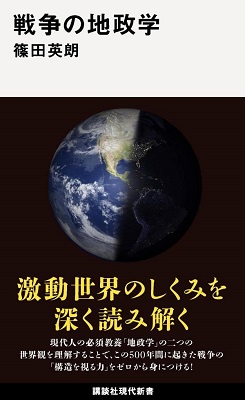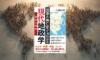5月31日、米国のバイデン大統領が、三段階の構想からなる「イスラエルの停戦案」を発表した。これに対してハマス側が、前向きに検討するという声明を出した。ところがイスラエル政府では、一斉に反発の声があがり、ネタニヤフ首相も「ハマスの壊滅まで軍事作戦を止めることはない」と述べ、事実上、「停戦案」を否定した。

唐突に停戦案を発表したバイデン大統領 同大統領インスタグラムより
通常は、配慮を施した交渉によって紡ぎ出される停戦合意案が、唐突に第三国であるアメリカから発表されるだけでも、異例である。しかもアメリカが「イスラエルの停戦案」と呼ぶものを、イスラエルが拒絶しているのは、奇異な事態である。それにもかかわらず、「停戦案」が成立しなかったら、アメリカはなんとか理由をつけてハマスを糾弾し続けようとするのだろう。かなり混乱した状況である。
バイデン大統領は、イスラエル政権内の一部の人間の意見で「イスラエルの停戦案」なる脚色を思いついてしまったのか。あるいはネタニヤフ首相の狡猾な言い回しに翻弄されているだけなのか。いずれにせよ背景には、超大国の驕りがあるように思われる。
超大国であるアメリカが「イスラエルの停戦案」だと言って発表してしまえば、たとえ本心では停戦案の内容に納得できなくても、イスラエル政府も簡単には異を唱えて反対することができなくなるだろう、といった甘い読みがあったのではないか。
だがアメリカの現在の影響力は、イスラエル政府に対しても、それほどまでに大きくないのだ。バイデン大統領の勝手な期待通りにイスラエル政府が動いてくれる保証はどこにもなかった。
中国が、アラブ諸国に対して、和平会議の開催を呼びかけ、自国も貢献する準備がある、という態度をとっているのも、アメリカにとっては面白くないだろう。中東における中国、及びロシアやイランの影響力の拡大を防ぐためにも、自国のイニシアチブによって戦争を終結させたいという願望を強く持っているはずである。

中国の「ガザ和平会議」提唱に、日本は賛同表明すべき 篠田 英朗
今回の「バイデン大統領が発表したイスラエルの停戦案」は、以下のような内容を定めている。第一段階で、6週間の最初の停戦を実施し、その間に、ハマスによる最初の人質解放とイスラエル軍の人口密集地からの撤退を実現し、大規模な人道的支援を実施する。次に第二段階で、人質全員の解放とイスラエル軍の完全撤退を実現する。第三段階では、ガザに対する大々的な復興支援を入れる。
バイデン政権は、イスラエル軍がラファの中心部にまで到達したところを見計らって、今回の停戦案を発表してみたと思われる。ラファ侵攻は、ガザ地区の主要都市部で、イスラエル軍が侵攻していない地域がなくなったことを意味する。
イスラエル軍は、もはや領域的には、新たに展開する場所を持たない。それでもイスラエル政府自らは、戦闘はまだ今年いっぱいは続く、と明言している。地下に潜伏しているハマスの戦闘員の「殲滅」は、まだ達成されていないからだ。だが、そうなると凄惨なゲリラ戦が継続していく。アメリカとしても、「もういい加減にしたらどうか」と言いたくなっているのは、本音だろう。
しかしネタニヤフ首相にしてみれば、今ガザから撤退を始めたら、ハマスの殲滅を果たすという目標を放棄しなければならない。ラファに侵攻しても、ハマスのガザ地区責任者であるシンワル氏は発見されなかった。ハマス指導部を発見されなければ、ネタニヤフ首相が設定した目標は、達成されない。目標を放棄したら、極右勢力を抱える政権の維持が不可能となる。アメリカに少しくらいは気を遣っておくか、というレベルで、決定できるような事柄ではない。
もし仮にイスラエルが、「バイデン大統領が発表したイスラエルの停戦案」に合意をすると、どうなるだろうか。ハマスの主要な勢力が地下に潜伏した状態で、イスラエル軍が撤退する。その状態で、大規模な復興支援なるものを単純に導入しても、ハマスの活動が再開されることは防げないだろう。ハマスの勢力が顕在化したら、イスラエルが再び軍事展開しないはずはない。結局は、元に戻る。
「バイデン大統領が発表したイスラエルの停戦案」は、力の空白を埋める中立性を標榜しながら、イスラエル軍撤退後のハマスの活発化を抑え込める国際部隊の展開がなければ、破綻する。
私は、半年以上前から、イスラエル完全勝利のシナリオに懐疑的であり、ハマスが狙う戦闘膠着化の可能性が高いが、そこを乗り越える国際部隊の展開のシナリオこそが望ましい、と論じてきた。

行方の見えない「ガザ危機」で、これから起こりうる「3つの主要なシナリオ」 篠田 英朗
国連PKO要員派遣数で世界5位を誇るインドネシアが平和維持部隊の派遣に前向きな発言をしており、トルコのエルドアン大統領も関心を持っている趣旨の発言をしたことがある。
これに対してアメリカは、親米・親イスラエル的に動いてくれると期待するアラブ諸国、特にエジプト、モロッコ、UAEに、部隊派遣を働きかけている。
だがアラブ諸国は、自国の軍隊の派遣には、難色を示している。アメリカが、イスラエルとアメリカが操作できる余地を作っておくことを画策しているからである。イスラエルの代理人のように部隊を派遣することは、アラブの国には、国内世論対策上、できない。アメリカの動きは、今のところ、机上の空論で終わっている。
なおイスラエルの国会は今、UNRWA(国連パレスチナ難民救済事業機関)をテロ組織として認定しようとしている。
今年1月、10月7日のハマスのテロ攻撃に関与していたUNRWA職員がいた、とイスラエル政府が糾弾したため、各国が一斉にUNRWAへの資金提供を停止する、という事件が起こったことがある。結局、イスラエル政府が何も証拠を出さなかったため、日本を含めたほとんどの諸国は、資金提供を再開した(ただしアメリカやイギリスは停止したままである)。
このときの混乱からもわかるように、イスラエルは、パレスチナ人の生活を支えているUNRWAを敵対視しており、潰しにかかっている。事実認定の問題ではなく、作戦行動の一つとして、UNRWA敵対政策をとっている。アメリカは、それに協力している。
「バイデン大統領が発表したイスラエルの停戦案」は、第三段階に「復興」期を置いている。アメリカとイスラエルが操作できるパレスチナ人とアラブ人の平和維持部隊がハマスを抑え込みながら、イスラエルとアメリカが操作できるUNRWA以外の組織に、援助活動を行わせる、という見込みだろう。
具体的には、アメリカ系のNGOや、アメリカの意向が反映されるUNRWAではない他の国連機関へと、援助の窓口をすり替える、ということである。同時に、アメリカの同盟国の二国間援助が、大々的に求められることになるだろう。新興国のドナーを排除し、アメリカの意向を聞くかどうかを踏み絵にしてNGOや国連機関を種別したうえで、「復興」を進める、ということになる。

UNDPのガザ「早期復旧」アピールに覚える虚無感 篠田 英朗
私は、このアメリカが描く見取り図の実現可能性・持続可能性を疑っており、昨年10月から一貫して、より広い国際的なプラットフォームを作るべきだ、と主張している。政治的解決の進展を重視して、性急な開発「復興」支援を進めていくような態度には懐疑的であるべきだ、と主張している。
アメリカ追随で和平から復興まで進んでいこうとしている日本の態度は、これからどうなるか。このままではアメリカに、国力に見合わない巨額の資金提供を求められることも、必至である。日本にとっても、他人事ではないのだ。真剣に考えてみるべきだ。
■