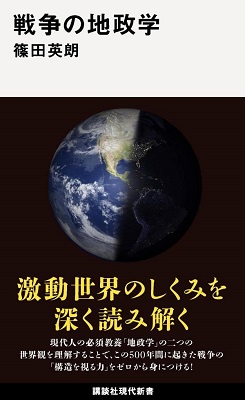5月31日、米国のバイデン大統領が、「イスラエルの停戦案」を発表した。この「停戦案」の骨子は、段階的にハマスの人質解放とイスラエルの撤退を進めていくことだった。これにハマス側が「前向きに検討する」という声明を出したのに対して、ネタニヤフ首相らは「ハマスの壊滅まで軍事作戦を止めることはない」と述べて、事実上の拒絶の立場を内外に明らかにした。
こうした情勢を受けて、私は次のように書いた。
通常は、配慮を施した交渉によって紡ぎ出される停戦合意案が、唐突に第三国であるアメリカから発表されるだけでも、異例である。しかもアメリカが『イスラエルの停戦案』と呼ぶものを、イスラエルが拒絶しているのは、奇異な事態である。それにもかかわらず、「停戦案」が成立しなかったら、アメリカはなんとか理由をつけてハマスを糾弾し続けようとするだろう。
「バイデン大統領が発表したイスラエルの停戦案」の混乱 篠田 英朗

わずか数日で、私が予測した通り、アメリカ政府は「ハマスのせいで停戦案が成立しない」と述べ、「イスラエルが軍事作戦を継続することを理解する」と述べ始めた。全くの茶番である。
バイデン大統領は、反イスラエルの気運が高まった国内世論に配慮した選挙対策をしたつもりなのだろう。あるいはもう少しイスラエル側があわせてくれると期待したのだろうが、ネタニヤフ首相は、バイデン大統領の失点はよりイスラエルにとって有利なトランプ大統領誕生の可能性を高めると計算している。全くあわせてくれない。アメリカの超大国としての威信のかけらもなかった茶番劇であった。

バイデン大統領 同大統領インスタグラムより
果たしてイスラエルは、このまま軍事作戦を継続して、どうするつもりなのだろうか。ガザ地区のハマスの最高指導者であるシンワル氏を見つけ出し、ハマスの殲滅を宣言することが、当面の目標である。だが、仮にそれが実現できたとして、その後はどうするつもりなのか。
ガザ侵攻当初は、ガザの人々をエジプト側に押し出そうとしていたことは、明らかであった。だがこれは強硬なエジプト側の対抗措置に直面して、実現が難しかった。入植者を入れて実態としての併合の度合いを高めていくだろう。ただし、200万人のガザの市民にイスラエルの国政に参加させる地位を与えることだけは、絶対に防ぐ。
西岸にいるパレスチナ自治政府のガザ統治を助ける、ガザ区域内の土着の有力者に統治機構を作らせる、などの案が出ているが、いずれも有力な案となっていない。いずれの人物にも、安定的な統治ができるとは思えないからだ。とはいえ、これらの案の相互の違いは、イスラエル政府にとっては些末な事柄である。
誰でもいいので、パレスチナ人だと言える者で、しかしイスラエルの意をくんで統治をしてくれる者を、いわばイスラエルの傀儡政権として据える。それがイスラエル政府が目指している路線だ。「誰のこと?」は見えない。だが、「誰でもいい、傀儡を作る」、という机上の空論の方針だけは決まっている、と言ってよい。
ネタニヤフ氏は、自身が繰り返し汚職スキャンダルを作り出してきた人物だ。それを反映して、敵も金まみれにしようとする傾向が強い。現在のパレスチナ自治区のファタハが汚職で腐敗しきっているとされるのも、根本的には国際支援金をファタハ指導者の懐に集中して入れ込むことによって、指導者層を堕落させる作戦が功を奏したからだ。
ハマスの政治指導者がカタールの高級ホテルで腐敗した生活をしている、というのは、ハマス批判の文脈でよく指摘される。しかしカタール政府に頼んで、そのような待遇を提供する依頼をしているのは、イスラエル政府である。全ては、堕落した生活に陥らせて、敵を腐敗させるためである。狡猾なのは、その際に使う資金を、国際援助や、湾岸アラブ国などから、出させてしまうことである。
ガザにイスラエルの傀儡政権を作り出した暁には、大々的に国際的な「復興」援助を呼び掛けるだろう。イスラエル軍が破壊しつくした後のガザに、他人の金でイスラエルの意向にそった新しい入植地を作るためである。
アメリカは、その国際援助の強力な旗振り役となる。この流れに巻き込まれて、巨額の「復興」資金の提供を求められるのが、日本のような従順なアメリカの同盟国である。
世界のほとんどの諸国は、このような道義的に間違った茶番劇に巻き込まれるのを避けるため、すでにイスラエルに反発する立場を明らかにし、戦後「復興」でイスラエルの意に沿う行動はとらないことをはっきりさせている。ということはいっそう日本のような寡黙なアメリカの追従者として、いっそうつけ狙われることになる。
イスラエルは、パレスチナ人の現地スタッフを大量雇用して、現地で信頼関係を築いて活動してきたUNRWA(国際連合パレスチナ難民救済事業機関)をテロ組織と呼び、潰しにかかっている。
UNRWA職員はすでに200人近くがイスラエル軍に殺害された。UNRWAに資金提供している諸国に資金の停止も働きかけた。ほとんどの諸国が、停止の根拠が見つからないとして、一度は止めた資金提供を再開した。しかしアメリカはイギリスなどの目立った親イスラエル諸国は、再開していない。それどころかほぼ恒久的にUNRWAへの資金提供を止める政策をとりはじめている。
これらの諸国は、代わってアメリカ系のNGOや、政治情勢を気に留めず資金を運用してくれる他の国連開発機関などに資金を振り替えようとしている。日本にも、この動きに同調するように、という強い要請が来るだろう。
UNDPのガザ「早期復旧」アピールに覚える虚無感 篠田 英朗

このイスラエル=アメリカの動きは、上手くいく見込みが乏しい。泥船に乗る日本の未来も暗い。しかし「面倒な外交は疲れる、金だけで済ませたい」と言わんばかりの今の日本政府は、目をつぶり「思い切って泥船に乗るしかない」と思いこむ可能性が低くないように見える。暗澹たる状況である。
■