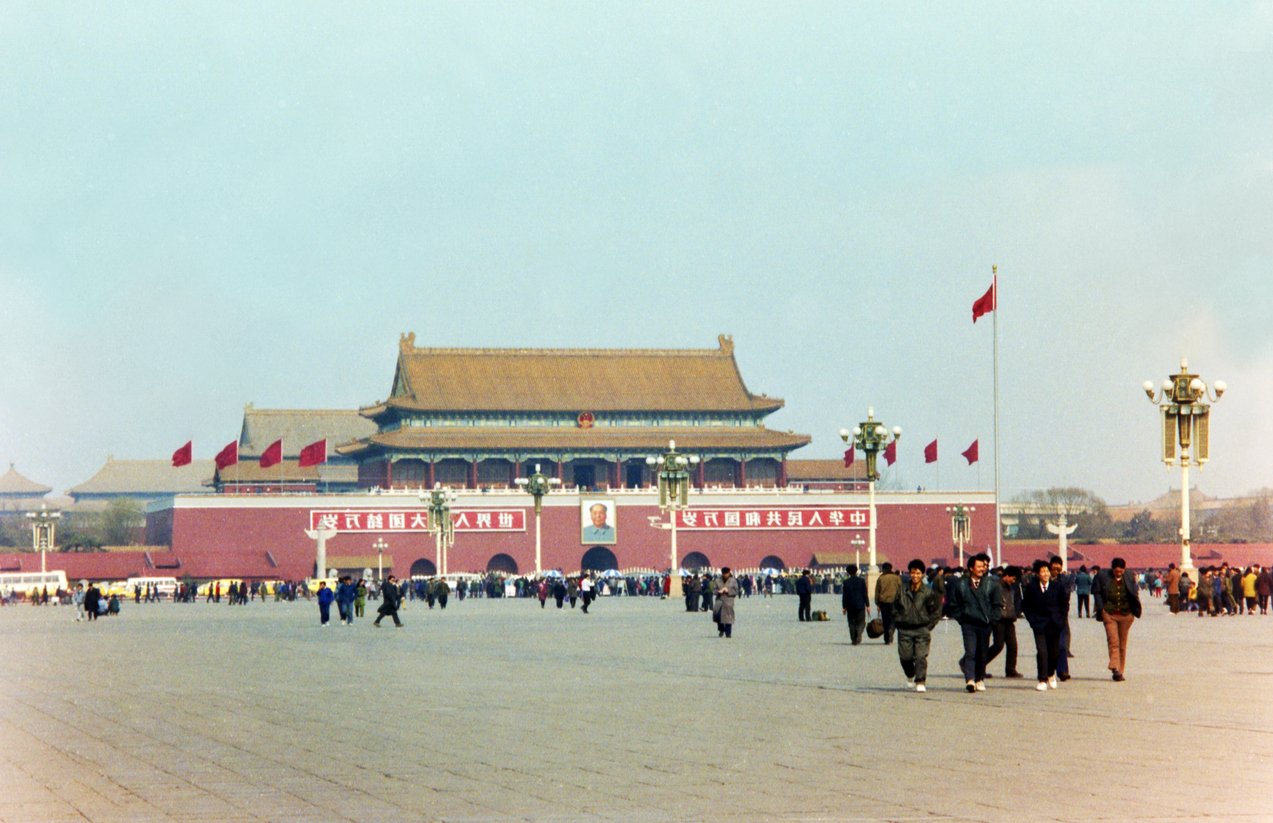
Ralf Menache/iStock
1996年から北京の日本大使館経済部で働いた4年間、強く印象に残ったことがいくつかあった。一つは朱鎔基総理の下で進められた国有企業のリストラだ。中国語では「下岗(シァガン:仕事を降りる)」という。
昔の中国では、企業、党・政府機関など、およそ組織のユニット(単位(ダンウェイ))は、所属する職員・労働者の衣食住ばかりか、幼稚園から病院から墓場まで、構成員の生活・福祉万般の面倒を見ていた。これに伴う経済的負担はたいへん重いものだった。
しかし、改革開放を進めて貿易の障壁をなくしていくと、海外企業との競争が始まる。もともとが旧式のうえ、そんな重い負担を担いだままの国有企業では競争に勝てる訳がない。こうして、それまで国家財政に利潤を上納してきた国有企業はどんどん経営不振に陥った。
時の総理朱鎔基は、この難局を打開するために、国有企業のリストラに踏み切る。それは進めていたWTO加盟のためでもあった。余剰人員を解雇し、幼稚園だの養老院だの、企業が抱え込んでいた社会的機能を切り離す、国家にとって重要な基幹産業の大企業は温存するが、そうでない中小の国有企業は売りに出すか清算する…
このリストラは中国社会に甚大な痛みを及ぼした。解雇された人員数は90年代末には2000万人を超えた。それまで終身雇用どころか終身福祉を疑わなかった人々が突然、社会的セーフティネットも整っていない中国で「単位」の外に放り出されるのだから当然だ。経済、生活面だけでない、中高年の、とくに女性などは「無用の存在」の烙印を押されて仕事を失ったことによるメンタル面の打撃も大きかった。90年代の中国社会にはそんな暗いムードが漂っていた。
国有企業のリストラ問題は日本でもよく知られていて、「カネもない中国はこの試練を乗り切れまい」と見る悲観論が多かった。ところが北京で暮らすうちに、私は「中国は暗いムードばかり」でもないことに気が付いた。中国には、国有企業以外に、民営企業も居ることに気付いたからだ。
1997年から、それまでは日陰の存在、言わば(社会主義公有制を建前とする)体制の軒下で「雨宿りくらいはさせてやる」程度に扱われてきた民営企業に急に脚光が当たるようになった。これが印象に残った二つめの出来事だ。
転機が1997年に来たのは偶然ではない。この年に開かれた第15回共産党大会が「国家の安全に関わったり自然独占性を帯びるような業種を除くが、競争産業からは国有資本を退出させる」ことを謳って、民営企業の存在を正面から認知したためだ。国有経済の範囲を狭め、民営経済を発展させていく流れは「民進国退」と呼ばれた。
私は強い興味を覚えて、北京の邦人有志と連れだって各地に視察に出かけたりして、民営企業家と付き合うように心がけた。活力と野心に溢れ、社業の発展のため寝食を忘れて働く、それまで会ったことのないような中国人との交流は新鮮で、興奮した。
中国民営企業は日本でほとんど知られていなかったから、北京から帰国後の2001年からは彼らと日本の経済界の交流イベントも開催した(日中経済討論会、このあたりの思い出は私の処女作「中国台頭」に記した)。
中国共産党が宗旨違いの「民進国退」を進めたのは何故か?かなり時間が経ってから思い当たった。チコちゃん流に言うと(w)、「国家財政におカネが無かったから~♫」だ。
1980年代に進んだ改革開放は国家財政を直撃した。それまで農産物の売却益(専売制を敷いて農家から安い価格で買い上げ、都市では高い価格で売って差益を出す)と、国有企業の利益上納を2大財源にしてきたのに、農産物流通の自由化が進むと差益を取れなくなった。国有企業は海外との競争が激化して政府に利益を上納できなくなった。中央財政は2大財源を失って、90年代に素寒貧(すかんぴん)状態に陥る。
経済を成長させるには資本(キャピタル)が要る。借金だけで事業を興せば黒字は出しづらく、累積赤字の山を築くことになり易い。でも財政にはカネがない。一方、国民に「カネがないので経済成長は諦めろ」とも言えない。どうするか?
中国で急に民営企業が脚光を浴びるようになり、一方政府はWTOに加盟するために辛い国有企業リストラを進めるようになったのは、国家財政にカネがない中で経済を成長させるためには、カネのある外資企業と民営企業に成長を担ってもらうしかなかったからだ。
後で述べるように、国内にはWTOに加盟すれば国内産業がますますダメージを被るという不安もあれば、「民営企業を経済の主役に位置づけることは社会主義の理念に反する」という保守派の反対もあった。しかし、江沢民主席と朱鎔基総理のコンビは「財政に金がないんだから、仕方がないだろう」で反対論を押し切った(ように思えた)。
昨今、欧米では「中国は我々を騙してWTOに加盟した」という論調を聞く。しかし、人を騙す仕掛けにしては、国有企業リストラがもたらす痛みは大きかった。「WTOに加盟すれば必ず成功する」勝算があるとも見えなかった。
1999年CCTV(中国中央電視台)の公開討論番組に出演したことがあるが、一緒に出演した某大国有企業の総経理は「WTOに加盟できなければ、中国の未来はない」と言い切った。聞いていて「中国はそれくらい危機感に迫られ、それくらい追い詰められているんだ」と感じたことを覚えている。
蓋を開けると、2001年中国が正式にWTOに加盟する前後から、世界中から外資企業が中国に殺到して投資した。彼らはカネだけでなく当時の中国に最も欠けていた技術や経営管理も持ち込んだ。次々と沿海部に建つ外資の工場で働くために、1億人を超える内陸の農民が引っ越してきた。こうして中国経済の躍進が始まった。私には、それは辛い試練を乗り越えた報酬、配当に思えた。
2000年、江沢民主席は「三つの代表」論を唱えて、民営企業家でも共産党に入党できる途を拓いた。「中国道」に入門してわずか数年の私は「民営企業の時代が来る」と信じた。①で取り上げた宮沢総理の懐疑論に全く思い至らなかったのは、そういう訳だ。
(その③につづく)
編集部より:この記事は現代中国研究家の津上俊哉氏のnote 2024年12月31日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は津上俊哉氏のnoteをご覧ください。













