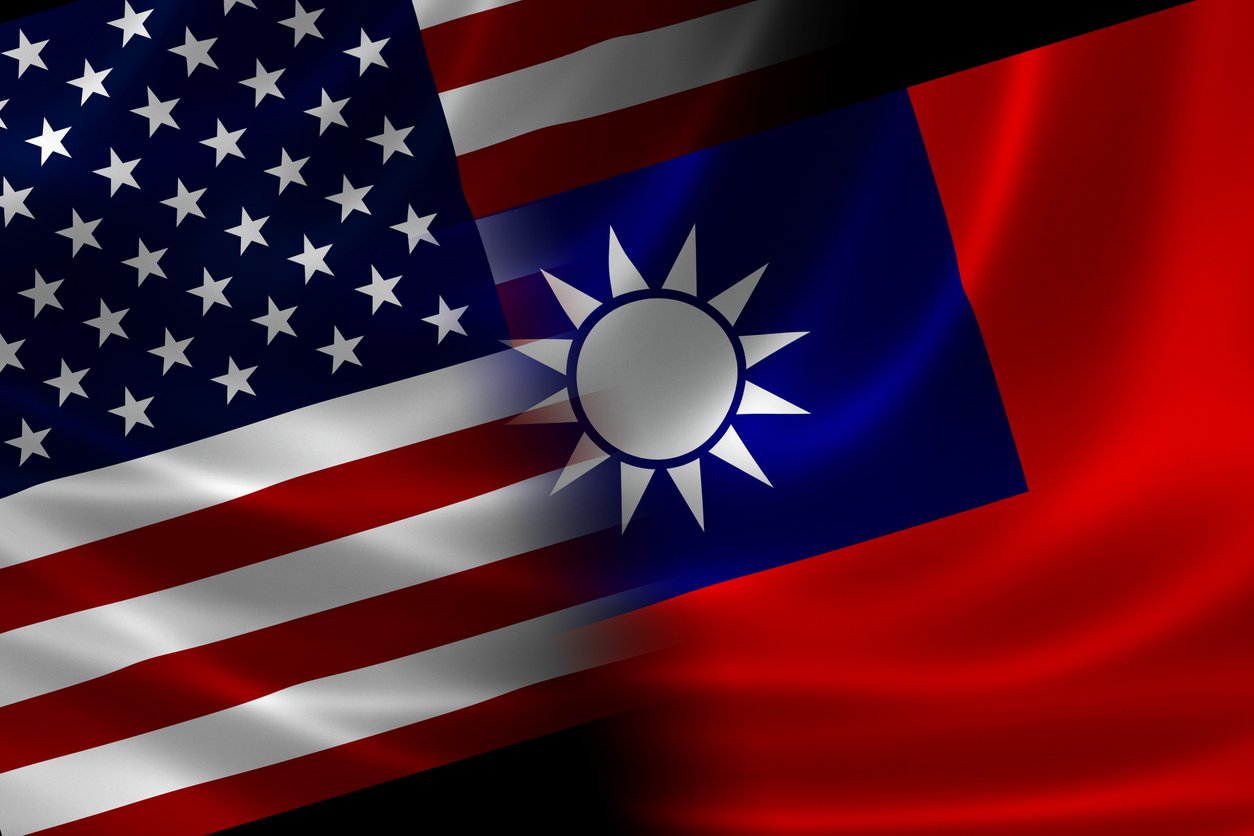
ronniechua/iStock
米国務省がホームページに掲載している「二国間関係ファクトシート」(「FS」)のうち、2月13日に変更された「米国と台湾の関係」の「FS」の内容が話題を呼んでいる。17日の台湾政府系紙『台湾国際ラジオ(RTI)』はそれを、「米国務省が『台湾独立を支持せず』をサイトから削除」との見出しで報じた。
その「FS」の当該部分はこのようだ。(以下は拙訳、太字は全て筆者)
東アジア太平洋局 2025年2月13日
米国の台湾に対するアプローチは、何十年もの間、どの政権でも一貫している。米国は長年「台湾関係法」「3つの共同声明」「6つの保証」を指針とする「一つの中国」政策をとってきた。我々は台湾海峡の平和と安定に変わらぬ関心を持ち続けている。我々はいずれの側からの一方的な現状変更にも反対する。我々は海峡両岸の相違が、海峡両岸の人々に受け入れられる方法で、強制のない平和的手段によって解決されることを期待している。
残念ながら、「台湾独立を支持しない」との一節が書かれていた変更前の文面を確認することは、今となっては叶わない。が、幸い17日の「RTI」別記事が、13日に付け加えられた文言を報じていた。それは上記引用で筆者が太字にした箇所である。
台湾紙『聯合報』は、国務省の「FS」から「台湾独立を支持しない」という表現が、「長年にわたって現れたり消えたりして来た」とし、政権交代時は勿論のこと同一政権でも変更されたとして、バイデン政権が22年5月に台湾関係の「FS」を2度修正した出来事を記している。
即ち、5日に「台湾は中国の一部である」「米国は台湾の独立を支持しない」などの文言を削除して中国の猛批判に逢い、更に23日の日本訪問時にも「中国の台湾侵攻に米国は軍事介入する」と発言して強い反発を招いたため、バイデン国務省が28日、「台湾独立を支持しない」と書き加えたというのだ。トランプのいうバイデン政権の「弱さ」を見る思いである。
台湾外交部は「米台関係に前向きな姿勢」として、これを歓迎した(19日の『産経』主張)。が、どちらかといえば反民進党の前掲『聯合報』は、この変更は注目に値するが「過度に解釈する必要はない」と冷静だ。筆者も同感である。
確かに、台湾シンパのルビオ国務長官は、初の外遊先に台湾との国交を維持しているグアテマラを選び、「同国・米国・台湾の外交上における関係強化に努める」と述べ、台湾を「民主国家」と呼んだ。が、ルビオの主たる目的は、親台湾のジャマテイ大統領から代わったアレバロ大統領に、米国が強制送還する不法移民受入れの同意を求めることにある。
要すれば、国務省が「FS」の文言を変更しようが、ルビオが台湾を「民主国家」と呼ぼうが、トランプ大統領が「台湾の独立を支持する」と述べた訳ではない。何より「両岸」に関する米国の方針が一貫して、「台湾関係法、3つの共同声明、6つの保証を指針とする『一つの中国』政策」の維持にあることを忘れてはならない。
それよりも筆者は、新たに「FS」に付け加えられた「一方的な現状変更にも反対する」「両岸の相違が・・強制のない平和的手段によって解決されることを期待している」との文言の方が、「平和と団結の使者」を標榜する「2.0」のトランプの、ノーベル平和賞を目指す気持ちに沿う、と考える。
この「平和的手段による解決」については、23年9月の拙稿「両岸問題の平和的解決が前提:日米の対中国交樹立」で、米中の「3つの共同声明」及び「日中共同声明」が「平和的解決」についてどう書いているかについて触れ、これが「キーワード」と書いた。以下に改めてその要点を述べる。
■
先ず「一つの中国」政策と「台湾関係法・3つの共同声明・6つの保証」について述べれば、米国の「一つの中国」政策は49年10月1日の共産中国成立以来、一貫して不変である。そしてそれは、決して中国の台湾への主権を認めている訳ではない。72年2月の「上海コミュニケ」で米国はこう述べたのである(日本外務省仮訳)。
米国側は次のように表明した。米国は,台湾海峡の両側のすべての中国人が、中国はただ一つであり、台湾は中国の一部分であると主張していることを認識している。米国政府は、この立場に異論をとなえない。米国政府は、中国人自らによる台湾問題の平和的解決についての米国政府の関心を再確認する。
この「認識している」との英語は「acknowledge」であって、「承認する」を意味する「accept」ではない。このことは、「米国が中華人民共和国政府を中国唯一の合法政府であることを承認」した、79年1月1日発出の「外交関係樹立に関する共同コミュニケ」においても、再確認された(「8・17コミュニケ」の日本外務省仮訳)。
前記の「8・17コミュニケ」とは、1982年8月のレーガンと鄧小平の共同コミュニケだが、これの論点は米国の対台湾武器売却問題にあった。詳細は4年前の拙稿「台湾への武器売却:百歳の天寿を全うしたシュルツ元国務長官の遺産」をご覧願いたいが、この時レーガンと鄧は「台湾関係法」について議論し、心配した台湾の蒋経国にレーガンが「6つの保証」をしたのである。
9項目にわたる「8・17コミュニケ」の4項と第5項はこう書かれている。
4. 中国政府は、台湾問題は中国の内政問題である旨を重ねて言明する。中国が1979年1月1日に発した「台湾同胞に告げる書」は平和的祖国復帰へ向けて努力するとの基本的政策を規定した。中国が1981年9月30日に提示した9項目提案は、台湾問題の平和的解決に向けて努力するとのこの基本的政策の最も顕著な努力の表われであった。
5. 米国政府は、・・・1979年1月1日に発出された「台湾同胞に告げる書」及び1981年8月30日に中国から出された8項目提案に示されている台湾問題の平和的解決のため努力するとの中国側の方針を理解し、評価する。以下略
レーガンは国務省が同コミュニケを発表するに当たり、こう記された書簡を添えた(「本当に『中国は一つ」なのか』ジョン・J・タシクJr著 草思社 2005年12月第一刷)。なお、これの最後の一文は「6つの保証」項目の一部である。
今後の台湾向け武器売却について、今回の声明で明示された米国の方針は「台湾関係法」と何ら矛盾しないものである。武器売却は同法に従って継続され、また中国政府が台湾問題に向けて平和的姿勢を続けるという期待の下に継続される(中略)。当問題に関する米国政府の立場は常に明確であり一貫している。台湾問題は、台湾海峡の両側の中国人によって解決されるべき問題である。この問題に関して米国は干渉する意思もなければ、台湾人民の自由な選択を阻害したり、圧力をかけたりすることもない。
横道に逸れるが「上海コミュニケ」でもここでも、米国は「両側の中国人」と述べている。が、そのことが既に時代に合わない理由を、前掲した23年9月の拙稿に書いたので参照願う。
さて、前掲書には前記の書簡と共にレーガンが発した、国務長官と国防長官の署名入りの極秘大統領令の内容もこう記されている。
・・・このコミュニケの署名に至る交渉は、次のことを前提として進められた。武器売却の削減は台湾海峡の平和次第であること、そして台湾問題の平和的解決を目指すという中国政府の「基本方針」が継続されているかどうかで決まることだ。
つまり、米国が台湾に売却する武器を削減するには、中国が台湾との相違を平和的に解決すると確約していることが絶対条件なのである。これら二つの事項の結びつきが米国の外交政策にとって恒久的な必須条件であることは明白である。
さらに、台湾に供給される武器の質と量は、すべて中国による脅威に応じて決定される。台湾の防衛能力は、質・量の両面において、中国の防衛能力に応じて維持されることになる。
ニクソンとキッシンジャーが道を開いた米中国交正常化が、疲弊した両国(中国=文化大革命と中ソ国境紛争、米国=ベトナム戦争)が、ソ連の覇権を牽制する目的で一致した結果であることは良く知られている。そうした背景もあって、「両岸の平和的手段による解決」という文句が終始これでもかとばかり謳われている。
が、それを自覚して韜光養晦(才能を隠して、内に力を蓄える)に徹し、経済に資本主義を取り入れて発展させた非凡な鄧小平の果実を、単に収穫しただけの習近平が故事を忘れて「武力統一」を唱えたところに、習の凡庸さが現れている。
76年になろうとする米国の「一つの中国」政策、そして半世紀を超える「米中国交」が、何れも「両岸問題の平和的手段による解決」を前提としている以上、これを脅かす「ボイコットや経済封鎖」でさえも、脱退や廃止が大好きなトランプをして「一つの中国」政策と「3つの共同声明」を棄てさせる口実になると、習近平は知るべきである。
そんな折、『ロイター』が17日、「台湾、自衛の決意目指す」との見出しで、米国から70億~100億ドル(1兆5百億~1兆5千億円)相当の武器購入を検討していると報じた。台湾国防部はノーコメントだが、『聯合報』は見出しに「台湾はトランプ大統領の支持獲得を目指して」と加えて転載している。この方が台湾らしい。













