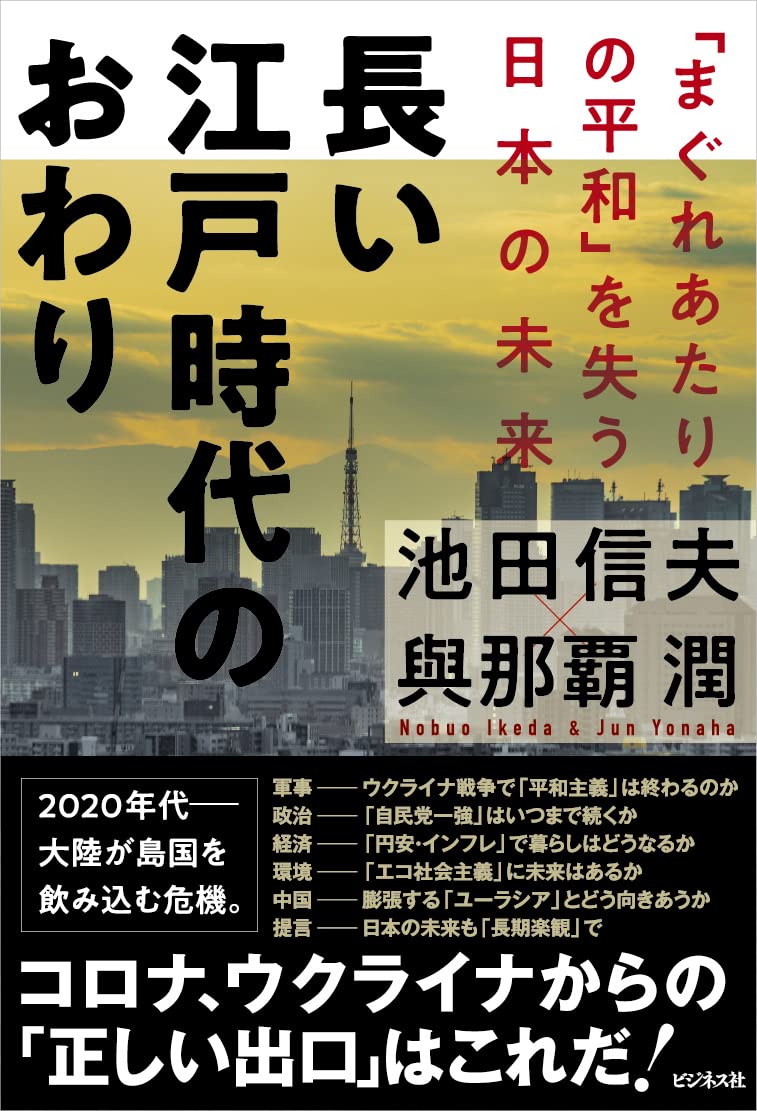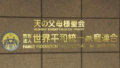まだアメリカが民主党のバイデン政権だった1年前に、こんな記事を書いた。安易に「意識の高さ」を誇ろうとする演出があだになって、アカデミー賞授賞式が炎上した不祥事を扱う内容である。

ご存じのとおり、いま共和党のトランプ政権は、むしろそうした「ダイバーシティはキラキラしている☆」といった風潮を全否定すべく、敵意をもってDEI(平等化政策)の排除に乗り出している。そんななか、今年もアカデミー賞がやらかしたのは、正しく時代の象徴になったかもしれない。
こうしたことは、記録に残さないと記憶からも消えていくので、後世のためにまとめておこう。
今年の本命と呼ばれていた作品は、ヘッダー写真の『エミリア・ペレス』。本人もトランスジェンダー女性を自認する俳優が、性転換して女性になる主人公を演じて「主演女優賞」にノミネートされた。発表時には、トランプ政権に屈しないというメッセージとして、好意的に報じられた。
ネタバレになるから伏せるけど、1992年に見事な「女性」を演じた男性俳優は、助演男優賞で候補になった(知りたければこちら)。2007年の『アイム・ノット・ゼア』で、男装してボブ・ディランを演じたケイト・ブランシェットも、あくまで助演女優賞でのノミネート。トランス女性が「女優賞」で候補になるのは、画期的なことだった。
ところがその後、この人が過去(といっても2020~21年)に、ムスリムや黒人、アジア系など他のマイノリティへの差別発言を連発していたことが判明した。スペインの俳優なので、ハリウッド側のチェックが甘かったらしい。
ノミネートの剥奪こそなかったものの、映画を配給するNetflixは一切のサポートの拒否を表明し、誰も彼女に好意的な態度を見せたくないということで、授賞式の演出まで変更になった。要は捨てられたわけで、むろん賞も他の人が受賞した。
この事件が起きるまで、キャンセルカルチャーと言えば「トランス差別」をした(と見なされた)人に対して発動されるものだった。しかし今回の顛末を受けてむしろ、『エミリア・ペレス』はこのトランスジェンダー女性に対するキャンセルで、作品賞まで逃したとさえ報じられている。
つまり潮流はいまや、180度逆転したのだ。そしてそれは、差別の問題を真剣に考える人にとっては、なんら驚くべきニュースではなかった。
エズラ・ミラーという俳優がいる。細面なハンサムで、かなり人気のあった(たぶん)男性なのだが、本人は自身をトランスジェンダーだと認識している節もあるらしく、2022年にはすでに不品行が騒動となっていた。
なにせ女性を犬扱いし、口答えするならトランス差別だからナチスと同じとまで言い放ったというから、すさまじい。被害の規模がだいぶ違うとはいえ、「ウクライナで抵抗しているのはネオナチ」と公言する某国の独裁者(ただし、遠からず復権予定)を思い出させる。
ミラーはナディアに「座れ」と命令したそう。ナディアが「犬に言っているみたいだ」と怒るとミラーは「ああ、俺は犬に話している」と返答。ナディアが「そういう風に話すなら部屋を出ていって」と求めるとミラーは彼女を「トランスフォビアのナチス」と罵ったという。
ナディアはナチスのホロコーストを生き延びた人の子孫。そのためこの言葉にとりわけ大きなショックを受けたという。
「私はミラーに私がホロコーストの生存者の子孫だと話したのを覚えているかと尋ねた。するとミラーは私に向かって『覚えている。でも俺の家族は何人死んだ?』と言った。これを聞いて私は『ああそうか、これは誰が一番トラウマを負っているかというゲームなんだと思った』」。
強調を付与し、段落を改変
実はこの人が出た『ウォールフラワー』(2012年)は、14年からぼくが病気で働けない間に見て印象に残り、励まされた映画のひとつだった。そこですばらしい演技を見せた人が、いつしかこうしたほとんど「無敵の人」の状態で、ハラスメントを続けていたと知ると、暗鬱な気持ちになる。
こうした映画界のスキャンダルの教訓は、たとえばトランス女性といったなんらかの属性を根拠に、批判したら差別になるからと相手を黙らせるポジションを作ってはいけない、ということだ。それは、単なる芸能ゴシップにはとどまらない。
ジョージ・クルーニーといえばNo.1のハリウッド・スターで、熱心な民主党のサポーターとして知られる。しかしいまや彼を扱う記事でも、遠回しながら、トランプ再選を後押しした要因のひとつが「トランスジェンダーの ”無敵化” への反発」にあったと認めているように見える。
彼の見解では、「政策が不人気だったのではなく、メッセージの伝え方が効果的でなかった」という点が問題だった。……バイデン自身の発信力の低下も影響したとクルーニーは指摘している。
選挙の数ヶ月前に行われたギャラップの世論調査では、移民、犯罪、ホームレス問題、インフレが有権者の主要な関心事であり、カマラ・ハリスの支持率はバイデンが撤退する前から控えめだった。また、選挙運動中で最も効果的な広告は、トランプがトランスジェンダーの権利を巡る議論を武器にした広告だとされている。
日本人が洋画を見なくなって久しく、今月のアカデミー賞の話題もまた、この国では伊藤詩織監督のドキュメンタリーの当否(落選)に集中していた。しかしそれ以上に、今回の顛末は「時代の転換点」として、歴史に刻まれる可能性が高い。

アカデミー賞の惨状が示すように、自分は特定の属性を持っているから、なにを言っても「被差別者の声」として聴かれる資格があり、批判するなら差別者だと言い張ってよい「無敵の人」(通常の意味とは違うが)のポジションを作ることは、かえって反差別の運動を弱体化させる。なぜか。
露骨な偏見の持ち主や、現体制を絶対視すると公言して恥じない反動家は、そもそも「あなたは差別者だ」と批判されても痛くも痒くもない。逆にダメージが大きいのは、私は差別のない社会をめざしますと主張するリベラル層だ。つまり「無敵の被差別者」の出現は、実際には差別をなくそうと取り組む運動を内ゲバ化させるのだ。
アカデミー賞やトランスジェンダーといった、「欧米の最先端の話題」を素材にするから新しく見えるだけで、そうした事態は日本でも先例がある。ぼくもまた以前から、はっきりそう述べてきた。
與那覇 個人のアイデンティティを政治イシューにする際には、憎悪や憤懣を煽る手法に陥らない配慮が必要です。70年代の社共共闘を崩壊させる一因になったのは、社会党の支持母体だった部落解放同盟と共産党の全面衝突でした(ローラ・ハイン『理性ある人びと 力ある言葉』岩波書店)。
そうした教訓を、いまハッシュタグ・アクティビズムで盛り上がる人たちが踏まえている気がどうもしません。
61頁(2022年8月刊)
1970年代から左派優位が崩れた日本と同様に、バイデン政権までは米国民主党を支えてきた、労働者・貧困層・マイノリティ・知識階層の連合も壊滅した。その最大の楔となったのがトランスジェンダリズムであり、トランプ政権の多様性への攻撃は、結果であって原因ではないのだ。リベラルな人ほど、見誤ってはならないと思う。
さて、このnoteの読者にはご存じのとおり、日本でもかように「無敵の人」を作り上げて内ゲバを繰り返し、社会の分断を煽り、本当の意味での多様性を衰弱させてきた人たちがいる。もちろん、トランスジェンダリズムの隠れ蓑として、2021年にオープンレターを振りかざした面々だ。

トランプが支配する米国のようなディストピアを避けるためにこそ、ぼくたちは何度も彼らを蒸し返し、焼きを入れ続けてゆくべきだろう。それもRareではなくWell-doneで、ソースはハバネロを利かせたDiavolaが望ましい。
そうすることが、自由を強化する。少数者への偏見を減らし、勘違いした活動家が私欲で行うマイノリティへの搾取をなくし、正しい意味で誰もが尊重される、多様性の根づいた社会を作る。
次回の連載「オープンレター秘録」では、アメリカでいま如実に示されたトランスジェンダリズムの崩壊が、日本ではオープンレターの炎上に重なって進んだプロセスを、明らかにしたい。

ぼくたちは米国と同じ泥沼にはまる前に、引き返すことができる。そのために必要なのは、すでに燻し出されたニセモノの「反差別」を鉄板にのせ、火を入れながらの批判と検証を続けることだ。ぜひ、ご期待ください。
参考記事:


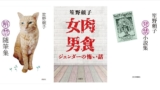
編集部より:この記事は與那覇潤氏のnote 2025年3月27日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は與那覇潤氏のnoteをご覧ください。