
2019年だと思うが、『永続敗戦論』の白井聡さんと話していて、「加藤典洋は『敗戦後論』を、北岡伸一に読ませたくて書いたのでは」なる噂を聞いたことがある。もちろんあくまで憶測で、白井氏にも確かな証拠があるわけではなさそうだった。
とはいえ、まったく無根拠というわけじゃない。『群像』の1995年1月号が初出の「敗戦後論」には、実際にこうした一節がある。
湾岸戦争のおりの分裂の様相として、日本も国際平和維持に寄与する米国主導の国連軍に合流する平和部隊(軍隊)をもつべきだとする小沢一郎、あるいは北岡伸一の ”現実主義” 的な「普通の国家」論と、……柄谷行人、あるいは浅田彰の観念的「ラディカルな平和主義」論の対立を該当させることもできる。
しかしここにあるのもわたしの考えからいえば、ジキル氏とハイド氏の分裂を本質とする、〔敗戦後の〕半世紀来の半身同士の対立なのである。
『敗戦後論』ちくま学芸文庫版、55-6頁
(段落を改変し、強調を付与)
ジキル氏とハイド氏とは、日本では護憲派も改憲派も「一貫した自己を保ちえない」ことを喩えて用いた、加藤の論考の核になる表現だ。護憲派は憲法が押しつけだった史実を、改憲派は壊滅的な敗戦という前提を、それぞれ見なかったことにして自分の立場を作っており、その自己は脆い。
しかもそう書いた後、加藤は小沢一郎やそのブレーン(『日本改造計画』の執筆者)だった北岡氏の「普通の国」論を、さらに追い討ちする。
「普通の国家」なる主張に進み出ているところに特徴的だが、この〔改憲して ”普通の” 軍隊を持とうという〕主張は国外を気にするその仕方において没理念的である。
「普通」などという普遍、理念は存在しない。こう主張しているのは、あくまで国内に向けられた内向きの自己でしかないのである。
同書、56頁
小沢=北岡は「国際的に通用する国になるために」軍隊を持とう、と、あたかも外向きな主張をするが、「ぼくらも ”普通の国” でありたい」などと言われて、そこに価値を見出せるのは日本人だけじゃないか。彼らもまた、日本国内でのみ「9条は世界に誇れる理想で…」と繰り返す護憲派と、実は大差ない、とする批判である。
北岡伸一氏と加藤さんは、どちらも1948年4月の生まれで、学園紛争さなかの東大で学んだ(北岡氏は当時から保守派で、学部も違ったが)。ふたりに面識があったのか、ぼくは知らないけど、もし互いに意識するところがあったなら、ちょっと素敵な話だと思う。
別の記事でも紹介したが、2015年の安倍談話に関わった北岡氏は、国際社会に通用するロジックで書くことを、最も重視したといま回顧している。
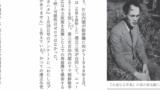
世界の、日本の歴史認識についての見方に対し「いやいや、日本はこう思ってるんだ。そんなこと〔=A級戦犯の賛美〕は思っていない」とはっきり出すことは大事だと思った。
(中 略)
──談話には国際社会に向けたメッセージという意味合いもあったのか?むしろ、それが主だ。もう1つが国民に向けてのメッセージ。 国際社会、アメリカ向けのメッセージだったと考えている。
一方の加藤さんは、生前最後の単行本になった『9条入門』で、「護憲版の ”普通の国” 論」を提起していたように思える。保守とリベラルとで団塊の世代を象徴する二人の知性は、生涯をかけてすれ違ったのだろうか。
同書もまた、別の記事で先日紹介した。9条に基づく戦後の平和主義を、賛否両派ともに「日本に特殊なもの」として語りがちだけど、それはどこまでホントなのか? を加藤は腑分けしてゆく。
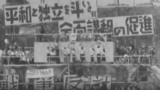
実はそもそも、憲法に「戦争放棄」が記されること自体は、珍しくない。『9条入門』からの重引で、フランス(第四共和政)・イタリア・西ドイツで、WW2の後に制定される条文を見てみよう。
フランス「共和国は、征服を目的とした、いかなる戦争も企てないし、その武力をいかなる国民に対しても決して使用しない」
イタリア「国は、征服または人民の自由の侵害の手段としての戦争を放棄する」
西ドイツ「諸国民の平和共存を阻害するおそれがあり、かつこのような意図でなされた行為、とくに侵略戦争の遂行を準備する行為は、違憲である」
『9条入門』158-161頁
しかし、と加藤さんはいう。これら仏伊独の憲法はいずれも、戦争放棄という形で国家の主権を制限するにあたり、「相互主義の留保の下に」(仏)・「相互的であることを条件として」(伊)という前提を明記した。要は、他の国ともみんなで一斉になら、戦争を放棄できるよという話で、表現は異なるが西独もそこは同じだった。
これに対して、日本の9条はそうした相互主義に基づかず、自国だけで一方的に戦力や交戦権を放棄する点(だけ)が、特殊だ。しかし制定時には、後に改憲派となる人も含めて、多くの政治家が「日本人ならではの使命として、世界に先駆けて理想を示す!」とそれを礼賛していた。
そうした新憲法への熱狂は、戦前の万世一系、戦時下の八紘一宇といった「日本だけがこんなにスゴい!」と謳う理想が、敗戦でポキッと折れてしまった空白を埋める代償行為ではなかったかと、加藤は述べる。そして、次のような評価を下す。
ほんとうは「特別の戦争放棄」よりも、〔相互的で、他国にも類例のある〕「ただの戦争放棄」のほうが大切なのではないでしょうか。
(中 略)
しかし、日本の場合、そのような「相互主義化」ないし「正常化(ふつう化)」に向けての努力は、見あたりません。……むしろ、その逆の動き、「特別化」への動きが、それを「与えた」GHQのマッカーサーと、それを「受けとった」日本国民の側、双方に特徴的に見られるというのが、ドイツ、イタリアと比較した場合の日本だけに見られる特徴なのです。
同書、155・164頁
日本だけの素晴らしさという、過度な重荷を9条に背負わせる平和主義は、ちょうど安倍談話と重なる時期だった2015年の安保政局で完敗し、限界が見えていた。むしろこれからは「ふつうの平和主義」に、それを軟着陸させることが課題になると、晩年の加藤さんは考えていたように思う。
白井聡さんと、作家の島田雅彦さんが一緒にやっているYouTube番組「Air Revolution」が、6/4(水)20:00~の配信で、拙著『江藤淳と加藤典洋』を採り上げてくれることになった。もちろんぼくもゲスト参加して、ぜひ率直にこうした問題を、両氏と議論してゆく。
チャンネルは有料だが、前半は無料パートとして(上から)誰でも視聴できるそうだ。保守とリベラルを問わず、多くの人に届きますように。
参考記事: 1つめの6/25イベントもよろしくです!
(ヘッダーは「日本の古本屋」から。平成初頭はこんなの出てたんですね。戦後は終わると誰もが思った時代でした)
編集部より:この記事は與那覇潤氏のnote 2025年6月1日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は與那覇潤氏のnoteをご覧ください。













