
発売中の『文學界』7月号で、上野千鶴子さんと対談した。タイトルは、ずばり「江藤淳、加藤典洋、そしてフェミニズム」。ネットでも2つ、PR用の抜粋が出ている(もう1つのリンクは後で)。

前にも書いたが、拙著『江藤淳と加藤典洋』に帯をいただいたとはいえ、この対談がガチの初対面である(ぼくの方は、大会場で上野さんの講演を聞いたことならあるが)。仕上がったテキストを読んで、ふと懐かしく思うことがあった。
「初対面が対談」って、活字がメインのメディアだった時代の感覚なのだ。
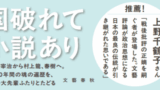
動画配信が定着したいま、初めて誰かと共演するなら「文字よりも映像で」だろう。コロナ以降はZoom経由で、より気軽な開催も増えた。会う前からSNSで絡んで、打ち解けている場合も多い。
ライブ配信は「どうも~」の挨拶から始まって、フレンドリー感も含めて楽しむ媒体だから、(視聴者も飲みの席に居合わせたような)居心地のよさが魅力である。逆にいうと、そのぶん「よそ行き」感は控えめになり、互いに共有しているものをベースに話を進めやすい。
ぼくは2013年に対談集を出したけど、その頃がちょうど「活字から動画へ」の転換期だったかなと思う。当時の、相手と話が合うかがまだわからない状態で、居住まいを正して手合わせ願うといった感じが、久しぶりだった。

最近は流行らないこのスタイルのよさは、そんな他人行儀が幸いして、まったく異なるバックグラウンドをお互いに訊き、すり合わせながらの対話ができることだ。たとえば、こんな感じである。
上野 「正嫡」と言っても、江藤さんから加藤さんの順に行くんじゃなくて、加藤さんを通じて江藤さんに遡るっていうあなたのような人が出てくる。
與那覇 世代ゆえですよね。上野さんが回想でよく仰るのは、60年代の青春を小林秀雄や吉本隆明に耽溺して過ごしたけど、そうした女性は当時、ほぼいなかったと……。
上野 私は、小林に入れこんだ悲しい過去があるので。自分を不幸な女だと思っていました(笑)。
與那覇 僕は90年代が青春の男性ですが、小林や吉本は威張った文章を書く大昔の思想家だと感じて、「偉さ」の中身がまるで不明でした。
(中 略)
江藤と加藤をつなぐキーマンを十分に読めないのは、拙著の弱点でもあると思います。ここはぜひ、女性学に向かわれる契機として「吉本の衝撃」をしばしば語られる、上野さんに伺いたいのですが。
雑誌版、96・98頁
(強調を付与)
続いて吉本隆明の『共同幻想論』(1968年)がどう、自分のフェミニズムに影響したかを上野さんが話すけど、拙著で柄谷行人と加藤典洋の対談(85年)を参照したぼくには、吉本の扱いのズレが興味深かった。当時はまだ「骨のある若手」と見なしていた加藤を相手に、柄谷氏はこう語る。
柄谷 吉本さんでも、江藤さんでも、50年代に書かれたものはいまでも新鮮に読めるんですよ。ところが、60年以降のほうは鎖国的になっていて、独立した、自立した言説空間みたいなものができていて、そのなかで何もかも意味づけられるようになっている。
(中 略)
そんなもの、どこにも存在してないじゃないかという気がするわけですよ。……これは「全体」が包めるような世界があるからです。江藤さんの言う「アメリカ」も、「全体」を包みこむ視点において出てきている。50年代はそうじゃなかったんですよ。
『加藤典洋の発言1』104-5頁
(算用数字に改訂)
『共同幻想論』は、名前に惹かれて手を出すと挫折する本No.1である。吉本は、古事記の日本神話から「国家」とはなにかを演繹するが、なんで古事記には共同体のなりたちが「すべて書いてある」と思い込めるのか、その謎すぎる前提を読者(ていうかぼく)は共有できないからだ。
同じく江藤淳も、アメリカを「戦後の日本人のすべてを規定する強大な父親」だと思い込んで、そうした江藤ワールドの下にあれこれの小説を位置づけるようになっていった。――というのがたぶん、柄谷氏の批判である。

対して、上野さんが吉本の著書から読み取ったものはまるで違った。むろん世代の差もあるが(柄谷が1941年生で、上野・加藤は48年生)、やっぱり大きいのはジェンダーの違いだろう。その諸相は、ぜひ雑誌で見てほしい。
久しぶりのクラシカルな対談を経て、再確認したのは、次のことだ。
たとえ同じ文章を同じ時に読んでも、そこからなにを持ち帰るかは、人によって違う。その違いには「読み手が何者か、どんな人生を歩んできたか」が表れる。だから、全体主義的に全員の生の様式を画一化でもしないかぎり、解釈の相違やそれが生む対立は消えない。
しかし、違った読み取り方をする相手を「他者」と呼ぶとして、互いにどこでズレたのかを確認しながら、対話を愉しむことはできる。なにより、自分の中にもけっこう他者がいて、「え! こういう風に読めるのか?」となる――かつてとズレてきた自分を見つけられるのが、読書の醍醐味だ。

與那覇 江藤の文章ってタイトルは「何々と私」だし、『成熟と喪失』も失われた自国の過去を嘆くばかりで、むしろ「自己」の思想家でしょうと。その印象が変わったのは、僕がメンタルの病気をして、歴史学をやめた後なのです。
日本史の学者として「加藤典洋が紹介する江藤淳」から逆算してゆくと、江藤さんは日本の「自画像」を描くナショナリストに見える。でも実は江藤にとって、戦後の日本はそもそも自己じゃない。むしろ理解不能な時空間であり、他者です。……その感覚を掴むには、僕自身がいちど病気で、社会から疎外されてみないとダメでした。
雑誌版では95頁
昨今はそう言うと、でも明らかに無理筋な読み方で難癖をつけてくる、対話不能な他者だっているじゃん? という話になりがちだ。ぼくもそうした人によく嫌がらせされるので、懸念はわかる。
違えばなんでもOKなわけじゃ、もちろんない。自分独自の読み方を、 ”豚の嘶き” (意味は以下のリンクを)に陥らずに、どう相手に伝えるか。そこでこそ、読書を通じた成熟の度合いが試される。

具体的には、どういった姿勢が必要なのか? それも対談の中で、しっかり示したつもりだ。
他人を罵り、マウントをとるために「読書」や「フェミニズム」を使うSNSのお子様学者に飽きた人ほど、日本のフェミニスト批評の草分けでもある上野さんとの、今回の対談に触れてほしい。成熟したほんとうのダイバーシティは、読み方の多様性から始まることが、わかるはずだから。
参考記事:




編集部より:この記事は與那覇潤氏のnote 2025年6月9日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は與那覇潤氏のnoteをご覧ください。













