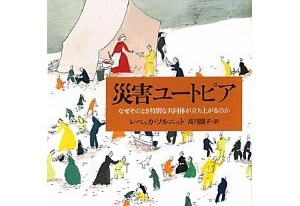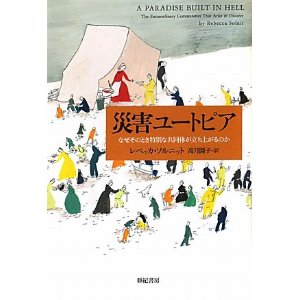 当初は夏に入る前にも復興のバトンを引き継ぐのかと見られた菅政権でしたが、場当たり的にも見える仕方で「脱原発」政策を矢継ぎ早に打ち出し続ける姿が賛否両論を呼び、これに与野党双方を巻き込む政局が絡んで、被災地を置き去りにした政治の混乱もいよいよ極まった感があります。震災当初、復興支援に対して国民みなが抱いたはずのあの結束感――もしくは「誇れる日本人」だとか、「世界一優秀な民族」だとか、今となっては口にするのも恥ずかしい類の国民性論まで沸騰させたある種の高揚感は、いったいなんだったのかと、絶望に近い諦念に打ちひしがれている方も多いのではないでしょうか。前年末に邦訳初版が刊行(原著は2009年)され、期せずして今回の不幸な震災にも逢着して版を重ねる本書は、災害発生当初にはなぜ、(“国民性”の如何にかかわらず)いかなる被災地でも互いに力をあわせあう利他的行動が自ずと発生し、そしてそのようなユートピア的な共同性がどのようにして喪われていくのかを辿るノンフィクションです。
当初は夏に入る前にも復興のバトンを引き継ぐのかと見られた菅政権でしたが、場当たり的にも見える仕方で「脱原発」政策を矢継ぎ早に打ち出し続ける姿が賛否両論を呼び、これに与野党双方を巻き込む政局が絡んで、被災地を置き去りにした政治の混乱もいよいよ極まった感があります。震災当初、復興支援に対して国民みなが抱いたはずのあの結束感――もしくは「誇れる日本人」だとか、「世界一優秀な民族」だとか、今となっては口にするのも恥ずかしい類の国民性論まで沸騰させたある種の高揚感は、いったいなんだったのかと、絶望に近い諦念に打ちひしがれている方も多いのではないでしょうか。前年末に邦訳初版が刊行(原著は2009年)され、期せずして今回の不幸な震災にも逢着して版を重ねる本書は、災害発生当初にはなぜ、(“国民性”の如何にかかわらず)いかなる被災地でも互いに力をあわせあう利他的行動が自ずと発生し、そしてそのようなユートピア的な共同性がどのようにして喪われていくのかを辿るノンフィクションです。
南北アメリカを中心に、地震やハリケーンから9.11テロのような人為的現象まで、ここ100年近くの巨大災害から豊富な事例を引く本書ですが、著者ソルニットの理論はきわめてシンプルで、本来人間には進化の過程を通じて相互扶助の精神が埋め込まれているとするクロポトキン主義です(p126)。クロポトキンというとロシア・アナーキズムのイメージがありますが、著者の見るところこれは『コモン・センス』で独立革命の狼煙をあげたトマス・ペインの、公的政府の解体期にこそ市民の自治が堅固になるという観察(p135)に示された――後にトクヴィルやアーレントも着目した――アメリカ社会の基層にある精神に等しい。しかし合衆国政府も含めて西洋の近代国家は、利他心ではなく利己心を人間の本質と見なし、それを公権力が抑制しない限り社会は「万人が万人に対して狼」になるというホッブズ主義を教条として設計されているため、政界や官僚機構に適応している人間ほど「公的政府に機能不全が生じると、必ず社会は混乱し無秩序に陥るはずだ」という先入見に囚われる。このため大災害が発生すると、民間では平時に抑制されていた相互扶助の本性がむしろ開花してユートピア的な自生的秩序が育まれるのに対し、逆に統治機構の方が過剰に秩序崩壊の恐怖にさいなまれるエリートパニックが発生する(p178)――1906年のサンフランシスコ大地震では市長が軍と警察に「略奪者の即時殺害」を通達し(p61)、2005年のハリケーン・カトリーナの際ですら“暴徒”の乱入を恐れて近隣地域は橋を武装保安官で封鎖、威嚇射撃でニューオーリンズからの避難民を追い返したと(p363-4)、著者は告発します。
かような米国の事例に比べれば、現今の日本で見られる“パニック”はまだ相対的には安穏たるものに思えてきますが、これには由縁があるでしょう。そもそもホッブズ的な「利己心の塊」としての人間像を前提にしつつ、しかしその利己心の追求競争こそが経済成長をもたらすとしたスミスの教義――『国富論』刊行とアメリカ独立宣言は同じ1776年――に則って発展してきた米国の歴史文化は、同じ時代に江戸時代という「停滞した平和」を享受してきたわが国とは、好一対のものといえるからです。
アメリカ人の幸福に対する考え方は、一般に誰でもがどしどし行動して新しい事業などきりひらいてゆけば、それはその個人の幸福になると同時に社会全体の富をふやすことにもなるといった楽天的なものを多分に含んでいる…ところが日本の場合、社会の富には限りがあって、誰かが幸福を多量に獲得してしまうと、その分だけ他人の幸福の分け前が減る、とでもいうような感じが、少なくとも1950年代までは人々の幸福観の底にひそんでいた。だから日本映画では、幸福を他人にゆずることや、他人の幸福のために自分を犠牲にする、あるいは自分の幸福を自分で笑って制限する、というような物語がいちばん同情をこめて描かれ、不幸に耐える、という主題が最も力強い表現になる(佐藤忠男『小津安二郎の芸術』p424)
ソルニットの叙述は社会主義をはじめとした、人類が徐々に歴史的な階梯を辿ってユートピアへ到達するという西洋近代の“解放の物語”が失効した後の代替物を「それまでの秩序を転覆させ、新しい可能性を切り開く、災害のもつ力」(p21、30)に求めたものとも解釈できますが、これもまた、日本の歴史文化とは微妙な差異を孕んでいます。そもそもキリスト教圏の千年王国主義に相当するものとして、仏教圏にも「五十六億七千万年後」(!)に理想社会が来るとする弥勒信仰がありますが、これは――特に稲作が普及した近世以降――定住性の高い日本社会に定着する過程で、きわめて現世利益的な安全祈願に変容しました。換言すれば、既存の秩序の永続性を前提とし、未来志向の“解放の物語”を根本的に欠いた、「初めから聞き分けのよい」社会が成立していたのです。
一つの封鎖的な村をそのまま現実的世界と認識する村人にとって、村を破滅させる災難から救ってくれる存在が、メシアとしてのそれであったろう…仏教の教理が五六億七千万歳後の弥勒出世を説いても、その天文学的数字の示す未来世は民衆の直接的願望に応えることができない。柳田国男が鋭く指摘したところでもあるがこの仏教思想の浸透は、天文学的数字が容易に捨象されることによって、等しく民衆の至福千年説にマッチするところであった(宮田登『ミロク信仰の研究』p134、159)
したがって江戸時代の震災時に観察された「災害ユートピア」は、驚くほど慎ましやかなもので、地震の発生を神意による「世直し」と解釈する場合も、その内実は「上層町人から救済のための御用金を出させることを鯰に託して表現する」(宮田著、p228)程度の憂さ晴らしにしかならなかった。(更なる発展ではなく)例年と同様の豊作が繰り返されることだけを願い、そしてそれを妨げる「悪」(たとえば強欲な富者)をどこかに措定して彼を除去しようとする(同、p216、196)、よく言えば分をわきまえた、悪く言えばむしろマイナス志向の強い変革の理念しか持ち得なかったのが、近世日本の民衆運動の限界だったと指摘されています――積極的な復興策や代替案の提示ではなく、ただただ“不徳”な政治家や原発関係者の「除去」のみが高唱され、日に日に険悪になってゆく震災後の日本社会もまた、同じ轍を辿りつつあるのではないでしょうか。
裏返せば、人々が自発的に助け合える「災害ユートピア」の可能性を喪失させてしまうメカニズムは、人間はしょせん利己的だとするアジェンダに自縄自縛となった西洋近代と、富の総量を一定と見なし倹約(私益抑制)に従わないものに悪の烙印を押しがちな日本社会とでは異なっていますが、そこから導かれる教訓には重なるところがあるともいえます。ソルニットが述べるように、想定外の衝撃によって生じた困難の中で「片側通行の慈善とははっきり異なり、相互扶助への参加者全員が、与える側と受け取る側の両方であることが人々を団結させる」(p124)のに対し、そこに“与える側/受け取る側、秩序を守る側/乱す側、節制する側/貪る側”といった日常の対立枠組を持ち込むことが、「災害の起きている瞬間には利他主義が優勢だが、それに続くのは、時にスケープゴート探し」(p119)という状況を招くのだと。避難所生活を余儀なくされている幾多の人々を現地に抱えたまま、被災地を遠く離れた場所で展開される政治が(悪い意味で)「日常」の政争に回帰しつつあるようにさえ見えるいま、自身が前提にしている認識枠組みや価値観が「あの時」に垣間見えたユートピアを引き裂くものになっていはしないだろうか。もういちど省みるゆとりを、誰もが心の中に持ちたいものです。
與那覇潤(愛知県立大学准教授/日本近現代史)