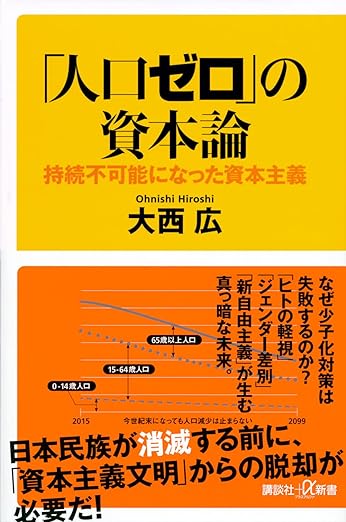m-1975/iStock
(前回:要するに人口減が資本主義で解消されるのかどうかという問題①)
マルクスはどう言ったか
ただし、このようにして「余程のことをしない限り人口減の解決は無理」ということがわかっても、そして、それが(子育て費用の内部化という「社会化」とともに)「貧困の撲滅」という「共産主義」を必要としているとしても、それがマルクスの名前で主張されることへの説明は別に必要であろう。
濱田氏はマルクスが「資本主義は人口問題を解決する」と言っていたとされ、また確かに「人口ゼロ」の予測まではもちろんしていなかったからである。そして、それには、小著80ページで述べたように、『資本論』における「再生産」という観点の重要性を確認する必要がある。
というのはこういうことである。『資本論』は第1巻の最後のところに「資本の原始的蓄積」についての章を置き(第24章)、資本主義的再生産が開始される条件について述べているが、これは逆に言うと、その他のすべての章がその条件が揃ったことを前提にしていることを示している。そして、それは平均的にではあっても賃金で必要な労働力が再生産されることを含むので、第1巻第24章以外はすべてそもそも労働力を再生産するための賃金が支払われている、ということになる。
つまり、ここでは「労働力の適切な再生産」は「前提」なのであって、強いて言えば、そのために必要な諸条件が示されているにすぎない。私が「賃金には次世代労働力の再生産費が含まれていなければならない」と書かれているとした『資本論』第1巻第4章を「賃金論」と呼んだ趣旨はここにある。
賃金の諸形態については『資本論』は別に書いているので、そちらをこそ「賃金論」と呼べとの批判はそれとして理解できるが、問題はこの箇所でマルクスが何を言おうとしたかの趣旨であって、それを理解できているかどうかなのである。
なお、マルクスと私の相対的過剰人口論の相違については濱田氏に若干の誤解もあるのでここで述べておきたい。というのは、置塩氏が論じたのは相対的過剰人口の否定ではなくその証明であったということ、それを否定したのは私であるということ、これがひとつ。そして、置塩氏の「相対的過剰人口論」の理解と異なり、私が小著で示した理解は、マルクスは必ずしも過剰人口の絶対的増大を意味していなかったということである。
いずれにせよ、マルクスの「相対的過剰人口論」は「不変資本」と表現される機械や原料の部分の増大に比しての人口の過多でしかないから、一般的な人口減とも一般的な人口増ともすぐに矛盾するものではない。そのために小著では補論として「「マルクスの相対的過剰人口論」は一般的に通用しない」と述べたまでである。
「ホモ・エコノミクス」への批判について
金子氏、澤村氏の両氏に共通する私への批判は「ホモ・エコノミクス」の仮定を使った「数理モデル」への批判であり、本稿の最後にこの点についてのリプライを行ないたい。そして、その最初のものは、金子氏が社会学者として違和感を表明されるのは当然である、ということである。
経済学には経済学の人間観があるのと同様に(ホモ・エコノミックス)、社会学には社会学の人間観があり(ホモ・ソシオロジクス)、政治学には政治学の人間観があり(ホモ・ポリティックス)、学生たちが4年間各学部で身に着けているのはそうした人間観であるからである。
つまり、社会学者としての金子氏が自らの学者生命を賭けてその人間観をぶつけられているのはいわば当然のことであって、学者たるもの、それくらいの信念がなければならないと私も思う。それだけ真剣に自分の学的立場に向き合っておられるということである。ちなみに、経済学者であったとともに社会学者でもあった高田保馬氏へのこだわりもここから理解できる注1)。
ただ、しかし、氏が拘られるのと同様、経済学における「ホモ・エコノミクス」という人間観の強固さはまた格別なもので、経済学の世界に生きる殆どすべての研究者はこの立場への疑いをもたない。言い換えると、経済学の世界における数多の「人口モデル」はすべてこの立場から作られている。
私のモデルが特殊なのではまったくない。もちろん、一部には「再考すべし」との考えの研究者もいて、さらには旧来の「マルクス経済学」もまたそうした立場を維持していた。が、問題は、そうした「マルクス経済学」は今や学界で影響力を大幅に喪失しており、強く言うと、それを乗り越えた「数理マルクス経済学」だけが今元気に活動をするに至っているということである。今、マルクスを現代的に再生したいのなら(少なくとも「経済学」の中で再生させたいのなら)、不可欠な立場であると私は考えるのである。
例えば、この立場を補強するために次のような例を考えてみられたい。TPPに最も反対したのが農業団体であったということである。彼らは「理念」で反対したのではなく、それが彼らの利益に矛盾したから反対したのである。彼らがどのような理念をその時に語ったにせよ、そして、その一部活動家は本当にそう思っていたにせよ、その業界が全体として反対したのはそうした「利益」を持っていたからである。
マルクスの場合もまったく同じである。映画「マルクス・エンゲルス」の冒頭シーンにあったので多くの読者は覚えておられようが、マルクスが「ライン新聞」時代に関わった紛争案件は林野における農民の枯れ木拾いを合法とするか不法とするかという問題であった。
農民たちはこれが過去に慣習として認められていたことを主張し、逆に土地所有者はその枯れ木拾いを「窃盗」と断じた。が、「前近代的な所有権」という「正義」と「近代的で排他的な所有権」という「正義」の間の闘争として現れるこの紛争の本質を、マルクスは利益と利益の間の対立として理解した。そして、人間社会のリアルな諸関係は利害と利害の間の諸関係であると認識し、ここからマルクスは経済学に転向して行ったのである。
マルクスがエンゲルスとともに打ち立てた人間観の基本はこうして「社会学」のそれではなく、「経済学」のそれであったということを述べておきたい。
最後の最後に、この論点と関わって澤村氏があまり「遠い将来」を語らず「我らの時代、少なくとも次の時代ぐらいまでの話にして欲しい。」と述べられたことにも言及させていただきたい。
私が考えるに、人口予測というものは前期のようにかなりの確度で100年後が語れるから、100年くらいのスパンは持って欲しいと思うのであるが(その時には日本は3900万人に縮む)、この澤村氏の指摘はその直後に書かれた「各人(親)は子供より自分のほうが大事」という私の仮定(というよりすべての数理経済学者が措いている仮定)への批判と矛盾しているからである。
澤村氏が「次の世代より先は語って欲しくない」とおっしゃっていても、澤村氏の孫の世代はそうは行かない。もちろん、ひ孫の世代はもっとであり、これは各世代のパースペクティブが無限でないこと、つまり将来世代への考慮は減衰(逓減)していることをしている。経済学のモデルが表現しようとしているのはこういうことなのである。
以上、提起されたすべての論点ではないが、主な論点にしてはご質問にお答えできたかと思う。討論の機会をいただけたことに深く感謝したい。
【関連記事】
・要するに人口減が資本主義で解消されるのかどうかという問題①
・【社会学の観点】「少子化論」に対する「数理マルクス経済学」の限界①
・【経済学の観点】「少子化論」に対する「数理マルクス経済学」の限界②
■